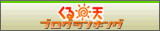| 「白装束をした子どものような小さな人が突然訪れて、オリコシの山が崩れて神田は埋め潰されるから、安全祈願な場所に逃げなさいと告げた。(1) | |
| [森羅万象] | |
| 2019年4月5日 18時24分の記事 | |
『進化する妖怪文化研究』 小松和彦 編集 せりか書房 2017/10/1 『<洪水怪異伝承の構造と意味 小松和彦>』 <「経験知」としての土地災害伝承> ・近年の日本列島は、大地震や集中豪雨に襲われ、甚大な被害を被っている。そのつど、私たちは自然の計り知れない猛威に恐怖し、その猛威からいかに身を守るかに思いをめぐらす。そしてその過程で、日頃は忘れていた災害をめぐる民間伝承や先人が残した警句を思い出すこともあるのではなかろうか。例えば、大地震や大津波に襲われると、その後に過去の地震や津波の伝承が掘り起こされるのである。 いま少し具体的な例を挙げよう。2014年の8月の集中豪雨では、広島市宇佐南区八木地区で多くの犠牲者・被害が出た。土地の伝承によれば、被害があった地域は、もともとは「蛇落地悪谷」と呼ばれ、大雨が降れば水が出るので、人が住むことを避けてきた地域であった。また、この地域には、中世の在地武将による悪蛇退治の伝承も語り伝えられていた。災害報道ではしきりにこの伝承が取り上げられていたが、こうした伝承があるにもかかわらず、行政や住宅開発業者は、そのことを知ってか知らずか、住宅開発を進めた結果、今回のような悲惨な事態になったのであった。 ・同じ年の7月には、長野県南木曽町の梨子沢で台風8号による豪雨で土石流が起こり、死者1名、全壊家屋10戸の被害をもたらした。被害が少なかったことや、その後も山口県岩国市(8月6日)、兵庫県丹波市(8月17日)、上述の広島市の土砂災害が続いたこともあって、それほど注目されなかったが、一連の報道のなかで、やはり山崩れ・土石流災害に関する土地の伝承が取り上げられていた。この地域では、山崩れ・土石流(山津波)のことを「蛇抜け」と呼ぶ。報道関係者が注目したのは、1953年7月に発生した南木曽町伊勢小屋沢の土砂災害を記念するために建立された「悲しめる乙女の像」(蛇抜けの碑)である。この碑には「白い雨が降るとぬける 尾先 谷口 宮の前 雨に風が加わると危い 長雨後、谷の水が急に止まったらぬける 蛇ぬけの水は黒い 蛇ぬけの前にはきな臭い匂いがする」という、土石流発生の前兆に関する俚諺(経験知)が刻まれていたからである。一昨年の土石流発生時にも、ここに書かれていたことと同じ前兆があったのだ。 ・この二つの事例は、民間伝承(経験知)を知ることの有効性を端的に物語っている。それをふまえて生きることによって、自然の猛威を完全には予防することはできなくとも、その被害を少なくすることができるのである。 さて、このように述べると、だから民間伝承をもっと研究しよう、それは社会に役立つ学問なのだ、という論調になりがちである。しかし、こうした地元の民間伝承にも説き及ぶ報道を聞きながら、民俗学者の端くれとして、内心忸怩たる思いになっていた。というのは、それらの報道のなかで、防災研究者は登場しても、ついに民俗学者がコメントを求められることもなければ、民俗学の災害伝承研究の蓄積に言い及ぶこともなかったからである。 少しでも民俗学をかじったことがある者ならば、民俗学が厖大な民間伝承を記録し、そのなかにはさまざまな災害伝承も含まれていることを知っているはずである。にもかかわらず、報道関係者には、民俗学者や民俗学という学問にまで思いが及ばないのだ。 それはなぜだろうか。ひと言でいえば、民俗学という学問研究の低調さが関係しているのだろう。別の言葉でいえば、社会に向けてその成果を発信する力が弱いのである。 <初心に立ち返って考える> ・この論文の眼目は、龍宮童子譚などの背景には、民間伝承として広く浸透している「童子」の信仰があるということを明らかにしたものである。 しかし、その分析のなかで浮かび上がってきたもう一つの説話的形象があった。「翁」である。龍宮童子とは、水界に薪や花などを贈った見返りとして「水界の主」(龍王)から与えられた、富を生み出す醜い童子のことである。その「水界の主」は「翁」として語られている。この「水界の主」のイメージは、「白髭水」伝説のなかの、「洪水のさいに出現する翁」とも関連があるのではないか。例えば、新潟県古志郡東谷村栃堀の伝承では、昔、大洪水のとき、白髭の老人が現れ、夜明けに村人に大声で、「大水が出るから早く逃げよ」と知らせた。この老人の言葉を信じた者は助かり、信じなかったものは多くは死んだという。大正15年の栃尾郷の大洪水も白髭水の類だと村人は語っていたという。民俗学者の宮田登は、この伝承について、「終末を予言する白髪、白鬚の老人とは一体何者なのか素性は総て不明である。むしろ諸事例から判断すれば、終末の危機感の中から生まれた共同幻覚の一種ではなかろうか」と述べていた。私は、この見解に対して、「その素性は龍宮の龍王のイメージと関係しているのではなかろうか」と解釈したわけである。 ・こうしたこともあって、その後、機会あるごとに洪水にかかわる怪異伝承を集めてきた。ところが、集めれば集めるほど、その種の多様さに驚かされることになった。多様性に目がくらむと分類が細かくなってゆく。右の「白髭水」という分類もその一つであるが、白髭の老人が登場しない洪水伝説では、例えば洪水の最中に怪しい声がする伝承は、その声が「やろか、やろか」ということが多いので「やろか水」と分類されて、同じ洪水伝承でありながらも「白髭水」から切り離されて分類されてきた。 <どこに着目するのか> ・私が着目するのは、「洪水伝説」のうちでも、その伝承のなかに「怪異」と呼びうる要素が含まれている伝承である。 今日、大雨、洪水、大日照り、地震、津波、噴火などは「自然現象」とされている。そしてそれがもたらす災害は「自然災害」である。ところが、かつてはそのような自然現象それ自体が「超自然現象」として、もしくは「超自然的存在」によって引き起こされるものであるとみなすことが多かった。そして、それらの伝承のなかには、そのことを示す「怪異」が語り込められていた。例えば、先述の「白髭水」では、洪水発生を告げる「白髭の老人」である。たしかにこの「白髭の老人」は、分類の指標となるだろう。「白髭の老人」が登場する他の地域の伝承があれば、それらをまとめたくなってくる。しかし、この分類の難点は、「白髭の老人」ではない存在が洪水の危険を告げるような場合には、この分類から排除されてしまうことになる。 しかし、話の展開という点でいえば、例えば、「白髭の老人」を「見たことがない童」とか「白い動物」とかに変えても、伝承それ自体の「構造」を損なうことはない。つまり、「洪水の前に洪水を予告する神秘的存在が登場する」というふうに抽象化することで、同様の伝承群を重ねることができるはずなのである。 もちろん、地元の信仰伝承では、「白髭の老人」であることに意味があるのだろう。それが、例えば「白装束をした小さな人」になったならば、地元の信仰伝統にそぐわないために解読が不可能になるかもしれない。しかし、理論的には、伝承の物語構造(統辞的構造)の全体の保存という点では、「白髭の老人」が「白装束をした小さな人」に置き換わっていてもいっこうに問題がないはずである。 <洪水が起こらなかった伝承と洪水が起こった伝承> ・(長野県木曽郡開田村)「白装束をした子どものような小さな人が突然訪れて、オリコシの山が崩れて神田は埋め潰されるから、安全祈願な場所に逃げなさいと告げた。この言を信じて、村人が安全な場所に避難したあと、山が崩れて、神田の村は壊滅した」 <水界の主・洪水・異人> ・さて、いよいよ、これら「洪水怪異伝承」群の解読・魅力について議論することにしよう。これまで紹介してきた事例のなかでも、「他言禁止という条件がついた洪水発生情報」が組み込まれた物語は、とりわけ聞く者の心を揺さぶる。というのも、洪水から村人を救うために、水界の主から洪水を起こる情報を得た者が、命を捨ててでも村人を救おうと約束を破り、情報を村人に漏らし、結果として命を落としてしまうからである。 ・しかし、いくつか気になることがある。その一つは、水界の主から洪水を起こすことを教えて貰うのが「盲目」の「座頭」(琵琶法師)であり、その情報を村人に告げて犠牲になる者もやはり「旅」の座頭として語られることが多い、ということである。 『<柳田國男の妖怪研究 「共同幻覚」を中心に 香川雅信>』 <『妖怪談義』> ・昭和31年(1956)に刊行された柳田國男の『妖怪談義』は、日本民俗学の学父御自らが著した妖怪研究の書物として広く知られている。実際に、柳田の書いたもののなかで最も入手しやすく、かつ長く読み継がれている著作であろう。また、コナキジジ、スナカケババ、ヌリカベ、イッタンモメンなど、水木しげるの漫画や妖怪図鑑に描かれた妖怪の多くが、この『妖怪談義』から採られたものであり、その意味では現代日本人の通俗的な妖怪観に大きな影響を与えた著作でもある。 この『妖怪談義』の重要な論点とされてきたのが、「妖怪は人々の信仰を失って零落した神である」という仮説、「零落説」である。だが、この説は現在では厳しい批判にさらされ、ほぼ否定されていると言ってもいいだろう。 <妖怪研究の三つの画期> ・もっとも、柳田の怪談研究の根本には、「神隠し」への関心があった。その最初の仕事である『近世奇談全集』に収録された奇談随筆には、いずれも「神隠し」の話が含まれており、『遠野物語』の「神隠し」のエピソードも有名である。明治43年(1910)に『中学世界』に発表された談話「怪談の研究」では、「日本の如く俗に云う神隠し、女や子供の隠される国は世界中余りない。これが研究されて如何なる為めか解ったならさぞ面白いだろう」と述べている。 <「共同幻覚」探求の意味> ・ここで「言論」が「共同幻覚」と同じ次元で扱われていることに注意すべきであろう。ここで問われているのは「言論」の中身ではなくその「形式」、いわゆる「声の大きな」もっともらしい意見に流されがちな日本人の気質である。 つまり柳田にとって「共同幻覚」の探求とは、「共同幻覚」がいかなる信仰や不安・恐怖により生み出されたのかを探るのと同時に、日本人がどのような条件のもとでたやすく共同の感覚に陥ってしまうのかを見極めようとしたものではなかっただろうか。そして柳田は、その拘束を脱するには「個人教育」ではなく「社会改革」が必要だと考えていたのである。しかし、時代はそうした柳田の考えとはまったく逆に、全体主義的な傾向を強めていき、泥沼の戦争へとなだれ込んでいくのである。 <「零落説」再考> ・このように柳田が、一種の「社会問題」として妖怪を考えていたというふうに捉えなおしてみると、いまや陳腐なものとすら思われる「零落説」も、まったく別の相貌を見せはじめる。 以前から気になっていたのだが、柳田が「零落説」について述べている文章を読んでいると、やや奇妙なこだわりのように見える部分がある。それは、妖怪によって怖い目に遭わされるのは、決まってそれを否定しようとした人間であった、という一節である。 ・柳田が指導する郷土生活研究所が、日本学術振興会の援助を得て昭和9年5月から12年4月にかけて行った「山村調査」では、柳田により百の質問項目が設定されたが、その一つに「世の中に不思議な事は無いと威張って居て、ひどい目にあったという話はありませんか」という項目がしっかり入っていることからも、これは柳田が特に注意していた点であったことが推察される。 ・だとすると、柳田の「零落説」は、古い信仰が忘れ去られ、形を変えて妖怪になる、という点よりもむしろ、元の意味が忘れ去られ形を変えてもなお、古い信仰が残り続けているのはなぜかを問うことに重点が置かれていたのではないだろうか。だからこそそれは「現代の問題」となり得たのだ。 柳田は最晩年の昭和35年(1960)、「日本民俗学の退廃を悲しむ」という題で知られる講演を行い、「お化けの研究」などの趣味的な研究に民俗学徒たちがうつつを抜かしている現状を痛烈に批判したとされているのだが、『妖怪談義』がやはり晩年の昭和31年(1956)に刊行されていることを考えると、問題は「お化けの研究」それ自体ではなかったことは明白である。柳田にとって「お化けの研究」は、人々を自律的な思考から遠ざける「古い信仰」の拘束からの解放という、経世済民的な意図を持っていた彼自身の民俗学の最も重要な部分だったのである。 『<三島由紀夫の幽霊談「第二段階」と村上春樹の「地下二階」 大谷哲>』 ・「怪異」という語と「異界」という語は密接であるが、「異郷」でも「他界」でもない、「異界」なる語が一般的にも流通するようになったのはいつからか。この語を広めた一つには、小松和彦氏の仕事が挙げられる。慣れ親しんだ既知の領域と、そうではない未知の領域。小松氏の言によれば、前者は秩序づけられた友好的な世界、「われわれ」として分類できる者たちが住む世界。「われわれの世界」と「かれらの世界」の対立は、「人間世界」と「異界」との対立となる。 ・先走って言うことになるが、日本の近代小説は<超越>の問題が主観的に含まれているのみならず、<語り>の構造において<超越><言語以前><語りえぬもの>の領域を拓いていく<言葉の仕組み>を有している。例えば、田山花袋や島崎藤村に代表される日本の自然主義文学から私小説の流れを近代小説の主流として構成されるのが既存の文学史である。これを常識に反し<近代の物語>とする一方で、北村透谷を含め森鴎外、夏目漱石、芥川龍之介、川端康成、宮沢賢治、太宰治、三島由紀夫、その嫡子としての村上春樹らによる作品を<近代小説>の系列として峻別するのが田中実氏の提起である。本稿はこの提起を踏まえた新たな文学史的構想の枠組みを採用するが、これもまた一つの対立関係の構成比ではある。 <ランボー<未知なるもの>と<見者>、透谷<インスピレーション>と<生命の眼>> ・「他界」というものが在るか無いかという様な奇怪な問題は暫く置く(尤も、そういう問題にいっぺんも見舞われた事のない人の方が、一層奇怪に思われるが)。確かな事は、僕等の棲む「下界」が既に謎と神秘に充ち充ちているという事だ。彼等が理解している処から得ているものは、理解していないところから得ているものに比べれば、物の数ではあるまい。而も、その事が、彼等の生存の殆ど本質をなすものではなかろうか。 ・この「他界」とは本来ランボーにとっては、われわれの住まう現実を構成する「言語」という制度の<向こう側>としての「彼岸」「彼方」のことである。そうだとすれば、現実と異界、「われわれ」と「かれら」といった言語による二項対立に支配された世界をさらに超えたもの、<超越>への跳躍のもとに垣間見られるものである。 ・『他界に対する観念』に話を戻せば、確かに透谷は『竹取物語』『羽衣』を挙げ、たとえ「繊細巧妙」ではあっても「崇高荘偉」に欠けるとして、日本の文学(詩)においては乏しい「他界観念」の重要性を説いている。だがその真意は光と影、神と悪魔といった二元論的対立を作品の結構として取り入れ、想像力と無難に戯れることを奨励するものではない。 <幽霊談の「第二段階」へ――「小説とは何か」と『遠野物語』、または柳田と賢治の共振> ・小林秀雄と三島由紀夫の『金閣寺』をめぐっての対談を、両者の小説観の相違が際どく現れたもの、小林が<小説>を<物語>で読んでいること、その思考の制度を余すところなく、象徴的に示すものとして取り上げたのは先の田中実氏である。「小林は『金閣寺』から物語の動機に当る「やるまで」(金閣放火)を読み、三島自身はその後の「やってから」、「詩はおろか、手記のようなものさえ書いたことがない」主人公があたかも小説家、三島由紀夫そっくり、簡潔にして豊穣、あるいは饒舌な「言葉」をどのように(HOW)、何故(WHY)、手にいれて書いているのか、それが「牢屋」に入ることになると読んでいる」と述べる。 <ミシマからムラカミへ>から<三島から村上へ>へ> ・2000年以降、海外での日本近代文学の受容状況報告の中で、三島や川端と村上春樹のそれを時系列的に比較する言説が形成されつつあるという。 ・かつては村上への批判者であった大江健三郎との関係から形成された「大江か村上か」の二項対立から「大江と村上」へという両者をともに見はるかす理解の構図への変換を説くに至っては、漱石や川端に加えて、谷崎潤一郎、安部公房、大江健三郎、中上健次までを等し並に「日本の純文学の系譜」と一括し、従来はこれらと村上を対比的に捉えたことに問題があったとするのが加藤氏の問題構成である。 ・かつて人間の存在を「二階建ての家」と「地下室」に例えた村上の発言がある。一階は「ごはん食べたり、テレビを見たり、話したりするところ」。二階は「一人になって本読んだり、一人で音楽聴いたりする。そして、地下室というのがあって……日常的に使うことはないけれど、ときどき入っていって、なんかぼんやりしたりするんだけど、その地下室の下にはまた別の地下室がある」と言うのである。 ・日本の一種の前近代の物語性というのは、現代の中にもじゅうぶん持ち込めると思ってるんですよ。いわゆる近代的自我というのは、下手するとというか、ほとんどが地下一階でやっているんです。……だからみんな、 なるほどなるほどと、読み方はわかるんです。あ、そういうことなんだなって頭でわかる。そういう思考体系みたいなのができあがっているから。でも地下二階に行ってしまうと、これはもう頭だけでは処理できないですよね。……たとえば地下一階で行われている作業を批評していた人が、地下二階に潜っていって同じコンテクストを使って同質的に批評できるかというと、それは無理だろうと僕は思います。………僕の自我がもしあれは、それを物語に沈めるんですよ。僕の自我がそこには沈んだときに物語がどういう言葉を発するかというのが大事なんです。 ・ただこの「地下二階」が、「通常は抑圧され封じ込められている意識や欲望」という「地下一階」のさらなる「外部」を示唆する領域であることは了解できよう。「地下二階」の出来事とは、物語(ストーリー)におけるプロットを支える領域、因果関係のさらなる根源である。<語りえぬもの><言語以前>の領域と同義と解せよう。村上作品には、「僕」と「鼠」に顕著な主題論的な分身関係も含め、鏡や夢の境界性、山中他界往還譚を参照したであろう異界性、また壁抜け、同時存在といったまさに怪異が繰り返し描かれてきた。ただし、それらが<言語以前/言語以後>の対立関係に基づく<超越>を介在させた<世界観の表象>であるとすれば、<怪異>はそれ相応のものとして対象化されることになる。本稿はその所以を長々と述べてきたにも等しい。いかなる水準かは措くとして、今日海外では三島の後裔としての位置が村上に代表されているのだという。そうであればいま最もチャレンジングな批評的企ての一つとは、作品固有の<言葉の仕組み>に正対した個別具体の<読み>の成果の側から、<三島から村上へ>と受け渡されたものを見定めることではないか。三島の幽霊談「第二段階」から、村上の「地下二階」への振幅と深度が、<近代小説>の圏域である。 『アジア未知動物紀行』 ベトナム・奄美・アフガニスタン 高野秀行 講談社 2009/9/2 <「こんな世界は前衛文学か落語にしかないですよ!」> ・今回の旅の目的はアジアで未知動物を探すことだ。「未知動物」とはネッシーや雪男みたいにまだ科学的に存在が確認されていない動物のことで、巷では「UMA(ユーマ)(未確認不思議動物)」とか「怪獣」とか「そんなもん、いるかよ」などと言われている。 ・そう思って今回も相棒のカメラマン森清とともに、ベトナム、奄美大島、アフガニスタンの三ヵ所に飛んだ。 <奄美の妖怪「ケンモン」> <原始の森にひそむ物の怪> ・辛い単調な道を走るときは、同じことを繰り返し考えがちである。そのとき私は、ずっとケンモン(もしくはケンムン)のことを考えていた。ケンモンとは奄美にいると言われる妖怪みたいなものだ。沖縄では「キジムナー」と呼ばれるものとほぼ同じとされている。 ケンモンもキジムナーも両方とも「木のモノ」を意味すると何かで読んだことがある。大きなガジュマルに棲むとされている。木の物の怪なのだ。 私が初めてケンモンを知ったのは小学生のときだ。図書館で借りた『日本の伝説』とかいう本に「ケンモンとキジムナー」という章があり、ケンモンについての話がいくつか載っていた。 ・ケンモンには、夜、ひょっこり出会うという。それを恐れた村の人は、夜間の外出にはトウモロコシを持っていく習慣があった。ケンモンとばったり出くわすと、ケンモンが尻尾を振る。そのとき、こっちもトウモロコシを尻につけて尻尾のように振るのだ。するとケンモンは「あー、仲間か」と思ってそのまま行ってしまうのだという。 ケンモンは単純な性格なので、頭のいい漁師は「あんた、漁の名人なんだってね!」とケンモンをおだてて一緒に漁に連れて行く。ケンモンは気をよくして、どんどん魚を捕まえる。ケンモンは魚の目の玉しか食べないので、魚はみんな漁師のものになるのだ。漁師、ニンマリである。 しかし、ケンモンは怒らせると怖い。二人の漁師がケンモンを騙した(何をどういうふうに騙したかは忘れた)。すると、ある晩、怒ったケンモンが仲間を何十匹も引き連れ、どっと漁師の家に押し寄せて来た。慌てた漁師の一人は家の屋根に上り、もう一人は舟底のスノコの下に隠れた。屋根の漁師はたちまち見つかり、引き摺り下ろされたあげく、寄ってたかって殺された。舟底に隠れた漁師は見つからず、無事だったという……。 ・街角のタバコ屋などで「ケンモン、見たことあります?」と何気なく訊くと、「あー、最近見ないね。でも4、5年前にはよく出たよ」と言われたりしたそうだ。さらにその後輩が続けた。 「もっとすごいのは、ケンモンが実在するのかしないのか、島の人たちと民俗学者が真剣に討論会をやったって話です。結論は出なかったそうですが」 「そりゃすごいな!」 私は他愛なく驚いてしまった。地元の真剣度は、ツチノコやヒバゴン、屈斜路湖のクッシーなど日本の代表的なUMAを超えている。下手をするとムベンベ・レベルだ。ムベンベ探しに行く前、私たちはコンゴ共和国政府と権利関係で揉めた。もしムベンベを発見したり捕獲したりしたとき、我々と政府、どちらに優先権があるのかという問題だ。最終的に「写真は早稲田大学探検部が先に世界に発表する権利をもつが、捕獲された場合、その個体の所有権はコンゴ政府がもつ」という内容で契約書を交わした。 結局捕獲どころか目撃もできなかったから、“捕まらぬムベンバの皮算用”だったのだが、それくらいコンゴ政府は本気だったわけだ。私の経験では、奄美のケンモンに対する現地の人の真剣度はそれに次ぐ。 ケンモンはもしかすると未知動物と妖怪の境目にある存在なのかもしれない、とそのとき初めて知った。私の中で、ケンモンが「準UMA」という位置に格上げされたのだった。 <妖怪とUMAの間にあるもの> <「おい、フイハイはベトナムの猿人だぞ。こっちはケンモン」> ・「でもたしかに、ケンモンはフイハイに似てるんだよな」 ・意外なことに、古仁屋の町では50代、60代の人でも「ケンモン?…………あー、そんな話、昔あったねえ」と遠い目をする。単純に「知らない」と首を振る人すらいた。 探検部の後輩が「探索」に来てからすでに20年が経っている。奄美の人々が当たり前のように信じていた物の怪も、居場所をなくしてしまったのだろうか。 ・ちょうど野良作業中という感じのおじいさんがいたので、「昔この辺にケンモンっちゅうもんがおったでしょう?」と訊いてみた。すると「あー、おるよ。あの木におる」とおじいさんは指差す。縦よりも横に枝葉を伸ばした巨木があった。でもガジュマルではない。 ・92歳になるというこのおじいさんによれば、ケンモンは「貝が好物」で、「悪口を言ったり、ケンモンが棲むガジュマルやホーギの木を切ると口がひん曲がる」という。「寒い日には塩焚き小屋(海水から塩を作る小屋)へ火にあたりに来たもんだ。人間のふりをしているが、座ると膝が頭より高いのですぐわかる」そうだ。 うーん、面白い。いつも海外で未知動物の取材調査をしているときと同じ感触だ。こうなるともはやケンモンが実在しないとか、妖怪の一種だとかはどうでもよくなってしまい、夢中で会う人、会う人、片っ端からケンモンについて訊いた。 「ケンモンを見たことはないけど音は聞いたことはあるよ。夕暮れ時、外でざーっという何か大きな木か石が倒れたような音がしたんだけど、家から出てみると何もなかった」 民宿をやっている82歳のおばあさんは言う。 「子どもたちが何人かで遊んでいてね。日も暮れてきたから『もううちに帰んなさい』と言ったら、1人だけが山の中へ入って行っちゃったなんて話を聞いたね。あと、知らないうちに子どもの数が1人増えていたけど、誰が途中で紛れ込んだかわからないとかね」 こう話すおじいさんもいた。こちらは座敷童子みたいな逸話だ。 ・集会所のようなところに工事関係者らしき人が数人いた。30代から40代の若手だが、彼らは「ケンモン」という言葉に強く反応した。かなりキツイ訛りで「何年か前に古志で、校長先生が見たってさ」と言う。古志とは私が怪しいヤギに出会ったところに近い集落だ。「ケンモンが木をゆすってたんだって。先生はうちに帰ってカメラを取って戻ってきたけど、もういなかったんだってさ」 うーむ、こちらでは「若手」の間でもケンモンはまだバリバリの現役らしい。私はすごく幸せな気持ちになっていた。 ・なぜ、奄美に、そしてケンモンにこれほど惹かれるのか。私自身よくわかっていないが、一つのポイントは地元の人たちが今でもその存在を強く信じているところにあるだろう。 <「ケンモンの足跡」の写真> ・「この本がいちばん詳しいですね」恵原義盛著『奄美のケンモン』 ・明治38年(1905年)生まれの著者は、幼少時よりケンモン話が好きで、長じて自他ともに認める「ケンモン博士」となったと書いている。 ・「ケンモンの足跡」の写真だった。動物とおぼしきものの足跡が砂浜に点々とつづいている。 ・この本が出版されたのは今から25年前の1984年で、私の後輩がケンモン探しに行ったのはその5年ほどあとだ。つまりその当時は少なくとも、奄美大島では「ケンモンはいるに決まっている」というのが島民の共通認識であり、それに一分でも疑問をもつほうがどうかしていると思われていたらしい。 ・もっと言ってしまえば、「ケンモンに疑いを持つなどとんでもない」という畏れに近いものが人々の間にあったようだ。なぜならケンモンはやはり怖い存在であるからだ。 著書によれば、奄美ではケンモンの話を屋外ではしてはいけないという。ケンモンのいるところを指で差す、ケンモンの棲むところを汚すとかガジュマルなどその棲家である木を切ることもいけない、祟りがある。 著者が子どもの頃に存命だった根瀬部の村田豊長という人は、誰が見てもそれとわかる巨大な睾丸をぶらさげていたが、それはガジュマルの木を切った祟りだといわれていた。 他にも、『明治以前生まれの人にはよく、片方の目が潰れたようになっている人が見かけられたものですが、それはケンモンに突かれてそうなったものだといわれました』とか、『ケンモンに目スカレ(目を突かれて)隻眼になったという現存の人には、知名瀬に岡山信義氏(80歳)が居ます』と実名で記してもあった。岡山老人が何をして隻眼にされたかはわからないが、これはたしかに怖い。 ケンモンは恐ろしい存在である一方、「蛸をヤツデマルといってキャアキャア怖がる」とか「臭い屁をひる」とか愛すべきものとしての逸話も多い。むしろ、滑稽話のほうが恐怖譚より多いらしい。一見矛盾するようだが、これについて著者は、『愛すべきものとしてのケンモン話はそれをケンモンが聞いても祟りがなかろうと人々が安心して話せるからだ』と説明する。 ・河童もユーモラスで「愛すべきもの」として扱われているし、ベトナムの猿人フイハイも「たいていは人には危害を与えない」とされていた。 <死闘! ケンモン対マッカーサー> ・このような調子で「マッカーサーの命令」という合い言葉のもと、奄美の主要なケンモンハラ(ケンモンがたくさん棲む原っぱ)のガジュマルはほとんど切りつくされ、以降、ケンモンが現れたという話も聞かなくなった。「棲家がなくなったケンモンはどこに行ったんだろう」と村人は話し合ったという――。 ・アジアのUMAには米軍の話がついてまわる。それはとりもなおさず、米軍が常にアジアの各地に駐留し、さらにアジア諸国に侵攻、占領を繰り返してきたからにほかならない。米軍は地元の人間にとって巨大な“物の怪”みたいな存在なのだ。よそ者の物の怪と現地の物の怪は衝突せずにはいられない。「米軍ミーツUMA」である。そして現地のUMAはたいてい米軍にやられてきた。 ベトナムでは、フイハイや別のUMAバンボが米軍に射殺されたり生け捕りされたりしていた。現地の物の怪が米軍というもっと巨大な物の怪に呑み込まれていた。 <奄美の本格UMA「チリモス」> ・チリモスか――いかにも未知動物っぽい名前じゃないか。 それにしても奄美に、「準UMA」ケンモンとは全く別に、ちゃんと「本格UMA」がいたとは驚きだ。 <奄美はやはり「辺境」だった!> ・「昭和2年生まれですが、ケンモンをじかに見たことはないですね。ただ、父親の世代の人たちにいろいろと話を聞きました。相撲をとってネッパツ(発熱)したとかね」 義永さんはそう言って話し出した。 ケンモンと相撲をとっても勝てばいい。ケンモンは実は相撲がすごく弱いらしい。ところが、ケンモンは負けても「もう一丁」とかかってくる。何十匹もいて、次から次へと挑戦してくる。だから、最後は根負けして投げられてしまうのだという。 ちっこいのがわらわらと出てくるという不気味な感じが、私が昔抱いたケンモンのイメージと少し重なった。 ケンモンのいる場所は「やっぱり山の中だね」。昔の人は薪とりとかタケノコとりで山に入る時、危なそうな場所や変な感じを覚えるところでは、「あ、これは何かいるな」と察知してタバコを一服したのだという。タバコを吸わない人は塩をなめた。タバコや塩はそういう怖いものを遠ざける。そして「とうとうがなし」と神様にお祈りする。 「『よろしくお願いします』みたいな、一種の呪文のようなもんだ。山では小便をしたり、卑猥な言葉を使ってはいけないとよく言われた」 どうやら、ケンモンは山の神とごっちゃになっているようだ。 ・ご老人は断片的な話をいくつか話してくれた。 例えば、安脚場という集落では、「体が真っ赤なケンモン」を見たという人がいたそうだ。また、嘉入という集落では、ケンモンと一緒に貝拾いをしたという話が伝わっている。 ケンモンは貝が好物で貝拾いもうまい。たくさん取れたところで「蛸だ!」と騒ぐとケンモンはびっくりして逃げてしまう。「ケンモンは蛸が苦手なんだ」とご老人。 ・代わりに87歳の老人に話をうかがった。だが、この人はケンモンについてやけに素っ気なかった。「ケンモンはだいたい、若い娘や子どもが外に出ないようにと戒めるためのもんだったんじゃないかな、私は見たこともないし、あまり信じてもいない」 唯一私の興味を引いたのは、昔、諸鈍という集落で、若者が15、6人で山中にケンモンを捕まえに行ったという話だ。 「ケンモンを見世物小屋に売ったらお金になる」と意気込んだが、逆にケンモンに騙されて山で迷子になったという。「見世物小屋に売る」という俗っぽい欲が妙に生々しい。だが、ご老人は、この話にしても「詳しいことは知らないけどね」と突き放した口調だった。 <未知との遭遇> ・奄美で最も一般的な「ケンモンの火」で、おかみさんの話とさして変わらないが、「普通の子は小学生の低学年で見えなくなるが、俺は中学生になっても見えた」というから、本人は否定しても何か「特別な能力」があるのかもしれない。 ・実際、橋口さんは小学校3年か4年のころ、すでに不思議な体験をしている。 「みゃー」と呼ばれる広場で友だちとかくれんぼをしていた時、橋口少年が鬼になって、他のみんながどこかに隠れたあと、ふいに「ミツヒロ」と名前を呼ばれた。 「澄み通っていてすごく鮮明だったけど人間の声じゃなかったな」 橋口さんはドキリとすることをサラリと言う。すぐ後ろで聞こえるのでパッと振り向いたが、誰もいない。「そういう声が聞こえた時、返事をすると取り憑かれて連れて行かれる」と親や祖父母から聞いていたので、黙っていた。それっきり声はしなかった。 「それだけよ」と橋口さんは言い、口をつぐんだ。 ・「だいたい、俺の親父がよくそういう変なものを連れてきたのよ」 「変なもの?」 「うん、実久と芝の間に村道を作ることになった時もあったよな」橋口さんは妹であるおかみさんに話しかけた。 「あー、あったらしいね。私はいなかったけど」 「そうか」と言うと、「親父は測量の仕事をしていてね」と話し出した。 お父さんも他の人たちと一緒に「神山」と呼ばれる山へ下見に出かけた。「神山」は名前のとおり、ケンモンや物の怪がいることで知られていた。 お父さんは6、7人のグループの先頭を歩いていた。すると「クニミツ」と父の名を呼ぶ声がする。「はい?」と返事をして振り向いたが、誰もいない。他の人たちはずっと後ろのほうでお喋りをしながら歩いてくるのが見えた。 「何だったんだろう」と思うが、深く考えずにそのまま下見を終えて家に帰った。すると玄関に入るなり、出迎えたお母さんが「何かいる!」と叫んだ。お母さんは台所から包丁と塩をもってきて、後ろ向き、つまり父に背を向けるかっこうで塩をまき、包丁をかざした(顔を見せてはいけないのでこうするらしい)。そして呪文を唱えると、「あ、いなくなった」とお母さんは言った……。「うちの父は心やさしい人で、死んだ動物や無縁仏を見ると『かわいそうに』と思うので、よく家に変なものを連れてきて、その都度母が退散させていたのよ」 おかみさんが補足説明する。 <ケンモン話から突然UFOはないだろう> ・「で、ふと東の太陽を見たら、何かがスッと横にずれこんだ。何だろう、小さい灯りみたいなものだなと思ってたら、それがジグザグしながらものすごいスピードでこっちに来たんだ。時間にしてどのくらいだろう。2、3秒かもしれない。とにかく『あっという間』だった。 気づくと、『みゃー』の角にある家の上にこんな形をした巨大な“物体”っちゅうのかな、なにかが浮かんでいたんだよ」 橋口さんは両手で、底が丸くて横から見ると三角の形を描いた。円錐のようだ。 「びっくりしたんだけど、体を動かそうとしても動かない。動くのは目だけ。目を動かすと、自分は斜め下から見ていたはずなんだけど、いつの間にか真下から見上げていた。物体の中が丸見えで、三重の光の輪が紫というのか虹色というのか、とにかくピカピカ輝きながらぐるぐる回っていた。物体は底の大きさが広場と同じくらいあった。とにかく、でかかった。 不思議なのはね、これだけ大きな物体が飛んできたのに、木の枝が揺れていないんだ。揺れてないというか、なにもかもが止まって見えた。他の人たちもみんなビデオの一時停止みたいに止まっていた。 どのくらい物体がそこにいたかは分からない。なにしろ、俺、パニック状態だったから。短い時間だったと思う。それで物体は突然、来たのとは別の方角に飛んでいき、あっという間に消えちゃった。 それと同時に体がふっと動くようになって、みんなも動き出して、すべてが普通に戻ったんだよ。他の人たちは今起きたことにまったく気づいていないみたいだったな」 ・今でも崖の上から石が降ってくるとか、火の玉が見えるという場所はたくさんあるのだと橋口兄妹は口をそろえた。それは普通、ケンモンの仕業とされている。 ・一番不思議なのは、こんな突拍子もない話なのに、順番に聞くとそれなりにつながりが感じられることだ。最初の怪火以外の不思議な体験は橋口さんに訊いても「ケンモンと関係があるかどうかわからない」という。だが、ケンモンの火、見えない誰かの声、見えない声に答えてしまったがゆえに家に付いて来て、呪文と包丁で撃退された謎の霊みたいなもの、やはり包丁で撃退されたものすごいスピードで迫ってきた巨大火の玉、そしてやはり猛スピードで飛んできた未知の巨大な物体………。 それぞれの話がゆるやかにつながり、ケンモンからUFOに至っている。 それにしてもいったい何なんだろう。妖怪とUMAの境目を丁寧に追っていったのに、どうしてUFOにたどり着いてしまうんだろう。もう消化不良や異物感といったレベルでなく、何がなんだかわけがわからない。 <すべてはケンモンに還る> ・――ケンモンに出会ったことは? 「あるよ。濡れた貝殻が乾いた石の上にふせておいてあるのをときどき見たね」 「あー、あったね。貝が好きなんだよね」 <「白いかわいい犬に化けることもあったね」> ・「ブタに化けるって話もあったじゃない」 ――それはミンキラウヮー(耳切豚)じゃないですか?(恵原さんの『奄美のケンモン』でケンモン以外の「怪異」として詳しく触れられていた。ミンキラウヮーに出会って股の下をくぐられると、魂が抜かれてしまうとか男性機能がダメになってしまうという) 「そう、ミンキラウヮーともいうね。だけど、おんなじなのよ、ケンモンと」 「そうそう、新聞やテレビやらではね、ケンモンっていうのは河童みたいだとか、二本足で歩いて、毛が生えていてとかいうけど、それはちがう」 <「ちがうっていうかね。ケンモンには形なんてないのよ」> ・ケンモンには形がない。怪現象がすなわちケンモンだとこのおばあさんたちは言うのだ。 犬でも魚でも火の玉でも奇妙な音や声でもみんなケンモン。ケンモンはまだモノが妖怪とか精霊とか動物とか光といった存在に分化する、あるいは人間が分類する以前の存在なのだ。ならば、巨大な宇宙船のような物体だってケンモンではないか。このおばあさんたちがもし子どもの頃に同じものを見たら、「あれはケンモンだった」と言うだろう。 <自慢にもならないが、私ほど未知動物をしつこく追及してきた人間はいないんじゃないかと思う。未知動物探索20年。> ・ベトナムでは「フイハイはバナ族の人間しか見ることができない」と聞かされて途方に暮れた。奄美では87歳のご老人に「ケンモンなんて迷信だよ」と諭されてそのまま東京に帰りたくなった。アフガニスタンでは「そんなもんを探しに来たのか」と現地の人に呆れられて赤面した。 ・フイハイは精霊とも妖怪ともつかない存在だった。ケンモンは精霊や妖怪を飛び越え、宇宙に通じていた。ペシャクパラングは荒廃した近未来を舞台にしたSFに出てきそうな動物だった。にもかかわらず、現地の人たちの多くはそれが超自然的な現象とは考えていない。あくまで「自然」の存在だとしている。 ・この3つの旅で、途中から私の頭にこびりついて離れなかったのは、柳田國男『遠野物語』だった。 『遠野物語』は民俗学的な記録ではない。遠野出身の一青年が自分の知っている話を柳田に語って聞かせたものだ。天狗や川童、幽霊などの物の怪や怪異現象がふんだんに登場するが、これはみな昔から伝わる話でなく、柳田國男が生きていたのと同時代の話である。「菊池弥之助という老人が大谷地を通りかかったとき」とか、「松崎村の川端の家では」など、たいてい体験者の具体的な名前や事件の起きた場所の名前が記されている。 私は最初に読んだとき、「現地に行けばいいのにな」と思った。現場第一主義で、一次情報しか信用しない私なら絶対にそうする。ところが柳田は動かなかった。ただ青年の語る山の人の話を簡潔にまとめた。そして序文に「願はくは之を語りて平地人を戦慄せしめよ」と書いた。 不思議な話を、不思議なままに読者の前に放り出したのである。 ・だが、柳田はその後、妖怪や怪現象を民俗学的に研究するようになる。山の人の怖さを解体し、自分たちを平地人の知識で理解しようとした。「一つ目小僧というのは、神に供える魚が時代とともに変化した歴史的産物である」とか、山の人の力を無化する一種の武装解除ともいえる。なぜなら理解してしまえば、もう「戦慄」させられることもないからだ。どうやら、柳田國男は日本中の村々を武装解除して回り、二度と『遠野物語』の世界に帰ることはなかったようである。 私は柳田國男と逆の道をたどっているような気がする。初めはあくまで謎の生物を科学的にアプローチし、次に現地の伝承や習慣を考慮したうえで民族学的に理解しようと努めた。だが、今回、ベトナムと奄美、アフガニスタンをうろついているうちに、だんだんそれもわずらわしくなってきた。小賢しい気がしてきた。 聞いたことをそのまま投げ出したくなった。つまり、平地人(もしくは都市住民)を「戦慄せしめ」たくなったのだ。 <高野秀行 1966年東京八王子生まれ。> ・早稲田大学探検部当時執筆した「幻獣ムベンベを追え」でデビュー。タイ国立チェンマイ大学講師を経て、辺境作家になる。 『クマ問題を考える』 野生動物生息域拡大期のリテラシー 田口洋美 山と渓谷社 2017/4/21 <捕獲と威嚇のメッセージ性> ・現在、私たちが行っているツキノワグマ対策は、出没や被害の現場での「対処駆除」、いわゆる対症療法が主体である。被害に遭えば捕殺し、市街地に出てくれば捕殺する。当然のようであるが、実は肝心なことが抜け落ちている。それはクマの出没を減らすための努力である。その努力は、クマたちにこの一帯から先には行ってはいけない、人間の生活空間に出て行けば極めてリスキーである、ということがわかるように仕向ける努力のことである。 ・現在のツキノワグマの推定棲息数(全国に1万6000頭前後が棲息している)がいるとすれば、年間200頭から300頭のオーダーで捕獲をつづけたとしても対処駆除は永遠につづけていかなければならない。それは被害に遭いつづけることを意味している。被害に遭いつづけることが駆除の持続性を保障するという、現在のジレンマから一向に抜け出すことができないのである。このようなジレンマの持続性を喜べる人はほとんどいないだろう。被害に遭うのは農林業に従事する人々に限られたことではない。ランダムである。散歩やジョギング中に、あるいは登下校中にクマと遭遇することもあり得る話である。実際にそのような事故が起こっている。 ・問題は、ツキノワグマに限らず、野生動物たちに人間の側のメッセージをどのように伝えるか、なのである。そのための苦肉の策の一つとして行われているのが、新人ハンター(猟師やマタギ)の養成ということになる。東北地方に限って言えば、この5年あまりのなかで地域の窮状を見かねてハンターを志してくれる人々は微増とはいえ増えてきている。しかし、増える以上に熟練猟師たちの引退も増えているのである。このような新人養成は、マンパワーの維持にほかならないが、同時に捕獲と威嚇という手法、しかも野生動物たちに伝わるメッセージ性のある手法をどのように実践するか、が問われることになる。 ・例えば、現在、東北地方にはマタギと呼ばれる近世以来の歴史と伝統を有する猟師たちは3000人程度存在すると見込んでいるが。このなかで経験に裏打ちされた高度な現場判断ができる猟師は500人程度に減少しているだろう。いかに東北地方といえども日常の時間を自由にでき、毎日のように山を歩いていられる人はほとんどいない。多くの人は職を持ち、猟で山に入ることが許されるのは土日だけという場合が大半を占めてきている。このような状況で、被害や出没が起きた時に直ちに現場に走れる猟師はわずかしかいない。 なかには、春のツキノワグマの生息調査や子察駆除の期間に有給休暇を溜めておいて出猟するという熱心な猟師もいるが、極めて少数である。むしろ、いくらそのような有給休暇の取り方を求めても許してくれる企業はまだまだ少ないというのが現実であろう。 ・地域の山岳や沢、地名や地形に詳しく、単独で山々を歩け、クマに関する情報を収集し、クマたちの動きの先が読める猟師は育ちにくい時代である。現在、猟友会を支えている熟練した猟師たちは、ほとんど1940年代から1950年代前半に生まれた人たちである。この人たちはかろうじて親の世代の猟師たちが生計をかけて狩猟に携わっていた当時、親や近隣の先輩たちから動物の追い方など、伝統的な技術や地域の山々に関する知識を継承できたぎりぎりの世代である。この人たちが元気な内に、若い新人ハンター付いて学んでいけば10ぐらいの経験で相当の知識と技術をものにすることも可能であろう。しかし、現場を差配し安全を保ちつつ大型野生動物と向き合うにはさらに10年という歳月がかかる。この時間の短縮は難しい。バイパスはないのである。 <遭遇しないために> ・クマ鈴を腰に下げている人をよく見かけるが、遭遇した時にはよい効果をもたらさない。 ・山で生きていた人たちは、大なり小なり、クマをめぐる体験を持っている人が多い。この体験の蓄積は、危険を回避するための貴重な知識となる。地域の人たちが歴史的に蓄積し、鍛え上げてきた民俗知(民族知)の世界に多くの人が触れてくれれば、事故などそうそう起こるものではない。自動車事故よりも遥かに確率が低い。もし、そんなにクマが危険な動物であれば、すでに人類は滅んでいただろう。 <東日本大震災> ・この数年来、気が晴れない日々がつづいている。それは、東日本大震災をきっかけに生じた福島第一原発の事故による野生動物の放射能汚染問題のためである。現在も数多くの方々が避難生活をされているなか、避難区域はイノシシなどの野生動物に荒らされ、これを軽減させるために日々奔走している人たちがいる。 ・クマ問題の核心は、クマをいかに排除するかではない。出没をいかになくすかである。出没がなくなれば、問題は半減する。そのための努力がまだまだ足りていないと思う。 <狩猟と農耕> ・つまり、農耕によって発展してきた日本社会であるからこそ、狩猟を必要としてきたのである。農耕に依拠する社会には狩猟という営みが必要不可欠な存在であり、狩猟は農作物被害を軽減する抑止力として機能してきたのである。このような狩猟と農耕の相補的な関係は、ヨーロッパ社会にもアメリカにも、アジアやアフリカにも確認することができる。狩猟と農耕はまるで別物であるという理解は明らかに間違った考え方なのである。 ・この5年あまり、アメリカを調査しはじめているが、2016(平成28)年にアイオワ州のアイオワ・シティー郊外の農家を訪ねる機会があった。 訊ねた農家のビル氏が所有する広大な畑の周辺には、隣の耕地との境に幅100メートルほどの森が残されている。その森のいたる所にハイシートやハイハットと呼ばれるシカ猟用の施設が設けられていた。ハイシートというのは日本では据木と呼ばれていたもので、中世の鎌倉時代に描かれた『粉河寺縁起絵巻』などに登場する。樹上から下を通るシカを待ちぶせして弓で射るための台のことである。アメリカではコンパウンド・ボウと呼ばれる弓やボウ・ガンを用いてシカを射る猟が盛んに行われている。そのための施設が森のいたる所につくられている。 ・シカに作物を食べられながら養い、シカを狩猟している。訊ねた時、自宅から600メートルほど先の畑のなかで採食するホワイト・テール・ディアの群がいた。彼はまったく興味を示さず、私たちを家のなかに案内し、シカのトロフィーを見せながら猟の話に夢中であった。彼もまた半農半猟の暮らしをしていた。 ・ドイツのヘッセン州を訪れた時も同じであった。ドイツには80万人も狩猟者がいる。猟場となるのは農村地帯に設定された猟区であった。農家の人たちが互いに耕地を提供し合って猟区をつくっていた。その猟区を猟師が訪れ、アカシカやイノシシを獲物に猟を展開しているのである。耕地を猟区に提供している農民たちは、耕地内に生息する野生動物を獲って貰うために土地を提供していたのである。 アフリカのケニアでは、農耕する部族社会の周辺に狩猟採集民の部族がいるという話を聞いた。ラオスでも中国の雲南省でも、黒竜江省でも、ロシアでも聞いた。狩猟と農耕は、これらの国や地域でやはり分かちがたい関係にあった。何という不思議だろうか? 『熊撃ち』 久保俊治 小学館 2012/2/3 <山の魔物との遭遇> <帰国と再会> ・アイダホ、モンタナ、ワイオミング、ユタ、それにカリフォルニア北部にわたる、3ヵ月間の猟期も終わった。 各地でいろいろなプロガイドに会うことができた。だが、足跡を的確に読み、距離、時間差を正確に判断してくれる技術を、私の期待通りに示してくれるガイドには会えなかった。いっしょに行動できるガイドの数が、限られていたせいもあるだろう。そしてガイド業が、動物相手というよりも、客相手のビジネスとして成り立っていたせいかもしれない。 私が北海道でやっていたように、一人対動物という関係は、一部罠猟師や、イヌイットの人たちを除けば、もうアメリカにも存在しないのだろう。本物の猟のプロフェッショナルは、映画の中だけにしか残ってないのかもしれない。 アメリカでは、北海道の私のようなやり方、自分で獲った獲物を金にして生活するやり方の人間を、マウンテンマンと呼び、ハンターとは呼ばないようだった。 ・故国へ帰る飛行機の窓から見えてきた少し雪をかぶった山々は、まさに日本の山々だった。ロッキー山脈ほどの広さはないが、それがかえって懐かしくさえ思えた。 <なくなった林> ・4月も近づき、春の気配に山が黒ずんでくる。待ちに待った熊の季節がやってきた。フチとともに、一年ぶりに標津へ向かう。 アメリカの山の、乾いたマツくさい香りとはまったく異なる。湿っぽい腐土のような懐かしい匂いを、胸いっぱいに吸い込む。北海道にいることが、アメリカから帰ってきたことが実感される。設営を終えたテントの中で、広げた寝袋の上に寝転び、翌日からの熊猟に思いを遊ばせる。 ・やはりフチとの山がいい。 翌朝、硬雪を踏んで、熊が早い時期から穴を出る山へと向かう。 ・解体、運搬し、街に出て売れるものは売ってしまった。このときは熊一頭とシカ二頭で、当時のお金で50万円ぐらいにはなった。山に戻ったころには雪解けも進み、テントのまわりの雪もだいぶ少なくなった。 体についた熊の匂いは、2週間ほど経っても消えず、焚火の煙の匂いとともに、自分の体臭のようになる。 <異様な吠え声> ・4月も末になり、春めいてきた山の中を歩く。8月中には再びアメリカへ行くという思いが、あまり気乗りしないものになってくる。厄介なビザの取得のことを思うと気が重い。フチを連れていけるならともかく、もう置いたままにしてはいけない気持ちが強くなっている。このまま北海道で、自分の猟を完成させることのほうが大事ではないか、と思えてくる。 アメリカでは、できることはほとんどやり尽くしたような気もする。プロのハンティングガイドとしても、あちらのプロガイドと比べて遜色はなかったとの自負も持てた。まだ行ってみたいと思う州もあるが、ガイドとして、客相手では気が弾まない。 ・冷や飯に、熊の脂で炒めた味噌をつけながら夕飯を食う。フチもその味が気に入ったとみえ、旨そうに食う。 寝袋に体を入れ、オレンジ色の榾火を見ながら眠りについた。 「ウーッ」、フチの異様な唸り声に目覚める。傍らにいるフチが、ぼんやりと白っぽく見えるだけの、星明りもない闇の一点を見つめ、体に緊張感を表わし低く唸っている。焚火も消えている。 ゆっくりと寝袋から這い出し、立てかけてあるライフルを掴み、懐から懐中電灯を出し、いつでも点灯できる用意をし、闇に目を凝らす。 フチは低く唸り続けている。ゆっくりと立ち上がり、フチに行けの合図を心の中で送る。暗闇にスルスルと消えていったフチが、突然に吠え出す。吠え声が異様だ。今まで聞いたことがない怯えた吠え声なのだ。懐中電灯を点ける。ほんの一部だけ照らされた闇の中を、ライフルを構え吠え声を目指して一歩一歩と近づく。少し行くと、闇に向かい吠えているフチが、小さな明かりの輪の中にボーと浮かんでくる。尻尾を垂らし、背の毛を逆立て、怯えた声で激しく吠えたてている。熊に対してさえこんなに怯えた姿を見たことがないし、こんな怯えた吠え声を出したことがない。そのフチが闇に怯えている。懐中電灯で照らしてみても、何も見えない。熊ではないのだ。熊だとしたら、寝ている傍らで、ただ唸ったりだけしていたはずがない。足元まで唸りながら戻り、また闇に数歩踏み出しては激しく吠えることを繰り返す。 ・突然に体の中を恐怖が走った。今までに感じたことのない、得体の知れない恐怖が背筋を昇り、全身の毛が逆立つ。 ああ、これが山の魔物と言われるものなのか。猟の伝承で言われてきた、「魔物に逢う」という現象なのだ。闇を見つめ、フチの怯えた吠え声を聞きながら思った。犬には魔物が見えると言われている。今フチは、その魔物を見ているのだ。そして私自身、その魔物と言われるものの前に、暗闇で対峙しているのだ。 得体の知れない恐怖感が重く体を包み込み、押し潰そうとする。まわりの暗闇よりもっと濃い暗いモノがまとわりついてくる。額に冷たく汗が滲み出てくる。今まで、人魂と言われ火の玉も、山の中で数度見たことがあるが、そのときにも感ずることのなかった恐怖感に体が包み込まれている。なんとも言い表せない。はねのけることができないような恐ろしさが感じられる。闇に目を凝らし、耳を澄ましてその恐怖を払いのけようとしながら、ただ佇んでいた。 ・落ち着いてみると、地場の変化などによる電磁波を感じたのかもしれないと思う。犬は電磁波に敏感だといわれている。フチにとっては、得体の知れない電磁波の、その感覚に怯え、吠えたのかもしれない。そして私自身も、フチの傍らへ行き、それを感じ取ると同時に、フチ怯えを目の当たりにすることにより、電磁波の感覚が、恐怖という形で現れたのかもしれない。 ・山の中でたった一人で生活していると、奇怪なことをたびたび経験する。そして猟の伝承の中で言われていることの一つ一つが自分なりになるほどそういう訳なのかと納得できることがよくある。 例えば、サンズナワと言われるものがある。 山で泊まるとき、なんとなく嫌な感じがする場所というところがある。そんなとき、獲物を引っ張るロープなどで、「一尋、二尋、三尋半」と唱えながら3回ロープを扱き、そのロープを寝るところのまわりに張り巡らせて、結界を作れば、魔物が入ってこず安心して寝られると言われているものだ。 ・私も一人で山を泊まり歩いていたとき、熊の通りそうなところではよくやってみた。 何回か扱いたロープを張り巡らすことで、他の動物を寄せ付けない効果は確かにある。解体した獲物の肉を残しておくときに、手拭いや軍手などを肉の側に置いておくことによって、2日間ほどは、キツネなど他の動物が近づかず、肉も食い荒らされることがない。サンズナワを張り巡らすのも、これと同じような理由だと思われる。またキャンプを出るときテントの入り口に唾をつけたり、タバコの吸殻を立てておいたりすると、キツネ、イタチ、テンなどの動物にテントの中を荒らされることがないのも、サンズナワと同じようなことだと思われる。 ・山の中では1回だけの呼び声には決して返事を返してはいけない。返事をすると魔物に連れていかれてしまうとも言われている。幻聴を呼び声と間違い、よく確かめもせずに返事をしてしまうという心の弱さ、注意力の乱れが方向を間違い、山に迷ってしまう原因になるのだろう。山での猟、特に単独猟では、何事も確認し直してから行動せねばならないとの戒めと思っている。 自分なりに理由をつけ納得したつもりになってみると、たわいもないことのようにも思えるが、弓矢の時代の昔から言われつづけている猟人の伝承には、山に対する大いなる畏敬と、深い尊敬の想いが込められ、そこから得られる獲物に対する愛情が感じられる。 ・牧場での生活も順風満帆な時ばかりではなかった。牛の販売価格の下落によって、計画した収入が得られなかったり、白筋症という病気で半数以上の仔牛を失ったこともあった。特に全国的に騒がれたBSEの事件は経営に大打撃を与え、長くその影響を受けた。 『山怪 弐』 山人が語る不思議な話 田中康弘 山と渓谷社 2017/1/19 <神様の孫> ・秋田県の森吉山北麓に杣(そま)温泉という一軒宿がある。ここは秘湯として、知られ、登山客も多く訪れる場所だ。温泉宿の主人であり、また地元のベテラン猟師でもある杣正則さんに話を聞いた。 「私の親父が亡くなった時に人魂は見ましたね。祭壇は大広間に作ってたんですよ。その時、私は何か凄く体の調子が悪くてね、こう首から背中にかけて鉛でも入ったみたいに重くて苦しかったんですよ」 一週間ほど謎の体調不良が続いた頃、話を聞きつけた住職がやって来た。そして早くこの祭壇をかたづけろと忠告してくれたのである。 「和尚さんがお経を上げてくれて、それを聞いているうちにどんどん体が軽くなっていくんですよ。あれ?不思議だなあと思いながらふと窓の外を見たら………」 目に入ったのはバスケットボールくらいの大きさの人魂だった。それを見た瞬間に杣さんは分かった、あれは親父だと。 ・杣さんのお婆ちゃんはいわゆる地域の神様、拝み屋さんで、さまざまな相談ごとに応じてアドバイスをする霊能力者の類いだった。その力が孫である杣さんにも若干受け継がれているらしい。 ・杣さん自身も山の中で迷ったことがある。そこは行き慣れた場所であり、決して迷うような複雑な地形ではない。しかし歩いているうちに妙な感覚にとらわれ始めた。 「あれ?何か変だなって思ったんですよ。自分の前に足跡があるんですね。さっきまで無かった足跡が突然現れたんです。これは変だと思って立ち止まって周りをよく見たんです」 気持ちを落ち着けて確認すると、それは先ほど自分が通った所ではないか。目の前の足跡は自分の物に違いなかった。 「完全にリングワンデリングなんですよ。そんな馬鹿な、こんな所でなぜだって思いましたね」 腑に落ちない杣さんが周囲を調べると、やはり多くの狐の足跡を発見したのである。 「やられたな、こりゃ大変だ。さてどうすべ?」 杣さんは左へ左へとなぜか進んでいるようだった。そこで極端なくらい右へ曲がりながら登り始めたのである。しばらくすると目的地に近い場所へ辿り着いたが、それでも若干左寄りの地点だった。神様の孫と狐の攻防戦はいい勝負のようである。 <マタギの里で> ・秋田県の阿仁地区はマタギの里として有名である。ここには根子、比立内、打当という3ヵ所のマタギ集落がある。現役最古参のマタギで長老的存在でもある松橋吉太郎さんに話を聞いた。吉太郎さんは12歳から狩猟に関わり、16歳で本格的な山仕事を始め、多くの男たちを剛腕でまとめてきた人物である。 ・「同じ集落(比立内)のマタギで若いのと年寄りがおってなあ、いつも一緒に入っておったよ。猟だけじゃなくて山菜採りやキノコ採りもなあ」 歳は離れているが、ウマが合ったのか二人は行動を共にしていた。ところがふとしたことで若い人が寝込んでしまい、そのまま帰らぬ人となったのである。 「あれは可哀想なことだ。順番から行けばおらのほうなのにな」 年長のマタギは相棒の死を悲しんだ。そして翌年、山菜の季節がやって来るとその寂しさはひとしおである。いつもなら二人で向かう山も、一人では味気ない思いが嫌でも込み上げてくる。 「その人は次の年に一人で山さ行ってな、いつもの場所で山菜を取り始めたんだと。しばらく採ってるとな。後ろのほうで何かガサガサ音が聞こえてきてよ」 何だろうと振り向くと、昨年亡くなったはずの相棒が自分と同じように山菜を採っていた。ああ、今年も一緒に山へ入ってくれたと少し嬉しくなったそうである。 ・「そういえばおらの婆さんは山でひでぇ目に遭ったってなあ」 それは吉太郎さんのお婆さんがまだ若い頃の話である。ある日、山の畑で作業をしている夫の所へ昼飯と酒を持っていった。夫は午前中の仕事を終えて汗を拭いて一休みしていたが、来るはずの妻の姿は一向に見えない。今なら携帯電話の出番だが、当時は連絡の手だてがないのである。待ちくたびれた夫は妻を探しに山を降り始めた。 「すぐに婆さんは見つかったども、それがあまりに凄い格好でな」 髪をざんばらに振り乱した婆さんの姿に爺さんはびっくりしたそうだ。彼女が爺さんに飲ませようとした酒やご馳走の天ぷらは跡形もなく消えていた。 「あれは狐にやられたんだと爺さんは言ってたな」 <青い服の女> ・東京には2千メートルを超える山がある。青梅市から西へ進むと徐々に森が深くなり、本格的な山歩きを楽しめる地域が広がっているのだ。そのような東京の山岳地帯で聞いた話。 ・それは熊鈴事件から数日後の出来事だ。 「枝打ち作業をしている時です。現場にね、青い服を着た女の人が歩いてきたんです。それを見つけて、危ないから声を掛けて止めたんですよ。上から枝が落ちてきますからね」 切られて高所から落ちてくる枝が頭に当たれば大変だ。そこで気がついた作業員が青い服の女性の足を止めたのである。しかも……。 「後で他の奴に“お前何してたんだ”って言われました」 木に登って枝打ち作業をしていた同僚は、下で声がするのに気がつき手を休めたそうだ。 顔を向けると件の作業員が何やら話をしている、それも身振り手振りで一生懸命に。 「木の上の人には見えなかったらしいんですよ。青い服の女性が。だから私が一人で話をしていると思ったんですね。あいつおかしくなったんじゃないかってね。それ以外にも白っぽい感じのお爺さんが歩いていたりするのも見ましたね。とにかく何とも嫌な感じのする現場でしたよ」 山で白い服を着た人は時々見かけるものらしい。登山道に近い現場で作業をしていると白装束のお爺さんが歩いてくる。少し足元がおぼつかない。危ないなと思いながら見ていると、その姿が忽然と消える。それが何者かは分からない。 「夕方近くに山に入ってくる人は注意して見ますよ。気になりますよね、かなり」 何が気になるのか、それは自殺である。実際に自殺者は昔から少なくない場所なのだ。大抵は夕方近くに入るらしい。そこが夜明けとともに動き出す登山者とは違うのである。 <山の中で聞こえる音は> ・道迷いはかならずしもそれらしい場所で起こるとは限らない。天気が良くても複数でいても疲れていなくても、迷う時は迷うのだ。そして誰もが不思議に感じる。なぜあんな所で迷ったのかと、このような場合、東北ではほとんど狐のせいですべて片づくのであるが、どうやら奥多摩には悪さをする狐や狸がいないらしい。 <降りてくる山の神> ・山の神は女性だと言われている。嫉妬深く、若い男のイチモツを好む少しスケベな面も持ち合わせているらしい。古のマタギは初猟の時に最年少の男を裸にして山の神にご機嫌を伺った。そうすると獲物が捕れるというのである。現在でもこれは有効なのかもしれない。 ・獲物が捕れますように、怪我をしませんようにとありふれたお参りである。それから猟が始まり、山の中で一日を過ごすと夕方には全員無事に帰路に着いた。 「帰りに3人で車に乗って厚木市内に向かったんです。私は後部座席に乗って2人が前にいました」 街中に入ると家が立て込んだ住宅地の中を進んだ。後部座席から何気なく前を見ていた服部さんは、不思議な人物に目が留まった。 「あれ?何か変な人が来るなあって見てたんです。少し長めのおかっぱ頭で白い服を着ているんですよ?その服が凄く変なんです」 彼女が着ている服はやたらと袖が長かった。いや、尋常ではないくらい長い。それは手の長さの2倍以上はあるのだ。2メートル近くはあろうかという長い袖をひらひらさせながら、不思議な女性はこちらに向かってくる。 ・3人が同じ方向を見ていたにも関わらず、見えたのは服部さんだけだった。後日その話を知り合いにすると………。 「それは山の神だって言われました。何でも山の神の着ている物はひらひらしているらしいんです。私が山の祠に手を合わせたから、きっと一緒に降りてきたんじゃないかって」 山の神もたまには街で息抜きをしたかったのかも知れない。お茶目な女性神である。 <幻の巨大石塔> ・五箇山の酒井眞照さんが古い新聞記事のコピーを見せてくれた。日付は明治27年である。その記事は岐阜、富山、石川三県に跨る笈ヶ岳近辺に巨大な石塔が存在することを伝えている。 内容はこうだ。ある一人猟師が熊を追って山深く入り込んだ。いつの間にか熊を見失い、どこにいるのかさえ分からない状態で彷徨っていると。突然目の前に巨大な建築物が現れたというのである。その規模が尋常ではない。5層の構造で3階までは螺旋階段があり、登れるようになっている。中にはたくさんの仏像が安置してあった。何より石塔の高さが27メートルもあることに驚く。誰もその存在を知らなかった巨大建築物の話に、新聞記者が取材に訪れて記事にしたのだ。 “天然石造り希代の塔”の見出しが、その驚きをよく表している。これが公になると巨大石塔を探しに多くの人が山に入ったが、未だに見つかっていない。NHKが番組の企画として探したこともあったが、わざわざヘリコプターを飛ばしてそれらしき場所を調査した人もいるが、結局現在まで何も分からなかったのである。 ・石塔の謎については現在でも諸説入り乱れているが、最近でも見たという人はいる。 「白川で煎餅を作っているお爺さんがいるんですよ。その人は石造りじゃないけど大きな建物を見つけたと言うとりますね」 そのご老人も山奥に入り込んだ時に立派な建物に遭遇している。こんな山奥になぜあるんだろうと不思議に思い、中へ入ってみると、広間には荘厳な仏像が6体安置されていた。ご老人はしばらくそこで休憩をして、無事に家路についている。もちろん二度と彼はその場所に行くことは出来なかった。 「いやあ、あの辺りの衆もやっぱり言うことがでかいから………」 酒井さんはそう言うが、これもホラ話なのだろうか。私は彼らが実際にその建物に遭遇したのだと思う。山の中には二度と行けない場所があり、そこへたまたま迷い込んだのだろう。そのような経験者の話は日本国中どこにでもあるのだ。 <最新科学と交差する謎> ・岐阜県の旧神岡町は古くから鉱山の町として栄え、今はスーパーカミオカンデが有名だ。再現された神岡城から眺める四方を山に囲まれた地域である。交通の要衝でもある神岡町で180年続く旅館の主、茂利昌彦さんに聞いた話。 ・誰もいないはずの本堂から、子供が楽しそうに走り回り、大人たちが賑やかな話をする様子がはっきり伝わってきたのである。不思議なこともあるものだと、翌日和尚にそのことを話すと……。 「寺には亡者が集まってくるもんだと言われましたね。そういう場所なんだと。それは決して怖いもんじゃなくて、落ち着く安心出来る場所なんだと言われました。自分もそこに最後は入る訳だから、恐ろしい所じゃないんでしょうねえ」 本堂ではこんなこともあった。それはある夜のこと、茂利さんが本堂で和尚と一杯やっていると、玄関の戸がカラカラと開く音が聞こえた。 「誰か来たんか? こんな時間に」 「ほお、あれが聞こえたか、それは良い経験じゃあ。そろそろ〇〇さんが来る頃だからなあ」 和尚が言うには、今日明日の命と言われている檀家さんがいて、その人が今し方亡くなったらしい。 「寺はこうしてみんなが帰る場所だから怖くも何ともない。良い所なんじゃあ」和尚に言われて茂利さんは寺がますます好きになったそうだ。 ・神岡町は四方を山に囲まれている。朝日が当たる山(西側)には天狗が棲み、夕日が当たる山(東側)は仏の場所であり、南側の山は観音様、そして北側の山は修験の地だと言われている。特に北の山には入ると出られないところがあるので気をつけないと危ないそうだ。 「この西側の山にはUFOがよく出るんですよ。私は何回も見ております」 茂利さんが初めてUFOを見たのは随分と前のことである。それ以来、空を注視する癖が付き、その結果頻繁に見るようになった。ある時は娘さんと2人で、またある時は家の裏で複数の人たちと見ている。オレンジ色のUFOだったり、銀色で不可思議な動きを繰り返すUFOなど、さまざまな形態があるそうだ。 「この辺りじゃ小学校でたくさんの生徒がUFOを見ているんですよ。ああいうモノは何かは分からんけど当たり前にあるんでしょうねえ。見たことの無い人は信じませんけどね、あるんですよ、間違いなく」 <不気味な声> ・岡山県の北部、鳥取との県境に蒜山高原は位置する。ここは名峰大山を望む高原リゾートとして有名で、夏場は大勢の観光客で賑わう場所である。 ・そんな蒜山で長年農林業に従事してきた筒井蒸さんが狐の話をしてくれた。「昔ね、夕方まで野良仕事をしとったんですよ。山のほうの畑で大根を収穫しよった。だいぶ辺りが薄暗うなってきよったんやけど、そいでも荷車に大根を積んでおったら、すぐそばで気持ちの悪い変な声がしよるんですわ」 その気持ちの悪い声を再現してもらったが、どう表記してよいか見当もつかない不思議な音である。 「“:¥〜%#><$∄∓∢”(表記不能)って山の中からね、聞こえてくるんです。それが気持ち悪くてね」 「それは何ですか?」 「狐なんですよ。あれはよう人の話を聞いとるもんなんですよ。それで話が分かるようになっとるんでしょうねえ。昼間は近くには出てこんですよ。でも夕方になるともう自分たちの時間じゃ、天下じゃ思うんでしょうねえ。そいで“お前ら人間はもう帰れ”言うちょるんや思いますよ」 その表記不能の不気味な声を出す狐の姿は確認したのだろうか? 「狐を見たか?いや見とらんですよ。もう暗くて姿は見えませんから。ええ、でもそれは狐に間違いありませんね」 <拝み屋と憑きもの封じ> ・体の不調が続いたり家族に不幸が重なると拝み屋の出番となる。以前は各地区に存在した拝み屋も、今ではほとんどいなくなった。とはいえ絶滅した訳ではないのである。東城地区で最高齢の猟師黒川始さんに聞いた。 「災いが続くと拝み屋さんを呼んだもんですわ。大体言うことは同じなんですけえね。家の周りをぐるっと回って水神さんを直せ、竈のろっくうさんを直せ言うくらいですかねえ」 この場合の水神さんとは家への水の取り口に祀ってある神のこと。ろっくうさんとは水の神のことである。その他には“墓が汚れている”が定番の台詞だったようだ。 ・「いや、真っ暗の山の中ですけんなあ、何も見えはしませんよ。でもあれは狐なんです。狐はこうやって人を威かすんですよ。それで驚いて本当は右に行くべき所を左に行ったりして迷うんですなあ。それが狐に化かされたということなんじゃないでしょうか」 狐の姿は見えないが狐に違いないと思う理由はよく分からない。筒井さんの祖父の時代にはもっと多くの狐話があったそうだが、今はほとんど聞かないようである。 <ヒバゴンの里> ・広島県庄原市の西城地区は、ヒバゴンの里として知られている。地区にはヒバゴン饅頭、ヒバゴン煎餅とあらゆる所にヒバゴンが溢れている。ヒバゴン騒動が起こったのは40年以上前の話なので、元祖ご当地ゆるキャラと言えるかもしれない。 ・「小学校6年生の時でしたかねえ、ヒバゴンを見たことがありますよ」 西条支所に勤める加藤隆さんは、地区猟友会の若手である。加藤さんが生まれた頃はちょうどヒバゴン騒動の全盛期である。 「家の近所の川にゴギ釣りに行っとったんです。あれは夏休みの午後でしたね」 真夏の日差しの中で釣り糸を垂れながら輝く水面を見ていると、上流部に何か動く気配を感じた。加藤さんは顔をゆっくりとそちらのほうに向けて息が止まる。 「猿のでかいのがいたんです。こう立ち上がってね、かなり長い毛で全身を覆われとるんですよ。ちょうど、そう、そんな頭の感じでね」 加藤さんが指したのは私の頭である。少し長めの白髪頭はよく似ているそうだ。 ・この頃には新たなヒバゴンの目撃談もほとんど無く、話題にもならなくなっている。しかし加藤少年は、これがヒバゴンじゃないのかとすぐに思ったそうだ。ただ話を詳しく聞くと、ヒバゴンとはかなり形態が違うようでもある。もしかしたら、最初の頃に目撃されたヒバゴンが歳を取って老人(老猿?)となった姿だったのかも知れない。 <神船> ・島根県の奥出雲町は旧横田町と旧仁田町が合併して出来た町である。その名の通り出雲地方の奥座敷のような佇まいで、有名な奥出雲おろちループを超えると広島県に通ずる。 御年取って80歳になる恩田愛吉さんの話。 「もう60年くらい前の話ですね。私が仕事を終わって家に帰りよると途中でした。三所川の上のほうにある中村地区を歩いておったんです。夕方でね、まだ明るい空を見上げたら何か飛んどるんですわ。最初はあれは飛行機かいなと思いましたね」 ・ところが行き過ぎたはずのその物体は、すぐに山蔭から姿を現し、戻るように移動する。 「あれ?これはやっぱり飛行機じゃねえの思いましたよ。今じゃUFOなんて言葉もありますけど、その頃は無いですけんねぇ」 奥出雲町には船通山という山がある。古事記によると、この麓にスサノオノミコトが降臨して八岐大蛇を退治した。古来より神の通り道だと信じる人も多い場所なのである。実際に船通山の頂上はほぼ平地で樹木も無い。恰好の離発着場のようにも見えるが、それが自然の姿なのか人為的なものなのかはよく分からない。 ちなみに、恩田さんが謎の飛行物体を見たのはこれ一度きりである。 <犬神家> ・四国で憑きモノといえば犬神が一般的だ。いわゆる狐憑きと同じような現象かと思っていたが、どうやらそうではないらしい。どこから来るのか分からない狐とは違い、その存在する場所(家)を誰もが知っているのだ。この点は秩父地方などのオサキ(オザキ、オサキ狐)と似ている。 『山怪』 山人が語る不思議な話 田中康弘 山と渓谷社 2015/6/16 <狐と神隠し> ・秋山郷は新潟県と長野県を跨ぐ古い集落だ。江戸末期から明治期にかけて阿仁マタギが数人住みついた山里でもある。中津川を挟んだ急峻な地形で、日本有数の豪雪地帯だ。それ故に稲作が始まったのは明治に入ってから。それもごくわずかな生産量で、つい近年まで焼き畑で雑穀類を作り、それと栃の実を混ぜ合わせた“あんぼ”を主食にしていた。そんな秋山郷で阿仁マタギの末裔という人に話を聞いた。 「私は特に不思議な体験をしたことなどねえすなあ……う〜ん子供がいなくなった話くらいかな」 それは今から50年ほど前のことだ。ある夫婦が農作業のために山へと入っていった。前述したように、この辺りは焼き畑農法で耕地は山の斜面である。 夫婦は4歳の一人娘をいつものように山の畑へと連れて行った。 ・今日中にここの畑を終わらせようと、午後はいつも以上に精を出して働いた。途中で娘の様子が気になり顔を上げたが、姿が見えない。辺りにいるはずだが、いくら名前を呼んでも返事はなかった。 集落が大騒ぎになったのは、血相変えて夫婦が山から降りてきて間もなくだった。母親は泣き叫び半狂乱状態、父親も顔色が失せていた。 「急にいなくなったか………神隠しでなきゃええが」 急遽捜索隊が組まれ、畑に近い山を中心に多くの人が探し回ったのである。しかし、いくら探してもどこにもその姿が無かった。少しずつ傾く太陽に誰もが焦り始めていた。夜になると危ない。みんながそう感じ始めた時である。 「帰ってきた、帰ってきたぞ」 その声に皆が駆け寄ってきた。真っ先に駆けつけた夫婦の喜びようは、それは凄いものだった。娘を見つけたのは奥山に木材の切り出しに入っていた男である。どこで娘を見つけたのかを話し始めると、全員が言葉を失った。 「いや、おらの作業場から帰る途中になあ、ちょっと開けた所があっただろう」 誰もが知っている場所だった。奥山の入口だが、なぜか平地があって、狐が出るとか天狗が出るとか言われている場所だ。 「そこの大岩の上にちょこんって座ってニコニコしてたんだぁ」 その大岩は大人でも登るのに骨が折れる大きさなのだ。その上に4歳の子が一人で上がれるとは思えない。いやそれ以前に、その平地まで子供が行ける訳がなかった。 <道の向こうに> ・マタギや猟師たちは、山を縦横無尽に動き回りながら獲物を追いつめる。地元の山を知り尽くした達人であるが、やはり不思議な空間に時々迷い込むことがあるようだ。 兵庫県朝来市の吉井あゆみさんは、確定申告の職業欄に猟師と書き込むくらいの実績の持ち主だ。小学生の頃から猟師である父と山に入り経験を積んできたベテランでもある。その吉井さんに聞いた話だ。 ・「どうも抜けた(逃げられた)みたいでマチ解除いうことになったんですわ。それで、いったん集合して次をどうするか話をしようと言うんで、みんな戻ることになったんです」 その時、山の上で待機していた一人の猟師が妙なことを言い出した。 「あれ?こんなところに道があるわ。こっちに行くと近いんちゃうか、俺こっちから行くわ」それを全員が無線で聞いていた。吉井さんもそれを聞いて首を捻った。 「道?あんな所に道なんかあったやろか」他の仲間も不審に思ったらしく尋ねる。 「道って?そこに道があんのか?」 「うん、あるよ。真っすぐで綺麗な道が出来とる。これ絶対近道や。白くて新しい道や」 これを聞いて全員が思った。それは変だ、そんな所に真っすぐな道などあるはずがない。「おい、その道、絶対行ったらあかんぞ。おい、おい」 無線はそこで途切れてしまった。それ以上どうすることも出来ず、仲間たちは集合場所へと降りていった。 ・最初のうちは笑い話で片づけていたが、その彼は一向に集合場所に現れない。1時間ほど待ったが、さすがにおかしいと誰もが思い始めた。 ・姿を見せた彼はボロボロだった。帽子は無くなり顔中傷だらけ。全身泥だらけで、藪漕ぎしながらも何度も滑り落ちたのは誰の目にも明らかだった。 「お前どこ行っとったんや」みんなは怒り気味で聞いたが、彼は少し惚けたような顔でいった。 「それがよう分からんのや。何でわしここにおるんやろ」 ・吉井さんはかなり不思議な体験をする体質らしい。そんな吉井さんの話を続ける。 「山から帰る時のことなんです。ちょっと遅くなって、もう周りが暗くなっとったんですよ。そこで小人に遭ったんです」 「小人?ですか、白雪姫に出てくるみたいな?」「そうです、あんな感じです」それは吉井さんが暗くなった林道を走っていた時のことだ。ぐねぐねと曲がりくねった道は、車のライトがあたる所だけが闇に浮かび上がる。そんな状況下で急なカーブを曲がると、明るく照らされた山際に何かが立っていた。 「何やろ、思うてよう見たら小人なんです。5、60センチくらいでしたね。それがこっちをじーっと見てるんですわ」 思わずブレーキを踏むと運転席でしばらく小人と見つめ合った。ほんの数分か、はたまた数秒か定かではないが、睨めっこに飽きたのか小人はぴょいと山へ姿を消したのである。 ・「いや凄いもんに遭ったなあ思うたんやけど、誰も信じひんのですよ」 小人に遭った話は、誰にしても馬鹿にされるだけである。悔しくてしょうがない吉井さんは、助手席にカメラを常に置くことにした。これで小人の写真を撮ればみんな信じるはずだと考えたのである。それからしばらくは、夜の山で何ごとも起きなかった。しかしついにその日がやってきた。 「また夜林道を走ってたら出たんですわ、あれが」 前回と同じく、暗闇の中にライトで照らされた小人の姿があった。吉井さんはかねての計画通りに車を止めると、静かに助手席のカメラに手を伸ばす。そしてドアを開けて外へ出ようとした瞬間、小人はぴょいと森へ姿を消したのである。残念がる吉井さん、しかしそれ以降、謎の小人が吉井さんの前に姿を現すことは無かった。 <山塊に蠢くもの> ・山形県は南に飯豊連峰、北に朝日連峰という山塊を持つ。それぞれに阿仁マタギの文化が残る集落がある。小国町の小玉川地区と鶴岡市の旧朝日村地区だ。 小玉川地区の前田俊治さんは最近Uターンで戻って来て、現在は地区のマタギ交流館などで働いている。前田さんのお父さんは地区を代表する名物マタギだった。 ・小国の各集落は、飯豊連峰から流れ下る玉川に沿って点在する。藤田さんが住んでいる地区から下った所にある新田地区で、半世紀ほど前にあった話である。 その日、山仕事を終えて父親が帰ってくると家の近所が騒がしかった。何ごとかと集まった人たちに尋ねると、4歳になる我が娘がいなくなったと言うではないか。畑仕事をしている母親のすぐそばにいたはずなのに、それが忽然と姿を消したのだ。 「そんな遠くに行ってねえ。空が明るいうちに探すべ」 涙に暮れる母親を待たせて集落の者が一斉に探し始めたが……。 ・「それがなかなか見つからねえんだ。いなくなった時間からしても近くにはいるはずなんだ、川に流されでもしてなきゃ」 時間が経てば経つほどに最悪の事態が皆の頭をよぎる。すっかり暗くなった集落は重苦しい空気に覆われていた。 「そうしたらよ、川さ探しにいった連中が子供を見つけたんだ。それがな信じられない所にいたんだと」 彼女が見つかったのは向こう岸の森だった。そこに行くためには丸太を渡しただけの一本橋があるだけで、大人でも渡れない人がいたくらいの場所だ。そこへまだ足元のおぼつかない女の子が一人で行くとは到底考えられない。皆は口々にこう言った。 「ああ、こりゃあ狐に連れて行かれたんだべなあ」 ・上流部でもほぼ同じ時期に同様の出来事があった。新田で行方不明になった子と歳も近いその女の子は、少し変わったことを言う子供だった。 「私の後ろには狐がいるんだよ」 それを口癖のように言う女の子は両親が仕事で毎日忙しく、自身は寂しい想いをしていたようである。 その子が突然集落から姿を消した。やはり集落中が大騒ぎになって山狩りまでしたが、女の子の姿はようとして見つからなかった。 「そこでな、法院様にお頼みして、その子の居場所を探してもらったんだぁ」 法院様とは山伏、修験者のことである。その法院様は印を結び呪文を唱え、女の子の行方を占った。 「法院様が言われたのは水辺だったんだ。その特徴から多分あそこだべって探しにいったら、いたんだよ、そこに」 暗い森の沢筋で、その子が恐がりもせずに佇んでいた。両親が留守がちで寂しがっていたその子のために、きっと狐が相手をしたのだろうと集落の人は思った。これは50年ほど前の出来事である。 ・小国の小玉川で最も有名な狐話を一つ。 ある人がゼンマイ採りに山へ入ったが、夕方になっても帰ってこない。心配した集落の人が山へ探しに行くと、その人は集落からさほど離れていない場所ですぐ見つかった。 「それがなあ、葉っぱさ山ほど集めていたのよ。本人はそれを布団にして、もう寝るつもりだったらしいんだ」 狐に化かされてどこかの家で布団に入ろうとしていたのかと思いきや、 「いやそうではねえ、とんでもない所さ迷い込んで、諦めて野宿しようと葉っぱを集めてたんだぁ。すぐそこの山でな。やっぱり狐に化かされたんだべ」 <巨大すぎる狐火> ・福島県の只見町は、阿仁から移り住んだマタギたちが狩猟の技術を伝えた所である。そこで林業系の会社を経営する渡部民夫さんは、40年に及ぶ猟暦を誇るベテランである。その渡部さんに聞いた話。 「狐ですか?確かにそんな話はよく聞きますねえ。婆ちゃんがぐるぐる同じ所を歩き回って家に帰れなかった話はありますよ。山の中じゃないですよ、すぐそこです。集落の中でね。狐火は知らないなあ、見たこともないですねえ」 渡部さんも一人でかなりの奥山まで入る人だが、怖いとか不思議だと感じることはあまりないという。 ・先に狐火は見たことがないと言った渡部さんだが、実はもっととんでもないものに遭遇している。 「あれは入広瀬のほうから真夜中に戻ってくる時でしたねえ。午前2時頃に田子倉ダムの上のほうの峠があるでしょ。あそこの所を通りかかった時なんです」 季節は真夏の頃である。すっかり帰りが遅くなって真っ黒な山道を走っていると、渡部さんは妙な光景に出くわした。 「ちょうど左に大きな山が見えるんですが、そこに光が見えたんですよ。狐火?いやそんなもんじゃないんです。山の斜面が光ってるんですよ。大きさは2百メートル以上あったでしょうねえ」 バレーボール大の狐火とは桁違いの大きさだ。季節は真夏で蛍もいるが、それほどの広さで山に群れるとは思えない。 「あれは何だったんでしょうねえ?やっぱりUFOなのかな」 さすがの渡部さんも、これはまったく分からないらしい。 只見町の猟師は現在危機的な状況にある。2011年の原発事故以降、熊肉の食用や流通が禁じられているからだ。 <天川村の事件> ・奈良県天川村は吉野町から少しばかり南下した山村である。すぐそばに2千メートル近い山があり、冬場はかなりの積雪地帯だ。歴史は古く、役行者(役小角)が修験道を開いた地として知られている。その中心地である大峰山登山道の入口には未だに女人結界門があり、ここが修行の場であることを物語る。霊場でもあり、日本のみならず世界中からもスピリチュアル系の人々が多々訪れるそうだ。 ・近所で遊んでいた男の子がふいに姿を消したこともある。集落は当然大騒ぎになり、近辺をくまなくさがしたが二人の姿は見つからない。夜になっても帰ってこず、誰もが不安を抱えたまま夜明けを持った。翌日はさらに大がかりに捜索をしたが結局見つからず、諦めの気持ちすら漂い始めた。 「2日2晩戻ってこんで、3日目にかなりの山奥で見つかったんです。信じられんような所ですよ。なぜにあないなところまで行きよったんか………あれも狐やろ思いますねえ」 ・山菜採りに出掛けた爺ちゃんが行方不明になることも珍しくはない。単なる迷子だとは思うが、やはり地元の人は狐のせいだと感じるようだ。探す時の叫び声が何とも興味深い。 「かやせ〜、かやせ〜」 かやせ、つまり返せと集落の人々に叫びながら探すのだ。いったい誰に向かって、何に向かってかやせと言っているのだろうか。 <妖怪と山怪> ・山の不思議な出来事で一番多かったのは、やはり狐に関してだ。全国すべてを緻密に取材した訳ではないが、西に行くほど狐の影響力は薄れる感じがする。それに反して、雪深い北東北が狐話は格段に多い。定番の池沼にはまり込む話から何かを盗まれる話、果ては死に至る話までのほとんどに狐が絡む。 <怪異探しは“砂漠の井戸掘り”> ・この本で探し求めたのは、決して怖い話や怪談の類いではない。言い伝えや昔話。そして民話でもない。はっきりとはしないが、何か妙である。または不思議であるという出来事だ。 これが何とも説明しづらい内容で、取材依頼が実は最も大変な作業となったのである。知り合いの猟師やマタギ、またはその関係者に話を聞くのはさほど難しいことではない。しかし、まったく無縁の地域で取材するのは骨が折れた。 猟師関係には役所の農林課から猟友会に話を通してもらったり、または地域振興班や教育委員会から地元の方を紹介してもらう。この時に細かく説明をしても分かってもらえず、企画書を送っても結局民話の語り部を紹介されたりと、ちぐはぐな対応は珍しくなかった。対策としてなるべく地元の民宿に泊まって話を聞いたり、そこから人を紹介してもらったりと、ジタバタを繰り返しながらの取材である。それでも動けば動くほどに何らかの話は聞けたから、行動としてはあながち間違っていなかったのだろう。 『実録 自衛隊パイロットたちが接近遭遇したUFO』 佐藤守 元自衛隊空将・南西航空混成団司令 講談社 2010/7/22 <なぜ自衛隊でUFOはタブーなのか> ・ただ単に、「UFOなどという非科学的なものを見たというような人物は精神的にどこかおかしい」とする観念に国や自衛隊のトップが囚われていて、UFOの目撃は非現実的な錯覚だと決め付けているのです。 <自衛隊パイロットが接近遭遇したUFO> <「こんな問題には深入りしないほうがいい」> ・UFOに遭遇したなどというと、精神異常を疑われかねません。精神的におかしくなった人間を任務に就かせるわけにはいかないので、パイロットを辞めることになるか、最悪、自衛官の職を失うことになりかねないのです。 これは民間航空会社の話ですが、実際、UFOを見たと週刊誌に喋ったパイロットが、精神状態がおかしいとされて、飛行停止になったという事件が、ずいぶん昔にありました。 <UFOとともに発生した機体異常> ・しかし、三陸沖の飛行物体には翼がなく、葉巻型で変則的な飛行をしている。どう見ても民間航空機ではないという結論に達したそうです。 ・この一件は当時の松島基地では有名な話で、誰も口には出さなかったものの、皆が知っていた「UFO騒動」でした。 ・「航空自衛隊でUFO目撃が相次いでいる」などというと、「航空自衛官はなんと非科学的な人たちばかりなのか」と誤解する方もいらっしゃるかもしれません。 <UFOが見える人、見えない人> ・UFOを頻繁に見る人もいれば、私のようにパイロットを長年務めていても、一度も目撃できない人間もいます。 <それは超高速で飛んでいた> ・今回取材したなかで、UFOの最多目撃回数を誇ったのは船附昇元三佐でした。彼は候補生時代から、築城基地で、私と共に飛んでいた信頼できる人物ですが、松島基地でT-2練習機の教官を務めていたときの彼の体験です。 ・船附の証言によると、スピ―ドは地上では想像できない速さで、マッハ8〜10ぐらい。高度は恐らく6万フィート(約18キロ)。 ・当時の同僚Sが、入間から西に向かっているとき、名古屋上空で物凄く大きな葉巻型のUFOを発見しました。高度は2万4000フィートだったそうですが、「こんなに大きな物体が空中に浮かべるのか!?」と驚いたくらい巨大だったそうです。 <シンガポールでも遭遇したUFO> ・船附元三佐はよほどUFOと縁があるらしく、退官して民間航空会社にパイロットとして再就職した後も、UFOらしき飛行物体に遭遇しています。 ・船附によると民間航空機のパイロットたちもたびたびUFOに遭遇しているといいます。 <UFOの故郷、福島の千貫森> ・こうした数々の証言から自衛官がUFOを頻繁に目撃する地域は、関東以北が多いということがわかりました。 UFO伝説が盛んに囁かれているのも東北地方です。たとえば、福島県。福島にはUFOが頻繁に飛来することで有名な場所があります。 私の両親の故郷と近い福島県福島市飯野町一帯などです。飯野町は「千貫森」という山のふもとにあり、千貫森では数多くのUFO目撃例が報告されているのです。 ・霊力に引き寄せられるのでしょうか。霊山付近にはUFOがたびたび訪れるそうで、実際、目撃した地元の人も多く、最近ではテレビでも紹介されているようです。 飯野町ではUFOを町おこしに活用しようと考えたのでしょう。霊山に向かう途中の飯野町青木に、「UFOふれあい館」なる施設がつくられています。私は両親の墓参りの際に偶然、「UFOふれあい館」に出会い、ここがUFOの名所だと知りました。 ・興味を持った私が、土地の人々にUFOについて尋ねると、笑いながら曖昧な答えしか返してこなかった人がいる一方で、「昔からUFOがよく出る場所だ」と淡々と話す人もいました。 ・「千貫森」が古来UFOの里といわれているのは、この山自体がコンパスの針を狂わせるほどの強力な電磁波を出しているからだそうです。 <キリストの墓とUFOの関係> ・青森県にはUFO伝説や宇宙人の飛来を連想させる話も多いのです。その一つに三沢基地の南西にある戸来村(現在は青森県三戸郡新郷村大字戸来)に関する伝説があります。戸来村は、その昔キリストの兄弟が住んでいて、その墓があるというので有名になったところです。 <日本にもピラミッドがあったのか> ・注目すべきは戸来村周辺に人工的とも思えるような、きれいなピラミッド型の山が並んでいるという事実です。 ・地元を訪れると、「UFOがその特殊な山を目標によく飛来してきていた」と語ってくれた人もいました。今でもUFOはよく姿を現すそうです。 私が青森県内各地を回ってみて、この地の宇宙人伝説、UFO神話に関して一番信憑性が高いと思ったのは、津軽半島の付け根付近にある青森県のつがる市木造の亀ヶ岡遺跡周辺です。 ・ここでは、有名な縄文時代の「遮光器土偶」も発見されています。この地で発掘された遮光器土偶は、当時の技術では制作できないだろうというほどの高温で焼かれた土偶。土地の専門家の話では「1000度以上のコークスでしか焼けない土偶」だそうです。 もちろん、土偶が盛んに作られた時代、そんな高度な技術は東北地方のみならず、地球上のどこにもなかったでしょうから、これはやはり宇宙人が作ったものではないか?というのです。 <古代の技術では焼けないはずの遮光器土偶> <地球外生物の空港> ・いずれにせよ、環状列石や人工山、電磁波の関係を考えれば、遮光器土偶は亀ヶ岡遺跡近辺の「環状列石空港」に「着陸」した宇宙船から移民してきた宇宙人作であるという説も、あながち否定できなくなるかもしれません。 <異星人に救われたパイロット> <かぐや姫と日本人の「宇宙人観」> ・日本人の宇宙人伝説ともいえる天女物語には、様々なストーリーがありますが、いくつか共通点があります。 最大の共通点は、天女はみなこの世の存在とも思えないほどの美女ということです。そして、空を翔るための羽衣をまとっています。天女は、最後には天へと帰っていくという結末も似ています。 ・たとえば、有名な謡曲『羽衣』の三保の松原の天女物語は、天女が水浴びをしている間に羽衣を盗まれて天に帰ることができなくなり、渋々その羽衣を盗んだ漁師と結婚して子供をもうけるのですが、やがて羽衣のありかがわかり、子供を残して天に帰っていく、という筋書きです。 ・また、沖縄の宜野湾市に伝わる天女物語も、 「昔、大親という百姓が畑から帰る途中、今の宜野湾市にある森の川という泉で手足を洗っていると、一人の美女が沐浴していた。大親は都から来た女だと思い近寄って衣を盗む。女は自分が天女であることを告げ、衣を探してほしいというので、大親は騙して自分の女房にする。やがて二人の間に一男一女が生まれる。 ある日、姉が弟の子守をしながら『母さんの衣は六柱の倉にある、母さんの舞衣は八柱の倉のなか』と歌うのを天女が聞き、衣を見つけて天に舞い上がる。天女は子供や夫と別れるのが辛く、何度も行ったり来たりしていたが、意を決してとうとう飛び去った。そして残された子供が後の察度で、やがて王となった」というものです。 <奇怪な墜落事故> ・私は、UFO目撃情報が集中する松島基地近辺には、東北電力の女川原子力発電所があり、だからこそ自衛隊パイロットが頻繁にUFOと遭遇するのではないかと考えています。 <予言されていた2件の事故> ・Sさんは、私が松島基地司令時代に知り合った地元の方です。石巻の山中に神社を創設して、そこの神主さんも兼務しています。地元では「超能力者」として知られている方。 ・すぐにSさんに電話すると、「済んだことは仕方がない。問題は7月4日にもブルーインパルスの2機が墜落して3人が死ぬから、これを止めないといけない」というのです。 ・――それから、1ヵ月余り過ぎた7月4日、予言どおりに事故は起きた。 <UFOが原発を回避させたのか> ・この周辺にはUFOが飛来するということを地元の人たちは古くからよく知っています。 ・その真偽は定かではありませんが、多くの自衛隊パイロットたちが、松島基地でUFOを目撃しているのは事実です。「UFOに愛された」船附元三佐も、秋の総合演習時に、基地上空に丸い点がぽつんと浮かんでいたといっています。 先述のジョンソン博士も「UFOの背後に存在する知性体が核兵器や原発に関心を示していると推測できなくもない」としていますから、案外、いつも基地上空で訓練を眺めているUFOは、チェルノブイリ同様、女川原発事故を防いでくれたのかもしれません。 <自衛隊機墜落とサリン事件を予言した人物> ・Sさんの答えは実に明瞭でした。まず事故の原因ですが、 「旧日本軍や自衛隊の戦死者や殉難者に対する供養は実に大切なことであり、松島基地周辺には、旧海軍時代からの多くの英霊たちが眠っているが、供養を怠ると英霊たちの加護が弱まり、霊的な乱れや邪気が生じ、その影響で事故に至る。今回もその一例であった。その危険を私に知らせてくれたのはUFOである」というのです。 ・「大きな事件か事故が起きる直前に、なぜかUFOが現れて私に知らせるのだ」 ・そして、彼が松島基地周辺でよく見かけるUFOまでスケッチしてくれました。 私は今回、これを書くためにUFOに関する資料を濫読しましたから、Sさんが自ら描いて送ってくれたUFOのスケッチを見ても驚きませんが、読者の皆さんはきっと驚いたことでしょう。 こんなものが四六時中、松島基地上空を飛んでいたわけです。しかも、私には見えず、船附元三佐や一部の部下たちにはよく見えていたというのですから、いささか癪に障ります。 そこで私は、「松島基地上空に来るのは円盤型だけですか?」と聞いてみました。 ・もちろん、Sさんにはそのことを黙っていたのですが、彼は「かなり昔に、T-2の編隊飛行か? と思ってみていたが、後ろの物体がやけに長い。射撃の標的を引っ張っているのかな、と思ってよく見ると、T-2の長さの3倍近くある葉巻型のUFOだったことがあった」といったので驚きました。私はやはりM一尉とG一尉が見た「葉巻型UFO」は本当だったのだ、と感じました。 ・こうなると何だか神主を務めるSさん本人が宇宙人ではないのかと疑いたくなります。 ハリー・古山氏が『私が出会った宇宙人たち』という本を書いていますが、それによると、地球上にはかなり多くの宇宙人が「同化」して住んでいるそうですから、案外当たっているかもしれません。すると、UFOに愛された船附元三佐が長崎の喫茶店で会った店長も、宇宙人だったのかもしれません……。 ・というのは、私事で恐縮ですが、私は三沢に転勤する前年の7月に義父を失い、その4ヵ月後に今度は義母が他界するという不幸に見舞われただけでなく、義母が死の直前に、ベッドの上で「幽界」の話を始めたという不思議な体験があるからです。 あのときのことは今もくっきり脳裏に刻まれています。 ベッドに横たわって点滴を受けていた義母が、突然私たち夫婦に向かって、「そこにもう一人私がいるでしょう?」と足元の病室の壁を指しながら語りかけたのですから。 普段と変わらない語りかけでしたから、私と家内はつられて壁を見たのですが何も見えません。続いて義母は私たちにはっきりとこういった 「これは私の幽体なのよ」と。 そして突然、大声を張り上げました。点滴針が刺さった腕で何かを払う仕草をしながら。「だめ! まだ行かない!」 義母には何かが見えていたのでしょう。が、私たちには見えません。私は驚いて、ゆれている点滴袋を止めるのが精一杯でした。 その後、しばらく何かつぶやいていた義母は昏睡状態に陥り、家内はこの時点で母の死を覚悟したようです、義母が息を引き取ったのは翌早朝です。奇しくも義父の納骨の日でした。 あとになってから、「あのとき、きっと母の元に、あの世からお迎えが来ていたのだわ」と家内は振り返っていました。そのとき、私はこの世には見えない世界があることを悟ったのです。 <●●インターネット情報から●●> UFOの里 福島県の中通り北部、県都福島市の南西部に位置する飯野町地区、ここはUFOの里として広く知られています。 飯野町地区北部に位置する千貫森周辺には、古来から多数の発光物体の目撃例が見られました。 また千貫森自体も謎多き山であり、その周辺にも多くのミステリーゾーンが存在する事が知られています。 そういった数々の謎の研究資料や、UFOやその他のミステリーに関わる資料を集め、展示する施設として1992年に開館したのがUFOふれあい館です。 その後パノラマ食堂(UFO物産館)、UFO広場等周辺環境も整備され、古くからある小手神社や謎の巨石群と合わせて一大ミステリー体験ゾーンを形成しています。 ウィキペディアWikipedia(フリー百科事典)から <福島市飯野UFOふれあい館> 福島市飯野UFOふれあい館(ふくしましいいのユーフォーふれあいかん)は、福島県福島市飯野町青木にあるUFO関係の書籍、資料などを集めた、全国的にも珍しい展示館兼多目的公共施設である。 (概要) UFO専門の施設は国内的にも珍しく、UFO関係のビデオや写真等の資料をおよそ3000点所蔵している。この施設のある福島市飯野地域はUFOの目撃例が多く、シンボルの千貫森と共にUFOの里として知られている。 1992年11月に開館。2008年7月1日の伊達郡飯野町の福島市への編入合併に伴い、いいのまちUFOふれあい館から改称した。 この施設は、ニンゲンBOX、1億人の大質問!?笑ってコラえて!、天才てれびくん、ひるどき日本列島、24CH△NNEL、月曜から夜ふかし、などで紹介されたことがある。 『深宇宙探訪記』 (オスカー・マゴッチ)(加速学園) (発売 星雲社)1992/11 <葉巻型の宇宙船は世界各地で目撃談が多い大型の宇宙船> ・中型船内宇宙研究室(連盟登録番号 SLA8701) 宇宙研究用の移動研究室。12の異なる世界を展示。多種族の乗組員と科学者が搭乗。総搭乗員数3000『人』 全長2400m。直径約400m(厚さ約188mの単独航行可能モジュール18基で構成) <宇宙研究室の外観> ・各モジュールは、居住者の便宜を考え、それぞれの貫通路に沿って観測窓が、一つずつ付いている(実際には大型の展望用球体で、拡大機能および夜間赤外線利用暗視機能がある。) <種々のUFO> ・『帝国同盟』の三角形をした地球外の戦闘機。『悪魔機』として知られている。 ・7機の円盤を収容できる中型円盤型母船。直径100m。高さ40m。 ・偵察型の円盤(直径25m。高さ10m) ・幽霊船(およそ、長さ40m、幅10m) 本船が生きている存在で、固体の固い金属構造物ではない。準バイオニック船である。 ・ダイヤモンド型エーテル船(高さ12m、幅12m) <『深宇宙探訪記』に書かれてある中型船内宇宙研究室は、葉巻型UFO> ・宇宙研究用の移動研究室は、搭乗員が3000人で、全長2400メートル、直径400メートルで長さ122メートルの単独航行可能なモジュール18基で構成されているようです。そして、バミューダ三角海域の次元間移行ゾーンを利用しています。これが、有名な葉巻型のUFOのように思われますが、大きさから考えると世界中で見られているのとは違うかもしれません。 ・オスカー・マゴッチの本によると「シリウスは連盟の送信センターである。暗黒の勢力とその地球の光明派の召使達はシリウスから来た善玉になりすましている。暗黒の勢力は、自分達の基地は、オリオン大星雲にあると、私達に思い込ませようとしている。 しかし、彼らはそこからやって来たにすぎない。オリオン座は、光の主たちの故郷であり、銀河系委員会の故郷であるのだ。そしてアルクトゥルスを中継基地に使っている。暗黒の勢力と彼らが支配する悪の帝国の本拠地は、大熊座にあり、ドラコニスを主要作戦センターとしている。宇宙連合の宇宙人は、友好的な善意の宇宙人であるが、惑星連合や地底連合の宇宙人は、邪悪な宇宙人である」 <アメリカ政府と宇宙人の契約> ・1947年7月2日ニューメキシコ州ロズウェルでUFO墜落事件が起きた。だが、米軍は、気球の墜落だと発表し、事実を偽装した。奇妙なことに1949年1月30日同じロズゥエルで、UFO墜落事件がおき、その際、偶然にも地球外生命体が1名生存しており、ロスアラモス研究所に送られた。その地球外生命体は、「イーバ」と名づけられ、1952年6月18日まで生きた。その間の調査では、イーバは自らの母星が、地球から55光年離れたところにあると告げたという。 ・彼の身体的外観は、現在多くの人に知られるところとなった「グレイ」に似ており、爬虫類と昆虫の特徴を持っていた。そして、1954年1月、アメリカは、後に「ラージ・ノーズ・グレイ」と呼ばれるようになる地球外生命体と初コンタクトを行なう。この地球外生命体の出自は、オリオン座のペテルギウスを巡る一つの惑星だった。これは、500光年離れた赤色巨星を巡る惑星からやってきた事になる。 ・1954年2月。ラージ・ノーズ・グレイの代理として、イーバそっくりの「クリル」と名づけられた地球外生命体が再度地球人とのコンタクトのため送り込まれ、この時、アイゼンハワー大統領が統括していたアメリカ政府は、この「クリル」を全権大使とした「オリオン座領域から来訪した」地球外生命体と何らかの契約を結んだと言われている。「それから50年、国家最高機密は、厳重に守られている」。 <ハリウッド映画で有名なグレイは、人類に比べ科学力で優に5万年を先んじている> ・Tシャツのプリントになるほど、スター化した地球外生命体の「グレイ」のルーツは、琴座である。約50年前、かって琴座領域にあったアペックスと呼ばれる惑星で核戦争が起き、生き残ったアペックスの人々は地下生活を余儀なくされた。核戦争を引き起こした2つの勢力は、ポジティブ派が、主として、レチクル座の2重星(ゼータ)付近を拠点としているが、ネガティブ派のほうは、その多くがオリオン座のペテルギウス領域や大犬座のシリウス領域に移住した。 ・ネガティブ派の中で特にオリオンに拠点を置く者たちは、リゲリアンという種族だが、地球でグレイと呼ばれる存在は、このリゲリアンを指している。リゲリアンという呼称そのものは、ケンタウルス座のα星であるリギル・ケンタウルスにも隠れたつながりがあるが、彼らのルーツには、判然としない部分がある。現在、地球には、惑星アペックスに出自を持つ地球外生命体が、時空を超え、過去、現在、未来の次元から同時に訪れている。 <ウォーク・インとワンダラー(スターピープル、スターシード、スターライト)> ・地球人に生まれ変わったワンダラーや、人生の途中で地球外の魂と劇的なソウル・チェンジ(魂の変換)を起こしたウォーク・インなどを地球外生命体(ET)の魂を持つという意味で、ETソウルと呼んでいる。ウォーク・インやワンダラーは、白色同胞団でも活躍している。白色同胞団(ホワイト・ブラザーズ・フッド)のルーツは、プレアデスと同じ牡牛座のアルデバランという説と、火星でアルデバランの人々と共存していたさそり座のアンタレスからの人々だという説がある。 ・また、チャネリングは、日常ではない別次元の意識やいわゆる地球外生命体と意識のレベルで交信することを言います。シリウス経由のチャネリングによりますと、地球に介入した2種類の生命体があると語ります。約2600万年前、地球に2種類の非人間的生命体が入植した。それらは、射手座星系からやって来た爬虫類的存在とオリオンのベラトリックス星系からの恐竜的存在だったという。 ・ここで言う爬虫類と恐竜は生物学的に分類されるそれらの意味とは異なる。そして、地球ではこの2種類の生命体が入り込んだ後に、人間の祖となる哺乳類的生命体が現れる。 『金正日は日本人だった』 佐藤守(元自衛隊空将) 講談社 2009/10/28 <日本を愛す将軍様> ・そして<かちかちのサンマをほおばりながら、「百年の宿敵」であるはずの日本の庶民料理が、とにもかくにも平壌のど真ん中で食べられるのは、なんとも不思議な感じがしたものだった。いま思えば、金正日が無頼の和食通だったのである>との感想を持った。 これまた、金正日の和食好きを表しているエピソードである。 <人民軍の大将たちの愛唱歌は「ラバウル小唄」> ・将軍が愛する日本のものは食べ物だけではない。 金正日の愛車はトヨタのセンチュリーだという。当然ながら安全性には細心の注意が払われており、防弾ガラス、鉄板も普通の市販車に比べると分厚い改造車で、藤本氏によると、ドアはことのほか重かったらしい。 ・藤本氏は、宴会場には必ず「カラオケセット」があり、日本の歌もよくうたわれたという。 ・演歌だけではなく、宴会で軍の大将が酔っ払うと、どういうわけか日本の軍歌を歌っていた。 ・藤本氏の証言では、金正日が執務室で使っていたのも、NECのパソコンだったらしい。金正日には毎日500〜1000件の報告が届く。報告はFAXとメールが主で、金正日はその処理のために、早くからNECのパソコンを導入していたという。 これらの物資のほとんどは、日本から万景峰号で運ばれたものだろうが、日朝間がいかに「太いパイプ」で密接に繋がっているかという証明でもあろう。 ・なぜ、日本のアーティストを将軍がご存じなのか。私は北朝鮮内部にも情報網をめぐらせている知人から、「実は、金正日は日本の衛星放送を好んで見ている」という話を聞いたことがある。そのとき非常に印象深かったのは、彼が「一番好きな番組は皇室関係の番組らしい」と語っていたことである。 天皇制と金王朝の関係を示唆する重要な証言だが、それはさておき、藤本氏の著書が伝える金正日の姿は、まるで親日家である。元在日の妻を寵愛し、日本人の料理人を傍に置き、和食に舌鼓を打つ。日本のテレビ番組を好んで観るし、移動はトヨタのセンチュリー。ときには日本の芸能人のショーを楽しむ。親日家を超えて「愛日家」という印象さえ受けるのだ。 <30年近く前に来日していた金正日> ・いや、それどころか、金正日は何度も来日しているという説を唱える専門家もいる。あまりにも突拍子もないので、大半の人が信じられないだろうが、そう主張しているのが、あの北朝鮮の専門家、早稲田大学国際教養学部教授の重村智計氏だと知れば、私でなくとも興味が湧くはずである。 重村氏は元毎日新聞記者で、30年以上、北朝鮮に関して取材を続けてきた。その取材のなかで、それまで書かなかった事実を、『金正日の正体』(講談社現代新書)と題して2008年に出版した。 その書には、金正日の影武者の存在など、驚くべき事実が、確かな裏づけに基づいて明らかにされているのだが、私が最も興味を持ったのは、<将軍様は82年から東京に遊びに来ていた>というくだりである。 重村氏はあるとき、衝撃的な内容の本に出合った。タイトルは『人生は、ショータイム』(ブックマン社)。著者は日本有数のダンスの振付師、小井戸秀宅氏で、2004年5月に上梓された本だった。題名だけを見れば、小井戸氏の振付師としての半生を綴っただけの本のように思えて、一般の人はほとんど関心を持たないだろうが、この書には度肝を抜かれるような事実が書かれていた。 ・若い方はご存じないだろうが、かつて東京・赤坂に伝説のレストランシアターがあった。「コルドンブルー」である。コルドンブルーが開店したのは1971年。約40年近くも前に、一人5万円の料金で、フランス料理のフルコースとレビューを楽しませる超のつく高級レストランシアター。フランスのル・モンド紙が「レストランシアターではフランスのクレイジーホースとジャポンのコルドンブルーが世界の雄」と絶賛するほど、その豪華なショーは評判が高かった。 ・この伝説のコルドンブルーで、ショーの振り付けを担当していたのが、小井戸氏だった。小井戸氏は『人生は、ショータイム』のなかで、北朝鮮の「喜び組」の踊りの振り付けは、コルドンブルーで彼がつけていた振り付けのパクリで、北朝鮮にはコルドンブルーのスタッフが呼ばれてつくった、まったく同じ舞台まであると明かしている。 これだけなら驚くに値しないが、続く記述に重村氏の目は釘付けになった。 <“喜び組”は、コルドンブルーを見た金正日が、『コルドンブルーと同じような女性ダンサーを育てたい』といって結成したものです。コルドンブルーは北朝鮮に文化輸出されました> <彼は芸能界、映画界に興味がありショービジネスも大好きで、お忍びで来て、コルドンブルーのショーを楽しんだのでしょう。日本のタレントのなかでもプリンセス天功にとくに興味があり、彼女のショーを見たのでしょう> ・金正日は来日し、コルドンブルーのショーを見て、すっかり気に入り、北朝鮮にコルドンブルーの舞台を再現し、「喜び組」にそっくり同じショーをやらせている。プリンセス天功のイリュージョンを見たのもコルドンブルーで、その後、彼女をたびたび招くようになったというのである。 しかも、小井戸氏は、1982年5月に金正日がコルドンブルーを訪れたときの写真まであるという。 ・それにしても、金正日のような有名人が来日すれば、すぐにばれて大騒ぎになってしまうのではないかと疑問を持つ方が数多くおられるかもしれない。だが、それは愚問だ。なぜなら、1982年当時、金正日の名は聞こえてきていても、顔は誰も知らなかったからだ。2009年の後継者騒ぎを思い出していただければわかりやすいだろう。 ・北の後継者として金正雲の名が取りざたされたとき、報道各社はその姿を写した写真を入手しようと奔走したが、テレビに映し出されたのは、先述の藤本健二氏が北朝鮮から持ち帰った、子供のころの写真でしかなかった。日本人は誰も現在の金正雲の顔がわからない。街で来日した金正雲とすれ違っても、誰一人気づかないはずだ。 ・1982年当時は、日本人はもちろん北朝鮮の人々も、金正日の顔など見たことはない。飛行機嫌いの金正日は万景峰号に乗船し、日本へやってきたといわれている。だが、将軍様が万景峰号に乗船して来日しても、北朝鮮の一般の乗客は、まさか偉大なる首領の後継ぎが自分たちと同じ船に乗っているとは思いもしない。 <北の指導者が赤坂に通い続けたわけ> ・なぜ、それほど熱心に金正日はコルドンブルーに通ったのか。プリンセス天功のショーが目当てだったのはたしかだが、重村氏は他にも重要な理由があったと分析している。 <金正男はなぜ密入国を企てたか> ・金正日が1970年代からたびたび訪日していたとすると、2001年5月1日の金正男事件も理解できる。 この日、「金正男氏と見られる男性」が、成田空港で入国管理局に拘束された。男は妻子を連れており、ドミニカ共和国の偽造パスポートを使用して入国をはかったところ、入国管理官に見抜かれ、拘束・収容された。 その際に、背中に虎の刺青が施されていることが判明し、金正男であることが、ほぼ確認された。ロイヤルファミリーの一員の身柄拘束は、北朝鮮から重要な人質を取ったに等しく、日本人拉致問題の解決の糸口になるのではという声も多くあがった。 ところが、外交問題に発展することを恐れた日本政府は、強制退去処分にし、金正男は5月4日、全日空機で中国に向け出国した。 『実録 自衛隊パイロットたちが目撃したUFO』 地球外生命は原発を見張っている 佐藤守 講談社 2014/11/20 <「貴様、頭でもおかしくなったのか」> ・ただ単に、「UFOなどという非科学的なものを見たというような人物は精神的にどこかおかしい」とする観念に国や自衛隊のトップが囚われていて、UFOの目撃は非現実的な錯覚だと決め付けているのです。私が危惧しているのは、こうした指導層のUFOに対する無関心です。 ・ところが今もって、自衛隊内部では、UFOを目撃したなどと報告しようものなら、「貴様、頭でもおかしくなったのか」と一蹴され、過去には正直に報告したがため、辛い目に遭った後輩もいます。 UFO問題は、かように日本の安全保障にもつながる重大問題であるにもかかわらず、民間でも「サイエンスフィクション」として興味本位に扱われるだけ。真正面から科学的に調査・分析するという姿勢がまったくといっていいほど見受けられません。 ・ただ、これだけはまちがいありません。彼らの話を総合し、かつ私自身の経験に照らし合わせてみると、「UFOは確実に実在する」と、自信を持って断言できます。 <UFOがたびたび目撃される基地> ・私が自衛官のUFO目撃談を集めてみると、ある傾向に気づきました。それは、不思議とUFO目撃談は、ある特定の基地に偏っているという事実、UFOの名所があるようなのです。 たとえば取材したなかで最も多かったのは、松島基地に関するレポートでした。 <アメリカからの強烈なコンタクト> ・UFOに関してはずぶの素人の私の問いかけに、これだけの目撃談が集まったのには驚きました。 「正体不明の飛行物体」に対処すべき任務を持つ防衛省・航空自衛隊が、今まで領空に侵入してくる対象は「他国の航空機」だけであるかのような感覚ではなく、レーダーに映った、またはパイロットが目撃した「正体不明物体」のデータも、いかがわしいと思うことなく素直に収集していれば、この五十余年の間に貴重な資料が集積でき、科学的根拠も整っていたに違いありません。 すでに北朝鮮のミサイルに備えなければならない事態が迫っているのですから、今までのような航空警戒レーダー網が「低速度目標」ばかりを意識していては、日本の空は守れません。 ・しかし、未だにUFOといえば、オカルトかSFのような感覚でしか捉えられていないようですし、わが政府の扱いも、麻生太郎氏の答弁からうかがえるように、サイエンスフィクション的発想に留まっています。これでは、第一線の部隊に「UFO関連情報」収集を義務付けるように求める日は、永遠にやって来ないのかもしれません。 しかし、私のUFOに対する調査に、信頼する部下たちから素直な体験談が寄せられたうえ、その後、私も家族とともにUFOを目撃することになったのですから、彼らの証言を簡単には否定することはできません。 ・ところが、資料を分析して一つ強く感じたことがあります。それは、現代日本人のUFOに対する姿勢に、排除または封じ込めようという風潮が蔓延している点です。 ・ところで、2010年に上梓した『実録 自衛隊パイロットたちが接近遭遇したUFO』を読んだ読者からは、本書に収録した以外にも多くのメッセージを賜りましたし、テレビや雑誌などからも取材を受けました。そのなかに、グレゴリー・サリバン氏という「ETコンタクト活動家」がいました。 ・名刺には「JCETI」、肩書は「ETコンタクト・コーディネーター」とあり、活動内容と経歴を聞くと、実に興味ある答えが返ってきました。「2003年ニューヨークを旅立ち、ニュージーランドに半年滞在、その後来日、日本が非常に気に入ったので現在は福岡を拠点に活動中」だというのです。 現在は、「地球外知的生命体(ETI)とコンタクトしながら、コンタクトのためのテクニックをナビゲートするセミナーなども交え、特別なスカイウォッチング『第5種接近遭遇』のイベントを全国で展開中」なのだそうです。 ・私の本を読んで、多くの自衛官たちがUFOを目撃したのはその第一歩であり、それは「第1種接近遭遇」段階だといいます。「第2種接近遭遇」段階は。「UFOをレーダーで記録すること」であり、「第3種接近遭遇」段階は「宇宙人を目撃すること」、「第4種接近遭遇」段階は「UFO船内で宇宙人とコミュニケーションを行うこと」であり、そして最後の「第5種接近遭遇」段階は、「人間から発信し、宇宙人と双方向のコミュニケーションを行うこと」――彼はそのナビゲートをしているというのですから、いつか私もコンタクトさせてくれるに違いありません。 ・3時間ほど楽しい会話が続き、時が経つのを忘れるほどでしたが、実に清潔感あふれる好青年で、彼こそ「地球外生命そのものではないか?」と想像を豊かにしたくらいです。 このときの彼との「遭遇」で得られた成果は、私に寄せられた多くの体験談の信憑性が確かめられたこと、「宇宙人=地球侵略者」という悪しきイメージは、「アメリカのメディアによって植えつけられた誤ったイメージ」であること、「宇宙人は常に地球、特に核エネルギーの未熟な扱い方について見守ってくれているのだ」ということ………。 ・結論は、UFOは物質ではなく、「光体やエネルギー体」であり、いろいろな「利権」に絡んでいる各国政府は、自己保存のためにその存在を隠蔽し続けてきたのだということでした。 ・本書は、2010年7月に講談社から発刊した『実録 自衛隊パイロットたちが接近遭遇したUFO』に新しく寄せられた情報を大幅に加筆、改題のうえ再編集したものです。 『実録 自衛隊パイロットたちが接近遭遇したUFO』 佐藤守 元自衛隊空将、南西航空混成団司令 講談社 2010年7月20日 <なぜ自衛隊でUFOはタブーなのか> ・私自身は、UFOを目撃したこともありませんし、いわゆるUFO信者でもありません。 ・「UFOなどという非科学的なものを見たというような人物は、精神的にどこかおかしい」とする観念に国や自衛隊のトップが囚われていて、UFOの目撃は非現実的な錯覚だと決め付けているのです。 <「貴様、頭でもおかしくなったのか」と一蹴される> ・誇大妄想狂という噂が立つ。精神異常を疑われかねません。 <自衛隊機墜落とサリン事件を予言した人物> ・ハリー・古山氏が『私が出会った宇宙人たち』という本を書いていますが、それによると、地球上にはかなり多くの宇宙人が「同化」して住んでいるそうですから、案外当たっているかもしれません。すると、UFOに愛された船附元三佐が長崎の喫茶店で会った店長も、宇宙人だったのかもしれません・・・。 <鳩山夫人の金星旅行の真実> ・一般に知られている、あのアーモンド形の目をした宇宙人は「グレイ」と呼ばれています。グレイには、体長1.2メートルほどで鼻は空気孔としてポツンと穴が空いている「リトルグレイ」と、体長は同じくらいでも鼻の大きな「ラージノーズグレイ」がいるとか。その他では、トカゲの顔を持つ爬虫類のような宇宙人、さらには人間と同じ姿をした異星人もいるといいます。 人間型の宇宙人は、金髪で、北欧系の目鼻立ち、女性は非常に美しいらしい。もし、そんな美女の宇宙人がいるとしたら、一度お会いしたいものです。 『ムー10月号 NO3591』 <ミステリースポット> <自衛隊独身寮に出没した異星人!?> ・私は、航空自衛官として、昭和53年に松島基地へ赴任しました。 ・そこに、あの“存在”がいたのです・・・。 ・先輩に訊いてみると「そいつは、明らかに幽霊とは呼ばない・・・・全身が黒くて両目は吊り上がって薄暗い黄色に光っている。何かを喋るわけではないけど、僕たちを見て、首を傾ける仕草をする・・・いわゆる、観察をしているような気もする。だからー結論からいって、異星人的存在なんだよ。いずれ見るよ、高い確率で」そんな助言めいたことを先輩はしました。 ・そんな、私も、昭和59年の春には異動が決まり、一度もその“存在”とは会わなかったな、と思いました・・・しかし、そんなある夜のこと。 ・夜中1時ごろ、ぼんやりと目覚め、あたりを何気なく見渡すと、一番外側のベッドに先輩らしき人影が腰を下ろし、肩を落としたような姿勢で座っていました。 ・まず、月の光を浴びているにもかかわらず、身体の表面上に光の照り返しがない・・・そして、その“存在”には影がないーしかも、大柄でありながらベッドのマットレスの体重による沈み込みもない・・・・。 ・何より、昭和53年のあの日の先輩の言葉が頭の中を巡り、全身真っ黒、頭の先からつま先までまったくシワのないウェアでもまとっているかのような・・・・。頭髪はなく、横顔を見つめると、鼻の隆起や口もなく、唯一、両目と思しきところだけは、薄暗い黄色の発光が強調されており、吊り上がっていました。 ・次の瞬間、その“存在”は私の布団の上に乗ってきました!しかし、体重をまったく感じとれないほどに感じられません。ほかに気付いたことは、その“存在”が動いても空気の流れやにおいなどもありませんでした。 ・その“存在”の顔は私の顔とくっつくほど接近、それでも息づかいや熱気も感じ、首を傾けるような仕草だけをしていました。 ・しかし、いつの間にか私は、気を失い、翌朝には何ごともなかったかのようにいつもの朝を迎えたのです。とてもたとえようのない疲労感だけが残り、そのことは上司に報告しました。それから数日後には異動することに。 ・しかし、あの“存在”、確かに「幽霊」と呼ぶには違う存在だったようです。あれはやはり異星人だったのでしょうか。 {岐阜県羽島市(51歳)徹次}
| |
| このブログへのチップ 0pts. [チップとは] [このブログのチップを見る] [チップをあげる] |
| このブログの評価 評価はまだありません。 [このブログの評価を見る] [この記事を評価する] |
|
◆この記事へのコメント | |
| コメントはありません。 | |
|
◆この記事へのトラックバック | |
|
トラックバックはありません。 トラックバックURL https://kuruten.jp/blog/tb/karasusan1122/425187 |
|