| くる天 |
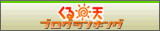 |
|
| プロフィール |
| 道化童子 さん |
| 他人の代表ノベル |
ブログの説明:
小説の公開を行います。
一部有料。 |
|
| RSS |
 |
|
|
| 第一章 猫又の訪問 前編 |
| [妖の棲む丘] |
| 2010年7月27日 15時21分の記事
|
|

|
玄関のドアを開けると、外には見知らぬ少女が立っていた。
「…………?」
少女は成長しきっていない身長で、表情も幼さが残る。
目の大きな愛くるしい表情は、将来美人になることを期待させる。
だが、そんな少女がこの部屋に何の用事なのかは分からない。
彼は少女を知らないし、そもそも今年で二十六歳になる陽司には、中学生くらいに見える少女との接点は全くない。
「えっと……」
必要以上ににこにこしている少女に、とりあえず話しかけてみることにした。
「誰? 何の用かな?」
彼は、とりあえず、最大の疑問をぶつけてみた。
「あと、どうやってここに来たんだ?」
ここは商業ビジネス住宅複合ビルの上階のマンション。
ヒルズと呼ばれるこの建物のセキュリティはかなり高い。
どうやって少女はここまで来たのか。
とにかく、何もかもが謎の存在だった。
「にゃー」
少女の答えは、彼の想像を絶していた。
満面の笑みの少女。
「あー……」
もはや彼の理解の範疇を超えた。
「じゃあ、またどこかで会えたらいいね。そういうことで……」
彼は理解できない存在と付き合いたくないと本能的に感じ、ドアを閉じようとした。
「にゃぁぁぁぁぁ」
すると少女は、するりとドアの間に入り込んできた。
「な……に」
密接した少女に一歩引き下がる彼。
少女の身長は、彼の肩にも及ばない。
そんな少女が、首を七十度に傾けて彼を見上げている。
「あのね」
文句を言おうとした彼の言葉より早く、少女は初めて人語を話した。
彼を見上げる瞳はあくまでも笑み。
少女の開いた口は、またも奇妙な言葉を紡いだ。
「めいど」
彼の名前は、高崎陽司。
今年で二十六歳になる、一見普通の青年だ。
少し前までは、一見だけでなく、本当に普通のサラリーマン青年だった。
だが、今はITを専門とする会社の社長となったのだ。
勤務していた会社が倒産し、無職となった彼は、思い立って起業した。
それがたまたま時流に乗り、急速に売り上げを伸ばした。
最初の事務所もすぐに手狭になり、周囲に勧められて、このヒルズへと事務所を移した。
このビルは家賃は大きいが、それも軽くまかなえるほどの売り上げが継続的に上がるようになっていたのだ。
彼の収入も倍に倍にと増えて行き、ヒルズの住居区域の中でも高級な階に居を構えるまでになった。
ただ、彼もいまだ一人身。
広く、大きな住宅はあまりにも寂しすぎた。
何せこのマンション、部屋の中に二階があるようなマンションだ。
リビングは必要以上に広く、下に広がる夜景を眺めることが出来た。
彼はそれらの部屋の多くを使いこなせず、特に二階は全くの手つかずになっていた。
食事は全て外食だ。
別にそれで困ることはない。
このビルの商業区だけであらゆる料理屋が揃っているし、デリバリーも豊富だ。
いつもは下に食べに行くか、職場にデリバリーするかして、食事を済ませていた。
家に帰っても寂しいだけなので、外に出ることがなければ一日の大半を職場で過ごし、早朝から深夜まで、寝る時間を除くとほぼ大半の時間を仕事で過ごした。
それは別にIT企業社長の仕事っぷりとして、珍しいわけではない。
だが、創業期よりも大幅に安定し、社員も増えて仕事も覚えてきた今となっては、暇なわけでもないが、社長が余暇もなく働きまわるほどの忙しさもない。
創業時からの社員達も、いつでも事務所にいる社長の身を案じて、なるべく社長である彼に仕事を回さないようにしていたので、彼は仕事がしたくてもない事もあった。
だから、仕方がなく家に帰ってくる時間が増えてしまった。
通勤時間二分。
十時に会社を出れば十時二分には帰宅出来る、誰もがうらやむ住宅事情であるが、そこに帰ると、やる事といえば本を読むか、テレビを見ることくらい。
六畳一間あれば済むところを、無駄に広い部屋で過ごす。
家にいれば食事に行くのも面倒になる。
自分で作るのはもっと面倒だ。
家にいる時間が長くなれば、部屋は汚れるので掃除の時間も増える。
広い家の中で、長時間一人で過ごす。
そんな寂しさに耐えかねて、彼は一つ思い立ったことがある。
そうだ、メイドを雇おう。
家政婦と言ってもいいかもしれない。
だが、メイドの方が夢がある。
家政婦の喫茶店はないが、メイド喫茶はある。
それがただのアルバイトなのは彼も知っている。
だが、この世にはメイドという職業があり、従事している人がいるのは事実なのだ。
そういう人を雇って、料理を作ってもらったり、掃除をしてもらったり、何より「お帰りなさいませ」と言ってもらえるなら、帰るのも楽しみになるというものだ。
通いが大変なら、二階の空いている部屋にでも住んでもらってもいい。
だから、彼は求人を出してみた。
「メイドさん募集(住込可)」という広告を出したり、ネット求人に載せたりしてみた。
ネット上では多少注目されたものの、応募者はゼロ。
周囲の失笑をかうだけで終わってしまった。
結局彼は、メイド雇用を諦めて、寂しい日々を送っていたのだ。
そんな経緯があるため、目の前の少女の放った「メイド」という言葉の意味や目的が分からなくもなかった。

「もしかして……メイドの応募者なのか?」
彼はおそるおそる聞いてみた。
「すみこみ」
少女は、頭を二度縦に振りながら答えた。
間違いない。
彼女はメイド志望者だ。
応募がなかったメイドの応募者がやっとここに現れたのだ。
だが、日本の法律では義務教育者の就業には色々な制限があり、また、未成年の就業には親の許可が必要なのだ。
そもそもローティーンと思しき少女にメイドをさせること自体、倫理的な問題も浮上するだろう。
彼はもはやただの人ではなく、勢いのあるIT企業の社長なのだ。
それが原因で足元をすくわれ、会社自体のイメージが低下することもないとはいえないのだ。
住込と言っている以上、住むところを探しているのだろう。
おそらく家出少女か何かではないだろうか。
ただ、荷物を何一つ持っていないのは気になるが、どこかロッカーにでも預けているのだろう。
「いやね、気持ちは嬉しいんだけどさ」
彼は言葉を選びながら言う。
「未成年を雇うには、保護者の許可が必要なんだよ。保護者の方に連絡取れるの?」
「ほごしゃ?」
彼が言うと、少女は不思議そうな顔で聞き返した。
「お父さんかお母さんはどこにいるの?」
さすがに中学生で保護者の意味を分からないということはないと思ったが、念のために分かりやすい言葉で言い換えてみた。
「おとうさんとおかあさん、むかしにしんだ」
少女はにこにことした顔のまま即答した。
「え? そうなんだ……」
まずいことを言ってしまった、と陽司は目をそらす。
「と言っても、雇うのは難しいなあ。念のために聞くけど、年はいくつ?」
「んー、ひゃくさい」
少女は何の迷いもなく、見当違いの数値を返した。
彼の頭の中に、老人が二人並んで「ひゃくさいひゃくさい」と言うCMが思い浮かんだが、百歳と言えば高齢中の高齢だ。
後期高齢者になった年に生まれた子供が、衆議院選挙に立候補出来るようになるくらいの高齢だ。
当然のことだが、目の前の少女が、そんな高齢者には見えない。
「そっか、百歳か。だったらご両親がお亡くなりになってても仕方がないね……っていうと思ったか!」
「にゃ?」
彼は思わず声を荒げてしまった。
少女は不思議そうに彼を見上げている。
よく考えると、怪しいことが多すぎる。
求人広告にはメールアドレスや電話番号は書いたが、住所はヒルズとは書いたものの、部屋の番号や名前までは明記していない。
更にこの住宅区は、一般的なマンションよりも遥かにセキュリティが厳しいため、そう簡単に入り込めたりはしない。
つまり、求人広告を見た希望者が、この家のドアを叩くことなどありえないのだ。
これは誰かの悪戯に違いない。
このビルには何人かの起業家の友人もおり、彼らは彼がメイドを募集していたことを知っている。
彼らが知り合いの少女をここに送ったと考えるのが極めて妥当な線だろう。
「で、誰に言われてここに来たんだい?」
単刀直入に聞いてみた。
「じぶんで」
少女は、当たり障りのない回答をした。
「じゃあ、君の名前は?」
どうせ、誰かの家族か親戚だろう、と考えた彼は、苗字から推測出来ないものかと、名前を聞いてみた。
「たかさき たま」
少女は、彼と同じ姓を名乗った。
「そこまで設定が出来ているのか……じゃあ、ここに来るまでは何してたの?」
正体を暴こうとする彼の質問に、少女は不思議な答えをした。
「ねこ」
これまで猫をしていたという少女に、これ以上付き合いきれないとは思ったものの、万一彼女のバックにいるのがビジネスパートナーだったりして、関係が悪くなったら問題だと思い、付き合うことにした。
「そうか、百歳の猫か。そろそろ猫又になるんじゃない?」
彼は多少投げやりに言う。
「うん。なったばかり」
彼女の言葉は、彼女のこれまでの行動に対して、一貫して筋の通った答えだった。
「そっか、だったらまだ幼いのも、ボキャブラリーが貧困なのも仕方がないな」
「うんうん」
少女はにこにこと笑いながらうなずく。
「じゃ、猫に戻れるのかな?」
彼は、少し意地悪な質問をしてみた。
「うんうん」
少女は、全く変わらない口調でそれを肯定した。
「へ?」
彼が少女の言葉の意味を理解し、素っ頓狂な声を出した瞬間、少女の姿が消えた。
少女に合わせるべき焦点が、ぼやけたドアを映した。
「あ……れ?」
ドアに焦点が合う頃にはまだ、彼の頭は状況を理解し切れてはいなかった。
少女は猫又で、猫になれると言った。
「にゃー」
足元から猫の鳴き声がする。
いや、しゃがんだだけと言うこともある。
彼は恐る恐る足元を見た。
「にゃー」
そこには、黒い猫がいた。
嬉しそうに彼の足にじゃれ付いていた。
「………………」
状況から判断すれば、先ほどの少女が猫になったと考えるのが最も適当だ。
だが、彼はその解を嫌い、何とかして他の理屈を探そうとした。
「す……」
頭をフル回転させ、今までの経験、見聞きした情報を探り、常識的な解を高速で導き出そうとした。
「凄い奇術だ……」
それは、彼の最大で最後の抵抗だった。
「人を消して、猫を出す奇術なんて、こんな近くで見たには初めてだよ、うん」
だが、その抵抗は、あっさり退けられた。
「にゃー」
彼の目の前で、猫は少女に戻ったのだ。
「………………」
もはや何も言えずにいた彼を見上げ、満面の笑みの少女が言った。
「ねこまた」
※
「分かった、猫又と認めよう」
場所を移し、部屋のリビングで相対して座る陽司と猫又少女の珠。
「信じたくもないけど、見てしまった以上、信じるしかない」
「にゃー」
珠は嬉しそうに首を傾げる。
その姿からはどうにも猫又には見えない。
そもそも、衣服も着物ではなく、洋服であり、髪型も肩で切りそろえられている、古さを感じさせない髪型であり、妖怪っぽさのかけらもなかった。
そこらを歩いていても、別に見咎めて振り返るような不審点は何もない。
いや、確かに可愛い少女なので、別の意味で振り返る人間はいるだろうが。
ともかく、珠は猫になり、人に戻った。
これは抗うことが出来ない事実である。
猫又というのは単に伝記が江戸時代以前であるから着物を着ているだけであって、その時代に合った人間に化けるのかもしれない。
「そっちはいいんだが───」
陽司が困った顔で言う。
「だが、それとメイドとは話が別なんだよ」
「にゃ?」
珠が首をひねる。
「この前まで猫だった奴に家事が務まるのか?」
陽司は、当然の疑問を言う。
確かに今は人間の姿をしている。
少女の容姿は、愛嬌のある笑顔と合わさって、とても可愛い外見である。
たとえ百年人間とともに生活してきて、人間を知っているにしても、人間としての経験はほとんどない。
「だいじょうぶ」
珠は、何の根拠も示さずに、そう答えた。
「料理や掃除が出来るのか?」
「みようみまね」
少女は自信たっぷりに不安にさせることを言い出した。
「うーん……どうしようかなあ」
陽司は腕を組む。
どうせ他にメイドの応募がない以上、猫又だろうが信頼に足りなさそうが、この少女で手を打つのも一つの方法でもある。
ただ、余計な迷惑をこうむるのは面倒だと考えた。
それは意味として二つある。
一般に住み込みで働く場合は、その人物の身分を保証してくれる人が必要となる。
家の中で仕事をするため、信頼できる人間でなければならないからだ。
早い話、泥棒したり、機密を持ち出したりするような人間ではまずいので、その者が信頼できなければならない。
が、この少女はそれを証明するすべはない。
人間のように物を盗んだり、情報を漏洩される心配は薄いと思われるが、そこは妖怪である。
見た目の可愛さに安心して、夜中に取って食われる可能性もなくはない。
それはもう、確認しようがないので、この少女を信用するかどうかというだけの話にしかならない。
そして、もう一つ。
メイドとしての腕である。
当然今までのやり取りで期待できないことは分かっているが、とはいえ、少しでもプラスの仕事をして、自分が楽になればそれでもいいかと思った。
陽司が雇わなかったとしても、彼女が路頭に迷うことはないだろうが、人間の少女には、猫とは違う危険もこの都会にはある。
何も知らない彼女を無下に追い返して、どこかでひどい目に遭っては、とも思う。
とりあえず保護して、仕事については二次的でもいい。
だが、マイナスの仕事をされると迷惑ではあるのだ。
マイナスの仕事とは、この少女が仕事をすることにより、陽司が何らかの後始末をしなければならない状態のことで、現状そうなる可能性は否定できない。
最初だけなら見習いとして問題ないが、いつまでもそんな状態が続けば困る。
確かに今は仕事も楽になっているが、これが今後永久に続くわけでもない。
社長なんて仕事は、今日は早く帰ることが出来ても明日から何の前触れもなく、毎日徹夜になる事も往々にしてある職業だ。
前も見えないくらいに疲れて帰ってきて、まずは後始末、などということは避けたい。
「まあ、出来る出来ないを口で言ってても始まらないから、何か料理でも作ってくれないかな? それで決めようか」
陽司は立ち上げる。
「りょうり」
珠も立ち上がる。
「つくる!」
嬉しそうにそう答えた。
「自炊はほとんどしてないから、食材買いに行かないとな。行ったことないからどこに店があるかよく分からないけどな」
陽司は大半を外食で済ませている。
一応、調理器具は一通り持っている。
昔は自炊もしていたこともある。
だが、今は多忙なため、また、別に料理が好きでも得意でもないため、ほとんど作ってはいない。
米くらいはあったかも知れないが、一般的な食材はないのだ。
「うってるところ、しってる」
珠が嬉しそうに陽司の服の袖を引く。
「分かった。じゃ、行くか」 |
|

|
|