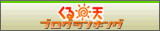| 他の多くの蒐集された民間説話に現れた幽霊には足もあり全く普通の人間のようであるのを見ると、琉球で幽霊の足の無くなったのは、極最近の事ではないかと思われる。(1) | |
| [森羅万象] | |
| 2021年9月30日 19時52分の記事 | |
1 『妖怪』 怪異の民俗学 2 小松和彦 責任編集 河出書房新社 2000/7/1 <金城朝永「琉球妖怪変化種目――附民間説話及俗信――> 1、 マジムン(虫物?) 妖怪変化の総称。 2、 ユーリー(幽霊) マジムンと同義語。但し田舎ではそうでもないが、那覇では、単に人間の死霊のみに使用されている。これに反してマジムンは人間、動植物、器物の化物にも用う。 3、 ハーメー・マジムン 老婆のお化。 4、 ジュリグワー・マジムン ズリ(遊女)の化物。これは琉球の各地で最も有名なお化けの一つで、ただ都会地那覇のみに限らず田舎にも流布している。 人間の幽霊には女が多く、そして大抵型の如く皆アレーガミ(洗洒の髪)を垂れている。琉球の幽霊は日本本土の幽霊画や歌舞伎等に見えるような形装の凄味はなく、大方生前の姿の儘であるが、精々青白い着物を着て髪を振り乱しているとか、舌を出している位が関の山である。今では日本本土のように幽霊には足が無いと云うが、他の多くの蒐集された民間説話に現れた幽霊には足もあり全く普通の人間のようであるのを見ると、琉球で幽霊の足の無くなったのは、極最近の事ではないかと思われる。 然し身体の一部、例えば足とか手だけとか顔だけとかの化物の話は相当ある。 5、 アカングワー・マジムン 赤坊の死霊。四ツ匍いになって人間の股間を潜ろうとする。これに股間を潜られた人は、マブイ(魂)を取られて死んでしまう。 6、 ミミチリ・ポージ(耳切坊主) 大村御殿に誅された琉球の伝説中の怪僧「黒金座主」の化けたものと云う。 7、 ナカニシ(仲西) 人の姓。晩方、那覇と泊の間にある塩田潟原の「潮渡橋」の附近で「仲西ヘーイ」と呼ぶと出て来ると云う。 8、 タチッチュ(嶽人) 山原地方の怪物で、夕方山から杖をついて下りて来て、子供を攫って行く。非常に力が強くて村の強い若者でもこれと角力をとって勝つ者はないと云う。 9、 ユナバル・ヤージー(与那原屋宜) 与那原(地名)屋宜(姓)。男性の怪物。 10、 ユナーメー 髪の毛のぼうぼう生えた怪物。 11、 ワーウー 面相の怖ろしい怪物。現今鬼面を刻んだワーウー石敢当や魔除けに屋根の上に置く素焼の唐獅子「シーサー・ワーウー」等の熟語あり。単に醜男、醜女にも使用されている。 12、 マー 形態は漠としているが、牛の啼声をすると云う。 13、 シチ 真黒で、山路を歩くと前に立ち塞がって人の邪魔をする。クルク山のシチ・マジムンは山原地方で有名だそうだ。 14、 ムヌ 漠然として形を現わさないようである。妖怪のことを「ヤナ・ムヌ」(悪物)とも云われる。人が神隠しにあったように突然行方不明になる時は「ムヌ・ニ・ムタリユン」(ムヌに持たれる)―日本の天狐に攫われるーと云い、又迷子になる事を「ムヌ・マイー」(物迷い)と云う。「ムヌ」に「ムタレ」た人を発見したら最初左足で三度臀部を蹴ると「ムヌ」は去ってしまう。 15、 キジムン 琉球の民間説話中で一番活躍している怪物である。多くの説話を通して其形態性質を箇条書にして見よう。 (1) アカガンターワラバー(赤い髪をお河童にした小人)。 (2) 古い木に住んでいるが海の事に詳しく、水上を自由に歩く事が出来る。 (3) 怪力で角力が上手である。 (4) 大変に悪戯好きである。 (5) よく人を魘(うな)らせる。(その時は「キジムン」に「ウスラリユン」(襲われる)と云い、頭ははっきりしているが、手や足を動かす事も、又声を立てる事も出来ない)。 (6) 屁が大変嫌いである(キジムンに連れられて水上を歩いていて屁をひった為に水に溺れかかった人の話等がある)。また蛸も好きでない。 (7) 線香の火が好きである。 (8) 魚を食べる時は片目しか食べない。 16、 カムロー カー(井戸)に住んでいて、小児等が井戸をのぞくと引入れてしまう。 17、 フィー・ダマ(火玉) 鬼火・人魂の類。琉球では、人の死ぬ時は、そのマブイ(霊魂)がフィー・ダマに成って、墓場に行くと信ぜられ、フィー・ダマの上った近所には近々に人死があると云う。 18、 イニン・ビー(遺念火) フィー・ダマに同じ。変死人のあった所や墓に現れる。 19、 トジ・マチヤー・ビー 刀自(妻)待火。最初に一つの提灯大の火が現れ、他方から今一つの火玉が来て二つ合してゆらゆらと立ち上って消えたかと思うと、又現れる。 20、 ウワーグワー・マジムン 豚のお化。 21、 ウシ・マジムン 牛の化物。 22、 アフイラー・マジムン 家鴨のお化。 23、 ミシゲー・マジムン 24、 ナビケー・マジムン 前者は、飯笥(めしげ)(しゃもじ)、後者は鍋笥(なべげ)(杓子)のお化。琉球では古い食器物は化けると信じられている。 <俗言一束> 1、 妖怪を見る能力のある特殊な人を、マジムン・ンジャー(幽霊を見る人)と那覇辺では云う。 2、 夜間石垣に向って立っているのは幽霊であるから話しかけてはいかない。 3、 ハン(家紋)のない提灯を持っているのは幽霊である。 4、 夜間自身の名を呼ばれても三度聞かない中は返事してはいけない。二度までは幽霊でも呼ぶ力がある。 5、 夜口笛を吹くと幽霊が出る。 6、 妖怪に股間を潜られると、マブイを取られて死んでしまう。 7、 妖怪は鶏の鳴き声を恐れる。 8、 戸外で妖怪に会ったら、豚小屋の豚の臀を三度蹴って鳴かせると魔除けになる。 9、 妖怪のよく出る場所を通る時、男はサナジ(褌)、女はハカマ(猿股の大きいもの)をはずして、男は肩に、女は頭に被ると魔除けになる。 10、 幽霊は多く四ツ辻に出現する。犬が其処でタチナチ(立って吠える)するのは幽霊を見るからである。又犬の向って鳴いた方向には必ず近々に不幸がある。 11、 妖怪は門に張ったミンヌフダ(梵字を書いた護札)を恐れる。石敢当も魔除けになる。 12、 夜子供が外出せねばならぬ時は、其母が鍋の尻の墨を指に付けて三度子供の額に黒子を付けてから出すと魔除けになる。 13、 食物を親類や近所の人に配る時はその上にサン(藁又はグシチ(薄の一種)で結んだもの)を載せる。サンをして置かないと、食物の精を魔物に取られるからで、其を食べても何の滋養にもならない。 追記。琉球には天狗の話は無いが、鬼の話は相当ある。しかし最早伝説中の怪物に属して現今では話されていないので略した。前記の妖怪変化は段々その影が薄らぎつつあるが、総て現在彼等の信仰の中に生存しているものである。 <収録論文解題 香川雅信> <江馬務「妖怪変化の沿革」1923年> ・江馬務は、風俗研究会を組織し、雑誌『風俗研究』を主宰して、日本風俗史学の確立に努めた人物である。彼は民間の風俗として妖怪信仰についてもいち早く注目し、大正12年に『日本妖怪変化史』を刊行した。これは「妖怪博士」と呼ばれた哲学者・井上円了の一連の著作と並んで、柳田國男以前の妖怪研究において重要な位置を占めるものとなっている。江馬は、啓蒙主義的立場から妖怪を迷信として否定して、人間との交渉が古来どうであったか、換言すれば、われわれの祖先は妖怪変化をいかに見たか、いかに解したか、いかようにこれに対したかということを当面の問題として論」じようとした。これは、「化け物の話を一つ、できるだけきまじめにまた存分にしてみたい」と述べた柳田國男と同様の立場である。 <今野圓輔「妖怪」1959年> ・民俗学の対象となる妖怪を「常民の生活経験、民間における伝承」の中の妖怪に限定し、それらを神霊に対する信仰の衰退したものとして捉えるという、民俗学の妖怪研究のあり方を端的に示している。とりわけここでは、魔風や通り神・ミサキを例として、神から妖怪への変化を論証しようとしている。このように妖怪を「神の零落した姿」として捉える視点は、柳田國男によって打ち出されたものであり、長く民俗学の妖怪観を支配してきた。 <井之口章次「妖怪と信仰」1964年> ・本論文は、柳田の妖怪研究を前提として、妖怪と信仰とのかかわりについて論じたものである。「個々の妖怪種目に関しても、河童・一つ目小僧・天狗・座敷童子などは、妖怪としての段階では、ほとんど解決されてしまったといっても、おそらく言い過ぎではあるまい」といったように、柳田の説を無批判に受け入れているところに難があるが、普遍的・超歴史的に存在する「妖怪現象」と具体的な「妖怪種目」とを区別する必要を説いたり、「綜合日本民俗語彙」の中の妖怪種目を統計的手法を用いて分析するなど、見るべきところが多い。 <澁澤龍彦「付喪神」1977年> ・幻想文学、オカルティズムなどに造詣の深い博覧強記のエッセイスト澁澤龍彦が、器物の妖怪である「付喪神」について述べたエッセイである。「付喪神」というこの特異な妖怪を、「物」に対する両義的な感情であるフェティシズムの表現として捉えようとしている。論考とは呼べないかも知れないが、多くの刺激的な発想に満ちた魅力的な文章である。 <中沢新一「妖怪画と博物学」1988年> ・筆者は、ポスト構造主義的理論を駆使して刺激的な文化論を世に問い続けている宗教学者である。本論考では、江戸期に大量に作られた妖怪画が、この時代に生まれつつあった「博物学的理性」に基づいて生み出されたものであった、というきわめて興味深い指摘がなされている。妖怪を「自然」と「意識」の境界面上に生まれるものと捉えるあたりには、フランスの精神分析学者ジャック・ラカンの思想の影響がかいま見えるが、著者は後に同様の分析枠組を用いて、人気ゲーム「ポケットモンスター」について論じている。 <野口武彦「髪切りの怪」1986年> ・著者は江戸時代の文化に関して多くの論考のある文芸評論家である。本論考では、江戸時代にたびたび起こった「髪切り」という怪現象をはじめとして、髪にまつわるさまざまなエピソードが紹介され、江戸時代における髪のシンボリズムが論じられている。小文であるが、鋭い視点に裏打ちされた、示唆に富む内容である。 <橋爪紳也「日本における『化物屋敷』観」1994年> ・著者は近代建築史を専門とする研究者であるが、殊に見世物小屋や博覧会のパビリオンなど、仮設建築に大きな関心を寄せている。本論考は、娯楽施設としての化物屋敷(お化け屋敷)について著された著作の一章をなすものである。著者はまず娯楽施設としての化物屋敷が、西洋では屋敷そのものが妖怪化したものとなっているのに対し、日本では「屋敷」とはいいながら内部は屋外を表現したものとなっている、という点に注目し、その違いを生み出した背景として、日本における「化物」と「屋敷」との関係性について考察している。日本においては建物そのものは妖怪とはならないという結論は、妖怪観・建築観を考える上で非常に重要な示唆を与えるものとなるだろう。 <武田正「百物語――その成立とひろがり――」1996年> ・本論考は、昔話を主な研究領域としている著者が、百物語という特異な語りの形式の成立と広がりについて考察したものである。まず「語りの座」としての百物語が生まれる前提として、江戸期の文人たちによる怪談集の成立について述べ、次いで民俗としての百物語がどのようなものであったかを、聞き取り調査によって得られた事例などを元にして述べている。 <横山泰子「芝居と俗信・怪猫物の世界――『獨道中五十三驛』試論――」1996年> ・著者は近世の怪談演劇に大きな関心を寄せている研究者である。ここでは、『獨道中五十三驛』といういわゆる「怪猫物」の怪談狂言について、当時の猫にまつわる俗信や文学的伝統などとの関連性を探っている。このように大衆演劇を民俗的背景と照らし合わせながら読み解いていく研究は、今後さらに進められるべきものであろう。 <アダム・カバット「化物尽の黄表紙の考察――化物の概念をめぐって――」1997年> ・黄表紙とは、見聞きの絵の中に文章を書き込むという絵本風の体裁をとった、近世における一種のパロディ文学である。江戸時代のマンガとでもいえばよかろうか。この黄表紙の中には、妖怪を主要なキャラクターとした「化物尽」のものが多くみられる。アメリカ人の日本文学研究者である著者が、そのような「化物尽」の黄表紙に注目し、そこに登場する「化物」について分析したのが本論文である。「化物」が人間と逆転した存在として描かれることによって、鋭い風刺性とユーモアを生み出している、という指摘は、服部幸雄の『さかさまの幽霊』(1989年)と並んで、文化人類学における「象徴的逆転」の問題へとつながる興味深いものである。 <宮田登「女と妖怪」1987年> ・著者にはいくつかの妖怪や怪異伝承に関する論文・著作があるが、それらの輪のキーワードとして、「境界」「都市」「女性」などを挙げることができる。本論考では、そのうち「女性」と妖怪の問題が論じられている。ここでは特に女性の「産む性」としての側面と怪異との関連性への注目がなされている。 <岩堀貴美子「ミカワリバアサンと八日ゾ」1971年> ・本論文は、著者が東京女子大学に提出した卒業論文の要旨である。神奈川県において、12月8日と2月8日の「八日ゾ」に家々を来訪するとされる妖怪であるミカワリ婆さんと一ツ目小僧についての伝承を比較検討した上で、それらが本来は全く別のものであったという仮説を提出している。結論としては、ミカワリ婆さんの伝承は八日ゾという行事の本来的な要素ではなく、この時に行われる物忌みの意義を強調するために付加されたものであるとしている。 <酒井薫美「七尋女房――山陰の妖怪考➀――」1990年> ・本論考は、「山陰の妖怪考」の第一弾として発表されたものである。島根県と鳥取県の一部にのみ伝承されている「七尋女房」という妖怪について紹介し、考察を加えている。結論としては、妖怪は神の零落した姿であるという古典的な民俗学の仮説を抜け出ていないのが残念であるが、ある地域に特有の妖怪に注目し、他の「背の高い妖怪」との比較を試みている点は興味深い。このような研究が、今後さらに進められることを期待したい。 <佐々木高弘「伝説と共同体のメンタルマップ――徳島県美馬郡脇町の『首切れ馬』伝説を事例に――」1992年> ・本論文は、徳島県美馬郡脇町の「首切れ馬」という妖怪にまつわる伝説を事例に、メンタルマップ(認知地図)研究の資料としての伝説の可能性を探ったものである。伝説の構造分析と伝承地の歴史地理的背景とを結びつけながら、共同体どうしの対立関係がメンタルマップの中に反映されていることを明らかにしている。 ・この論文の中では、「首切れ馬」が徘徊する「縄筋」などと呼ばれる道が古代の条里地割の境界線に当たっていることから、「首切れ馬」伝説が境界線の記憶装置としての意味をもっていた、という興味深い指摘もなされている。 <柳田國男「狸とデモノロジー」1963年> ・デモノロジーとは「悪魔学」の意味だが、ここでは「妖怪観」とでも訳せばよかろうか。柳田はここで、妖怪としての狸の性質について述べながら、妖怪に対する観念の変遷について説いている。すなわちデモノロジー(妖怪観)は文明の進歩に逆比例して、第一期《人に憑く》、第二期《人を誑す》、第三期《人を驚かす》という具合に退歩していくとする。そして妖怪としての狸は《憑く》よりも《誑す》《驚かす》といった性質が濃厚であるため、「お化党中の最も新党なるもの」であるとしている。また狸の化け方として、「目を欺く」よりももっぱら「耳を欺く」傾向が強いことを指摘しているが、その中で、狸が汽車、蒸気船、自動車、飛行機などの近代の交通機関の音響をまねるという事例が挙げられていることに注目すべきであろう。 <小松和彦「妖怪と現代文化」1994年> ・「近代の科学文明の発達・浸透とともに人間世界から妖怪は消滅するはずであった」という多くの人々の予想に反して、「口裂け女」など、現代の都市空間の中にも妖怪は出没しつづけている。著者はこうした事実をふまえ、不安や恐怖心など、人間の心のなかの「闇」が妖怪を生み出すとし、「人間がいるかぎり妖怪は存在しつづける」と述べる。 <野村純一「話の行方世河童疎遠『口裂け女』その他――」1984年> ・著者は、昔話・伝説・世間話などの口承文芸を主な関心領域としている研究者である。ここで考察の対象とされているのは「珍しい話」あるいは「噂」であるが、これらを民俗学では「世間話」の語でとらえている。 <常光徹「子どもと妖怪――学校のトイレ空間と怪異現象――」1989年> ・著者は『学校の怪談』(1993年)によってその後の「学校の怪談」ブームの火つけ役となった研究者で、本論文はその著作の元になったものである。現代の妖怪譚として「学校の怪談」を取り上げ、その「伝承母体」となった学校という社会空間に特有な心性について考察している。とりわけここでは、トイレという空間の非日常性・境界性に焦点があてられている。現代における妖怪の問題について考える場合、「学校の怪談」は間違いなく中心的な話題となるはずである。 <清水時顕(中山太郎)「小豆洗い」1916年> <大野芳宜(柳田國男)「小豆洗いに就て」1916年> <大藤時彦「小豆とぎ」1943年> ・地名から「起源」を説明してしまおうとする中山に対し、狸や鼬などの仕業である可能性は否定できないとしながらも、一元的な説明を避け、比較研究による解明を説く(ある意味で構造主義的な)柳田の議論の方が説得力があるが、結局のところ、「猶同種の話を多く集めた上で講究を続けたい」という柳田の展望は、その後明確な結論にたどり着くことはなかったようである。いずれにしても、中山・柳田・大藤という大物民俗学者たちが「小豆洗い」という妖怪をめぐって論を展開していること自体、非常に興味深いことである。 <山崎里雨「影わに・犬神・牛鬼・河童――石見邇摩郡温泉津――1933年> <岡田建文「石見牛鬼譚」1933年> ・いずれも『郷土研究』誌上に寄せられた石見地方の妖怪についての報告であるが、とりわけ牛鬼が代表的な妖怪として取り上げられている。これらによると、石見地方の牛鬼は海の妖怪であり、また椿の化したものであるとか、濡女という妖怪と二匹一組になって人間を襲うなどの特異な伝承をもっている。牛鬼という名のついた妖怪の伝承は多くの地方で聞かれるが、それぞれに異なる属性をもっているようであり、それらを比較検討してみるのも面白いだろう。 <桂井和雄「土佐の山村の『妖物と怪異』」> <金城朝永「琉球妖怪変化種目――附民間説話及俗信――> ・土佐および琉球の妖怪に関する伝承を行目的に紹介した報告である。妖怪の博物誌として興味深くかつ慎重な資料である。 <桜田勝徳「船幽霊など」1932年> <花部英雄「船幽霊の型」1983年> ・いずれも海の妖怪である船幽霊について書かれたものであるが、桜田のものが中国地方西部から九州地方北部にかけての船幽霊の伝承に関する報告にとどまるのに対し、花部のものは表題にあらわれているように船幽霊の伝承を類型として整理・分類し、かつ考察を加えたものとなっている。さまざまな事例の報告はもちろん貴重であるが、それらの事例を整理し分析する試みが、妖怪研究の進展にとって今後さらに重要になってくるであろう。 <三浦秀宥「中国地方のミサキ」1972年> ・ミサキ信仰は日本に広く分布する民間信仰で、柳田國男もこれについて「みさき神考」という論考を著している。ミサキは本来、神の示現に先立つ「先駆者」や神使を指すものであったが、それに対する禁忌の厳しさや祟りの厳しさから「祟る神霊」を指すようになったと考えられている。中国地方は特にミサキ信仰が顕著にみられる地域であり、さまざまな性格をもったミサキが伝承されているが、その中には怨霊や祟り神・憑きものとしての性格をもつものもみられる。一種の妖怪の伝承として、ここに紹介することにした。 <大竹信雄「かまいたち談義」1998年> ・カマイタチは、妖怪としてはかなり名の知られた部類に入るだろう。しかし、カマイタチに関する報告は意外に少ない。本論考では、実際にカマイタチに遭ったとする人々の体験談なども含む貴重な事例が報告されている。 <関口武「一目連のこと」1975年> ・一目連とは竜巻を神格化した風の神で、三重および愛知などで信仰されている。妖怪とはいえないかも知れないが、カマイタチとの関連もあってここに紹介することにした。現代の電力会社や水道局もこの一連目を信仰しているという報告はきわめて興味深い。 従来、妖怪を研究対象として主に扱ってきたのは民俗学であると一般には考えられてきた。そして近年の妖怪ブームの中で、民俗学の妖怪研究に対する期待はさらに高まりつつある。 <妖怪 解説 小松和彦> <「妖怪」とはなにか> ・もう長いこと、静かな妖怪ブームが続いている。しかし、このブームは主として水木しげるの妖怪画やその先人たちの妖怪画への関心によって引き起こされたものであって、妖怪研究はこのブームに刺激されてやっと少し活性化してきたというのが実状である。したがって、現在はまだ、妖怪に関心をもつ研究者がそれぞれの関心から個別研究を蓄積しつつある段階に留まっているように思われる。 ・妖怪を定義するのはむずかしい。しかし、あれこれ考えるよりも、ここはまず文字通りに理解して、「あやしいもの」や「あやしいこと」、つまり「怪異」というふうに理解しておくのが無難である。 ・「妖怪」という語のもう一つのやっかいな点は、「妖怪」と同義と思われているいくつかの語があることである。しばしば、「妖怪」と「化物」とは同じものなのかとか、「お化け」と「幽霊」とはどこが違うのか、というたぐいの質問を受ける。言葉は生き物であるので、時代とともに意味が変化する。したがって、厳密に区別しえないのだが、ここで若干の説明をしておくのは無駄ではないであろう。 ・まだはっきりしたことはわからないのだが、明治時代になって、妖怪現象・存在に興味を抱き、その研究に従事した人たちが「学術用語」として「妖怪」という語を意識的に用いたようである。そうした意味での最大の功労者が、後に述べる妖怪博士との異名をとった哲学者の井上円了であった。つまり、学術用語として作られた「妖怪」が、研究者の枠を超えて次第に世間にも広まっていったのである。そしていまではすっかり現代人の日常生活に入り込んだ語彙となったわけである。 ・「妖怪」が学術用語として作り出されたものであるとすると、それでは明治時代や江戸時代の庶民の間には、「妖怪」に相当するような民俗語彙は存在していたのだろうか。民俗語彙のなかに適切な語がなかったがために、研究者が「妖怪」という用語を意図的に使いだしたのだから、この語の概念にぴったりと一致する語があるわけではない。しかし、もっとも近い民俗語彙は「化物」あるいはその幼児語である「お化け」であろう。 ・「化物」とほぼ同じ意味で流通していた語に「百鬼夜行」という語もあった。これは平安時代の貴族社会から生まれてきた語で、当時は、都大路を群をなして徘徊する「鬼」を意味していたが、中世になると、鬼とはいえない異形の者もそのなかに混じり出し、江戸時代には「たくさんの化物」を意味するようになっていた。この他にも、「物の怪」「変化」「妖物」「魔」「魔性の者」などさまざまな語彙が存在するが、それらはいずれも、学術用語としての「妖怪」に含めることができるものである。 ・すでに述べたように、近年の妖怪への関心の高まりのきっかけになったのが、水木しげるの妖怪画の人気であった。 <妖怪研究の黎明期> ・さて、20年ほど前から現在に至る長い妖怪ブームがあるにもかかわらず、じつは妖怪を学術的に研究する人はきわめて少ない。妖怪は、絵画のみでなく、民俗学や文学、芝居、遊戯などさまざまな分野に登場している。 ・そうした学問的状況のなかで、妖怪研究を許す雰囲気をもった唯一ともいえる学問が、民俗学であった。 ・ところで、これまで述べてきた井上円了の妖怪撲滅学としての妖怪学の隆盛を苦々しく思う一方、江馬務の妖怪変化の歴史学に拍手を送ったと思われるのが、近代日本が立ち上ってくる過程で排除・放棄され撲滅されていった「日本文化」を「民俗」として括り出そうとしていた柳田國男であった。柳田は、昭和11(1936)年に発表した『妖怪談義』において、「無いにも有るにもそんな事は実はもう問題で無い。我々はオバケはどうでも居るものと思った人が、昔は大いに有り、今でも少しはある理由が、判らないで困って居るだけである」と述べるように、井上円了のような科学的合理主義に基づく妖怪否定論者とは異なる、妖怪の存在を信じていた人びとの思考構造=心性にそった「妖怪の宇宙論」とでもいうべき研究の必要性を説いた。 ・柳田は妖怪研究において、次の三点を強調した。第一に、全国各地の妖怪種目(種類)の採集をする、第二に、妖怪は場所に出るのに対して、幽霊は人を目指して出ると言った区別がある、第三に、妖怪は神の零落したものである。実際、民俗学的妖怪研究は長くこの指針にそってなされてきたのであった。 ・しかし、こうした、妖怪を前代の神信仰の残存、神の抜け殻としてしかみなさない妖怪研究では、すでに述べた妖怪の意味論や妖怪の機能論といった研究がどうしても欠落してしまいがちであった。 <妖怪研究の新しい展開> ・こうした民俗学的妖怪研究の不毛な時代に、わたしは人類学・民俗学の立場から妖怪研究に取り組みだした。わたしの妖怪研究は従来の民俗学的妖怪研究の枠を大幅に変更する視点からのもので、妖怪を俗言とみない、妖怪を神信仰の零落とみない、したがって妖怪を前代の神信仰の復元のための素材とみない、妖怪資料を民間伝承に限定しない、妖怪伝承を前近代の遺物とか撲滅すべき対象とみない等々の視点に立って考察することに心がけた。 ・わたしの妖怪研究がどの程度刺激になったのかはわからないが、幸いにも、最近の妖怪ブームの一躍を担ったことはたしかである。「幸いにも」という意味は、ブームのおかげで、滅多に見ることができないような妖怪画を存分に見ることができるチャンスを得たということである。ここではこれ以上自分の仕事に言及するのはやめたいと思う。 民俗学的妖怪研究が停滞しているなかで、わたしが大いに刺激を受けた研究は、文学や絵画の分野からの妖怪研究であった。 ・ところで、長い停滞期を経て、近年、ようやく民俗学でも新たな妖怪研究の胎動がおこってきた。近代以前あるいは伝統的な妖怪の研究も少しずつ復活しつつあるが、それにもまして活気づいているのが、現代都市にうごめく妖怪たちについての口頭伝承の研究である。そのきっかけになったのが、岐阜県の山の中から発生して瞬く間に全国を駆けめぐり、子どもたちを恐怖のどん底に陥れた「口裂け女」騒動や民俗学の外部で生じた妖怪ブームであった。撲滅されたかに見えた妖怪が現代社会のなかによみがえったのである。このような事態は、井上円了も柳田國男とその弟子たちにも想像しえないような事態であったといえるのではなかろうか。 ・この問題に取り組みだした先駆者が境界論の立場から都市妖怪を論じた『妖怪の民俗学』(1985年)を著した宮田登であり、口承伝承・世間話の視点から口裂け女騒動の行方を追った野村純一であり、「学校の怪談」ブームの火付け役になった常光徹の『学校の怪談』である。 ・最後に、中沢新一の「妖怪画と博物学」について触れておこう。中沢が論じた妖怪論は江戸の博物学的理性と妖怪の関係であった。しかし、その延長上にある現代の妖怪ブーム現象にもほぼそのまま適用できる、興味深い考察に満ちている。「自然」「意識」の境界に出没する「妖怪」は、また「第二の自然」や「第三の自然」(パソコン)と「意識」の境界に発生する「妖怪」の登場を暗示しているように思われる。 妖怪研究は、人間研究である。それはまだ胎児の状態にすぎないが、おそらくは新世紀にあっては、関連諸分野とも連携しつつ、人間の「心」の救済に深くかかわる学問となっているはずである。妖怪研究は、これから開拓されるべき将来性のある研究領域なのである。 『神々の予言』 (ジョージ・ハント・ウィリアムソン)(ごま書房)1998/9 <クリスタル・シティー> 「カタストロフィー以後の70年は、およそ次のようなものとなるだろう。理想的な都市が地球上に立ち並ぶであろう新時代は、瞬間的には訪れない。キリスト再臨以後の地球、つまり、激しく破壊された地球を新時代の輝かしいものに変えるためには、およそ70年にわたる努力の積み重ねが必要となる。70年という期間は、決して長いものではない。その期間が過ぎたとき、地球は完全に浄化され、そこには、クリスタル・シティー、すなわち理想的な都市が、あちこちに立ち並ぶことになる。そしてその頃には、宇宙旅行も頻繁に行なわれるようになるだろう。そのとき地球は、惑星間友愛同盟への加盟を果たし、宇宙連合議会の一員としての地位も手にすることになる。そうなれば、近年増え続けている宇宙人来訪の理由を、より正しく理解できることにもなるだろう」。 <神になった「シータ・ユニバース」のエルダー> ・ 彼らは、物理的な世界に住む、物理的な肉体を持った生命体ではあったが、厳密に言えば、今の我々のような三次元の世界のみで生きる生命体ではなかった。彼らは、種族全体で、はるか遠い昔から、時間と空間を超越した存在になることを目指していた。つまり、惑星や太陽系といった物理的な世界に束縛されない、非物理的な存在になることを夢見ていたのである。彼らは、時空を超越することにより、自分たち自身が神になるための方法を探究していた。 そして結局、この地球が、彼らの住みついた最後の世界となった。なぜならば、地球にやってきて間もなく、彼らは、その創造的な想念パワーに磨きをかけ、ついに物理的な束縛を完全に克服するに至ったためである。 ・ 彼らは、神になった。時間と空間を完全に超越した彼らに、地球や銀河に縛られている必要は、もはや全くない。彼らは、自由になったのだ! 彼らは「シータ・ユニバース」すなわち「八番目の宇宙」あるいは、「想念宇宙」の一員となったのである。 「エルズ」と呼ばれるようになったのは、その「シータ・ユニバース」への到達によってである。それより前は、単に「サイクロップス」と呼ばれていた。「エルズ」または「エル・レース」という呼び名は、彼らが物理的な束縛から自由になるために用いた手段に由来する。 ・ 彼らは、「直角位相シフト」の理解と、その有効利用により、地球や銀河系宇宙を離れそこを後の人類に開放した。「直角位相シフト」、そうなのだ、{エル(L)}という文字、まさに「直角」なのである。 そして、現在この地球には、ここに最初に住みついた彼らに由来する単語が、数多く残っている。彼らの別名「エルダー・レース」の「エルダー(elder)」も、その一つである。「エル」はもちろん、{L}を意味し、「ダー(der)」は、「由来する(derive)」の短縮形である。 <地球に留まった宇宙人の使命とは> 地球の惑星上には、一つ目の偉大なエロウヒム(神)の存在があり、彼の放射する波動が地球全体を覆っている」 クスミ師が、あの偉大な種族、エルダー・レースの一員について語っていることは明らかである。1956年の時点で、もはやエルダー・レースのほとんどはこの地球にはいなかったが、彼らの一部はなおもここに残り、地球の教師、聖者、賢者たちに対するメンターとして活動し続けていた。 <ムー大陸の賢者たちは宇宙人であった> ・人類に先駆けて地球上に住んでいた最古の生命体。 ・十億年前の地球。この地球が十分に冷え、生命体の居住が可能になったとき、宇宙の彼方から、ある種族がやってきた。彼らは、我々と違い“真の人”の種族だった。 彼らは「サイクロップス」すなわち「一つ目族」として知られる種族で「秘密の資料」のなかでは「エル(L)・レース」または{エルズEls}として紹介されている。 ・ 彼らは時間のあらゆる巨大な周期に乗り、常により快適な宇宙の住みかを求めて、限りない星の道を旅してきた「巨人」だった。 今でも彼らは、時空の別の次元の旅を続けている。「神の種族」あるいは「エルダー・レース」との呼ばれている。その種族こそ、我々に先駆けての地球に住んだ、最初の生命体である。エルダー・レースの一部の人々は、真のサイクロップスだった。つまり、目が一つしかなかったのである。その他の人々は、我々と同じように二つの目を持っていたが、それには別に「心眼」というもうひとつの目を発達させていた。彼らの身長は、平均3.7メートルもあり、男性と女性とに分かれてはいたが、今日我々が理解しているような性別とは異質のものだった。 ・彼らは、地球にやって来る前に銀河系宇宙内のあらゆる空間を旅し、そこに存在した数限りない太陽や惑星をことごとく自分たちの影響下においた。彼らは、ある天体が居住可能な状態になるや、他の生命体に先駆けていち早くそこに住み、やがてその天体を去るときはいくつもの巨大な都市からなる彼らの地底王国と膨大な資料を残していくのが常だった。 宇宙の歴史その他に関する情報を満載したその資料は、小さなクリスタルに記録されて、ある種の電磁場に囲まれた状態で保存されているが、後にその天体に住んだ敏感な人によって感知され、ときおり日の目を見ている。 『UFOと悪魔の世界政府666』 (コンノケンイチ)(学研)(2002年) ファチマ聖母予言が月面探査とケネディ暗殺の謎を解く!! <牡牛と蛇身の神々> ・筆者は、世界各地の神話や伝説を調べてきたが、その流れは、大きく二つに分けることができる。「龍神」と「牛神」伝説で、『旧約聖書』の時代には牛神と龍神という二種の異星人が地球に来ていたらしい。この事実をすり入れることによって、聖書の多くの矛盾点も解消されてくるのである。 ・そう、『新約聖書』のゴッドが牛神で、龍神が『旧約聖書』のゴッドだった。牛神が活動した本拠地は現在の西インドとギリシア地方で、それがインド各地の「聖牛伝説」や「ギリシア神話」として今に伝えられている。 ・メソポタミアの神話にも「天の神」と呼ばれた多くの牡牛の神々が登場し、その起源も龍と同じシュメール文明に始まっている。 ・牛神の信仰はインドに侵入したアーリア人にも引き継がれた。主神インドラをはじめ、シヴァ神の前身であるルドラ、雨の神であるマルトの神々など、天の神すべてが牡牛である。 ・ヒンドウー教の母体になったバラモン教の最古の文献『リグ・ヴェーダ』にある「天地両神の歌」では、天を「美しき種子ある牡牛」に、大地を「班ある乳牛」にたとえて、彼らは、「驚嘆すべき牡牛なる双神」と表現され、母星は牡牛座であると述べられている。牡牛座(スバル座)はプレアデス星団にあり、オリオン星系に属する。 ・彼らは、本拠地をインドやギリシアに限定していたため、分からないことが多く、牛神にまつわる神話や伝承が世界的に少ないのもそれゆえである。 ・わずかに日本でも「牛頭天皇(ごずてんのう)」の信仰があるが、各地に点在する「龍神」の祠の数とは比すべくもないが、それでもわずかに痕跡は残されている。たとえば正月に見る獅子舞いの風習も、日本には獅子(ライオン)は棲息してなかったので、牛神の動きを真似た「牛舞い」がなまって「獅子舞い」になったともいわれる。 ・一方の龍神はどうだろう。母星はシリウス星系、ルーツは蛇と同じ爬虫類らしい、日本にも龍神の祠が圧倒的に多いように本拠地は特定せずに地球規模で活動していたようである。 <牛神と龍神の対立!> ・このように「旧約聖書」のゴッドは、シリウス星系(人面蛇身)の異星人「龍神」だった。「旧約聖書」には「私は妬みぶかい神である」という表現が多く出てくるが、「妬む」とは、自分と同等か、それ以上の存在を対象にした表現である。人類はゴッドの被造物で、妬みの対象にならない。「旧約聖書」のゴッドは何者に嫉妬していたのだろう。言うまでもない、牛神に対してである。 『天孫降臨 / 日本古代史の闇』 神武の驚くべき正体 コンノケンイチ (徳間書店) 2008/12/8 <シリウス星系(龍)対オリオン星系(牡牛)> ・世界各地の神話や伝説を調べると、BC4000〜3000年ごろ「牛神」と「龍神」という2種の異星人が地球に来ていたようで、流れは大きく二つに分かれていた。 牛神が活動した本拠地は、現在の西インドとギリシア地方で、それがインド各地の「聖牛伝説」や「ギリシア神話」として今に伝えられている。 ・メソポタミアの神話にも「天の神」と呼ばれた「牡牛の神々」が登場し、その起源もシュメール文明に始まっている。バビロンの主神マルドゥクも、また旧約聖書にも記されるカナンの神であるバールの父エルも牡牛の神である。この流れは、ギリシアやエジプトにも飛び、ゼウスも牡牛の神である。白い牡牛の姿で美女エウロベに近づいた。豊穣の神ディオニュソスも、エジプトのミンも牡牛である。豊穣の神だけではない。メソポタミアの大地母神イシスも牡牛の姿で現れ、ギリシアの大地母神ヘラも牡牛の目を持つ神で、このようにシュメールからの流れの主神全てが牡牛だった。 ・原始密教(雑密)の発祥地インドでも、インダス文明の時代から現代まで牛は長く崇拝されてきた。モヘンジョダロの遺跡からBC2000年以上と思われる聖牛の印象や図象・彫像が発掘され、当時すでに牡牛への信仰が存在していたことが判明している。 ・彼らは、「驚嘆すべき牡牛なす双神」と表現され、発進母星は65光年先の牡牛座(地球から観測する最も明るく輝く恒星アルデバラン)にあると述べられている。牡牛座の近くにはプレアデス星団(スバル座)もありオリオン星系に属する。 ・一方の龍神はどうだろう。発進母星は地球から約8.7光年離れたシリウス星系でとくに地域を限定せず、全地球規模で活動していたからである。私達の銀河は直径が10万光年あり、その意味では龍神の発進母星シリウス、牛神のオリオンはお隣の星、隣接する恒星といってよい。 ・前記したインド最古の文献『リグ・ヴェーダ』には天上(宇宙)での両者の凄まじい戦闘が微にいり細をうがって描かれている。そこではテクノロジーの差なのか、圧倒的に牛神が優勢だったようである。 『能から紐解く日本史』 大倉源次郎 扶桑社 2021/3/21 <伝統文化> ・私はずっと、日本の伝統文化の中で「能楽」を見直すとはどういうことか?という問いを考え続けてきました。私たちが生きたしるしをいかに次の世代へ伝えるか、その役目を引き継いで、微力ながら必死に精進してきました。 能は、変わらぬ伝統文化として七百年近く、日本人とともにあり続けてきたものです。 <本書を楽しむ基本《能楽用語》> <◎能楽とは、何か?> 【能楽】能+狂言のこと ――まず一番大きな言葉の意味をお尋ねしますが、“能楽”とはどんなものなのでしょう? 源次郎 歴史的に言うと、室町時代に観阿弥・世阿弥親子によって大成された楽劇、ですね。 室町時代は今から約650年ほど前ですね。楽劇というのは“音楽と演劇が融合した藝能”です。西洋ではワグナーのオペラを楽劇と呼びますが、能楽もオペラと同じようにすべての台詞が音楽になっていますし、音楽・演劇・舞踊が高いレベルで一体化した音楽詩劇といえる舞台芸術ですね。 もう少し詳しくいうと、それ以前の奈良時代・平安時代からさまざまな藝能があり、田楽・幸若舞・猿楽などをすべて「能」と呼んでいたのです。が、猿楽が一世を風靡したため「能=猿楽」と同義語になりました。古は多くの座が活動していたのですが、中世に大和四座(観世・宝生・金春・金剛)にまとめられ、江戸時代に喜多流が加わって四座一流となりました。 明治維新以降は「能楽」と呼ばれるようになり、現代では「能」と「狂言」をあわせて表現するときに「能楽」と呼びます。 【能】五流が上演する、伝統的スタイルの曲 ――この本のメインテーマである“能”とはどのようなものか、簡単にご説明いただけますでしょうか? 源次郎 現代の用語では、「能楽」のうちの「能」とは、観世・宝生・金春・金剛・喜多のシテ方五流が主体になって上演する曲を指します。伝統的な演能スタイルに則った演じ方をもっぱら「能」と呼びます。これは古典でも新作能でもそうですね。 <◎能楽を演じる人たち> 【能楽師】能・狂言の演者たち 源次郎 「能楽(能・狂言)」の演者を総称して「能楽師」といいます。 公益社団法人能楽協会には、玄人の能楽師が一千百人ほど所属しています。必ず次のいずれかの役柄と、それぞれの流儀に所属しています。 シテ方五流=観世流・宝生流・金春流・金剛流・喜多流 ワキ方三流=高安流・福王流・下掛宝生流 狂言方二流=大蔵流・和泉流 囃子方には笛(能管)三流、小鼓四流、大鼓(大皮)五流、太鼓二流 笛=一噲(いっそう)流・森田流・藤田流/小鼓=観世流・大倉流・幸流・幸清流/大皷=葛野(かどの)流・高安流・大倉流・石井流・観世流/太鼓=観世流・金春流 ――源次郎先生は「能楽小鼓方大倉流」の宗家になるのですね。 ・【シテ】能・狂言の主役、演出 ――「シテ」とは能の主役とのことですが、他の演劇や映画の主役とはかなり違いますね? 源次郎 能の物語では、生きている人間が主役になることもありますが、“この世ならぬもの”である神・亡霊・鬼などの霊的存在が主役になることが多い、という特徴があります。また、狂女・狂男のように人生が狂ってしまった者も主役になります。 ――現代的なエンタメの主役と違って、謎が多いですよね。死んだ人や狂人が主役になることは現代ではめったにないですし、加えて、他のエンタメと違って、お面をかぶっていますよね。 源次郎 そうです。シテは役柄によって面をつけて演じられます。どの面をつけるかは曲に大体決まっており、面の種類で役の性格も定まってきます。 【ワキ】シテに出会ってしまう、生きている人 ――ワキはズバリ「脇役」ですよね? 源次郎 はい、そうです、と言いたいところですが……そうとも限らないのです。いってみれば“シテに出会ってしまう”“生きている人”でしょうか。観客の代表、ともいえます。 ワキは場面上、生きている人間、という設定なので、直面(素顔)で演じられます。諸国を巡る僧・神職・武士など男性の役が多いですね。 ワキには能の冒頭で場面設定・状況説明を行うなど構成上とても重要な役目があります。 【ツレ】付き従う役 ――舞台にはシテとワキ以外にもいろんな役者さんが登場しますが、その方々にも独特の呼び方があるのですか? 源次郎 そう、まず「ツレ」ですね。シテ(主役)の兄弟・姉妹・敵味方・貴人・従者などさまざまな役があります。 詳しくいいますと、シテに対して同じ意思をもち、シテに連れられている関係の場合と、反対に相対する関係で登場しているときがあります。 漢字では「連」。単に「ツレ」というと「シテツレ」の略で、主役側の従者など、「ワキツレ」というと、ワキの住者になります。 さらに、シテやツレに付き従う従者の役に対しては「トモ(供)」という呼び名もあります。 【子方(こがた)】能だけの、ちょっとした特別な子役 ――先日、拝見した舞台に出ていた子どもが凛々しくて、とても可愛かったです。 源次郎 「子方」です。いわゆる“子役”なのですが、能の場合はちょっと違います。 まず、“子どもの役”を子どもの役者が演じる場合。現代劇でもある、普通の子役ですね。これには『百万』や『桜川』の子方、『鞍馬天狗』の牛若丸、『隅田川』の梅若丸などの役があります。 次に挙げられるのが、能に独特な“天皇や貴人の役”です。 能は身分の高い人(貴人)の前で演じられることもありました。しかし天皇・皇族や貴人を大人が演じると似合わないことが多いのです。本当の貴人の前で大人の貴人の役を演じるのは憚れる、ということもありました。そういうとき、子どもが演じることでかえってリアリティが出るんですね。それが慣習化したのが“大人の役”を子どもの役者が演じる場合です。 こちらは『船弁慶』の義経、『国栖』の天武天皇、『花筐(はながたみ)』の継体天皇などですね。 <◎能の物語には、ジャンルが五つ> 【五番立】五つのジャンル「神・男・女・狂・鬼」 ――能のプログラム的なことを教えてください。ジャンルが五種類ある、とお聞きしたのですが? ・源次郎 じつは昔は、一日に七番、九番立のプログラムが組まれて、丸一日かけて能を楽しんでいたのです。そして、たくさんの謡曲を無理矢理分類したのが神・男・女・狂(雑)・鬼なのです。「神・男・女・狂・鬼」の五つの曲趣に分別された中から一曲ずつ、計五番を一日で演じるのが「五番立」です。そして能の合間あいまには狂言が演じられたのですね。 現在の能の公演は二時間におさまる構成が多く、能→狂言→能のようになっています。 <能には歴史の秘密が隠されている> <◎「国栖(くず)」――天武天皇の身を守った吉野の先住民族たち> 聞き手(以下、――) 能に隠された日本史の秘密を探る、というテーマなのですが、能が日本の歴史とどうリンクしているか、能の知識がなかったり、鑑賞に慣れていない初心者にもわかりやすい曲を教えてください。 大倉源次郎(以下、源次郎)そうですね、たとえば古代の天皇の隠されたエピソードを伝える能はどうでしょう。その一つが『国栖』です。古代の日本を大きく変えた天武天皇の、壬申の乱(672年)前夜を謡った曲です。 天武天皇の兄・中大兄皇子(のちの天智天皇)は、乙巳の変(大化の改新・645年)で歴史に残るクーデターをなしとげ、古代日本の政治を刷新しました。そこに始まる歴史の大変化がこの能に謡われているのです。 ――天智天皇が崩御すると、息子の大友皇子(諡号・弘文天皇)と弟・大海人皇子(のちの天武天皇)とが後継を争うことになってしまいます。世にいう壬申の乱です。 ・源次郎 この曲『国栖』にははっきりと、「吉野山地の奥に住む人びとが天武帝を守った」「権現(ごんげん)思想を奉ずる人びとが帝の後ろ盾についたのだよ」ということが描かれています。 天智天皇七(668)年から天武天皇元(672)年の4年間に起きた歴史上の出来事が、能に謡われているんです。 能では天武天皇を子方が演じ、「伯父何某の連(むらじ)に襲われ」ということになっています。しかし史実では大海人(おおあまの)皇子は壮年で、政敵・大友皇子はまだ若い。二人は叔父・甥の間柄ですから、『国栖』ではこれらの関係がなぜか逆転された設定になっています。能楽研究者の故・表章先生も「これはおかしい」と指摘され、天野文雄先生も「これは謎です」と首をひねっておられました。 さておき、天武天皇一行をかくまう老夫婦は、国栖族と呼ばれる先住民族です。平地の民族と違って米を食べず、山の幸(根芹などの山菜)や川の幸(国栖魚=鮎など)を食べて暮らしていたそうです。川に小さな舟を浮かべて漁をし、その舟で吉野水系を自在に移動していました。 ・翁はすごい剣幕で、山や谷に響きわたる大声を出して一族を呼び寄せようとしました。多勢に無勢と、追っ手は慌てて退散します。 この吉野の山中には翁と同じ国栖族の仲間が大勢住んでいるのです。 ではなぜ、大海人皇子は助けられ、天智帝側の兵士は追い払われたのでしょう?それは国栖の人たちと天武天皇とは同じ信仰を奉じていたから、ではないでしょうか。それが権現思想を信じる人びとから支持された、追い払われた天智帝側の人たちはどちらかといえば神道系だった、と考えられます。 国栖の翁は、兵士が家や舟を捜索しようとしても勝手にさせません。ほうほうの体で追っ手が去り、騒動が落ち着くと、官人が老夫婦を称揚し、帝もみずから感謝を示されます。老夫婦は、かたじけない、と感激の涙を流します。 現行の演出では、夜も更けたところで「中入」となり、老夫婦はいったん退場します。再び現れたとき、媼は天女に、翁は蔵王権現に変じています。 蔵王権現とは、吉野山中の金峯山寺・蔵王堂に祀られる菩薩さまです。 ・こうして終盤に蔵王権現が顕れることで、国栖族は権現思想を信奉した人びとだった、ということが明かされます。 ・『国栖』は、追いつめられた大海人皇子が、吉野山中で権現思想の民族=賀茂族や国栖族と出会い、助けられて復活し、ついに政権を取った、という物語です。別の言い方をすると、天武天皇は吉野で、山岳信仰の人びとの大きなネットワークに助けられた、ということです。 <◎権現思想とは何か――鍵を握る“役行者”> 源次郎 権現思想は『国栖』だけでなく、ほかの曲にもしばしば現れます。いわば、能楽に広く影響を与えた重要な宗教思想です。 「権現」とは“姿を持たないあらゆる神仏が、神仏習合から生まれた日本独特の神や仏として顕れる”という意味です。「権現」の「権」とは、「権禰宜(ごんねぎ)」「権大納言」などの「権」と同じで、「仮の」という意味です。「仮に現れる」から「権現」なのです。 <◎京の都を席巻していた天台宗と、世阿弥のすごい関係> ・源次郎 比叡山は、のちに念仏宗の法然・親鸞や、法華宗の日蓮、禅宗の栄西・道元など立派な宗派の宗祖を輩出しました。それだけ多くの人材が集まったということです。 天台宗の中心思想は法華経ですが、密教・念仏・禅なども含んでいて、仏教数学の総合大学のようなものだったといえます。 ・――本地垂迹とは、「日本のローカルな神々は、じつはインドの仏さまたちが化身したものだ」という思想ですね。 源次郎 そうです。ですがこれ、「神仏の姿は皆、仮のもの」という権現思想に似ていませんか? <能の謎の中心――翁と秦氏> <翁面(おきなめん)が各地の神社でご神体になっている謎> ・聞き手(以下、――) 大昔の能楽師たちが日本の各地からもち帰った物語は、どのように能の曲になり、今に伝えられたのでしょうか。その代表的なものは? 大倉源次郎(以下、源次郎) 一番に挙げるなら、『翁』でしょう。 能の中でも『翁』は特別な曲です。じつは「能にして能にあらず」と言い伝えられていて、ほかの曲のようなストーリーがありません。詞章も「とうとうたらりたらりら」という謎の呪文のような言葉から始まります。 もう一つ、『翁』の舞台では、能役者はほかの曲のように面をつけた姿で登場するのではなく、直面(素顔)で登場し、舞台上で面箱から翁の面を取り出して、お客さまの前でつけるのです。 それほど一種独特な曲であるにもかかわらず、やはり『翁』は能を代表する重要な曲なのです。 『翁』の舞いは天地開闢、天孫降臨、ビッグバンといった宇宙の出来事を象徴的に表している、とされます。すべての能が演じられる前に一番はじめに演じること、あるいは新しい舞台をはじめて使うとき、正月などの節目に上演する特別な「始まり」の曲です。 『翁』の曲構成は、各地の祭礼に見られる翁舞、翁藝能のパターンと共通しているといわれます。能の『翁』に関してもほかの曲とは分けて、特別に「翁藝能」と呼びます。 老いて神仏の境地に近づき、にこやかに微笑む老人は、近未来の象徴といえます。その老人が舞台上で「天下泰平、国土安穏」を祈願し、この“所”(場所)に集まった人たちを祝福する、あるいは鎮魂する。こうした構造を「予祝藝能」といいます。 ・能の古い形が今も生きている、いわば古典中の古典のような曲なのです。 始まりの頃の能楽師が、各地で、春の田植えや秋の収穫などの節目で演じたのがこの『翁』と各種の「藝能」だったことでしょう。 ・最初、そのご神体は岩や巨木のような依り代だったと思うのですが、だんだんと変わっていきました。たとえば丹波地方では翁面をご神体とする神社が多いのです。ほかにも翁面をご神体にする神社は多々あると思います。 おそらく翁藝能の発生と伝播にともなって、翁面がご神体となっていったのでしょう。仏教が東大寺から国分寺として全国に広がったように、寺社仏閣が協力して広げる全国ネットワークと、翁面の伝播ルートは完全に一致するのです。 これらの変化がいつの時代に起きたかを調べれば、もっとスリリングな日本の歴史がわかるのではないでしょうか。 <水田稲作と切っても切れない“在原(ありわら)”『伊勢物語』> 源次郎 翁藝能を稲作とともに広めたのは、在原氏ではないかと私は考えているんです。平安時代前期の頃でしょうか。 ――平安時代の前期、承和(じょうわ)(834〜848)や貞観(じょうがん)(859〜877)年間は、九州から奥州(現・東北地方)まで、藤原家が全国に勢力を伸ばした時代だそうですね。京都から九州・奥州へということは、貴族制度を支える荘園文化が各地で起こった天変地異などをきっかけに全国に広がったともいえるかもしれません。 承和の変では大伴氏・橘氏などの名家が追い落とされ、いよいよ藤原氏の権力が強くなっていきます。 源次郎 荘園制度の普及とともに、おそらく水田稲作も改良されていくと思うのですが、より進んだ水田稲作とともに能面も広がっていったのではないか、と思います。 ・翁というのは老年男性への尊称になっている通り、老人、大変に年をとった男性のことです。 稲積翁は、長年の経験と知恵で稲作を完成させる、ということの象徴ではないでしょうか。一人の人間ではなく、何世代もの人間が長老や先達の知見をもとに稲作を工夫し、それが成功する、という意味ではないかと。 米作り、稲作というのは大変な農作業です。今は水田といえば平野部に広がっているから、昔から平らな平野に田んぼを作っていたかのように思いがちですが、先にも触れたように、じつは平野にまんべんなく水を引くというのは平野部に水田を広げたときに出た残土を積み上げて作った、という説を最近知りました。なるほど、たしかにどちらも相当の土木技術がないと作れませんからね。 <『翁』――謎の翁たちは在原氏なのか> ・源次郎 在原の業平は『伊勢物語』では色男、陰陽の神のように描かれているけれども、じつは生産の神さまなんですね。陰陽の神さまですから男女の和合にも関係してくるのですが、要するに作物がどうすればできるかを知っている人たちなんです。 <大地震と管丞相(かんしょうじょう)> ・源次郎 ちょっと寄り道をしましょうか。“貞観大震災五点セット”というものがあるのだそうです。非常時持ち出し品ではなく、歴史の話です。 まず富士山の大噴火(864年)。次が播磨国大震災(868年)。そして陸奥国(現・東北地方)を襲った貞観大地震(869年)、それと日蝕(873年)。残る一つは? 菅原道真なんです。 ・さて、この五点セット、現代でもあったというのです。 まず阪神淡路大震災(1995年)、そして東日本大震災(2011年)。日蝕は2012年に九百年ぶりの見事な金環食が観察されたとのことです。さすがに富士山の噴火は起きていませんが……。 では菅原道真は? これがいたんですね。それも東日本大震災のときにいたんです。事故翌日の3月12日に福島第一原発の緊急視察に、菅直人総理大臣がヘリコプターで飛んでいった。 菅総理とは、古い言葉でいうと“菅丞相”にほかなりません。「原」が省略されていますが、貴人の古い呼称では「菅公」「藤家」など氏の一字で呼ぶのです。 ・在原氏は源氏や平氏と同じく姓を賜って臣籍降下した天皇家の傍流です。菅原氏は古代から天皇家に仕えた家臣の家系。藤原氏も家臣の家系ですが、歴史の中では藤原氏が押しも押されぬ主流派となってゆき、「望月の欠けたることもなしと思えば」と謳うほどの藤原の天下をつくっていきました。奈良時代から平安時代にかけて一大勢力だった興福寺も、鎌倉時代以降の大勢力となった本願寺も、皆、藤原氏と関係する寺院でした。 仏の教えで民衆をつかみ、経済効果を上げて、結果的に藤原氏が天下を支配したと批判材料にされますね。 菅原道真が地震について述べた百年、二百年後、東北に赴いて東蝦夷(アイヌ?)の地を開拓していった人たちも藤原氏の系統です。奥州藤原氏のもとになった人びとで、11世紀頃でしょうか、藤原氏の勢いが日本の隅々にまで及んでいきます。 その藤原氏のスポンサードを受けられたおかげで、猿樂は活躍の幅を広げていき、やがて能楽が生まれる下地になるのです。それは確かなんですね。 <◎驚くべき国際社会だった飛鳥・奈良時代> 源次郎 もう一つ寄り道して、少し時代をさかのぼりましょう。 6、7世紀には聖徳太子がたくさんのお寺を建てました。奈良に法隆寺、法起寺、中宮寺、橘寺、葛木寺。これに加えて難波の四天王寺、京都太秦の広隆寺が、太子建立七大寺と呼ばれます。また、太子建立四十八院という伝承もあり、たとえば奈良大淀町の比曾寺(ひそでら)などが挙げられます。 当時のお寺は単なる宗教施設ではありません。僧侶の修行道場・教育や研究の専門機関というだけでもない。もちろんそれらの機能はあるのですが、それに加え、外交などのデモンストレーションや祝祭も担う、一大文化センターだったのです。その代表が東大寺です。 6、7世紀の朝鮮半島は三国時代(高句麗・百済・新羅)ですが、日本と関係の深い百済が盛んでした。日本で大きな寺院が開闢するときには、大陸からは百済を通ってさまざまな使節が来ていたと思います。使節には藝能をつかさどる楽人や舞人も大勢含まれていたはずです。藝能は当時の外交儀礼には欠かせなかったからです。 <『梅』――権現思想と対立する儒教思想> ――なるほど、藝能の歴史に当時の政治や戦争が大きく影響していた、というのはたしかにありそうですね。むしろ影響を受けないほうがおかしいです。 源次郎 数世紀にわたってさまざまな渡来人がやってきた、これはもう歴史の定説として確定的だと思います。しかし、先住民たちとどのようにして仲よくなったのかがわからないのです。 たとえば、私は、徐福伝説の渡来人たちは仏教の影響を受けたユダヤ教徒だった、と考えています。では、その人たちが日本に入ってきたとき、アニミズムである多神教の先住民たちとどのように付き合っていったのでしょう? 戦争して征服したのでしょうか。平和的に取り込んだのでしょうか。 繰り返しますが、定説では3世紀以降の大和、つまり奈良にはさまざまな民族が入ってきました。難波からは巨大古墳の文化を持った人たちが、越前からは継体天皇とその一派の人たちが、また熊野からは神武東征の伝説を示す勢力が入ってきたとの考え方があります。あるいは伊勢など別のルートもあったのでしょう。 奈良盆地に多くの民族がひしめき合った結果、奈良は歴史の舞台として栄えましたが、争いも絶えませんでした。聖徳太子の時代、あるいはもっと前の第21代雄略天皇の時代から壬申の乱まで、戦乱が繰り返し起きています。 ・――都が奈良から京都へ移って、宗教的な権威も南都仏教から北嶺の天台仏教に移ります。どんな変化が起きてきたのでしょうか? 源次郎 そうです、天台宗が大きく台頭してきます。ですから謡曲、観阿弥や世阿弥が能をつくり出した頃の曲には、天台の教えが数多く入っているのです。梅原猛さんはそれをよくおっしゃっていました。「神仏習合の原型がそこに描かれている」と。 天台宗は仏教の立場から神仏習合を打ち出してきました。神道も神道で、神宮寺を建てるなどして仏教勢力を取り込む、といいますが宥和していこうとします。このトレンドは長く続いたと思います。 <『養老』――権現思想と風水思想で国家をととのえる> 源次郎 ひるがえって、権現思想にもとづいたお能の例を挙げてみましょう。たとえば『養老』ですね。室町時代、世阿弥作と伝えられる曲です。 ・つまり、お互いに扶け合って、豊かな国を造っていきますよ、といったことを謡うわけです。こうしてひと言ひと言を見ると、『養老』という曲の詞章は、まさしく権現思想を、そして国のあり方のようなものを謡い上げていることがわかります。 これを室町幕府の将軍宣下のときにプレゼントする。能楽師の心意気です。 <足利将軍・信長・秀吉もできなかったことをなしとげた徳川家康> 源次郎 謡曲『養老』に込められた意味が足利将軍には百パーセント伝わっていたのかどうか。もし伝わっていれば、足利政権はもっと続いたかもしれませんね。 ――それでも徳川政権に次いでおよそ235年も続いたのですから、立派ではないですか?この足利政権時代から戦国時代を経て、信長、秀吉の時代に、能が全盛を迎えますね。2016年の大河ドラマ『真田丸』でも秀吉の能好きの様子や武将たちの謡曲の素養が描写されていました。 源次郎 武田信玄や上杉謙信なども能の庇護者で、力の弱った足利将軍家から離れて地方へ散っていった能楽師たちを大勢保護しました。 <「謡」が方言を超えて、日本の共通言語になった> 源次郎 能楽が正式に武楽に制定されたのと同じ時期、参勤交代も精度として定まりました。 参勤交代というのは、「特産物を江戸に届けよ」という儀式でもあるわけです。つまり、全国各地の大名に「おのおの領民を督励して特産物を造らしめよ」と命令したのです。当時はまだまだ全国規模の流通網はありませんから、今でいう「地産地消」として全国各地で特産品に力を入れるようになった。これが全国の経済と文化を非常によくしていきました。 一方、能楽が武家の式楽に制定されたことで、全国に読み書きのできる人が増えました。 お能の基礎は謡、謡曲です。これをどのように習うかといえば、要は謡のできる人に弟子入りして、謡本を見ながら、先生のお手本にしたがって謡い、覚えていくのです。 ――よく「江戸時代は識字率が大変に高かった」といわれますが、文字を読み書きできたのは神官・僧侶や医師などの知識層と、庄屋・名主・行事など村役人と呼ばれる統治層だけだったそうですね。 しかし武家が皆、謡を習うようになると、それを真似て、農民や町人など庶民も謡をするようになった。庶民も謡本を手にすることになり、その結果、読み書きをするようになったのですね。 <『石橋(しゃっきょう)』――能楽師が“ゾーン”に入るとき> ・源次郎 あるとき、狂言師の野村萬斎さんが「オリンピック選手がいい記録を出すときは“ゾーン”に入るという言い方をされている」と話しておられました。なるほど、「ゾーンに入る」というのはよい表現だなと思いました。 私たち能楽師も舞台に臨んでいるとき、そういう“ゾーン”に入ることがあるのです。面白いことに、何十年も稽古をしないとこの境地に至らないかといえば、そうでもない。子どもでも“入る”ことがあります。 舞台には魔物が潜んでいるといわれますが、「この子はもう完全に入っているな」と思うときがある。そういうチャンネルを開くことができる子どもは羨ましいです(笑)。 <◎魂魄の記憶> 源次郎 『翁』が表現しているのは天地開闢、ビッグバンです。これを演じるというのは、始まりはここです、ですから皆さんくだらない喧嘩などやめましょう、というメッセージだと思うのですね。天地開闢に思いを馳せる、ビッグバンからの記憶が翁藝能には内包されています。 記憶には、細胞のタンパク質の中に宿るものと、もう一方の意志や意欲として顕れるものとがあるわけです。それを「魂」と「魄」に分けて考えます。魂が根源的な直感とすれば、能はその時の感情や意志的なものだといえます。合わせると「魂魄」という言い方になります。 <古代仏教寺院で展開された、世界最先端芸術ショウ> <能はさまざまな民族と歴史の藝能を取り入れたミュージカル> 源次郎 本書でお話ししている歴史は、けっして宗教学者や歴史学者の方々が認める学説などではありません。藝能者としてずっと伝わってきた曲を演じ続けることで感じてきたことなのです。 口承文学と同じで、身体で演じ続けていることの強みがそこにあります。そんないい加減なことを語っていいのか、とお叱りをいただくかもしれませんが、能自体、かかわった人の数だけ解釈が生まれる藝能なのですから。 <「翁狩衣」と蜀江錦、バチカン> <謎に満ちた聖徳太子と、太子を支えた秦氏> 源次郎 三国時代が終わると蜀=蜀漢という国はなくなりましたが、蜀という呼び名は残りました。蜀江錦も作り続けられ、貴重品として日本にも西洋にも売られていきました。蜀とローマ・バチカンがつながっていた、ということは蜀江錦という証拠によってはっきりしています。ではそれが日本に入ったのは?翁藝能の原型になるものを日本に伝えたのは、渡来人の一族、秦氏だといわれています。 秦氏は3世紀の応神天皇の頃に百済から日本に帰化した、あるいは5世紀雄略天皇の御代に新羅から渡来した、いや中国本土から渡来した漢民族系だ、などと謎に包まれた一族です。 はっきりしているのは、先進的な知識や技術で飛鳥時代以降、大和朝廷を支える大きな力になったこと。人口が多く、戸籍記録に載っているだけでも数万人もいたこと。きわめて有力な豪族でした。 秦氏は大陸から、感慨や陸墓造営などの土木技術者、寺院や神社の建築技術、養蚕・機織り・酒造の技術、そして紙や楽器を携えてきました。秦=機織り、の語源とも考えられます。 飛鳥時代の秦氏で著名な人物は秦河勝です。 ・――太子が建てた法隆寺の伽藍はなぜ現存しているのか。なぜ山背大兄王はじめ一族が突然滅びたのか。『日本書紀』や『聖徳太子伝歴』、『上宮聖徳法王定説』にある数々の奇跡の記述は事実なのか。あまりに謎に満ちているので、聖徳太子=実在しなかった説まで唱えられています。 奇跡の多さに、イエス・キリストを連想する人もいるでしょう。馬小屋で生まれた、という伝説一つだけでも似ている! と思ってしまいます。 たとえば『日本書紀』に、聖徳太子が片岡山を通ると飢えて寝ている人がおり、太子は憐れんで食物と服を与えたが亡くなったとの報せがあり墓に葬った。数日後、太子が命じて墓を開けると遺骸はなく、畳んだ服が棺に置かれていた、という記事があります。 これなど、『新約聖書』にある“ラザロの復活”とそこかしこが似ているのです。 源次郎 最近では、渡来人・秦氏とユダヤ民族には関係がある、といったこともイスラエルでは常識的に、日本でもオープンに語られるようになりました。とすると、聖徳太子の伝説にはなぜかキリスト教の影がつきまとっている、という謎も自由に考えてみてもいいのではないでしょうか。 がんばって考え続けてみましょう。 史書によると、聖徳太子は歴とした皇族ですから、キリスト教と関係のある渡来人などではありません。では、太子という存在にキリスト教の影を投影したのは誰か。 太子ともっとも関係が深かった豪族は蘇我氏です。蘇我馬子は太子とともに『国記』『天皇記』を著していますし、太子自身、蘇我系の皇妃の血を引いています。 ・しかし聖徳太子と蘇我氏は一心同体というより緊張をはらんだ協力関係だったようです。互いに利用し合い、牽制し合う関係です。太子は天皇家の権威を、蘇我氏は豪族の権力を追究したので、本来的には対立したのだと思います。 太子の側近として重要な枠割りを果たしたのは秦氏、秦河勝でしょう。 上宮王家とまで呼ばれた聖徳太子の一族は、山背大兄王が蘇我入鹿と対立したため、一族すべて滅んでしまいました。その後我が世の春を謳歌した蘇我氏も、乙巳の変(大化の改新)で入鹿は殺され、蝦夷は自害し、蘇我宗家は滅びます。 蘇我氏の中には中大兄皇子・中臣鎌足側に協力した石川麻呂という傍系有力者もいたのですが、のちに謀反を疑われて自害しています。蘇我氏も滅びてしまったのです。多くの氏族が聖徳太子と深くかかわっていますが、そのひとつが秦氏なのです。 <秦氏が残した謎のメッセージは、今も能の中に生きている> ――とすると、聖徳太子の生涯に見え隠れする数々の奇跡の意味もわかってくるかもしれません。すでに滅びてしまった聖徳太子とその一族を顕彰し、遺徳を語り伝えたのは、秦河勝以降の秦氏にほかならないわけですよね。 秦氏にとっては、聖徳太子が偉大な聖人であればあるほど、それを支えた河勝も偉かったということになるからです。 源次郎 ここでもう一度『翁』に注目してみましょう。『翁』は三人の人物によって舞われる曲です。まず「千歳」という、直面(素顔)の若い男。次にシテの翁ですが、白い面をつけるので「白色尉(はくしきじょう)」と呼ばれます。最後に狂言方が舞う「三番叟(さんばそう)」です。狂言方は前半は若い男の姿で「揉之段」を踏み、後半は鈴を持って「鈴之段」を踊ります。これは黒い面をつけるので「黒色尉(こくしきじょう)」。白いお爺さんと黒いお爺さんと若い男、の三人なのです。 この組み合わせで何かを連想しませんか? そう、キリスト誕生を祝福しに訪れた東方の三賢人です。 <日本史の影に存在した渡来人・秦氏と能楽> ――ここで秦河勝一族について、簡単にまとめておきましょう。ごく定説的なまとめです。 秦氏は一説に3世紀から6世紀頃、朝鮮半島を経由して日本にやってきた大陸系渡来人です。秦氏という氏族の名は始皇帝の秦に由来するとの伝承があるので、本人たちは秦の末裔を自任していたということでしょう。 源次郎 当時の渡来人は先進的な技術や知識をもってやってきました。秦氏はその一方の代表で、もう一方の代表は漢氏(あやうじ)でしょう。これは漢の劉邦一族の末裔を称し、奈良に本拠を置いた東漢氏(あずまのあやうじ)と大阪湾方面の西漢氏(かわちのあやうじ)とがあります。 秦氏の特徴は人数が多いことで、欽明天皇在位頃の戸籍には七千戸以上の秦姓が記録されています。古代律令国家では家族と郎党合わせて25人ほどで一戸を構成したといいますから、その計算でいくと17万人以上の動員力をもつ大勢力ということになります。 ――その頃から秦氏は「大蔵」や「内蔵」をもって朝廷に仕えたとされていますね。「蔵」とは財政のことですから、財力で朝廷の権力を支えたのですね。 源次郎 古代の秦氏でもっとも有名なのは先に触れた秦河勝で、欽明・敏達(びだつ)・用明・崇峻・推古の五代の天皇に仕えたともいわれ、推古朝では聖徳太子のもっともそば近くに仕えました。河勝は山城、今日の京都府に領地をもっていました。山城とは山背とも表記されます。聖徳太子の長子である山背大兄王は、山城の秦氏を後ろ盾にして育ったとも考えられます。皇族の名前にはしばしば地名が使われますが、それはパトロンの所在地であったり育った場所だったりするのです。 一説には山背大兄王子とその一族は聖徳太子歿後、蘇我入鹿に皆、一度に滅ぼされます。 <『翁』の祈り、神さまのお辞儀> 源次郎 『翁』はすべての曲の中でもっとも古く、神聖とされる曲です。特別な曲であるため、能の「五番立」(神・男・女・狂・鬼)のどれにも分類されません。能楽師だけで演じるのではなく、三番叟は必ず狂言師が演じます。果たしてこれは能に分類できるのか、ともいわれます。「能にして能にあらず」といわれる所以です。 能でも狂言でもないかもしれない。それゆえ『翁』だけ特別に『翁藝能』として語られることがあります。 『翁』は祝福の曲です。おめでたいことがあったときに特別に舞われます。 ・この『翁』の舞いの最初と最後には翁がお辞儀します。この礼が誰に対してのお辞儀なのか、謎といえば謎なのです。 『能を考える』 山折哲雄 中公選書 2014/3/14 <「翁」とは誰か> ・最初の問題であるが、私はかねて仏像の顔はその多くがみんな若々しいのに、古い神像の方にはむしろ森厳な老いの表情が漂っているということに不思議な思いを抱いていた。「ホトケは若く、カミは老いたり」とつぶやいていたのである。 ・そういえば記紀神話や八幡神の縁起などをみると、神々がしばしば老人の姿をとってこの世にあらわれるシーンがでてくることに気づく、天つ神が地上に降り立つとき、年たけた老人が出現して「われは国つ神」と名乗り、案内の役をかって出る。八幡神や稲荷明神は、地上の神主の懇請によってこの世に姿をみせるが、そのときは容貌魁偉な老翁に変身するのである。 そのようなこの国における古くからの伝承が、神像をつくるときに蘇ったのではないだろうか。翁(老人)は目に見えない神の存在にもっとも近い存在として尊ばれ、信仰の対象とされていったのである。 ・要するに、一口にオキナとはいっても、わが国には優しい「翁」と怖い「翁」という二種類のオキナの系統があったといっていいのではないだろうか。換言すれば、神に近いオキナと人間に近いオキナがどうも存在していたらしい。そして、おそらくそこからは、オキナの両義性といった問題までが生ずる。 ・佐成謙太郎氏の『謡曲大観』には、235番の曲が収められているが、そのなかに、いわゆる翁の姿でシテとして登場するのが50数番ある。そのほとんどは夢幻能で、そこにあらわれるシテは神霊であるか、または歴史上の人物の亡霊が姿を変えたものだ。「翁」は神霊や亡霊の化身として、舞台の上にしずしずあらわれる。それが歴史上の人物である場合は、はじめは翁の姿(前シテ)であらわれ、やがてその正体(後シテ)をあらわす。 後シテは胸のうちにつもり積もった怨念や心残りを掻き口説き、やがて生きている者(多くは僧)の回向と慰めの言葉をうけ、舞を舞って退場していく。翁変じて亡霊(または神霊)の正体が現れ、舞台は急速に終息に向かう。 ・ここでとくに注目したいのは、右の夢幻能に登場する翁の仮面がすべて尉面(注;老翁の相を表す能面の総称)であるということだ。さきの分類でいえば、怖い翁に属する。 ・このように考えてくると、この尉の仮面表情がいつしか時空のへだたりを飛びこえて、何とも不思議なことにあの松尾大社の男神像の表情にしだいに似てくることに気づく。 <「翁」はどこから来るか> ・翁のことを考えるには、やはり折口信夫の仕事に注目しないわけにはいかない。かれは昭和3年(1928)に「翁の発生」という論文を書いているが、そこに展開されている仮説が導きの糸になる。その要点は二つである。 第一は、能の<翁>や<高砂>にみられる翁の舞は、猿楽の伝承にもとづいてつくられたもので、それに先行する反閇芸や鎮魂・祝禱の儀礼から発展したものだという。 折口のいう第二の論点が、翁舞の翁の姿は山神のイメージと結びつく、ということだった 。その山神の源流をたどっていくと、「まれびと」(稀なヒト)の信仰にまでいきつくという仮説である。「まれびと」というのは折口の独自の概念で、農村のような定住社会に外界から尋ねきて祝福を与えるもののことをいい、新しい技術や知識を伝える一種の人神(ヒューマン・ゴッド)のようなものだ。定住民にたいして遊行・漂泊の民といってもいいし、異人といってもいい。 ・ところが、この二人組と一人稚児による翁舞は、古くは三人の翁によって演じられていたところが、この二人翁と一人稚児による翁舞は、古くは三人の翁によって演じられていたらしい。というのも当の能楽を大成した世阿弥は、主著の『風姿花伝』のなかで、翁舞は稲積の翁、代継(経)の翁、父の助(尉)の三人の老翁によって勤められるといっているからだ。 ・私は前に、日本文化における老人=翁の信仰が、歴史的に優しい翁と怖い翁という二つの表情を生み出したということを考えてみた。 ・そのことについて、最後につけ加えておきたいことがある。私は怖い翁とは「神に近い」老人のことだといったが、そのことについてである。いったいどうしてそうなのか。これについでは、柳田國男『先祖の話』のなかでいっていることが参考になると私は思っている。かれはそこで、日本人は古く、人間は死ねば家や周辺にある山や森や丘にのぼって祖霊になると信じてきたといっている。死霊が祖霊になり、さらに供養をうけて一定期間をへると、最後にそれがカミになる。このカミはやがて正月や盆などの季節になると里に下りてきて、村人を祝福するのが常だった。それらのカミはさまざまな形をとるようになるが、そのなかから鎮守の神や産土の神となるものが現れ、氏神として祀られるようになった。つまり日本人の深層意識に、人間は死後カミになり、この世の生者たちと交流する、という基層的な信仰ができ上がったというのである。 『大いなる秘密』(爬虫類人・レプティリアン) (デービッド・アイク)(三交社) 2000/8 <いわゆるメン・イン・ブラック(黒服の男たち) 、MIBと略されたり、「ブラックメン」などとも呼ばれる。> ・UFO研究所の周辺によく現れ、ときにCIAやFBIと偽称し、研究の妨害等を行う。黒い帽子に黒い服を着ていることが多いため、この名がある。近年では、研究所ばかりではなく、異星人やUFOに関する情報に深入りした人々に脅しをかけることで知られているが、彼らメン・イン・ブラック(黒服の男たち)が実体化したり非実体化するのを見たという情報が数多く上がっている。 ・それもそのはず、彼らは、次元と次元との間を自在に行き来する能力を持ち、あらゆる形態をとることができるのだから、エリート一族に見られる強迫的観念的同系交配は、このような変身能力を与えてくれる遺伝子構造を維持するためのものだ。彼らが、次元の間を行き来し人間の姿とレプティリアンの姿のあいだを自由にシェイプ・シフトできるのは、彼らが受け継ぐ特異な遺伝子構造のおかげなのだ。遺伝子構造がレプティリアンのオリジナルから離れてしまうと彼らはシェイプ・シフト能力を失ってしまうのである。 『宇宙人遭遇への扉』 (リサ・ロイヤル&キース・ブリースト)(ネオ・デルフィ社) 2006/2 <琴座は地球が存在する銀河系宇宙の領域における、人間型生命体の発祥地である> <銀河系宇宙共同体> ・エネルギーのレベル、あるいは物質のレベルで、地球の発展とかかわりを持つ、物質的および非物質的な宇宙人の各種族を指す。琴座の各種族、シリウス人、プレアデス人、ゼータ・レチクル人、オリオン人を始めとして、本書で述べられていない多数の宇宙人種が、銀河系宇宙の一族を構成している。 <ヒューマノイド> ・肉体的な特徴が地球人と似ている宇宙人を指す。ヒューマノイド(人間型宇宙人―地球人もこれに含まれる)の血統上の起源は琴座に求められる。 <琴座> ・地球上には事座に関する神話が古くから残されてきた。なかには琴座とプレアデス星団との関係について述べたものもある。琴座は地球が存在する銀河系宇宙の領域における、人間型生命体の発祥地である。シリウス人、オリオン人、地球人、プレアデス人、ベガ人、ゼータ・レチクル人、ケンタウルス人、アルタイル人を含むさまざまな宇宙人は、すべて琴座で発生した種族の子孫である。 <ベガ> ・琴座の一等星で、琴座にありながらその中のどの星系よりも距離的には地球に近い。琴座の中で、統一性がある独自の文明を形成した最初の星の一つである。アルタイル、ケンタウルス、シリウス、オリオンなどを始めとして、ベガ人が人種の創成や入植を行った星系は多数ある。 <アストラル・プロジェクション> ・「星気体の投射」の意。西洋神秘学によれば、「星気体」(アストラル体)とは、肉体よりも精妙な周波数からなり、通常は肉体と重なり合って存在する「身体」のことである。ある種の人々は意志の力によって、この「身体」を外部に投射でき、通常の感覚を保ったままで、これを通して旅をすることができる。 『怪異を魅せる』 怪異の時空2 飯倉義之、一柳廣孝 青弓社 2016/12/1 <『子どもと怪異』> <――松谷みよ子『死の国からのバトン』を考える 三浦正雄 / 馬見塚昭久> ・『死の国からのバトン』(偕成社)、は、『ふたりのイーダ』(講談社)などとともに、松谷みよ子が20年以上の歳月をかけて完成させた「直樹とゆう子の物語」5部作のなかの1冊である。5部作それぞれに直樹とゆう子が登場するものの、1作1作は完結した物語になっている。 この5部作は、社会問題を扱った「告発の児童文学」として知られるが、実はもう一つの大きな特色がある。いずれも題材として怪異が取り入れられているのである。特に『死の国からのバトン』は、タイトルのとおり、主人公の直樹が死の国へ赴き、バトンを託されて帰還するという物語で、いわば現代の冥界訪問記である。 ・向日性や理想主義から脱却し、多様性に富んだテーマを扱うようになった日本児童文学であるが、今日でもなお、本作品は特異な存在である。タイトルに「死」という言葉を使うこと自体がまれであるうえ、その内容も死んだはずの祖先と子孫が交流するという特異な題材を描いたもので、ひときわ異彩を放っている。特異な作品でありながら、従来、その点はあまり注目されてこなかったようである。 ・また、西田良子の「松谷みよ子論」は、本作品に通じる<根>として、<幼児的心性>と、<古代人的感覚>を探り当てた点で卓越している。だが、「松谷文学の特質である<幼児的心性>は、ややもすると、過度の幼児語使用となったり、<古代人的感覚>が時には呪術的迷信をも伝えてしまう危険性をもっている」とも語っていて、必ずしも肯定的に受け止めてはいない。筆者は「古代人的感覚」こそ、現代児童文学に最も必要な要素の一つであると考えるのであるが、西田はこれを「迷信」のひと事で切り捨ててしまっている。 ・では、なぜ松谷はこの作品を書いたのだろうか。公害の告発が主目的ならば、わざわざ「死の国」をその舞台に設定する必要はなかったはずである。実社会の被害状況をリアルに描いたほうが、はるかに訴求力のある作品になっただろう。作者の強い思いが込められているのではないだろうか。ここでは本作品の時代背景を探り、怪異の仕組みをひもときながら、作品に秘められた松谷の思いに耳を傾けてみたい。 <ムーブメントの交差点> <公害告発の文学> ・まず、「公害」という視点から、物語の時代背景を探ってみよう。本作品には、各地に伝わる伝説や民間信仰が複合的に組み込まれており、作中に描かれた公害は、阿陀野川に有害物質が流されて発生したという設定である。阿陀野川は松谷による架空の名称だが、昭和電工がメチル水銀を流し続けた阿賀野川を連想させる響きである。本文中には、「やがての、それがおさまると、ねこらは、目をうつろにみひらき、よだれを流し、足を引きつらせ、苦しげな息をはいて死んでいった」など、第二水俣病として知られる水銀汚染による中毒症状らしき記述も見られる。第二水俣病は、いわゆる四大公害病の一つだが、その他にも、高度成長の弊害ともいうべき公害が各地で報告され、1970年代初期には、「公害列島」なる言葉が新聞をにぎわした。 それに対し、公害問題に対する包括的な法律となる公害対策基本法が制定されたのは1967年、公害防止など、環境の保全に関する行政機関として環境庁が設置されたのが71年のことだった。 ・このような経過のなかで、公害問題を取り上げた文学も登場した。その先駆的な役割を果たしたのが石牟礼道子の『苦海浄土――わが水俣病』(講談社、1969年)だろう。この作品は、作者が患者たちの声にならない声を受け止め、自身のなかで純化させてつづったことで、比類のない訴求力を持つ作品になった。1974年には、有吉佐和子の『複合汚染』(新潮社、1975年)の新聞連載が始まり、大反響を呼んだ。 <民話ブームとニューエイジブーム> ・本作品巻末の解説で、安藤美紀夫は、「「ご先祖」が、けっして遠い存在ではなく、よく見れば、すぐ近くに生きているという実感も、それ[民話採集の旅:引用者注]をとおして得られたものに相違ない」と述べている。確かに、本作品は随所に民話的な要素がちりばめられていて、民話の強い影響を受けていることがうかがえる。 ・民話運動は1952年、木下順二を中心とする文学者や歴史学者が集まって「民話の会」を設立したのが、その始まりといわれる。松谷はごく初期の段階からこの会に関わり、民話の探訪と普及、啓発に努めてきた。彼らの活動は、民主的な歴史観の確立を目指した運動や、高度成長に対して伝統的な価値を再発見しようとした運動などと接点を持ちながら、日本固有の文化を再評価する機運を高めていった。やがてこの運動の影響によって、民話絵本や創作民話の流行などの「民話ブーム」が起きることになる。 <公害と民話の出合い> ・福井県大野郡和泉村に「公害を知らせに来た河童」として知られる民話がある。この村人たちは古くから河童と親しく交流してきたのだが、ある夜、村人たちは河童が悲しい声で「川の水をかえてくれ、川の水をかえてくれ、水がおとろしい、水がおとろしい」「もう住んでおれん」「あの川の水はお前さんらにもようないはずじゃ」と訴えるのを聞いた。だが九頭竜川は何の変わりもなく澄んで流れている。村人たちは相手にしなかったが、ある夜、河童たちは激しい雨のなかをよろよろと山へ立ち去ってしまった。その2年後、村人たちは行政からの知らせで、九頭竜川がカドミウムに汚染されていたことを知る。河童に対して申し訳なく、村人たちが山へ行って呼びかけると、「百年したらもどっていくさかい、それまでに川を綺麗にしておいてくれえ」と返事があったという。 <怪異の仕組み> ・本作品のなかで、主人公の直樹は、怪異に3回遭遇する。1回目は、五百羅漢でコドモセンゾの直七たちに出会ったこと、2回目は、崖から落ちて気を失い、直七に死の国へ連れていってもらったこと、3回目は、百万遍の数珠を回して直七を呼び出したことである。 <五百羅漢での邂逅> ・1回目の怪異は、1月14日の夕方、祖父母の家についてすぐのことだった。五百羅漢へ行こうとして裏山の雪道を歩いていた直樹は、大勢の子どもたちの歓声を聞く。ところが、声は聞こえても姿が見えない。「だれだい、でてこいよ!」と呼びかけると、五百羅漢の岩々が子どもたちの姿に変わり、直樹は直七と言葉を交わす。だが、そこに妹のゆう子がやってきて気を取られ、もう一度振り向いたときには、子どもたちの姿は消えていた。直樹はなぜここでコドモセンゾに会うことがきたのだろうか。 <小正月> ・直樹が直七に出会ったのは、1月14日の夕方ということになっている。14日の日没から15日までを小正月と呼ぶが、五百羅漢での邂逅はまさしく小正月を迎えようとしているときだった。小正月は元旦の大正月に対する言葉で、いまでも各地で粟穂、稗穂、成木責め、鳥追い、もぐら打ち、ドンド焼きなど、主として農耕に関わる予祝儀礼がおこなわれている。この小正月には、異界から何者かが村を訪れるという信仰があったのである。 ・来訪神接待の「来訪神」とは、小正月の訪問者と総称されている神霊に扮装した訪れ人のことで、各地各様の呼び方がなされており、名称上、ナマハゲ系、チャセゴ系、カセドリ系、トタタキ系、カユツリ系、トロヘイ系、オイワイソ系、その他(福の神・春駒等)に分けることのできる行事の主人公である。(略)これら来訪神の性格は必ずしも明確にされてはいないが、小正月の代表的な神であることに間違いはない。 ・直七たちもコドモセンゾも、まれにしか会えない異界からの来訪者という意味では、来訪神と呼んでいいだろう。五百羅漢での怪異は、小正月という特殊な時間の作用があって起きたのである。 <夢幻能> ・能には現在能と夢幻能があるが、夢幻能では生者と死者との交流が演じられる。例えば、『平家物語』を題材とした作品の多くは、死後も修験道で苦しむ武将が亡霊となって現れ、生前の栄華や死の苦しみを語っていく。 五百羅漢での邂逅は、こうした夢幻能における生者と死者との交流に通じるものがある。能ではしばしば、亡霊が出現する前触れとして不可解な自然現象が現れ、時空にひずみが生じ、ワキ(死者を弔うべき存在)が死者ゆかりの場所を通りかかることによって、シテ(死者)との交流が引き起こされる。シテは異界からの来訪者なので、時空間を支配する霊力を持っているのである。そこでは、現在から過去へと遡行する時間と、過去から現在へ順行する時間とが融合し、特殊な場が出現する。シテは遺恨を語り、ワキは新たな生を生き直すことができる。 <他界の巡歴> ・二回目の怪異は、直樹が直七と会話した直後、ゆう子を助けようとして岸から落ちたことがきっかけだった。直樹は、気を失って夢と現実の間をさまよう。やがて、鳥追いの列に直七を見つけた直樹は、ルウを捜すために、川向こうの「死の国」へ連れていってもらうことにする。「死の国」では、村に水路を引いた農民、直右衛門夫妻を訪ね、次に猫好きの喜平じい夫妻を訪ねる。直樹は、そこで白い猫に導かれ、思いがけず山のばばさに出会う。山のばばさは、死霊となって登ってきた猫たちに乳を飲ませていた。山のばばさは、死んだものの苦しみを和らげる不思議な力を持った存在である。 <三途の川> ・崖下へ転がり落ちた後、直樹は花が咲き乱れている野原をひとりで歩き、川の向こう岸に、亡くなったはずの父を見つける。直樹が川を渡ろうとすると、父は、渡ってはいけないと叫ぶ、しかし、どうしても行きたくて、流れに一歩踏み込んだその途端、冷たさと痛さで、直樹は正気づく。 松谷の手になる『現代民話考』(第5巻、立風書房、1986年)の第1章「あの世へ行った話」には、あの世を垣間見た人々の体験談が約260件紹介されている。その多くは、生死の境をさまよった際、三途の川が出現したというもので、向こう岸に知り合いの姿が見えたので渡ろうとすると「渡ってはいけない」と言われ、気がついたら病院のベッドに寝ていた、というような話である。特徴的なのは、川を渡ろうとしたけれども結局渡らなかったということであり、川を渡って向こうの世界へ行って戻ってきたという話は一件もない。 直樹が見た川も、まさしくこの川だろう。渡ったら最後、二度と戻ってくることはできないはずの川だったのである。 <他界巡り> ・ところが、再び意識が遠のいた直樹は、鳥追いの列に直七を見つけ、川までついていってしまう。そこで直七に頼んで向こう岸へ連れていってもらい、直樹は他界巡りを始める。 ・三途の川は、六文銭を支払い、船で渡るものというイメージが一般的だが、かつては生前のおこないに応じて、横、浅瀬、深瀬のいずれかを歩いて渡るものと考えられていた。 善人は橋を渡るので川の水には濡れないが、やはり死ぬことに変わりはない。すると、川の水に濡れる濡れないは、生死には直接関係ないということになる。直樹の場合は、直七に負ぶってもらうことによって自分の足で渡らなかった。だから、死なないですんだ、ということになるだろう。 直七という先祖の協力によって、直樹は生きたまま、この世とあの世の境界を超えることができたのである。これによって直樹は、他界巡りが可能になった。 <直七との交霊と空間移動> ・3回目の怪異は、足のけががあらかた治った1月16日の夜更けのことだった。直樹は床に就いたものの寝つかれず、どうしても直七に会いたくなる。彼に言われたとおり百万遍念仏の数珠を回してみると、そこに直七が現れ、雪靴を履かせてくれる。その途端、二人は目もくらむような眩しい雪の上に空間移動するのである。そこは五百羅漢で、直樹はコドモセンゾたちと羽子つきや掛けっこして遊ぶ。帰り道、直樹は亡くなったはずの父にも会い、理不尽なことと戦う覚悟を持つようにと、バトンを託される。この時空を超えた怪異の仕組みは、どのようになっているのだろうか。 <百万遍念仏> ・直樹が感じたのはおそらく、長い年月にわたって数珠に込められた、人々の鎮魂への思いなのだろう。直樹は、いまは亡き村の先祖たちと一緒に数珠を回した。蓄積された祈りが直七に届いたからこそ、直七が迎えにきたと考えるのが妥当ではないだろうか。民族行事、仏教行事としての百万遍には、先祖に呼びかける力が込められていて、直樹はその力によって、直七に会うことができたのである。 <先祖たちの力> ・百万遍の念仏に応じて現れた直七は、直樹に雪靴を履かせてくれた。その途端、二人は五百羅漢に瞬間移動する。これはどう解釈すればいいのだろうか。 五百羅漢での邂逅が可能だったように、霊は時空を超える力を持っていて、生きた人間の霊体をも連れ出しうるよう設定されているのである。 なかでも霊的な力が傑出した存在として、山のばばさがいる。 ・直七が、「生んで、そだてて、なにもかも土にもどして、またそこから、あたらしいいのちを生みだす」と語っていたとおり、山のばばさに遭遇したとき、ばばさは、公害病で苦しみ喘ぎながら登ってきた猫たちに、乳を飲ませて介抱していた。これは、松谷自身が民話の探訪によって得た胸乳豊かな山姥のイメージとも重なる。 <「祖霊信仰による魂の再生」> ・ここまで考察を進めてくると、「告発の児童文学」という世評とは別に、この作品のもう一つの重要な問題を見て取ることができる。松谷は、「祖霊信仰による魂の再生」というバトンを読者に手渡そうとしていたのではないだろうか。 現代っ子の直樹は、七谷を訪れるまで「先祖」について真剣に考えたことはなかった。ところが、直樹が先祖の地を訪れたことで、祖霊信仰のスイッチが入ったのである。天真爛漫な彼は、土地のお婆さんの話を真に受けて、阿陀野の山でルウを捜そうとした。そこに出現した直七を兄のように慕い、彼を信じて阿陀野の山を遍歴した。そこで、彼は、先祖たちとの交流を通して、脈々と続く命のつながりを知った。先祖たちの郷土への思いや無念を知り、その苦しみに思いを馳せた。一方、コドモセンゾや山のばばさは、村のために鳥追いをしたり、直樹を助けたりして、子孫でもある村の人々に何らかの浄福をもたらそうとしてきたのである。 ・こう考えると、直樹の他界訪問は、あたかも作品舞台のモデルとなった出羽三山を駆け巡る修験者の修行にも似ている。修験者が、なぜ他界に見立てた山を巡るのか、宮家準は次のように述べている。 このように修験道の峰入修行は基本的にはこの世から一度山中の他界に赴いて修行をして、再度俗なる里の世界に帰るという形式をとっていると捉えることができるのである。そして全体として見た場合は、修験道の他界観におけるこの世と他界の関係の特色は、このようにこの世の人間が他界に赴いて他界の神格の力を得て、この世に帰るということにあるといえよう。 ・父から託されたバトンが象徴するように、直樹にとっての「他界の神格の力」は、「現世を生きる勇気」である。阿陀野の公害について知らされなければ、直樹はこれまでどおり、平穏無事な生活を送っていたことだろう。知らなくてもよかった公害の実態と人間のおぞましさを知らされたことで、彼は生きることに疑問を感じてしまった。だが、現世に生き、命のバトンを受け継いでいくべき子孫として、それはどうしても乗り越えなければならない。成長のための試練だったのである。出発の朝から始まった一連の怪異を勘案すれば、この試練は、先祖たちが意図的に用意したものだったのだろう。 母親が迎えにきて、直樹たちがいよいよ祖父の家を出ようとしたとき、シロが子猫を生んだ。母親は、東京湾が水銀で汚染されていたことを告げ、直樹は、阿陀野で見聞きしたことが夢ではなく真実だったことを知る。この一連の結末は、先祖たちもまた、自己の苦しみを語り、バトンを託したことで、魂の安息を得たことを物語っているといえるだろう。直樹の他界巡りは、生者、死者ともに救われる「魂再生の旅」として提示されたのである。 『河童平成絵巻』 佐々木篤 ピエ・ブックス 2005/10 <かっぱ 〔河童〕> 1.想像上の動物。水陸両性、形は4〜5歳の子供のようで、顔は虎に似、くちばしはとがり、身にうろこや甲羅があり、毛髪は少なく、頭上に凹みがあって、少量の水を容れる。その水のある間は陸上でも力強く、他の動物を水中に引き入れて血を吸う。河郎。河伯(かはく)。河太郎。旅の人。 2.水泳の上手な人 3.頭髪のまんなかを剃り、周りを残したもの。→おかっぱ。 4.見世物などの木戸にいて、観客を呼び込むもの。合羽。 5.(川に舟を浮かべて客を呼ぶところから)江戸の柳原や本所などにいた娼婦。船饅頭(ふなまんじゅう)。 6.(河童の好物であるからという)キュウリの異称。 『広辞苑』(岩波書店)より ・日本人にもっとも親しまれている妖怪といえば、「鬼」、「河童」、「天狗」の三大妖怪があげられる。その中の「河童」は水辺の妖怪の代表格である。ただ、「河童」は妖怪というよりは未確認生物の先駆けとして、現代でもその実体が信じられるむきがあり、昭和のはじめまでは目撃の報告も数多く存在した。 現代の河童像といえば、童子のような姿、おかっぱの頭髪、頭上の水をためる皿、黄色でまんまるの目、とがった口、犬のような鼻の容姿にはじまる。そして、体は濡れて生臭く、背中には亀のような甲羅を持っていて、手足の指間には水掻きがあり、小さな尻尾があるとされる。また河童は好んで相撲の勝負を挑み、水中に人馬を引き入れて肛門から肝を抜きとるなど、危害がしきりに恐れられたりもした。ただ、逆に人間に捕らえられて詫び証文を書かされた失敗談、秘伝の秘薬を授けたという伝え、田植えの仕事を手伝った、田の水を引いてくれたとかいう恩徳の伝承も数多く存在する。 <河童とは> ・民話とは、口伝えにより、親から子へと語り続ける子供向けのお話です。それは、あるときは娯楽のためのお話であったり、生きてゆくための知恵を、解りやすい話に託しての教育の一環だったりもしました。 そんな民話は、それを語る親や祖父母、あるときは村の長老たち、そんな大人の人生観と、その時代の価値観をも包含した話として語られてきたのです。 よって、時代と共に、また地域により、同一のテーマの話であったとしても、微妙に差異が生まれるのはむしろ当然のことなのです。 江戸時代はもちろん、明治時代に入っても、各地で盛んに民話が語られていました。それが、印刷技術の進歩と普及につれ、しだいに勢いを失っていったのです。子供は、本により学ぶ、そんな時代の流れが生まれたのです。そしてそれは今、テレビ画面やコンピューターモニターを通じての、映像で学ぶ時代へと変わってきているのです。 <河童のルーツ> ・数え切れないほどある日本の妖怪の中で、河童ほど全国的に広まっているキャラクターはあまり例を見受けません。河童がなぜ、これほど広まったかの検証は後に譲るとして、河童伝承のルーツを探ってみたいと思います。 神話の時代、日本書紀には、川の神として「みづち」という名称が見られます。みずちは人にとって、フレンドリーな神ではありません。どちらかというと、陰気な川の淵などに棲みつき、通りかかる人に害を与えたり、川の水を氾濫させ、鎮めるために生贄を要求するなど、悪魔的な妖怪に描かれています。水と川に対する恐れが生み出した神なのでしょう。 仏教の伝来と共に、中国からの書物が輸入され、中国の水の妖怪の伝承が日本に伝わりました。中国には、「水虎(すいこ)」と呼ばれる水の妖怪がいます。幼児くらいの背丈しかなく、背中に甲羅のある妖怪です。西遊記にでてくる紗悟浄は、この水虎をイメージしているのかもしれません。 時代が少し下り、11世紀になると、物語文化の普及と共に、水の妖精の話が見かけられるようになります。「今昔物語」には、寝ている人に悪戯する子供ほどの身長の魔物の話があります。捕らえられると、水を入れた盥を要求し、その水の中に飛び込み逃げる水の妖精の話です。 <河童のいろいろ> ・全国に残る河童の伝承には、いくつかの系列があります。 山や川に棲み、キュウリを好み悪戯が大好き。悪さをし、捕らえられると泣いて許しを請い、許されると、律儀に、人間との約束を守る河童。実に日本的な性格の河童です。民俗学の生みの親、柳田國男氏の「遠野物語」ほか、広く一般的な河童の世界です。 もう一つは、九州に多い中国から移住してきたと伝えられている河童です。 人間に近く、指導者をいただき、社会を構成している河童族ともいえる河童たち。 そして、その状態はわからないものの、不思議な水辺の変事を、河童のしわざに違いないとして伝承している例もあります。 <河童伝承の特異性> ・民話に残る題材は河童だけではありません。道具類が、年月を経て変化する妖怪や狐や狸、兎に鶴などの動物も好んで扱われる題材です。そして、一般的な民話では、その地域特有のストーリーになっていることがむしろ普通なのですが、河童だけは、全国各地に、同じテーマ、同じストーリーの民話が、微妙に趣を違えて存在します。この特異性は重要な意味を持っていると考えています。 かつて、富山の薬売りが全国を廻って商売をしていました。近年になっては、紙風船を配りながら家々を廻っていた。記憶している方も多いと思います。そんな薬売りは、顧客に薬を売りながら、各地で起こったおもしろい話などを話して聞かせていたようです。生まれ育った土地しかしらない普通の庶民にとって、薬売りがもたらす話は、貴重な情報源だったのでしょう。 一枚の木版摺の絵が残っています。各地の河童の姿が描かれた絵なのです。今風に言うと河童のカタログ集なのでしょう。その河童絵と共に、河童の伝承を語って聞かせていたであろうことは容易に想像できます。同じストーリーが、全国に広く伝わっているのは富山の薬売りが、河童伝承を広めたからなのであろうと、私は思っています。 『河童の日本史』 中村禎里 日本エディタースクール 1996/2 <河童の相撲> ・人にたいする河童の攻撃行為には、水中に引きこむ行動のほか、いくつかの特異な方式がみられる。なかでも目立つのは相撲の挑戦である。 ・河童の行動の第一段階の終わりごろには、河童の相撲好きは、広く知られていたと思われる。 従来、河童のこの行動は、水神を祀る神示の相撲に由来すると説かれてきた。もちろんそのような由来を否定することはできない。たとえば、愛媛県の大三島町には、精霊と人の争いを演じる一人相撲が知られているが、河童と相撲を取っているという妄想にとらわれた男は、他人の目には、一人で相撲を取っているように見えるだろう。神事の一人相撲においても、古くは相撲者がトランス状態に陥っていたのかもしれない。奈良県桜井市では、二人の男が田のなかで相撲を取り、泥が多くついたほうを吉と判定する泥んこ相撲の神事がおこなわれている。 ・格闘技一般ではなく、新田がいう相撲の意味の二番目の層、すなわち四つに組み合う型を持つ格闘は、河童が人を水際まで運ぶのに適した恰好な手段であった。 ・日本以外においても、ヤコブが川を渡ろうとしたとき、水神らしいものが現われ、明け方までヤコブと相撲をとり、ヤコブの股の関節をはずした。『創世記』では、水神はヤコブを祝福してみずから去ることになっているが、より古い話型においては、水中に人を引いたのであろう。またドイツのヴァッサーマンとよばれる男の水精は、女性と手を組みあいダンスを踊ったまま川に入ってしまう。このような他の民族の伝承も、河童の相撲の意味を探る手がかりになる。 ・土俵が作られた17世紀末に、人と人の相撲が現行ルールに近づいたことは、人と河童との格闘形式にも影響を及ぼしただろう。この変化は、格闘形式の穏和化でもあった。私見によれば、土俵の出現により規定された相撲の特徴は、追い技、つまり寄り切り・押し出し・突き出し・吊り出し・打棄りなど場外に相手を追い払う技の重視である。 ・中世末になって、京都の相撲人集団に地方の相撲人があつまり、また彼らが地方に巡業に出かけるシステムが形成された。さらに近世の後半、安永・天明のころ(1770〜80年代)、吉田家がほぼ全国にわたって相撲様式の決定権を手中に収め、その門下の行司が各地に配置されると、地方のセミプロ力士のあいだにおいても、土俵の採用など江戸相撲に倣った様式がひろまったであろう。 こうして相撲が、格闘競技としてはきわめて淡白なルールを採用しはじめたことは、河童の行動の第二段階以後における人と河童との相撲にも反映せざるを得ない。いまや河童は、人を痛めつけ、あるいは水中に引く目的でのみ相撲を挑むとはかぎらない。河童が無目的でやたらに相撲を好むようすは、第5章で1800年前後、筑後川流域の河童の相撲について述べる時に、詳しく紹介する。この変化は、河童の凶怪性の衰退とうまく平仄をあわせて進行した。小妖である河童の戦いにふさわしい、穏やかな格闘としての18世紀以後の相撲が、河童の相撲の第4の源泉であった。 ・第5に、農民の文化としての相撲が、農民層の共同幻想としての河童の源泉であると考えられるが、この点についても第5章において別に検討したい。 河童憑きおよび人の女性にたいする河童の姦犯の問題を、相撲とおなじ項で論じるのは場ちがいだと疑われるかも知れない。しかし動物的な妖怪が人を襲うばあい、男性にたいしては外から攻撃し、女性にむかっては内部に入って苦しめるのは、かなり明瞭な傾向である。そして女性に雄性の妖怪が憑くときには、姦犯行為と幻想されやすい。河童をふくめて妖怪は、相手しだいで攻撃方法を自在に変更する。 河童が「童男と成り人と通ず」という記載が『本草補苴』(神田玄泉、1719年)にすでにみられるが、女性を犯したことを明記する噂話の管見初出は、貝原常春の『朝野雑載』(1734年成立)である。 ・たとえば豊後岡のある女性のもとに訪れる河童の姿は、他人には見えない。しかし女性の嘻笑するようすによって、河童の淫行が判明する。この例においては、河童が女性に憑いた事件が、姦犯とみなされた。類似の噂話は少なくない。 ・水神でもあるヘビが女性に憑いたと解される事件は、古代以来の文献に数多く見られる。 ・河童が、女性に憑きこれを犯すヘビの性行を遺伝したことは疑い得ない。しかし河童が女性を憑き犯す行為は、管見内では河童の行動が第1段階から第2段階に移行するころに始まる。したがって、河童の女性姦犯の習性が、その誕生期にヘビから直接に遺伝されたのか、あるいは河童の評判が世間に喧伝されるようになった段階つまり18世紀に、先祖がえりの現象によって、あらためてヘビの性行を復活させたのか、いずれとも断定できない。ただし管見の外の該当文献がなかったとはいえないし、いわんや口承でそのような噂が語られていなかったと断定することはとてもできない。ただし文献においては、この種の噂話はむしろ18世紀の後半になってから多く現われ、なかでも豊後に集中することは注目される。 ・近世中期以後、貨幣経済の浸透、新入村者の出現などにより村落共同体の構造に変化がうまれ、社会的緊張が発生した。それが主因になって憑きもの頻発地帯がいくつか出現した。その一つが豊後であった。この地方でとくに犬神憑きが多い。犬神が直接河童につながるとは思われないが、蔓延する憑きもの俗信に触発されて、河童憑きの事件も惹起されたという可能性は捨てられない。かりにそうだとすると、河童憑きの形成期は、近世中期以後であり、ヘビ憑きの直接遺伝ではないという推定が得られる。けれども豊後以外に、山陰・四国・信州・上州などに、著名な憑きもの地帯が分布しており、これらの地域では近世に河童憑きの噂話がさかんであった証拠は、まったく存在しない。 ・逆にその否定に有利な文献を示すことができる。因幡の人、陶山尚迪は『人狐辨惑談』(1818年刊)において、河童憑きを狐憑きと同レベルで扱いながら、「九州河太郎と呼者……九州の俗、此物の人を悩すことを言へば、彼地にはさだめて此者多かるべし。本藩には居ることなし」と論じた。因幡は、人狐およびトウビョウと称する憑きものが多発する地帯であった。したがって憑きものの俗信は、河童憑きの素地にはなり得るだろうが、これにさらに別の要因が加わらなければ、女性にたいする河童の憑き・姦犯の噂話は盛行しなかっただろう。 九州は、河童噂話一般についても、そのもっとも盛んにおこなわれた地域であった。これが上記の「別の要因」であったかも知れない。 <河童の手切り> ・河童の行動の第3段階で、河童が手を切られ、手接ぎ妙薬の秘伝伝授を条件に、その手を返却してもらうという形式が出現する。これには二つの型があり、そのうち一つは、『博多細見実記』巻14の説話のように、河童が人の尻をなでる型であった。そしてこの型の伝承は、河童よりまえにたぬきを犯人として流布していた。あと一つは、河童がウマを水中に引こうとして、かえって引き上げられ、厩でウマにつかまっているところを発見され、手を切られる型である。『西播怪談実記』巻3の説話はその例であった。 ・寛永ごろ(1620〜40年代)に成立したと思われる『小笠原系図』に、つぎの伝説が記されている。 小笠原清宗が廁に行くと怪物がおり、清宗をさえぎろうとする。そこで清宗は、剣で怪物の手を切りおとした。しばらくして窓のそとに声があり、切られた手の返却を乞う。誰何すると「たぬきです」と答える。「切りおとされた手をどうするのか」とたずねると、たぬきいわく。「われに妙薬あり。もってこれを接ぐ。すなわちこれを得させよ。恩のためその妙薬をあい伝えん」。たぬきは翌日手を接いできて、妙薬の効能を明らかにした。小笠原家伝来の膏薬の由来は、これである。 『河童の文化誌』 平成編 和田寛 岩田書院 2012/2 <平成8年(1996年)> <河童の同類とされている座敷童子(ざしきわらし)> ・ザシキワラシ(座敷童子)については柳田國男の『遠野物語』によって知られていたところである。 <アメリカのニューメキシコ州の異星人の死体> ・回収された異星人の姿は人間によく似ているが、明らかに地球人ではない。身長1.4メートル、体重18キロ前後、人間の子供のようだが、頭部が非常に大きい。手足は細長く、全体的に華奢。指は4本で親指がなく、水掻きを持っている。目は大きく、少しつり上がっている。耳はあるが、耳たぶがなく、口と鼻は小さくて、ほとんど目立たない。皮膚の色がグレイ(灰色)であるところから、UFO研究家は、この異星人を「グレイ」と呼ぶ。 ・異星人グレイと河童を並べてみると、素人目にも、そこには多くの共通点を見出すことができるだろう。 まず、その身長、どちらも1メートル前後、人間のような格好をしているが、頭部だけがアンバランスなほど大きい。 大きな目に、耳たぶのない耳、そして、小さな鼻穴と、オリジナルの河童の顔は、そのままグレイの顔である。 最も注目したいのは、その手である。 先述したようにグレイは河童と同じ鋭い爪、水掻きがある。おまけに指の数が、どちらも4本なのだ!。 また、グレイの皮膚の色は、一般にグレイだが、ときには緑色をしているという報告もある。 河童の色は、やはり緑が主体。ただ両生類ゆえに皮膚はアマガエルのように保護色に変化することは十分考えられる。 ・これらが、意味することは、ひとつ。アメリカ軍は、組織的にUFO事件を演出している。 捕獲した河童を異星人として演出しているのだ。 『水木しげる』 妖怪・戦争・そして、人間 河出書房新社 2016/5/26 <妖怪談義――あるいは他界への眼差し(水木しげる 小松和彦> <妖怪と生活空間> ・(小松)それらはみな、各々の村々で作られてきた妖怪なわけですからね。全国どこでも通用する妖怪というのは、なかなかないわけですよ。河童の場合は、民俗学者がその名前をよく使ったし、江戸時代の知識人などもずいぶん使ったおかげで、地方的な固有の名前のほうは次第に人々に忘れられ、河童という名前のほうが、残ったということでしょうね。 (水木)それと、日本人は河童好きだったと思いますね。それほど河童の話というのは、上手に作られています。中国などでは、そんなに河童は発達していないんですけど。 (小松)なぜ、日本人は河童が好きなんでしょうかね。 (水木)大変ユーモラスなものに仕立てられていますよね。きゅうりが好きだとか茄子が好きだとか、相撲が好きだとかね。 (小松)それに、河童の各々の属性の中に、日本人が日常生活の中で考えている事柄が、非常にたくさん盛り込まれていると思うんですよ。それがやはり人々を魅きつけたんじゃないでしょうかね。河童は近世になって作られた妖怪なわけですけど…………。 <神々と妖怪> (小松)ところで、日本の民俗社会、歴史社会においては、妖怪の世界と神々の世界とが、対比的に扱われていますね。水木さんが、神ではなく妖怪の世界のほうに魅かれていったのは、どういうことからなんですか。 (水木)私は、神と違って、妖怪の方は自分で感じることができたわけですよ。「真を求め、そのために詩を失う」という言葉がありますが、私はどちらかというと真よりも詩を好むのです。そして20歳ぐらいの時に、柳田國男の『妖怪談義』を読んで、「妖怪名彙」の所に出てくるいろいろな妖怪の名前を見て、アッと思ったんですね。もう非常によく分かったんです。それから鳥山石燕ですね。この二つで非常に自信を得たわけです。 ・私の場合、仕事でも何でも、妖怪となると元気が出てきて、もう一生懸命になってしまうんです。従って、資料のほうも妖怪ばかりがやけに増えちゃうわけです。 <<あの世>の世界> (水木)昔は、お寺なんかに行くと、よく地獄・極楽の絵がありましたね。そのせいか、鬼がいるという印象が強いんです。それと、日本では、お盆の行事などに、やはり“あの世”との関連を感じますね。いろいろなものを船に積んで流すわけですけど、それがどこに行くかというと、十万億土とかいわれるわけでしょう。子供心によく分からないながらも、あの海の先にもう一つの世界があるんだな、と思ったわけです。それからまた、祖先の霊がくるというんで、迎え火とか送り火とかをやりますね。そうすると、我々の目にはみえないけれど、ちゃんときているんだなと思うわけですよ。僕自身は、“あの世”と妖怪との直接の関わりというものを、あまり感じたことはないですけど、日本以外では、あの世から飛来してきた妖怪というのは、結構いるようです。そういう意味では“あの世”に対しては、非常に興味はもっています。 <美とグロテスク> (小松)昔の人たちは、自然の中に神を見、その自然の一部として人間を見ていたわけですから、人間だって同じような霊をもっていると考えていた。自然も人間も神も、いわば同じ一つの土台の上に乗っていたのですが、それが近代になると、人間だけがその土台から降りてしまったわけです。そして、人間は特別な生き物であるという特権を与えられてしまったわけです。 <「妖怪の棲めない国はダメになる」水木しげる ロング・インタヴュー> <人間が妖怪をいじめている> ・日本で妖怪が減ったのは、電気のせいです。電気で世の中が明るくなってしまった。妖怪というのは、やっぱり闇夜が必要なんです。 <闇夜が育む妖怪たち> ・水木を運んだのは、日本海海戦でロシアのバルチック艦隊を打ち破った老船「信濃丸」で、彼ら以降、ラバウルに着いた船は一隻もない。すべて撃沈されたため、水木らは永遠に新兵扱いのまま、攻撃の最前線へと送られた。まさに、「死」が必然であった。 ・水木サンは生まれた時から、妖怪が好きだった。だから、戦争でニューギニアのほうへ行っても、現地の人たちと妖怪の話を自然にすることができた。 ・約3分の2が敵の領土というニューブリテン島で、水木は最も敵に近いココボの陸軍基地に送られた。水木はここでもマイペースを貫いたため、“ビンタの王様”のあだ名がつくほど上官から殴られた。そして、さらに危険な最前線基地トーマからズンゲン、バイエンへと派遣され、バイエンでは到着早々海岸の警備を命じられた。不審番もいつもは上等兵が一番楽な早朝の監視をやり、水木たちは夜中に番をさせられる。ところがその日に限って、上等兵が交代してくれというので、早朝の番に変わった。それが運命の分かれ道だった。 ・左腕を負傷し、生命が危ないからと二の腕から麻酔なしで切り取られたのです。でも、そのおかげで傷病兵を集めるナマレという後方の野戦病院に移送されることになりました。 その時感じたのは、人間が持つ「運命」です。 ・トライ族の住民が用いる貨幣は、カナカマネーと呼ばれる貝殻でした。これを丸い大きな輪にし、二つか三つ持てばお金持ち。その貝殻でタバコの葉やパパイヤと交換するんです。 ・彼らはあまり働きません。皆、慢性のマラリアにかかっているので、疲れないようにしなければいけない。働き者だとすぐ死んでしまいます。怠け者でないと、生きていけないのです。 私も慢性のマラリアということで、しょっちゅう身体がだるいとか何とか屁理屈を言って、半年か1年しか軍隊で仕事をしませんでした(笑)。その間、彼らの集落に入り浸っているわけです。そうやって現地の人たちと交流して、バナナなどをたくさん食べていましたから、栄養がついて元気だった。逆に軍隊で真面目に働いていた兵隊は、終戦になってから帰国するまでにバタバタ死にました。水木サンは日本に帰るという時に、向こうの生活が合っているから、そのまま現地除隊させてくれと言った。でも、「日本に帰ってお父さんとお母さんに顔を見せてからにしたらどうだ」と上官に言われ、それもそうだと思って帰国しました。 『水木しげるの妖怪談義』 水木しげる ソフトガレージ 2000/7/15 <荒俣宏 世界のミステリー遺跡に残る妖怪の痕跡> <妖怪とは何かっていうと、自分とは何かっていこうことにもなってくるじゃないですか> (荒俣)でも、妖怪の音はものすごく重要なテーマですからね。柳田國男にしても、妖怪研究というのは音の研究ですから、逆に妖怪の姿の話っていうのは、彼もほとんどやっていませんし。 (荒俣)水木先生は妖怪研究のためにあちこち旅行してらっしゃいますけど、どこへ行ってもお土産は……たまには仮面もあるけれど………CDが多いですものね(笑)。これは、妖怪のイメージである音をいかに身近に考えるかっていう、新しい水木流のスタイルじゃないかと思うんですけど。 ・(水木)今までは平田篤胤の説いた死後の世界のような、背後霊だの守護霊だのを落ち着いて考えて、死後も転生して生まれ変わるというから、自分もやがては生まれ変わってなんて、楽しく考えていたんです。けれど、自分とは何かを観察してみると、どうもそういうなまやさしいものじゃないような感じが最近はしてきてね。 <「妖怪変換」みたいな機能が頭のなかにあって、妖怪の音や名前がそのまま絵に変換されちゃう………> ・(水木)というのはね、「私はなぜ妖怪を描くのか」っていうことを考えていたわけですよ。妖怪とは何か、なぜ描くのか、いろいろ前から気づいてはいたんだけど、結局は彼らにこき使われてるというか、もちろん好きでやってるんだけれども、同時に使われてるんです。(笑)そのために私は、土日も休みなしです。 ・(水木)そう、死。だから、死をむしろ待ち望んでるような感じがね、ちょっとします。ただ問題は、それほどまでにしてなぜ妖怪に使われなくちゃならなかったのかという思いが私のなかにあったわけです。そこから出発して、自分とは何か、という疑問のほうへ入っていく。 <人間は、人間が思うよりもすごく不思議な存在なんですから> ・(水木)それでね、どうして妖怪を……もうとっくに卒業してもいいはずなのにね……まるで鞭を当てられるようにやってこなければならなかったのか、となる。そうすると、自分は何かという問題が起こってくるんです。 (荒俣)これは恐ろしいことですよ、本当に。そういえばね、僕もずいぶん古い漫画本のコレクターで、昔の本を集めているんですけど、水木さんの本は昔の貸本時代の漫画を、今、お描きになってるものとつなぎ合わせても、そこに流れる迫力とか、あるいは妖怪に対するアプローチの仕方って、まったく変わらないんですよね。 (水木)そうなるとある意味で、そういう宇宙人みたいなやつがいて、私を操っているのかなあ、なんて思ったりもするんです。(笑) というのは、やっぱり自分の心のなかにも、こんな苦しいことはやめて、もっと開放された生活をしたらどうかっていうのがいますから。でも、実際はそんな生活にはぜんぜんならないわけです。土曜だろうと日曜だろうと、仕事をする。自分自身で抜けられないから、変だ、変だ、と。だから、妖精とは何かっていうよりも、突き詰めれば自分自身の問題になってしまう。 <神の源っていうのは、やっぱり妖怪だったんじゃないかという感じがするね> (荒俣)つまり、妖怪になっちゃうんですよ。だからおもしろいなあ、と。最初は神を作るつもりだったのが、やればやるほどね。なんていうのかなあ、神の源っていうのは、やっぱり妖怪だったんじゃないかという感じがするんですね。ふつうの感覚ですと、まあ、柳田國男なんかがいっているし、ヨーロッパでも妖怪研究者はだいたい同じようなことをいっていて、「神が零落したのが妖怪だ。だから妖怪ももともとは神で、妖怪を研究すると神になる。神のほうに近づいてくる」っていうんですよね。でも、どうもそうじゃなくて、妖怪は最初から妖怪で、むしろ逆に、人間が神のルーツを探り出していくと妖怪にぶつかるっていうか、妖怪のほうが先にあったんじゃないか、っていう感じですね、シュヴァルの城を見ていてもわかりますし………それをいったのは、結局、平田篤胤ですよね、日本でいえば。平田篤胤が画期的な妖怪学を作ったのは、「すべてのものは最初は神だった」っていう概念よりもむしろ、「すべてのものは最初から妖怪だった」という、この発想法に近いんじゃないかっていう感じがとてもしました。で、水木さんの場合はどうですか?神と妖怪の関係っていうのを、最初はどういうふうに考えてらっしゃいました? (水木)私もね、「妖怪とは何か?」っていうようなことから連想していくと、どうしても精霊ということを考えざるをえないようです。 ・(水木)それで、「癒し」をしたり、病気を治したりするわけだけど、私はセノイ族のところで病気を治す精霊を呼ぶための音楽というのを聞いてね、「録音しちゃいかん」っていうのを無理に録ってきて、それでいろいろなことがわかったんです。それが実にいい気持ちのする音なんです。木と竹の楽器だけで2時間くらい聞いていると、おかしな気持ちになるわけです。というのは、私自身が木になったり、石になったりすることができる。で、それと同じことがニューギニアに行ったときにもあったんです。 (水木)ええ、精霊っていうのは、ものすごく強大ですね。あの、いろんなことをするっていう意味じゃないですよ。それが、東南アジアにでもどこにでもいてくれるから、人も心地いいんです。それがどうも、実在する神々なんじゃないか、ちゅうことなんです。 (水木)それで私もですねえ(笑)、「鬼叫山の拝殿」(広島県)、あそこへ行ってから、よく縄文人の出る夢を見るんですけど、縄文人たちは非常に不満なんです。彼らは今の神の扱い方に非常に不満を持っているようなんです。1万年か2万年前の、本当の神は失われているわけですよ。どうもその、素朴な音でやってくる精霊、それが神だってことをいいたいらしくてね(笑)。 <「縄文の神を復活させるように」っていう指示がくるんです> (水木)縄文人は、夢とかなんかで私にしょっちゅう通信をしてくるんです。その、どうも今、日本でいわれているようなものとは、神の本来の姿は違っているような気配なんです。どちらかというと、私が見たような、東南アジアとかニューギニアとかにいた精霊たちが本来の神に近いものらしいんです。それで彼らは、現代のように強大になった神々っていうのを極端に嫌うんです。 <妖怪は、おだやかな精霊信仰に入れっていうことを知らせる存在なのかもしれないですよねえ> <20世紀は、霊魂の進歩っていうのは一切やっていなかったんですね> (荒俣)だから、19世紀末ごろにウォーレスとかいろんな人が、人間の霊魂の進歩っていうのは、もう進化論とかそういうものじゃ扱いきれないんで、別のものだっていうヒントをつかんだにもかかわらず、その展開はなかったんですね。 <西洋人にとっての妖精は、圧倒的に人魚> (荒俣)そうですね。よくいわれるけど、日本の妖怪はほとんどは中国がルーツだっていうことがあるでしょう?それと同じようにヨーロッパの妖怪は、イギリスとフランスなんかは特に接近していて、ベースはほとんどやっぱりケルトが持ってきたんです。 <エジプトは宇宙人が運んできた文化じゃないか> (シリウス星人)シリウスは全天でもっとも明るく輝く恒星。そのため古代エジプトではナイル河の氾濫を知らせる星として信仰された。そこから、エジプト文明はシリウス星人によってもたらされた、とする説も一部にはある。 <エジプトでは建物を作るという形で精霊と接触する文明ができたんですね> <魂を飛ばすっていうことが、人類が大飛躍する基本だったのかもしれませんね> (荒俣)ええ、だから、2万年から1万年前の人々っていうのは、どういう方法でかわからないけれど、精神的には太陽に行ったり月に行ったりっていうのは、自由にやっていたんじゃないですかねえ……。 <憑依霊っていう現象がまさに「人間は我思うゆえに我ありじゃないんだ」という証明になっている> <人間の脳ではかなりわからん部分が多いってことですねえ> ・(荒俣)その「わからん」という部分というのはほとんど、今お話したような精霊関係につながっているんじゃないんですかね(笑)。 (水木)森のなかに住んでるセノイ族というのはね、文字とかはないけれど、とても快適なんです。争いごともないです。 <精霊と妖怪の関係っていったいどうなんだろう?複雑微妙ですよ> ・結局、それで妖怪に関心のある人が増えて、精霊とか霊に対する関心も増えることを、きっと背後にいる精霊も望んでるのかもわからんのです。 <妖怪城を作るという計画はどうなったんですか?> ・(水木)おっ、『稲生物怪録』!あの、山本五郎左衛門! ・(水木)それでね、山本五郎左衛門の話をするけどね、出口王仁三郎は、書いとるんです、山本のことを。 (荒俣)山本のことを、ええ。 (水木)書きましたねえ。山本は霊界にいるんだって。 (荒俣)ははあ……霊界に………王仁三郎は会ったんですか? (水木)いや、会ったらしい。 (荒俣)あの『霊界物語』に出てくる……? (注;出口王仁三郎)大本教のカリスマ的「聖師」。日本の古神道・新宗教に与えた影響は限りなく大きい。 『霊界物語』出口王仁三郎が口述筆記した全81巻からなる神の書。 <●●インターネット情報から●●> (セノイ族の言葉から) 夢の神秘的な力を信じる人々に、セノイ族における夢の技法について。 1.セノイ(Senoi)族とは。 セノイ族はマレーシアのマレー半島に住む原住民です。人口は約4万9440人(1996年:推定)。マレーシアの山岳地帯のジャングルに住み、バンド単位で生活を送っています。 そんな彼らの最大の特徴は、夢に対する態度なんです。 1)1日の大半は夢の話をしている。 2)村会で夢の討議が行われ、村民全てが自分の見た夢を分かち合い、シンボルや状況の意味を話し合う。日常生活の活動の大半を討議で得た解釈で決定する。 3)夢の討議において、夢内容をポジティブな方向に解釈することで、次にみる夢をコントロールする。 2.セノイの夢理論の紹介者について。 彼らが注目を集めたのは、キルトン・スチュアート(1902−65)による「マラヤの夢理論」(1951)が発表されたことによります。スチュアートは1924−40年にかけて世界中を放浪して、1934年頃マラヤ(現マレーシア)に滞在し、セノイ族の夢の技法の調査をしました。 この「マラヤの夢理論」というのがまたUFOから話が始まるという型破りな物なのですが、この論文の趣旨は、セノイ族が平和な部族なのは、彼らが上記の「夢の技法」を用いているから、ということなんです。 当初、この論文はそれほど注目を集めませんでした。しかし70年代に一躍有名になります。 <●●インターネット情報から●●> 【大紀元日本8月6日】夢を積極的に活用し、自分の感情をコントロールする人々がいる。 マレーシアの高原に住むセノイ族(Senoi)だ。 研究者らの報告によると、セノイ族は夢の中の世界を現実と同じように重要視する。彼らは夢の中で、同じコミュニティーに住む人間と友人になったり、対峙したりしながら様々な経験を重ね、成長していく。 その一方で、彼らは現実世界においては精神的に成熟しており、控えめで自己抑制ができるため、争いはほとんど起こらないという。 1970年代にセノイ族と長期間過ごした心理学者のパトリシア・ガーフィールド氏(Patricia Garfield)は、彼らのユニークな夢の活用法を報告している。ガーフィールド氏によると、毎朝、親たちは子供にどんな夢を見たのかを聞き、彼らの方法で夢を見るようトレーニングをしていく。たとえば、夢の中で友人を作ったり、敵の集団とも仲良くなって助けてあげたり、それができなければ夢の中の友人と協力して敵を倒したりする。 そのほかにも、夢の中を自由に飛び回るなど、明晰夢(夢の中で、自分が夢を見ていると分かっていること)を存分に楽しむ方法を教えるのだ。セノイ族によれば、人間の体にはいくつもの魂が宿っている。主要な魂は額の内側に存在し、その他の小さな魂は瞳孔の中に住む。 この小さな魂が、恍惚とした状態や寝ているときに身体を抜け出し、夢の中で活躍するという。 セノイ族は、夢の中の友人と敵を大切にし、夢の中では積極的に友人を作ろうとする。夢の中で、敵が自分と友人になりたいと申し出るときは、「敵が自分に名前を明かし、自分のために歌を歌ってくれる」という。 もし、夢の中である人物と争いになった場合、夢を見た人は現実世界でそれを解決しようと試みる。 彼は争った人物に夢での出来事を伝え、自分に非があれば、相手に賠償することを申し出る。夢を活用することにより、「神経症や精神病といわれるものは、セノイ族の中には存在しない…。セノイ族は、驚くほど感情的な成熟がみられる」とガーフィールド氏は報告している。 現在、一部の学者はセノイ族の夢の活用法について否定しており、セノイ族自身も、そのようなことは存在しないと主張している。 しかし、多くの人類学者は、セノイ族が非常に警戒心が強く、外国人をあまり受け入れないことを認めている。 そして、セノイ族が彼らの夢の活用法を隠してしまったとも指摘している。 『妖怪になりたい』 水木しげる 河出書房新社 2003/5/20 <近藤勇と国境線> ・調布というところは、百姓の多いところで、僕は常に狭い土地の境界問題で頭をなやまされた。たとえば、右側の百姓は、茶の木から一尺という領有権をゆずらず、建具屋はそんなことおかまいなしに茶の木のあったらしいところに境界線のマークを刻みこんでいるのであった。そして、そのマボロシの茶の木をめぐって、ソ連と中共なみの国境争いを3年ばかりくり返したのである。 ・ある夜なぞガタゴト音がするので見ると、その境界線を一尺こちらに穴を掘ってよせていた。僕は、あくる日また穴を掘って一尺むこうにやったが、そんなことを三ヶ月ばかりくり返すうち、五寸のところに自然に境界の石がとまったようだ。 ・そのあとは、その境界石のかたむきかげんである。むこうは、気づかぬあいだに1センチばかりこちらにかたむけている。僕も30年も絵をやっていてデッサンには自信がある。すぐ、石のかたむいていることが分かる。まっすぐにやればなんでもないのだが、こちらもむこうもわずか1センチぐらいかたむける。といった生活をしているうちに、今度は、うしろの住人が境界の木より1尺3寸入ったところに壁をするといい出した。 風呂場の屋根がとれることから問題は重大化し、土地をはかる商売の人を呼んで境界線をつくった。 そのうち左側の百姓がおどりこんできた。「てぇへんだ、てぇへんだ」というわけ。これは長くなるので省略するが、僕は、この町の人間は、特別に欲が深いのではないかと思うようになった。 <奇妙な興味と仕事との格闘――紙芝居時代> ・戦後すぐの頃のぼくの精神状態から説明すると、戦争はかなり強烈な印象だったから、ぼくは復員したときも浦島太郎みたいな気持ちだった。そこで「これからの人生は好きなことをやって死のう」と思った。 好きなことといっても遊びではない。興味があって、しかも生活できるものではなくてはいけない。 ・ぼくは武蔵野美術学校に入るのだが、絵かきでは食えないということが分り、2年で中退して神戸で紙芝居かきとなるわけだが、どうして神戸に行ったかというと、神戸に安い売りアパートがあったから。 10万円だか20万円出すと、あと月賦でいいという、しかも15〜6の部屋があったから、一生寝て暮らすにはもってこいで、わが理想とピッタリだったというわけだ。 <妖怪の巣のような世界――貸本マンガ時代> <40年をふりかえって> ・まあ、一口でいうと「えらかった」即ち「苦しかった」ということだろうか。もともと漫画は好きでやったことだったが、職業ということになると、趣味と違って「つかれたな、ちょっと休もう」というわけにはいかない。 〆切というものがあって、建築業者が建物を期日に間にあわせなければいけないように“品物”をその期日に間にあわせなければダメなのだ。そういう意味で好きでやったとはいっても“漫画家”という職業で“生き残る”には、世間の業種でいわれているようなものと同じで、特別の仕事というわけではなかった。 表面的には自由でのんびりしているようにみえるが、世の中のシステムに組み込まれ、品物を作るように、何十年も漫画を作るということは、いくら好きでも、そんなにラクなものではない。 <言葉の不思議> ・ぼくは、紙芝居、貸本マンガ、雑誌マンガと、毎日机の上の紙と対決する仕事をしていたから、しゃべる言葉なぞはぜんぜん気にしていなかった。 ところが定年をすぎるような齢になって、言葉の不思議を感ずるようになった。言葉というものは何気なく使ってきたわけだが、これはひとこと多くてもいけないし、少なくてもなおさらいけない。 <運不運> ・昔から同じようにマンガを書いている人でも一方は売れっ子になって巨万の富をきずき、一方はいまだにうだつが上がらず、無名のままでいる。作品のほうでも違っているのかと思うと、それほど大差があるわけではない。 運・不運は人だけではなく、建物なんかにもあるらしい。神田あたりによくうすぎたないビルがあるが、そこへはいると必ず倒産する。僕の友人がそのビルにはいり、自動車のガソリンをつけにしてくれ、といったら断られたという。 「あのビルにはいる人は必ず倒産する」とガソリン・スタンドの男がいったというが、友人はそのとおりになり、3ヵ月で倒産した。 ・そのように人間の成功不成功は大いに運、不運が関係する。ツキに見はなされた人はどんなにあがいてもダメだ。立志伝なんかに、ツキを自分で作ったように書いてあるのをよくみるが、それは逆で、運をつけたのではなく、運がついたのだ。 ・毎日寝る時、そんなことを考えているのだが、やはり太古の人もソレを感じていたらしく、古代沖縄にセジ、というのがあった。 これは一種の霊力で物についてそのものに霊能を生ぜしめ、人間については霊能を生ぜしめるというが、これは、古代日本のカンナビ(神のいるところ)に移行するのだが、これを運、不運の霊と考えると、前記神田のビルには悪いセジがついており、くだらんマンガを書いて百万の富にありつくのは幸運なセジがついておるのだ。 ・だからいくら同じような実力があっても、セジについてもらわんことには、幸運はまいこんでこないのだ。 セジは普通巫女の媒介によって招かれたりしたらしいが、セジ自身の働きによって特定の人、あるいは物体、場所によりつき、そこにとどまることがあるという。 ・すなわち、聖なる森、聖なる石、聖なる場所、すなわち、幸運のいる場所なのだ。僕は昔、月島、神戸、西宮、甲子園、亀戸、新宿などをてんてんとしたが、どこも不運だった。 運命の糸にあやつられて調布なる畑の中の安建て売り住宅に、10年前、着のみ着のままでたどりついたのだが。 それから間もなく幸運がやってきた。マンガの注文がくるようになった。 <世の中不思議なことが多すぎて……> ・私は、子供の時に頭の中に入ってきた、カミサマの観念から、いまだに抜け出せないままでいる。 大人になってから、いろいろな“ヒト”の神様、例えば、菅原道真とか、武将をカミサマにしたものなどは、どうしたわけか、ぜんぜん受け付けない。子供の時、出来上がってしまった、カミサマ観は、アニミズムに近いもので、妖怪とごちゃまぜになったものだった。 ・神社には、願いごとをかなえてくれるカミサマがいた(それはどうしたわけか、ひげを沢山生やした男の形だった)。お稲荷さんには、狐とおぼしき神がいた(これは狐の形で頭に入ってしまった)。道端によく、団子なんかがおいてあるのは、“狐落し”のまじないであった。また家から千メートル位はなれた“病院小屋”には幽霊に近いものがおり、その近くをながれる“下の川”には河童がいた。従って、この川には小学校5年生くらいまでは、あまり近よらないようにしていた。 <おばあさんの死んだ日> ・幽霊とか妖怪といったものは、どうしたわけか子供の時に見ることが多い。これはなにか特別な理由があると思うが、いまのところ分からない。 僕も小学校3年の時、おばあさんが亡くなって2日目に、便所にゆこうとして前をみると、白い着物をきたものがぼんやり立っていたので、あわてて引き返した。その話をすると、父母は、「やっぱり、出たんだ」 ・それにしても、奇妙な偶然が、重なりあった出来事の多い日々だった。死後49日、霊魂がとどまるとかいって49日の法事をするならわしがあるが、まんざらいわれのないことでもなさそうだ。 <今も聞こえる兵長の「パパイアはまだか」> ・いまから三十数年前、あのいまわしい戦争のさなか、ぼくは名もない一兵卒として南方の前線、ラバウルに駆り出されていました。 すでに、終戦の近くになった昭和19年8月の出来事です。暑さと飢えで病人が続出し、兵隊はひとり、ふたりと倒れ、死んでゆきました。 ・そう思いながら、壕に行くと、見かけた顔があったんです。ぼくをいじめ目の敵にし、ぼくを憎んでいた兵長でした。下半身に腫れ物が出来、そこが化膿し、異臭が漂ってました。 ・「何か欲しいものはありませんか」と言うと兵長は弱々しい声で、「パパイアを食べさせてくれ。俺、パパイアが欲しんだ」 「パパイアなら、2、3日のうちに手に入るので持ってきます」 ぼくはそう言って、兵長と分かれたです。 それから3日後、パパイアが手に入りました。早く、兵長のところへ持ってゆかないと、と思いましたが、なにしろ空腹で、しかも、ぼくはひとより胃の調子がいいので、つい我慢出来ずに、パパイアを食べてしまったんです。 もの凄くうまかったです。ところが、その翌日の夕方、衛生兵が、「お前の中隊の兵長が死んだ」と言ってきたんです。 ・そうこうするうちに、足元にガツンと物が引っ掛かったような強い衝撃を受け、よろっとしました。足元を見ると、屍となった兵長が、「ぼくの足をつかんでいるんです。ギャー。兵長を遠ざけようと、足で押しても兵長はびくともしません。それどころか、兵長はまるで生きているように、ぼくの体にまとわりついてくるんです。兵長の目は開いていたような気がします。口も開いていました。 「パパイアを、どうして持ってこなかった」 「俺はパパイアが欲しいんだ」 と兵長は呻き声をあげるんです。それでも、ぼくはとにかく穴の外に出ようと必死でもがきました。 あの地獄から、どうやって這い上がってきたのか、いまでもよくわかりません。ただ考えられるのは、死ぬ直前にパパイアを食べたいといった兵長の願いをかなえてやらなかったために、そのうらみで死者に招かれた、ということです。無我夢中で、気づいたときには自分の病室に戻っていました。 いまでも、夏になるとどこからとなく聞こえてきます。 「パパイアをどうしたんだ」 <お化けの話> <幽霊とチガウ> ・よく幽霊と妖怪――お化け――と混同する人があるが、幽霊というのは、うらみが主な要因となって出てくるおそろしいもので、主として復讐を目的としている。 ところが、妖怪というのは(水木式の言い方によれば)自然に初めからそこにあるものなので、大した目的もなければ、なんでもない。ただ、奇妙な愛嬌がある。 それが愛されるといえば、愛されるのだろう。 ・2、3年前、東北に「ざしきわらし」の出る家というのがあったが、そこの主人は、それを深く信じて疑わず、むしろ喜んでいた。その古い家のたたずまいといい、いろいろと「ざしきわらし」と同居し、だれがなんといっても、いるという信念を変えない。 そこの主人のフンイキは、正に「ざしきわらし」そのものだった。 そのように、妖怪とは、奇妙なフンイキをかもし出す形なのだ。 人間の気持ちが形になって出てくるのだ。 <クマントン(座敷童)> ・座敷童(わらし)というのは、明治の初め頃、東北の小学校に現われて、小学1年生の子供と遊んだが、教師とか村会議員なんかには見えなかった。 即ち、大人には見えなかった。大騒ぎになりかけたが、童の方で遠慮し、2、3日で現われなくなったと、たしか柳田国男の本でみかけたが、どうもぼくは座敷童に縁があるらしい。 10年前、金田一温泉の緑風荘に出るというので、座敷童の親方みたいなそこの御主人と対談させられたが、主人、曰く 「わたすは1回しかみてないす。とにかくそこの奥の間に寝るとときどき出てきます。戦争中、陸軍中佐が泊ったが、なんとその中佐の前に出てきたのです。中佐はこの部屋になにか仕掛けがあるに違いないと騒ぎ出し、軍務そっちのけで天井裏をさぐったり、床下に寝てみたり」したらしいが、謎はつかめなかったらしい。 ・それから、5、6年してやはり東北の百姓家で座敷童が出るというところに行ってみた。いまは空家になっている二階家に時々出て、踊る物音をさせるという。要するにしかと見定めようとすると見えなくなくなるらしい。即ち一種の“霊”なのである。人間はなかなか霊をみることはできないから、一種の存在感みたいなもので感ずるようだ。 ・「タイ国にも座敷童がいます」というので、出かけてみた。 タイでは、死体をみんな焼いてしまうらしい。従って、“墓”はきわめて少ない。金持は飛行機で灰になった自分を空からまいてもらうのが夢らしい。そのせいか、やたらに“霊”が空から舞い下りてくるようだ。 “クマントン”と称するタイの座敷童もやはり舞いおりてきて、特定の人につくらしい。 <生まれかわり> ・生まれ変わるといえば、アメリカで「前世療法」という、精神科の医療方法があるという。催眠術で前世にまで記憶を進めて、そこでなにが原因かをみつけてなおすという方法らしいが、やはり前世はあるのかなァ、と思ったりする。インドなどでも生まれかわりの話はよくきく。 僕は偶然、スリランカの生まれかわりに会う機会にめぐまれた。 テレビの番組ではあるが、極めてめずらしく、本当の生まれかわりというのはかなり迫力があった。 ・日本の平田篤胤の「勝五郎の再生」そっくりの条件だった。 即ち、生まれかわった家が近い、生まれかわった子供は勝五郎のようにかしこく、よく生前のことを記憶し家族をうながしてそこにゆく、という全く同じようなパターンだった。 前おきはそれ位にして、ぼくはスリランカのコロンボの近くの村にバスでゆき、その子供の家に行った。 子供は4歳でかしこく可愛かった。 両親は40歳位だったが、とても可愛がっていた。 まず寝言で前世のことをしゃべるので不思議に思ってきくと、そこへ連れて行ってくれといってきかない。 ・4キロばかりはなれた生垣の囲まれた前世の生家にゆくと、息子は15年前に死んだという。それも交通事故のようなものだったらしい。ところが不思議にも、その子供が事故の様子をくわしく語るので、生家のじいさんばあさんも不思議に思ったが、まさか15年前の息子が生まれかわってここにいる、とも思えないのでポカンとしていたらしいが、決め手となったのは、誰も知らない(今はそこにいない)はずの長男の名前をいい、とても可愛がられた、といったことらしい。 ・僕が行った時も、むこうの老夫婦はみるなりその子供を抱きしめるのだ。生みの親はあまりなつかしがられるのでオロオロした風体であったが、子供はとてもなつがしがるのだ。 それをみて僕も「フハッ」と驚いてしまった、 「生まれかわり」それはやはり本当にあるのだと思った。 “百聞は一見にしかず”というが、かなりな迫力だった。 やはり生まれかわりというのはあるとしか思えない。 <精霊の呼び声> ・変わり者のM氏は、この12年来、アメリカ・インディアンのホピ族の村で、“精霊生活”にひたりきっている。 氏は25年くらい前からわが水木プロに出没していた。 その頃、夢知らせで氏の生活の面倒をみるようにという告知があったが、その頃は、それほどの神秘主義者でもなかったので、その夢を全面的に受け入れるという気持ちにはなれなかったから、夢の2割くらいを(いや、1割くらいだったかもしれない)提供したことがあった。 ・氏は20年くらい前、インドに行ってから、“精霊の誘い”みたいなものを受けたとみえて、それ以前も普通ではなかったが、インドに行ってから一線をこえてしまったようだ。帰ってから初めに訪れたのは沖縄だった。 そこに、なんでも思うことが出来る、という親方を見つけてひどく尊敬していた。「それがボクの理想デス」 「じっとしていて思うことが出来るなら、それはぼくの理想でもありますよ」と、ぼくはいった。 「そうです。親方、いや先生は、世界中に子どもがいるのです」 「というと?」 「カナダに行きたいと思えば、周りがそのようにうごめき、自然にカナダに行けるのです。そこで妻をもらい、子どももいます」 「ほう」 「カナダだけじゃありません。世界中に10人くらい妻がいて、子どもは合計で25人います」 「別に金持ちでもない……」 「そうです。要するに、思えばいいのです。もっともそれまでにはかなりの修行を必要とします」というような話だった。 その時は、おかしな話だと思っていたが、最近愛読している『シンクロニシティ』という本によると、それはありうるということらしい。 ・わけのわからない感動に包まれながら、M氏は「ゼヒ、ヨロク族のマジシャン(呪術者)に会ってほしい」とのことだったので、カナダ近くにヨロク族を訪ねた。 大自然の森の中に一軒だけ家があり、そこにマジシャンは住んでいた。ぼくは“ビッグフット”、すなわち雪男ともいい、“サスカツチ”ともいう謎の巨人がいるということ、それとマジシャンの家に小人が出るというので、大いに期待していた。 マジシャンたちは、川で鮭をとり(1年分油につけておく)、顔みたいな大きさのリンゴが簡単にとれるので、それを食べて暮らしているらしい。 ・「小人は2階に出る」というので、早速2階に寝た。2、3時間、ランプをつけたまま待ったが、いっこう現れなかった。朝起きてみたら、毛布があらぬ方向にあった。マジシャンに聞くと、「小人が引っ張ったのだ」の一点張り。「いや、ランプがついていたから」というと、「ランプがついてても出ますョ」という。たぶん毛布を引っ張って2、3メートル先に置いたのだろう。しかし、目で見て、写真を撮りたかったのだが、失敗した。 ビッグフット(雪男)は、大きいし、つかまって食べられでもしたら損だと思ったから、あまり会いたくなかった、なにしろ“人”というものがいない大自然の中だから、ビッグフットが“いる”といっても不思議ではない。 ・マジシャンは、ビッグフットの“家族”を見たといっていた。二人の親と子どもで、話し声はしなかった。間もなく消えたと言っていたから、ぼくはある種の“霊”みたいなものではないかと思った。たとえば沖縄の“キジムン”みたいに……。 しかし、雪男の足跡というのがたくさん石膏で固めてあるのをみると、簡単に“霊”だとも言い切れないと思った。 マジシャンは、ほかにも妖怪はたくさん来るといっていた。“妖怪”の大半は目に見えないが、ある種の“霊”である。 ・というのは、アフリカ、東南アジア、ニューギニア、アイルランドなどを回ってみると、それぞれ名前は違っているけれども、日本と同じ霊が形になっているのに驚く。 そこでぼくは、世界の妖怪の基本型ともいうべきものは千種でまとまる、形のはっきりしたものはそれぞれの国が350種くらいだということが分かったので、それぞれの国の妖精・妖怪を引っ張りだし、各国のものと比較する本を作って、ぼくの思っていることがどこまで本当か試してみようと思っている。 見えない世界の人々、すなわち神様とか精霊、妖怪のたぐいは、目に見えないからいあにのではなく、それはいるのだ。ただとらえ方が難しいのだと、ぼくは思っている。 ・それで、今回の“精霊の歌”を手に入れたことで、ぼくはとてもM氏を尊敬するようになってしまった、どうも“同族”らしい。……というのは、かの尊敬する沖縄の親方と最近なんだか似てきているみたい……知らない間にぼくは沖縄の親方みたいになっているようだ。………ありがたや、ありがたや、合掌……。 『水木しげるの日本妖怪めぐり』 水木しげる JTB 2001/8 <目に見えないものと目にみえるもの> ・世の中には目に見えないものと目に見えるものがおり、よく気をつけてみると感じられる。 感じられるというのは見えないからで…まぁ、妖怪とは感じでつかまえるものなのだろう。この感じは日本よりも外国、例えばニューギニアなどでは非常によく感じられるからおかしなものだ。 土地の人に聞くと、「そんなバカなこと聞くやつがあるか。そこのジャングルにたくさんいるじゃないか」といったぐあいで、そういう存在は自明の理、すなわちあたりまえのことじゃないか……というわけである。そう、それを感じるのは、ごくあたりまえのことなのだ。 <山に棲む、長い髪を振り乱す老婆> ・実際山の怪というのはとても多い。これは明暦三年(1657年)頃の秋の話である。陸中(今の岩手県)閉伊郡樫内に鷹狩場があり、足軽長十郎という男がそこへ働きに行っていた。その日もいつもと同じく丑の下刻(今の午前2〜3時頃)に家を出て、明け方に九十九折の細道をあがっていた。すると左の山の草木がわさわさと騒ぎ出した。どうも普通の風ではないらしく、やがて山鳴りが響きわたり雷のように激しくなってきた。 ・この夜明けに何事だろうと振り返ってみると、そこには背丈七、八尺(210〜240センチ)もある老婆が、腰まである髪を振り乱し、両眼を大きく輝かせていた。そして、老婆とは思えない風のような速さで走ってきたのである。長十郎はもう逃げることもできなかった。(中略) ・これが山に棲む老婆の怪『山婆』で「山姥」ともいわれる。なにしろ背丈がとても大きく、痩せていて、鋭い眼は光り、口は耳まで裂けている。真っ赤とも白髪ともいわれる髪は長く垂らし、ボロを纏っているという。 ・山婆は「河童」や「天狗」と同様によく知られている妖怪だ。とにかく恐ろしい感があるが、山婆には目撃談が豊富なため説話もまた様々で、人を襲うものと人に福を授けるものとがあるといわれている。 山に棲む老婆の妖怪は「山姥」だが、これが少し若い女だと「山女」となり、爺だと「山爺」、若い男だと「山男」、子供だと「山童」と、まるで家族のように世代ごとに存在する。本当に山というのはにぎやかだ。 <ザシキワラシ(座敷童子) いたずら好きの愛らしい精霊> ・岩手県を中心とする東北地方に出現する『座敷童子』は、3〜4歳、あるいは5〜6歳の子供の姿をした、可愛らしい精霊だ。男の子の場合もあるが、女の子の方が多いという。女の子は美しい黒髪を長く垂らしていたり、おかっぱだったりする。男の子はザンギリ頭で、赤や白の着物を好んで着ているという。 ・座敷童子は、その土地に古くからある裕福な家の奥座敷などに棲みつく。童子のいる家は非常に栄えるというから、まるで福の神みたいだ。逆に、童子が出て行くと、その家はあっという間に没落してしまうという。 ・また、家の中で座敷童子にばったり出会ったりすると、童子はその家を出て行ってしまうという話もあって、これなどはどう気をつけていても避けようのない、仕方がないことに思えてならない。何故家の者と出会うと、童子は家を出てしまうのだろう。 ・一方で座敷童子が学校に棲みついたという話もある。子供と一緒に遊びまわるけれど、大人や年上の子には、その姿は絶対に見えなかったそうだ。 <河童 人間に相撲を挑む水の妖怪の代表> ・全国各地に出没し、誰もが知っているくらい有名な妖怪の一つに、『河童』がいる。河童は主に川や池、沼、湖に棲んでいるが、中には海に棲むものもいるという。 2〜10歳くらいの子供の形をしており、いちばんの特徴は名前のごとく「おかっぱ頭」と、水をためるためのお皿が頭についているところだろうか。お皿の水は河童にはなくてはならないもので、この皿が乾燥したりすると、身動きが取れなくなってしまう。 ・また、背中にカメのような甲羅があるものとないものがおり、口は鳥のように尖っているものが多い。手足の指の間に水かきがついているのも大きな特徴の一つで、このおかげで泳ぎが得意なのだろう。 河童は自分の力を自慢したがり、人間にちょくちょく相撲を挑んでくる。これにうっかり勝ってしまうと、もう一回、もう一回と、自分が勝つまでせがんでくる。 ・時には馬を川へ引きずり込んだりもするが、これは力自慢というよりは、河童が元は中国の馬をつかさどる「猿神」であったからだという説がある。 中には悪どい河童もいて、人間を水中に引き込み、尻の穴から「尻子玉」を抜く。河童はこの尻子玉が大好物で、食べてしまうのだ。龍王への捧げものにするという人もいるが、どちらにしても、尻子玉を抜かれた人間は死んでしまうのだから、たまったものではない。 <天狗 山から山へ、ひらりと飛んでいく剛の者> ・「天狗」は、「河童」と並んで最も世の人たちに知られた、日本の妖怪の代表的存在だ。そして天狗の伝説・伝承の類は、それこそ日本全国にわたって残されている。 天狗には数多くの種類がある。中でも有名なのが、京都の鞍馬山に棲む「鞍馬天狗」と、同じく京都の愛宕山に棲む太郎坊という、日本最大の「大天狗」だろう。 ・これら大天狗たちは、自分の持つ知恵や技能を鼻にかけ、慢心したため鼻が高くなったことから「鼻高天狗」とも呼ばれている。 ・また、するどい口ばしと羽を持ち、空を自由に飛びまわれる「烏天狗」や「木の葉天狗」などの小天狗たち、犬のような口をした「狗賓(ぐひん)」、剣を持って、四肢に蛇を巻きつけた白狐の背に乗った飯綱系の天狗など、枚挙に暇がないほどだ。 ・大天狗の最大の武器は、その強大な神通力にある。一本歯の高下駄を履いて山から山へと飛び移ったり、手の羽団扇で大風を起こしたりする。 ・また超人的な怪力の持ち主でもあったようで、紀州(今の和歌山県)などには、天狗の怪力を見たいと願った男の頼みを受け、家ばかりか天地山川までをも震動させてみせたというから、スゴイ。 ・また、天狗は人間の権力闘争に非常に興味を持っており、劣勢側に味方して戦をわざと混乱させ、楽しむという一面もあるようだ。手裏剣などの様々な武器を作って、忍者たちに伝授したという話も残っている。 ・源義経が幼少の頃、鞍馬山で天狗に剣術を学んだという話は有名だが、天狗は武術にも長けていたようだ。天狗には○○坊という名前が多いが、義経と生死を共にした、武蔵坊弁慶などは、父親が天狗だったという伝説もある。どうやら天狗は、日本の歴史に深く関わってきたようだ。 ・今でも、高尾山などに行って天狗の像を見ると、いかにも深山にふさわしく、山の精が化して天狗になった気さえする。 超絶な神通力といい、一種崇高でもあるその存在感は、もう妖怪というより、神に近い感じさえするのである。 <鞍馬寺 牛若丸が夜ごと天狗に武術を習った寺> ・鞍馬山は、愛宕山と並んで、日本で最も多くの天狗が集結する場所として有名。鞍馬山に棲む天狗は「僧正坊」と呼ばれ、日本八天狗の一つに数えられる大天狗である。除魔招福の力に優れていたという。 ・『義経記』によると、八歳で鞍馬寺に預けられた牛若丸(後の源義経)に、鞍馬寺の天狗が、あらゆる兵法武術を教えたといわれている。 『あなたもバシャールと交信できる』 坂本政道 ハート出版 2010/12/10 <バシャールとは、どういう存在?> <惑星エササニの生命体> ・バシャールはエササニという星に住んでいる地球外生命体です。エササニとは、Place of living light (生きている光の池)という意味です。彼らの世界は、喜びと無条件の愛に満ち溢れる世界とのことです。 そこには彼らは、数億(人)位いて、その総称をバシャールと呼んでいます。ちょうど我々を地球人と呼ぶようなものです。住んでいるのは、恒星ではなく惑星です。 ・方向としては地球から見てオリオン座の方向です。もちろん、太陽系外の惑星です。地球から500光年ほどのところにあるShar(シャー)という星の周りを回る第3惑星のことです。 ・残念ながら地球からは見えないと言われています。暗すぎて見えないというよりも、我々とは、微妙に次元、あるいは、「密度」が違うためのようです。 ・地球は、そして人類は「第3密度」であるのに対して、バシャールとエササニ星の宇宙人は「第4密度」です。 ・その惑星から数百人?が宇宙船にのって地球にやってきています。現在、彼らは地球の上空にいて、アメリカ人のダリル・アンカという人を通して、チャネリングをしています。 <グレイの子孫> ・バシャール自体はどういう生命体なのかというと、実はグレイと呼ばれる宇宙人と地球人の間に生まれた混血だということです。では、グレイとはどういう存在なのでしょうか。ご存じの方も多いと思いますが、グレイはアーモンド型の黒い目をしたちっちゃい宇宙人で、悪いイメージがあります。ネガティブなタイプだといわれています。 ・ちなみに宇宙人はポジティブなタイプとネガティブなタイプ、それにニュートラルなタイプがいるとのことです。ポジティブなタイプの霊は、プレアデスに住む生命体(プレアデス星人とかプレアデス人)です。アークトゥルスやシリウスの生命体、こと座の生命体の一部もポジティブです。ネガティブなタイプに派、こと座やオリオン、シリウスの生命体の一部がいます。 ・バシャールによればグレイというのは、本当は宇宙人じゃなくて、「パラレルワールドの地球に住む人類」です。パラレルワールドでは、この世界と併存する世界のことです。 ・そして、時空間を超えてこの地球にやってきて、人類をアブダクション(誘拐)し、受精して、子孫を作りました。それがバシャールだということです。 ・ですので、バシャールの先祖というのは、グレイと我々人類ということになります。 <地球のまわりに集まる地球外生命体たち> ・バシャールたちは、今アメリカのセドナという場所の上空にいます。ただし、何度も言いますが、宇宙船自体も第4密度ですので、セドナに行って上空を見上げても通常は見えません。 ・このように、いろんな宇宙船がいろんなところにいるわけですが、ほとんどがポジティブ側の宇宙人たちです。ネガティブ側もいますが、比率としては10対1くらいだそうです。 ・ポジティブ側は連合を組んでいるようで、ル−ルがあるようです。そのルールというのは、2012年までは地球人類に直接的には干渉しないというものです。 『地球を支配するブルーブラッド 爬虫類人DNAの系譜』 スチュアート・A・スワードロー 徳間書店 2010/6/18 <リゲル 米政府と協定を結んだオリオン連盟リーダー> ・この集団は1954年に米国政府と協定を結び、彼らの技術と科学情報を米国に与えるのと引き換えに、米国民を誘拐する(ただし傷つけない)許可を米国政府から得ている。 ・こと座の内戦とそれに続くこと座星系へのりゅう座人の侵略を通じ、彼らの惑星は戦争で痛ましい損害をうけたため、肉体的にも遺伝子的にも弱々しい存在になっている。 ・彼らは、りゅう座人のために働いている。りゅう座人が攻略の前準備をできるように侵略予定ルートを偵察する仕事である。 ・軍隊型の厳格な階層制の文化を持っている。特にゼータ・レティクリ1と2のグレイが絡む場合はそうである。また肉体から肉体へと魂を移す能力を持っている。 <シリウスA イスラエル政府と契約の宇宙の商人> ・背の高い細身のシリウスA人は、青と白の長いローブを着ている。両腕を横にまっすぐ広げると、身体全体でアンク(エジプト十字架)の形になる。これが彼らのシンボルである。宇宙の商人であり、技術と情報を売買して、排他的な取り引きルートと特別な優遇を得ている。彼ら自身に向けて使用される恐れのある技術は絶対に提供しない。彼らは、オハル星人に創作されたが、本来の目的を見失っている。 <シリウスB 老子、孔子、釈迦に叡智を与えた銀河の「哲学者」> ・ジャングルか湿地のような惑星の洞窟状空洞や地下で隠遁生活を送っていることが多い。寿命は極めて長い。大半は、家族形態とは無縁である。 <くじら座タウ グレイ種を目の敵にし、ソ連と協定を結んだ> ・この人間のような生物は、グレイ種を目の敵にしている。宇宙のどこであろうとグレイを発見したら叩きのめすと誓っている。 ・地球までグレイを追って来た彼らは、1950年代にソ連と協定を結び、基地と自由に領空を飛行する権利を得た。 ・最近になって、ロシア人はタウ人との協定を破棄し、同じ協定をリュウ座人の前衛部隊と交わしてタウ人を追い払ったと考えられている。 <ビーガン シリウスA人の遺伝子から作られたグレイ> ・このグレイ種は、シリウスA人の遺伝子から作られている。シリウス人の船の標準的な乗組員である。主人のために労役、実験、雑用を行う。ゼータ・レティクリ1と2のグレイは、前向きにビーガンの指揮に従い、人間の誘拐や鉱物のサンプル収集などの特定の任務を行う。 <ゼータ・レティクリ1 地球人監視のためリゲル人が作ったグレイ> ・このグレイのエイリアンは、リゲル人が地球の人間を監視するために作った。人間とリゲル人の混合物である。人間の胎児と同じように四本の指と割れたひづめを持つ。ホルモン液と遺伝子実験のために人間を誘拐することで有名である。 ・遺伝子的・ホルモン的な欠乏症のため、彼らは、急激に死滅している。他者を誘拐することで、自らの種を救う交配種の原型を作ろうとしている。 <ゼータ・レティクリ2 遺伝子操作で作られたグレイ。爬虫類人に奉仕> ・このグレイは、遺伝子操作で作られた爬虫類人への奉仕階級のメンバーである。完全にマインド・コントロールされており、中央情報(コンピュータ)に接続されている。集団精神で一体となって動く。彼らは、無心になってゼータ・レティクリ1を手伝う。誘拐現場でよく目撃されるが、子供のように純真に行動する。 <アンタレス トルコ人、ギリシャ人、スペイン人のDNAに> ・極めて知識が高く攻撃的である。 ・彼らの社会の最深部まで入り込むことができた者は、ほとんどいない。 ・女がいるところが観測されたことはなく、彼らは、同性愛者で、生殖目的でのみ女を使用すると考えられている。ただ、実は、ある母系集団が彼らの背後で権力を握っているとも考えられている。 『オカルトの惑星』 1980年代、もう一つの世界地図 吉田司雄 青弓社 2009/2/23 <シャンバラへの旅>―80年代の日本の危うい夢(宮坂清) <アガルタの首都シャンバラ> <多彩な表象> ・ところが、1970年ごろを境にしてシャンバラやアガルタは表現の素材として広く用いられ、より大きなマーケットに流通するようになる。 ・まず、水木しげるは「ビッグコミック」1968年7月1日号(小学館)に『虹の国アガルタ』を掲載した。このタイトルからは、先述のディクホフがアガルタを「虹の都」と呼んでいることが想起される。主人公の青年がチベットを訪れ、アガルタを探し求めたあげく、鏡面に現れる女性に誘われてアガルタに消えるという物語である。アガルタがチベットにあるという点は「正確」だが、鏡面をアガルタへの入口にしている点は、管見ではほかに例がなく、むしろ鏡面を異界への入口とする物語(例えば『鏡の国アリス』)を参照したものとみるのが妥当だろう。 ・また、石森章太郎は1974から75年にかけて「週刊少女コミック」(小学館)に『星の伝説アガルタ』を連載している。この物語ではアガルタは秋田県のピラミッド型の山の地下空間にあり、金星からやって来た「ヘビ族」の子孫が、そこで「星のしずく」の原料となる薬草を栽培している。登場人物にディクホフの名を語らせているほか、ディクホフにならい「金星からやってきたヘビ族」の若者を主人公に据えるなど、内容とも大きな影響が見られる。また、この物語にはチベットとの関連はほとんど見られないものの、地下都市、UFOや宇宙人、ピラミッド、ポルターガイストなど、オカルト的な要素がちりばめられていて、アガルタが、70年代のオカルトブームに多少なりとも取り込まれていたことがわかる。 <チベットに回帰するシャンバラ> ・さて、1980年代を迎えると、シャンバラは新たに表れたオカルト誌「ムー」(学習研究社)によって急速に知られていくことになる。 ・「ムー」は1979年11月の創刊号で、すでに「人類最後のロマン 地底世界伝説」(阿基未得)と題した記事を載せ、その冒頭、シャンバラを「地底王国の首都」として取り上げている。この記事は、世界各地の地底世界伝説や地球空洞説を紹介しながら、それらが実在すると主張するものだった。 <精神世界の救世主へ> ・「ムー」のシャンバラ熱の頂点は、1984年11月号の30ページにわたる「総力特集 地底からの救済 シャンバラ大予言」(上坂宏)である。ボリュームもさることながら、注目されるのは、タイトルにも示されているように「救済の予言」がテーマになっている点である。 ・これらの記事の影響は、例えば、1988年に 高階良子が少女雑誌「ポニータ」(秋田書店)に連載した漫画『シャンバラ』にみることができる。地上、そして地下のシャンバラという二つの世界があり、シャンバラの光(光の御子)が闇(ジャンザ)と闘い、ジャンザに支配された地上世界を救う「どこも内乱や暴動が起こり危険な状態 ジャンザに操られている この内乱は、やがて世界を巻き込み核戦争へと拡がるでしょう 地上は死滅する それを止められるのはあなただけ」と救済を予言している。 ・しかし、いずれにしても、1980年代に至るまではほとんど知られていなかったシャンバラが、数年の間に現代社会の救済者として大々的に語られるようになったことは驚くべきだろう。 ・そして、86年にオウム神仙の会(のちのオウム真理教)が「シャンバラ新聞」なる新聞を発行し始めたこと、のちに「日本シャンバラ化計画」を開始したことを考えると、このことが持つ重みはさらに大きなものになるはずである。 『ニッポンの河童の正体』 飯倉義之 新人物往来社 2010/10/13 <宇宙人グレイ説> ・さまざまな河童の正体説の中でも極北に位置するのが、この河童=宇宙人グレイ説である。UFOに乗って地球に飛来し、NASAと取引をしてエリア51に潜んでいるという宇宙人・グレイ。彼らは、1メートル20センチ程度で、メタリックな灰色の肌をし、釣り上がった目と尖った顎が特徴である。彼ら悪の宇宙人グレイこそが太古から日本に出没していた河童であり、河童に尻子玉を取られるとはUFOにさらわれての人体実験、河童駒引とはつまり現在のキャトル・ミューティレーションのことだったのだ、というのがこの説である。 ・宇宙人という正体不明の存在を河童という正体不明の存在の正体にするというのは、つまり何も判明していないのと同じだというのがこの説の最大の弱点である。 宇宙人・グレイと河童の不思議な符合は、人や家畜を害するものに対する想像力のありようは、文化が違ってもどこかで似ることがある、と考えた方が合点がいくのではないか。 ・このグレイ説は雑誌『ムー』誌上で人気を博してさらにもう一段階の進歩を遂げ、実は宇宙人だと思われているグレイは地球固有の異次元吸血妖怪で、アメリカ軍はそれを知りつつ本当の宇宙人のカモフラージュに妖怪・グレイを用いているのだとされる。 ・世界中でチャパカプラとかスワンプ・モンスターと呼ばれて人や家畜を害しており、さらに彼らはプラズマを操って河童火を燃やす力があり・・・とまあ、八面六臂の大活躍である。この説に従うと、「妖怪だと思われていた河童の正体は、実は宇宙人だと思われていた妖怪である」ということになる。複雑さは増したが、何も言っていないことは同じと言うことになるだろう。 <河童で町おこし><町中の妖怪たち> ・日本では各地域に伝わる妖怪伝承をもとにした町おこしが行われている。近年では、鳥取県境港市の「水木しげるロード」が人気を博している。 <札幌市奥座敷定山渓温泉> ・札幌市奥座敷定山渓には、「かっぱ淵」の伝承がのこされている。ある青年が豊平川で急に何かに引きずり込まれるようにして淵の底に沈み、発見できなかったが、一周忌の夜、父親の夢枕にその青年が立ち、「私は、今、河童と結婚して、妻や子どもと幸せに暮らしていますから安心してください」といって消えたという伝承である。札幌市奥座敷定山渓温泉は、この「かっぱ淵」の伝承をもとに、河童で町おこしを行っている。 <岩手県遠野市> ・岩手県遠野市は、「河童のふるさと」として有名である。遠野市には、柳田国男『遠野物語』に河童の伝承が多くみられるように、河童にまつわる伝承が数多く残されている。 <宮城県加美郡色麻町> ・色麻町には、「おかっぱ様」として有名な磯良神社がある。 <千葉県銚子市> ・銚子市には大新川岸の河童伝承がある。昭和60(1985)年に、「銚子かっぱ村」ができた。 <東京都台東区「かっぱ橋本通り商店街」> ・「かっぱ橋本通り商店街」では、かっぱ像や、かっぱの絵の看板をたくさんみることができる。 <広島県南区段原> ・猿猴川は、猿猴(エンコウ)」という河童の名称がつけられているとおり、河童がいたと言う伝承がある。 <熊本県天草市栖本町> ・ガワッポ(河童)の伝承が残されている。 <福岡県久留米市田主丸町> ・河童の総大将の九千坊が筑後川に棲んでいた伝承がのこされている地域である。 <河童愛好家による全国ネットワーク><河童連邦共和国> ・日本全国で河童の町おこしをしている地域や河童愛好家の人々が集まり、「河童連邦共和国」というネットワークがつくられている。 『1冊で1000冊』 読めるスーパー・ブックガイド 宮崎哲弥 新潮社 2006/11/15 <アドルフの我執――人間ヒトラーの日常を分析する> ・オリヴァー・ヒルシュビーゲル監督の『ヒトラー〜最後の12日間〜』 が話題になっている。その焦点は、まずヒトラーの人間的側面を照らし出した戦後初のドイツ映画であること。そして、権勢と栄華を極めた第三帝国が地下壕の密室に追い込まれた後の末路が具に描き込まれていること、だ。 ・“T・ユンゲ”『私はヒトラーの秘書だった』(草思社)は、映画の原作となった最後の秘書の手記。人間観察が面白い。「愛し合っているなら結ばれるべし」と言い張るヒトラーのせっかちな結婚観を「中産階級的!」と嗤ったりしている。ヒトラーのみならず、取り巻きたちの寸評も秀逸。OLからみた独裁者像という感じ。 ・定評があり、入手し易い伝記ならばJ・トーランド『アドルフ・ヒトラー』(全4巻 集英社文庫)がお勧め。初めて「悪魔に人間の顔を与えた」という評言通りの大作。大部過ぎてとても付き合えないという向きには、水木しげるの大傑作『劇画 ヒットラー』(実業之日本社、ちくま文庫)を。考証の正確さも驚くべき水準だが、史実のマンガ化には留まらない。ヒトラーの人間的魅力までも伝える。 ヒトラーを信念、実行力、理想を兼ね備えた革命家に他ならないとするのは、M・ハウスデン『ヒトラー ある《革命家》の肖像』(三交社)。 E・シャーケ『ヒトラーをめぐる女たち』(TBSブリタニカ)は、ヒトラーを中心とした女性相関図。 だが、L・マハタン『ヒトラーの秘密の生活』(文藝春秋)は同性愛者説を検証し、肯定的な結論を引き出している。 精神分析的アプローチといえば、A・ミラー『魂の殺人』(新曜社)が著名だが、ヒトラーという複雑な現象を「幼児虐待のトラウマ話」に縮退させる。ミラーの単調な正義感、非社会性は、むしろナチズムやスターリニズムに一脈通じる。 <アドルフの我執?――今も大衆が好む陰謀論、オカルト……> ・映画『ヒトラー〜最期の12日間〜』のもう一つの原作はJ・フェスト『ヒトラー 最期の12日間』(岩波書店)だ。ヒトラーとその腹心たちの心中には「みずからを神話として、世界の意識の中に刻み込もうとする意図」がみえたという。そうした妄想はやがて、世界観の闘争と現実の戦争との区別を曖昧にしてしまう。 ・では、ヒトラーの思想、ナチスの世界観とはどのようなものだったか。A・ヒトラー『わが闘争』(上下 角川文庫)は、その最も重要な手懸り。意外に「読ませる」内容である。 自意識過剰で、反抗的で、嘘や無知が散見され、陰謀論と偏見に満ちているが、そんな質の書跡なら、いまも書店に平積みになっている。大衆は力への屈服を好み、感情で物事を決するという本書の臆見は結構当たっているかも知れない。 ・同書ではワーグナーの楽劇への心酔が吐露されている。J・ケーラー『ワーグナーのヒトラー』(三交社)はワーグナーがヒトラーに与えた影響に関する珍しい研究書。 ヒトラーとオカルティズムの関わりは「精神世界」や陰謀史観の世界ではあまりにも著名だ。L・ポーウェル、J・ベルジュ『神秘学大全』(学研M文庫)やT・レヴンズクロフト『ロンギヌスの槍』(学研M文庫)がその代表。なかなか巧妙に書かれているので、真に受けずに楽しむべし。 ・K・アンダーソン『ヒトラーとオカルト伝説』(荒地出版社)は、正統派史学からは無視され、通俗書の世界では猖獗を極めているヒトラー=オカルティスト説を客観的に検証する。「ヒトラーは極めて実際的な人物」であって、オカルティックなイメージを利用しただけというのが真相らしい。 そうして捏造された奇怪な妄想体系に対する批判的考察なら、小岸昭『世俗宗教としてのナチズム』(ちくま新書)が優れている。 各論的だが、藤原辰史『ナチス・ドイツの有機農業』(柏書房)はヒトラーのエコロジズムを詳説。「もったいない運動」の先駆者はナチス!? <空飛ぶお皿顛末記――UFO論議にやっと決着がついた?!> ・イギリス国防省がUFOの存在を否定する報告書を作成していたことが明るみに出た。4年間の本格的科学調査に基づいて、2000年にまとめられたという。 実は、こういうレポートは1960年代にもあった。アメリカ空軍がコロラド大学に委嘱して組織されたコンドン委員会によるものだ。 邦訳のエドワード・U・コンドン監修『未確認飛行物体の科学的研究 コンドン報告 第3巻』(プイツーソリューション)を読むと、かなり精緻で多角的な研究だったことが」わかる。その結論は今回と同じく否定だった。 ・ピーター・ブルックスミス『政府ファイルUFO全事件』(並木書房)は、コンドン報告の分析を高く評価している。にも拘わらず「感情的なUFO信者」には「あまりに難解すぎた」のだ。客観的な史料批判に徹した画期的内容。カーティス・ピーブルズ『人類はなぜUFOと遭遇するのか』(文春文庫)と併読すれば、UFO研究史を押さえることができる。 ・まともな科学が手を引いた後、新たな神話が蔓延った。例えばオカルト心理学の教祖、ユングはUFOを普遍的無意識の象徴と捉えたが、この考え方はニューエイジ方面で広く受容される。キース・トンプスン『UFO事件の半世紀』(草思社)はユング的視点による総括。 UFOに誘拐されて、外科的手術や性的虐待などを受けた「記憶」を催眠誘導で甦らせるという大真面目な研究書は、ジョン・E・マック『アブダクション』(ココロ)。例のトラウマ記憶回復運動の一環。著者はハーヴァード大学の精神医学教授。超一流大学の研究者が疑似科学に嵌った典型例だ。 こうした現象のなかに、「社会の心理学化」の徴を看て取るのは、木原善彦『UFOとポストモダン』(平凡社新書)。UFO神話の文化研究。 UFO陰謀論もお盛ん。マイケル・バーカン『現代アメリカの陰謀論』(三公社)を。 それらすべてを笑いのネタにしているのが、山本弘、皆神龍太郎、志水一夫『トンデモUFO入門』(洋泉社)。 『UFOとポストモダン』 (木原善彦) (平凡社新書) 2006/2/11 <アブダクションとエイリアン> ・ひょっとすると数百万人の人々がアブダクションされ、インプラントされている。 ・EBE「地球外生物的存在」は、合衆国政府と秘密協定を交わしている。EBEは自由にミューティレーションとアブダクションを行なうことができ、またニューメキシコ州ダルシーに秘密基地を建造することが許可された。それと引き換えに合衆国政府はハイテク技術と兵器を与えられた。 ・EBE「地球外生物的存在」が協定に違反し、使える技術や兵器を合衆国に与えなかった。 ・ 1979年、ダルシー基地内の人間を救出しようとして、合衆国の特殊部隊の兵士66人が殺された。(「ダルシーの大虐殺」) ・人類を家畜化しようとするEBEと合衆国政府は、既に戦争状態にある。 ・「スター・ウォーズ計画」の通称で知られる戦略防衛構想(SDI)は、ソビエト連邦を仮想敵とするものではなく、実はエイリアンと対決するためのものである。 『あてになる国のつくり方』 フツー人の誇りと責任 井上ひさし、生活者大学校講師陣 光文社 2008/8/7 <近隣との百年戦争> ・もっと根深い話をしましょうか。都会でもそうでしょうが農村では、隣り同士の仲が悪いのです。ま、わが家もそうですね。隣の隣の家とは、利害関係がないから仲がいいのですが、とくに後ろの家とは、親子三代で、もう100年も争っています。発端は、わが家の敷地が、裏の家の土地に三尺ほどはみだしていると向こうが三代にわたって言い続けていることです。私は、絶対うちの言い分が正しいと思っているのですが、どちらも物的証拠がない。後ろの家の言い方はしつこくて、 「お前は立派なことを言ったり書いたりしてるけど、何だ、お前、盗人じゃないか」と、こういう言い方を何度もしてくれるわけです。 ・とうとう私は頭にきて、「それならこの土地は俺が買う。坪100万でも買ってやるぞ」と、腹をくくりました。親戚や区長さんに来てもらい、立ち会ってもらって、金で折り合いをつけようとしたのです。ところが、当時まだ生きていた親父が、「絶対そういうことをしちゃいかん」と反対する。なぜか。 「お前がそういうことをすると、前の二代が嘘をついてたことになるじゃないか。自分たちがいっていたことは間違っているから、あいつは金を出したのだ、ということになるから、絶対しちゃいかん」 ・たしかにそうです。結局、話をつけるのはやめました。だから、まだまだ喧嘩は続く。うちの息子にも親父の教えを言い伝えていますし、小学校の5年生の孫にもきちんと伝えていますから、争いは100年は続く・・・そういう世界なのです。 ・そういう世界に何がグローバリゼーションだと、私は、いつも言っているのです。 <農村原理主義による運命共同体> ・日本の農村はよく、運命共同体だと言われますが、その根っこは、田んぼに使う水にあります。田んぼは自分のもの、つまり私有地、しかし、田んぼに使う水は自分のものではありません。上流から下流へ流れてくるものだし、皆で共同管理しなくてはいけないから、自分勝手なことはできない。流域全体のシステムに従うしかないのです。ですから、個人主義や自我は、稲作をやっている限り絶対に人々の心には育たないのです。 <大農場がつぶれる時代> ・では大農場をもつブラジルの農家がいいかというと一概には言えません。ブラジルは、完全に市場主義が成立していますから、弱肉強食が社会的に容認されています。国も何ら手助けしてくれません。だから大農場でもやっていけない現状が生まれてきます。 ・グローバリゼーションの中で、1ヘクタールだろうと1700ヘクタールだろうと農業では食えなくなっている、これが世界の農家の現実です。 <グローバル化に農業の未来はない> ・佐賀県では1800億円あった県下の農業粗生産額がこの間に毎年100億円ずつ減っていきました。 何度でも、声を大にして言いたい。毎年100億円ずつですよ。 ・本当に、農業で食えない状況は深刻です。しかも、高齢化はすすむ一方だ。これは、佐賀県だけでなく、日本国中同じ状態なのです。 ・「今、村の人が一番関心を持っているテーマは何ですか?」という質問をぶつけてみると、「若い者は出ていってしまった。残った者は歳取った。さあ、どうするかということだよ」という言葉が返ってきました。 ・しかし、私は日本の農業が滅びたって、百姓は困らないとずっと言ってきました。農家は、どんな時代になっても、自分と自分の家族の食べる分だけは作りますからね。他人が食べる分をやめるだけの話です。それで、いいんですよ。結局、日本の農業がなくなって困るのは消費者であるフツー人です。そういう意識も視点もフツー人の間に育っていない。そこが困った問題です。 『荒俣宏の不思議歩記』 荒俣宏 毎日新聞社 2004/11/1 <蜂須賀正氏の有尾人調査> ・平成15年4月13日、東京の立教大学で「蜂須賀正氏(はちすかまさうじ)生誕百年記念シンポジウム」が開かれた。永らく忘れられた人物だったので、まことに喜ぶべき復権である。正氏(1903〜53年)は阿波蜂須賀十八代当主だった一方、鳥類学者として華々しい業績を残した。日本人ばなれした冒険貴族でもあった。 ・それで思い出したのが、正氏は昭和3年にフィリピン探検を敢行した際、帝大の松村瞭博士から奇妙な調査を依頼された逸話がある。いわく、「フィリピンのどこかに尾のある人間がいるので、これを研究できたら世界的に珍しい報告になるでしょう」。 かくて正氏は有尾人発見という無茶なミッションを負って出発した。鳥類採集やアポ山登頂など多くの成果をあげたこの探検にあって、正氏は最初のうち有尾人調査にもずいぶんと力を入れたようである。30年前にフィリピンで撮影された証拠写真を入手していたので、自信もあったようだ。その他、マレー半島、ボルネオ島、ニューギニアでの有尾人情報を手にしていた。 ・じつは昭和初期、日本には密かな有尾人ブームが起きていた。端緒となったのは、大正期に開催された大正博覧会、つづいて平和記念博覧会にもお目見えした「南洋館」だった。南洋への関心を高めるべく、見世物に近い物産紹介が行なわれたが、その一部に有尾人まで加えた南方の風俗を含んでいた。数年前にわたしは、平和博のときと思しい南洋館発行の絵ハガキに、「ボルネオ、ダイヤ族有尾人」なる写真を発見して、驚きのあまりのけぞった記憶がある。その解説に、正氏が入手したのと同じような、アジア各地の有尾人目撃情報が載っていた。 ・しかし正氏の探検隊は、進展とともに純粋な博物学調査に謀殺されていったし、正氏自身もマラリアに罹って以後は有尾人への関心を弱めた。ただ、日本の一般市民は、みごとなキングズ・イングリッシュを身につけ、狩猟の技にもたけ、自家用飛行機で飛び回る破天荒な正氏を、あいかわらず「怪人」扱いしつづけた。たとえば、昭和14年に小栗虫太郎は『有尾人』と題した秘境冒険小説を発表。正氏が実地調査したアフリカ中央部に有尾人「ドド」を出現させた。正氏は絶滅島ドードーを研究し、「ドド」と表記していたから、モデルは正氏その人と思しい。 <平田篤胤の広い関心> ・平田神社に保存されてきた教材の中に、絵軸がいくつも残っている。どれも、晩年の篤胤が最も力を入れたテーマ「幽冥界」と「神代」を解決するのに用いたものだ。霊界だの神の時代(古)だのは、これを目撃した人がいないわけだから、『古事記』などの古典を講義しても、文章だけではどうしても限界がある。そこで篤胤は「物」を用いることを始めた。江戸後期には考古学も進展し、各地で古物の発掘が盛んになっていた。時代の遺物と考えられるものが、文字も含めて発見されていた。篤胤は実物を示しながら講義し、「神代文字」も実際に使ってみせた。神代のことを実物を介して説明したことで、門人たちの理解は画期的に向上したにちがいない。 ・しかし、神代はそれでよいとしても、霊界のほうは「物」で説明できない。なにしろ俗世とは別の空間であるから、幽霊や妖怪を捕えて展示するわけにもいかない。そこで篤胤が編みだしたのは、「絵」つまりビジュアルを活用する方法であった。篤胤は仙境や死後の世界を見て現世に戻ってきた「目撃者」を探し、その人たちから徹底した聞き取り調査を行った。仙境で暮らしたという「天狗小僧」寅吉などは、門人にして十数年にわたり調査を継続している。寅吉が伝える仙境の舞踏については、楽士、舞手の配置、見物人の並び具合、果ては楽譜にあたる音曲の詳細まで聞きだしている。 ・これらの情報を絵画化し、ついに「見えない世界」の講義術を確立した。たとえば、仙境に住む「角の生えたイノシシ」を、仙界の住民が鉄砲で狩猟する光景を描いた画軸がある。日本一の鉄砲鍛冶、國友藤兵衛が寅吉に確かめたところ、仙人は空気銃を使うと聞いて仰天した。また、それまでビジュアル化されたことがなかった日本の神々の姿をも、篤胤は絵画化した。「高根様」と称する仙界棟梁の肖像は、まことに迫力に満ちている。記紀に語られる地上最初の陸地「オノゴロ島」を克明に描いた軸もあった。国学の教授法の革命だったと思う。 ・篤胤を継いだ二代銕胤は、明治維新のあと大学校の開設を計画する役職に就いた。しかし、島崎藤村の『夜明け前』に見るごとく、絶望してすぐに新政府と距離を置いた。平田学派は幽冥界の主神、大国主命や、南朝の天皇にも敬意を払い、独自の神道思想を深めていた。しかも、その担い手は庶民が主体だった。 <稲亭物怪録を覗く> ・広島県の東側に三次という市がある。全国的には無名に近いが、二つの自慢がある。一つは、『忠臣蔵』の浅野内匠頭に嫁した阿久利姫(のちの瑶泉院)。もう一つは、1カ月間妖怪の来訪を受け続けながら耐え抜いた豪の者、稲生平太郎。2人とも三次の出身者で、郷土の誇りといわれる。わたしは『忠臣蔵』にも心惹かれるが、やはり時節柄、妖怪に食指が動く。 ・三次市では稲生平太郎の妖怪話を市興しのテーマに据え、すでに「物怪プロジェクト三次」が進行していた。この平太郎は江戸中期に三次に住んだ実在の武士だ。三次藩はその頃廃藩になったあとで、宗藩の広島浅野家から禄を受けてはいたが、仕事もなくブラブラしていた。16歳の平太郎はある日、江戸帰りの相撲取り三ツ井権八に「三次の侍は意気地がない」となじられたことに反発。肝試しと百物語に挑んだ。 ・ところが、これで比熊山から妖怪の一団を呼びこんでしまい、7月1日から1カ月間、毎晩のように妖怪の来訪を受ける結果となった。目玉のついた石、女の生首、割れた頭から出てくる赤んぼう、ぞろぞろはいりこんでくる虚無僧の群、浮きあがる畳、赤い舌でベロベロと舐めまわす大顔、果ては巨大な蜂の巣から黄色い液がボタボタ垂れてくる怪など、ゾッとするような物怪にたたられた。しかし平太郎はついに耐え抜き、妖怪大将を退去させた。この「実話」が広く流布したのは、なんといっても多くの絵巻が制作されたことに拠っている。2002年6月、県立歴史民俗資料館に寄贈された未見の絵巻『稲亭物怪録』があると聞き、ぜひとも見物したくなった。 ・最後の場面、妖怪大将が退散する光景では、無数の妖怪どもがツバメのように長い尾を引きながら宙を飛んでいる。今まで見た平太郎の妖怪絵巻のうちでは最も詳しく、他の絵巻では図示されなかったシーンが続出する。 ・さあ、エラいことになった。絵巻のタイトルも『稲亭物怪録』とあり、これまで使われてきた題、『稲生物怪録』とも異なる。他にただ一冊、同じタイトルの写本が慶應大学に所蔵されているが、ここに挿入されていた絵とよく一致する絵巻だ。つまり、これは別系統を構成する作品群の一つなのである。稲生平太郎の妖怪話は、江戸時代から、平田篤胤、泉鏡花、折口信夫など多くの人々を魅了してきた。いまだに実話だったのかフィクションだったのか、全貌が明らかにされていない。この新発掘の絵巻が新たな手掛かりとなり、世にも珍しい妖怪実見記の真相が解明されることを祈る。 『図説 奇形全書』 マルタン・モネスティエ 原書房 1999/9 <奇妙な人あれこれ> <しっぽのある人> ・1910年に旅行家のW・スローンは、ニューギニアの奥地で、四肢に加えてしっぽのある部族を発見した。公式発表によると、それはしっぽ状の突起物で、ヒヒのしっぽと同じくらいの長さがあった。 ・しかし、新たな報告が三つなされている。その内容はこれまでに述べたものとほとんど変わらなかったが、この報告をきっかけに、ヨーロッパ各地でしっぽのある人間の問題が再び取り上げられるようになった。一つ目は、フィリピンのルソン島に住むブトク族について、フォルバン医師が1926年に収集した観察に関するものである。この部族の者は、著者が撮影した多くの写真が示すように、たびたび長いしっぽを備えていた。二つ目の報告は、1928年にさかのぼり、最もよく引用されているものである。インドシナに派遣されたネデレック博士が、両親とともにサイゴンの監獄に入れられていた、12センチのしっぽを持つ、8歳の中国人の子供を見つけたのである。ネデレックによって撮影された子供の写真は、世界中に配信され、大きな反響を巻き起こした。 ・しっぽのある人間に関する論争に火をつけた三つ目の情報は、サン・ペロドのヴェラスケス博士が発表したものである。それは次のような文章で始まっていた。「ホンジェラスのトルヒーヨ市の近くで海水浴をしていたとき、カリブ族の中年の女性が海岸にやってきた。彼女が無造作にすべての衣服を脱ぐと、長さ16センチのしっぽがついているのが見えた。その先端は、すでに短く切ってあるようだった」。 これらの話をもとに繰り広げられた多数の論争を得て、今日でもなお通用している科学的な理論が導き出された。すなわち、しっぽのある人間という特別な種族は存在しないということである。それはただ、どんな種族であれ、同じ家族の中で代々伝えられる奇形にすぎないのである。 ・今日、この種の奇形に出会うことはまれだが、それは自然がこのような奇形を作り出すことが少なくなったからでなく、当然ながら幼いころにそれが見つかることが多く、ちょっとした外科手術で取り除くことができるからである。 とはいえ、今日でもなお、いくつかの国の奥地でときどき、しっぽのある大人の人間が見つかっている。数年前、トルコのアンカラにある陸軍病院の医者たちが、トルコ東部から来た21歳の若い徴集兵にしっぽがついているのを発見した。彼は兵役検査にかかるまで、しっぽのあることを隠していた。彼のしっぽは脊椎のほぼ先端に生えており、長さは30センチほどもあった。 『河童・天狗・神かくし』 (松谷みよ子)(立風書房)1985/7 <山の神などによる神隠し> ・ある時、この部落の小さい女の子がふっとかき消すようにいなくなった。部落総出で探してみても、いっこうに手がかりはない。幾日かたって、また、ふっと現われた。その現われ方がまた不思議なことだった。この部落のはずれの薬師堂の梁の上に、その女の子はちょこんと坐っていたんだ。村の衆は、あれは薬師様にさらわれたんじゃっていった。 (長野県) ・岩手県和賀郡がはんらん。和賀町横川目。私が15歳の頃(昭和10年前後)の事件である。大雨で村の中央を流れている尻平が氾濫した。その日、私の部落の幼児(5、6歳)が見えなくなったという騒ぎが出た。消防団も出たりして、部落総出で探しまわったが、夜中になっても見つけることができなっかった。きっと川に落ちて流されたに違いないというので、川下を探しまわった。ところが、朝になってその幼児が川向うの山の中で無事で発見された。これはどう考えても不思議なことでした。その川には、丸木橋一本かかっているだけで、当日の大雨の氾濫で大人でも渡ることができない状態でした。 ・長野県上伊那郡。浦の新三郎猟師といえば、山の神様となれ親しんだ逸話の持ち主として知られています。明治の初年のこと、新三郎は金子勢五郎猟師と連れだって仙丈岳へ猟に出かけましたが、二人は途中の小屋で単独行動をとることにきめ、別れ別れになりました。それから1週間、新三郎猟師は、杳として消息を絶ってしまいました。村人に依頼して山中を捜索してもらいましたところ、勢五郎と別れた小屋に戻っているところを発見されました。新三郎の話では、小屋を出てしばらく行くと、立派な婦人が現われて手招きするのに出会いました。誘われるままについて行くと、苺などの実る場所へ連れて行かれ、たらふくごちそうになりました。 こんなわけで、山にいる間は、ついぞ空腹を感じなかったという話でした。村人はその女性を山神であるとみていますが、山神男性説をとるこの地方にも、こうした観方のあることはおもしろいことです。 出典:松山義雄著『山国の神と人』(未来社) ・和歌山県西むろ郡上三栖。紀州西むろ郡上三栖の米作という人は、神に隠されて二昼夜してから還って来たが、其間に神に連れられ空中を飛行し、諸処の山谷を経廻って居たと語った。食物はどうしたかと問うと、握り飯や餅菓子などたべた。まだ袂に残っていると謂うので、出させて見るに皆紫の葉であった。今から90年ほど前の事である。又同じ郡岩田の万蔵という者も、三日目に宮の山の笹原の中で寝て居るのを発見したが、甚だしく酒臭かった。神に連れられて、摂津の西ノ宮に行き、盆の13日の晩、多勢の集まって酒を飲む席にまじって飲んだと謂った。是は六十何年前のことで、共に宇井可道翁の璞屋随筆の中に載せられてあるという。 ・昭和二十年頃の話。私の家の近くの男の子(小六年)が昼間、にわとりをいじめたから神かくしにあって大騒ぎとなりました。井戸のそばにしゃがんでいたそうなのに、家人にはその姿が見えず、子供には家人の姿が見えるけど声が出なかったそうです。二昼夜、その状態だったそうですから神かくしに違いないと、父母が言っていました。(青森県) 『山神を見た人びと』 高橋貞子 岩田書院 2009/3 <東北文化史の古層へ> ・今では有名になった『遠野物語』ですが、当時これを評価したのは泉鏡花と芥川竜之助くらいで、多くの人は趣味本位の書物にすぎないと見ていました。しかし、この発刊が機縁になって、地方に埋もれた文化への見直しが始まり、やがて民俗学が生まれました。人々の語る伝承の比較によって日本人の歴史がわかるというのは、まったく新しい学問の誕生でした。 ・遠野で、『遠野物語』が再発見されたのは新しく、昭和45年(1970)ごろからでした。岩手国体の実施に当たって、地域の文化を観光資源として活用することが図られましたが、その年はちょうど発刊60年にあたっていました。その後、遠野では民俗学資料に重点を置いた博物館、佐々木記念館を核にした伝承園、柳翁宿と柳田の隠居所を含むとおの昔話村、南部の曲がり家を移築した遠野のふるさと村といった施設を整備しました。 ・『昔なむし』の巻末にある「岩泉地方の昔ばなしとわたくし」には、幼少時に昔話を聞いた思い出から、家業と子育てをしながら採集と執筆を行った様子が書かれています。店先や汽車の中が聞き書きの場であり、夜中や早朝が原稿用紙に向かう時間だったのです。書くことへの執念と信頼が、こうした貴重な資料集を生みだしたのです。 <山の神に出遭った人> ・岩泉の向町の佐々木亥之松(いのまつ)さん(明治生)は、20歳だったある日、山仕事で山中に入りました。奥山まで行ったとき、いきなり樹の間から顔の真っ赤な大柄の人が出て、ずいと顔を合わせました。「あ、あー」とおどろいた亥之松さんは、後退りました。ところが、相手は亥之松さん以上におどろいた様子で、うろたえながら樹の蔭に隠れました。 さあ、亥之松さんは転がるようになって家に戻ると、 「その顔はらんらんとして燃える火のようだった」 と家の人に話したきり、40度の高熱を出して寝込んでしまいました。 高熱はなかなか下がりません。亥之松さんは重態でした。あまりのことに家の人は、神子さまに、ご祈祷を頼んでお宣託を聞きました。 お宣託は、「山中で出遭った顔の赤い人は、山の神だったのです。 山の神は<木調べ>のために山中を歩いておられたのです。人間に見られてはならない姿を見られて、山の神もおどろかれたのでしょう。亥之松さんの病は、40日間病床に臥せば恢ります」 と、告げました。 そのご、ほんとうに亥之松さんは40日間でもと通りの健康体にもどって、そのあと長生きをして生涯を終えました。 <山男にさらわれた娘> ・田野畑村田代の南という家に、名をハツエと呼ぶ美しい娘がおりました。ある日、ハツエは、手籠を持って春菜を摘みに出かけたまま、突然、姿を消しました。 家族はもちろんのこと、村中が総出となって探しましたが、ついにハツエを見付ける「ことはできませんでした。ところが、その日から十数年たったある日、村のまたぎ(狩人)が山中でハツエを見ました。 ハツエは、ごつごつとした岩の上に座って、長い髪を櫛でとかしていました。またぎはおどろいて、「ハツエではないか」と、声を掛けました。 ハツエもまたぎを見ると、おどろいた様子で、なつかしそうに涙をはらはらと流しました。やがて、 「あの日、山男にさらわれて山女になった。あのころのハツエではない。今は山女なれば、おいらに出会ったことをだれにもしゃべるな。もし、しゃべったら、われの命は無いと思え」 こう言うと、さいごは恐ろしい形相となって威しつけました またぎは、「だれにも一切しゃべらない」 と、約束をしました。ハツエは、 「約束を破れば、3年のうちにお前は死ぬぞ」と、更に威しました。 またぎは秘密を抱えて山を下りましたが、心の中は平らではありませんでした。だんだん体の調子まで悪くなるようでした。こらえかねたまたぎは、ついにある日、ハツエと出会った一部始終を、村のだれかに話しました。 またぎはだんだんやつれてきて、青白くなって死にました。山女に出会って3年以内のことでした。 <人身御供とヒヒ> ・遠い昔のことです。小本海岸の波鼓が舞のあたりに巨大な松の古木があって、その枝に強そうなヒヒ(マントヒヒの異称)が腰掛けていました。そこは浜通りとして人びとの往来するところでした。 ところが、よく人隠しがあって、突然、人が見えなくなってしまう騒ぎがありました。 「なんでもあのヒヒが人を食うらしい」と、人びとは恐れました。 村人たちは相談の結果、若い娘を人身御供にヒヒに差し出して、ご祈祷をすることになりました。 ・若い娘は毎年一人ずつ、裸にされてヒヒに供えられました。のちにその娘たちの魂を鎮めるために「人殺神社」が建立されましたが。明治以前に廃社になったということです。 <天狗山から鼓の音> ・小川の国境峠に天狗山があります。海抜654メートル。昔から天狗の隠れ住む山と伝えてきました。 今でも国境集落の人びとは、「トン、トン、トン、トン」 と、天狗山から鳴り出す鼓の音を聞いています。 やがて鼓の音は、集落を囲んで立つ峰から峰をわたり歩いて、 「トン、トン、トン、トン」と、鼓の音を聞かせるといいます。 鼓の音は、四季も時刻も関わりがなく、いつ、どうともなく聞こえ出すようだと、国境の人びとは気付きました。 「きっと、天狗様は、ご自分の所在を知らせたくて、鼓を打つのだろう」と言い合って、鼓の音を聞くと、どんな仕事をしていても手を休めて戸外に集まり、天狗山を眺めるということです。 <天狗に殺された12人の神楽団体> ・天狗森は、猿沢の奥にあって、昔は天狗が隠れ棲んでいた深い森でした。近くの与一屋敷では、あるとき神楽宿をしたのですが、朝には、12人の神楽団体全員が死んでいました。与一屋敷の人は全員無事でしたが、この一大事に気付きませんでした。 その夜、真夜中の与一屋敷に天狗が舞いおりて、神楽衆の一人ひとりの口に息を吹き込んで殺したのでした。人間は天狗に息を吹き込まれると、即、死ぬといいます。その方法は、天狗は鼻が高いので、人間の頬に頬を近寄せて息を吹き込むと伝えていました。 猿沢の武田博さん(昭和4年生)は、少年時代に与一屋敷跡に行ってみました。そのときの与一屋敷跡には、土台石や腐った建築材が見えたので、そんなに遠い出来事ではないと思ったそうです。 <ツチグモと呼ばれた種族> ・遠い昔、この地方をはじめて開拓したころ、われわれと別にアイヌとツチグモがいました。アイヌは狩猟をして山で暮らしていましたが、ツチグモは極端に小さい体で、山野に穴を掘ってその中に隠れ住んでいました。 穴の入口に木の葉や草を被せていましたが、とても獰猛でアイヌや村人が通ると、いきなり襲って穴の中に引きずり込んで、猟物や食料を奪い、衣類を剥ぎ取りました。ツチグモはとても怖かったということです。 結局、ツチグモは絶滅したのですが、ツチグモを退治したのはアイヌでした。
| |
| このブログへのチップ 0pts. [チップとは] [このブログのチップを見る] [チップをあげる] |
| このブログの評価 評価はまだありません。 [このブログの評価を見る] [この記事を評価する] |
|
◆この記事へのコメント | |
| コメントはありません。 | |
|
◆この記事へのトラックバック | |
|
トラックバックはありません。 トラックバックURL https://kuruten.jp/blog/tb/karasusan1122/464528 |
|