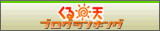*
|
※その書を再び開くかどうか わかりません※ 2.24
アカデミア・デイ・リンチェイ(Accademia (Nazionale) dei Lincei: オオヤマネコの学会の意味
ローマのコルシーニ宮殿にある科学アカデミー…
…Wikipedia…
ローマ教皇庁科学アカデミー
Pontificia accademia delle scienze
Pontificia Academia Scientiarum
…Wikipedia…
フェデリコ・チェージ
(Federico Angelo Cesi、1585年2月26日 - 1630年8月1日)
・・・・・・・・・・ ////////// ・・・・・・・・・・
『細胞学の歴史−生命科学を拓いた人びと−』1999
アーサー ヒューズ Arthur Hughes (原著)
西村 顕治 (翻訳)
望遠鏡と顕微鏡の双方が最初に用いられたのはローマであった
1601年 フェデリコ・チェジが山猫アカデミーを創設
1609年 ガリレオが参加
顕微鏡を用いて業績が継続的に積まれるようになったのは
英国の王立協会が創設(1662年)され 初代の装置管理者に
ロバート・フック(1635-1703)が任ぜられてから
顕微鏡は彼にとって、多くの興味ある対象の1つにすぎなかったのだが、それでも、1665年に出版されたかの有名な『ミクログラフィア』は、表題紙にあるように「微細なものの生理学的な記載」にもっぱら向けられたものであった。それゆえ、ほかならぬ、ここにこそ、本書の主題が始まる。細胞の構造がはじめて図に描かれて、私たちが用いているのと同じ意味での「細胞」cellという語が使われたのであった。 14
2.11 追加
・・・・・・・・・・
その化学的研究領域の創設者はフレデリック・ミーシャー(1844-1895)
彼の父親はヨハンネス・ミュラーのもとで学んだ
彼自身はバーゼル大学在学中にウィルヘルム・ヒスの授業を受けた
ミーシャーの卒後研究は 1860年代の後半に
当時の指導的生理化学者だったホッペ-ザイラーのもとで始められた
『細胞学の歴史−生命科学を拓いた人びと−』P139〜
…ミーシャーの課題選択は、しかし、完全に彼自身で決めたものであった。その頃までには、それが普遍的に存在することから、核が特別に重要な細胞成分であることは明らかとなっていた。しかし、核についてなんらかの化学分析が可能となる前提として、まずまとまった量の核をほかの細胞成分から分離しなければならなかった。これを試みようとミーシャーは決心し、研究材料に、捨てられた外科の包帯から集めた膿の細胞を選ぶという、一見異様な選択をした。確かに膿は、消毒が行われる以前の病院では十分豊富であったが、それでも、彼が言うには、「疵物きずものなしとはいかなかった」。彼は、臭気があまりすごい包帯は取り除く配慮をした。
細胞が懸濁液として得られ、さらに、稀塩酸、ペプシンおよびエーテルであると彼は知った。核はフラスコの底に沈んで、顕微鏡下にはこの沈渣が、「平滑な外囲と均質な内容物に、それぞれはっきりした輪郭をそなえた核小体を持ち、最初の大きさよりやや小さ目なながら完全に純粋な核」であることを観察した(Miescher,1871)。その当時数人の研究者が、似たりよったりの方法でいろいろな組織から核を単離していたが(Brunton,1870;Auerbach,1874)、そういった操作はその後も無視され続け、ようやく1930年代になって、細胞分画法の名称(Claude,1937)で復活した。
ミーシャーは膿細胞の核から注目すべき性質をそなえた物質を調整し、それに「ヌクレイン」nuclein の名称を与えた。それは既知のどんな生体物質よりも強い酸であり、さらに、当時は生物学関連の有機物中ではきわめて希少だとされた元素である燐が高い組成で含まれることで識別された。この研究段階で、ミーシャーが得た結果は当時としてあまりにも驚くべきものであったため、ホッペ-ザイラーはそれらの結論を自身で確認するまで公表を渋り、そのため、ミーシャーの論文が世に出たのは、2年も遅れて1871年であった。
しかし同じ年に、彼はバーゼルに帰郷して、ライン河の冬サケの成熟した精巣もまた、いっそう魅力的なヌクレインの材料に相違ないことを発見した。単利した精子の頭部中に、彼は酸性のヌクレイン、すなわち核酸ばかりでなく、それといっしょに複合体を作っていた塩基性の強い窒素化合物を発見したので、それに彼は「プロタミン」protaminという名称を与えた。この材料からのヌクレイン調整は、精子の頭部を強酸で溶解し、それを水で希釈して、ヌクレインでできた線維を沈殿させるというものであった。これらの調整試料をできるだけ冷却しておく必要があったため、彼は、冬に暖房なしの部屋で働いたのであった。彼は友人の一人に以下のように実験方法について述べている。
核酸を調整しようという時、私は朝5時に研究室に行く……どの溶液も5分以上は放置せず、どの沈殿も1時間以上は無水アルコール中にとどめることができない。しばしばそれが夜遅くまで続いた。唯一この方法だけで、私は一定の燐の組成を持つ産物をついに手に入れたのだ。(Greenstein,1943)
ミーシャーは、ヌクレインの特徴として、ペプシン消化に抵抗性があり、かつアルカリに可溶なことを発見した。高濃度の塩溶液で処理すると、膨潤してゲル化した。1881年にはザカリアスが顕微鏡下で、さまざまな種類の細胞や核に対してこれらの試験を適用した。彼は、ペプシンがカエル赤血球の細胞質を消化し去って、単離した核を残すことを見出した。同じ結果が Vorticella やゾウリムシ Paramoecium などの繊毛虫類で見られたが、その際に、大核は実験後も溶解しないまま残った。これらの小核はアルカリに可溶であった。彼が植物組織について興味深い観察をしたものがあったのだが、それは、分裂中の花母粉細胞の染色体はペプシンに抵抗性を持つが、紡錘糸は消化されたのである。フレミングは翌年、このザカリアスの仕事を念頭に置いて、彼の著書『細胞質、核および細胞分裂』の中で、核の「枠組み」を形成している物質である「染色質」chromatin を定義したのであった。
……その光学的屈折性、それが示す反応、そして何といっても色素に対する親和性から見て、私が染色質と名付けた物質である。たぶん染色質はヌクレインそのものであろうが、もしそうでなかったとしても、ザカリアスの業績から見て、相互に相通じるものである。染色質という言葉は、それの化学的な性質が知られるようになるまでは役に立つことだろうし、それまでの間は、細胞核内の易染性物質を指すのである。
現在、「核酸」nucleic acid という語は物質の1グループを指すことがわかっている。この物質は2種類に分けられ、両方とも核の中に見出される。そのうちの1つは、核の外には存在しない。さらに、生きている状態では核酸が通常結合しているのが、広義でいうところの塩基性タンパク質に属するものであるが、それらの中でも、成熟した魚の精子が持つプロタミンは、極端な事例である。
核酸の化学的研究の進歩は、アルトマン(1852-1900)がたんぱく質を含まない試料調整法を発見してから、加速されることになった。それは1889年に発表された。それから3年以内には、核酸の3成分が識別された。燐酸に加えて、プリンとピリミジンという2つのタイプの有機塩基、および第3には、五炭糖の炭水化物があった。核酸が調整されたおもな材料は、酵母と動物の胸腺であった。これら2つの材料から単離された産物に、ある相違がみられ、それから動物と植物の核酸の間にある基本的な相違であろうという早まった一般化が持ち上がった。しかし、1914年には、この2元論は誤っていることが示されたのである。生化学者のR.フォイルゲン(1914)によって、胸腺タイプの核酸が持つ不安定な炭水化物は、その頃まで考えられていたような六炭糖ではなくて、五炭糖であって、緩和な加水分解でアルデヒドを遊離し、それがこの類の物質検出に用いる通常の試薬である亜硫酸で脱色したフクシン色素によって兼sy通されることが示されたのである。10年後に、この試験が顕微鏡下で組織切片に適用された。そのときフォイルゲンと彼の共同研究者のH.ロッセンベック(2924)は、麦芽の核がこの試験に強く反応するのを発見して非常に驚いた。その結果は、胸腺タイプの核酸が植物の細胞に見出されたことを示していたからである。
現在では、核酸のタイプの区別が動物と植物の細胞内におけるそれらの分布状態と関係していることがわかっている。胸腺タイプの核酸は核の中でのみ見出され、その淡水化物成分はデオキシリボースで、デオキシリボ核酸、つづめてDNAとしても知られる。もう一方のタイプの核酸も、動物と植物ともに細胞質と核の双方に見出され、核では核小体の主成分である。ここでもリボ核酸、RNAの名称は、その炭水化物であるδ-リボースに由来する。さらに、それら2つのタイプの核酸は、同じプリン塩基[アデニンとグアニン]を持つが、ピリミジン塩基ののうちの1つが相違する[DNADEシトシントチミン、RNAでシトシンとウラシル]。
組織化学的方法として応用した場合の
〜P143
1.27 17:21:30 下書き保存分
2018年2月7日 9時46分
ステロイドホルモンは
細胞の性質を大きく変えるという面でくわしく研究されている
ステロイドは膜のなかに多く見いだされるものだが、ステロイドホルモンは膜を通過して細胞内に進入し、染色体DNAの特定部分に結合しているステロイドホルモンレセプターに相互作用してその性質を変える。レセプターは転写制御因子であり、これによって一群の遺伝子のRNA合成が活性化される。
エクジソンとよばれる昆虫の変態ホルモンはステロイドホルモンの一種であり、幼虫からさなぎに変わる過程での元締め的なマスタースイッチの役割をはたしている。このホルモンが昆虫のリンパ中に出され、各細胞のなかに入ると染色体の特定部分で転写が開始され、さなぎになるまでたくさんの遺伝子があらたに活性化される。昆虫の唾液腺細胞にある巨大染色体を用いて観察すると、パフとよばれる染色体が開いたような発現部位が多数視覚化され、遺伝子の継続的な発現がみごとにしめされる。
発生とか形態形成の観点で見ると、細胞の空間的な位置も遺伝子発現に大きく影響する。多細胞体制をつくるプログラムはDNAに書かれており、形態の形成に必要ないろいろな遺伝子が発見されている。これらの遺伝子の変異体は形態の異常をもたらす。本来発現されるべきタイミングと位置でこれらの遺伝子の転写がおこらないと、形態の異常がおこる。
P104『細胞から生命が見える』岩波新書387/2012年 第7刷(1995年第1刷)/柳田充光
・・・・・・・・・・
「染色体」 細胞観察の歴史
織物業が発展した19世紀 染料が多く開発された
当時の布 「生物がつくる繊維」からなっている = 細胞の集まり
染色体は遺伝子を格納している
細胞学者たちは,ある染料で染めた細胞を顕微鏡でくわしく観察すると,細胞の中ににある「核」だけが強く染色されていることに気がついた。ドイツの解剖学者ウォルター・フレミング(1843〜1905)は,染色されているのは核にある糸状の物質であることを発見し,「染色質」と名づけた。
さらに細胞学者たちは,染色質が別の姿に変化するようすを観察した。二つに分裂しようとしている細胞では,染色質からなる核が,何本もの棒状の物体へと変化していたのである。この,染色質が凝縮してつくる棒状の構造が「染色体」とよばれるものだ。ヒトの場合,1個の細胞に含まれる染色体の数は46本である。
さて,染色体の成分である染色質は,どのような物質でできているのだろうか? それが明らかになったのは,20世紀になってからのことである。染色質をつくっているのは,DNA(デオキシリボ核酸)と,それを巻きつけるしんの役目を果たす「ヒストン」というタンパク質だった。DNAとは,長いはしごのような分子で,はしごの段にあたる部分(塩基)の一つ一つが,いわば文字の役目を果たしている。
この文字によってあらわされる情報こそ,生命の設計図である「遺伝子」だ。おどろくべきことに,46本の染色体に含まれるDNAの全長はなんと約2メートルにもなり,そこには約60億文字の情報が含まれているのである。
P30/Newton/2006.2
…紆余曲折の末に確定した「人の染色体は46本」… P32-33
「X染色体」という呼び名は
…「正体のわからぬもの(X)」もしくは「eXtra(余分な)」からきているといわれており… P53
・・・・・・・・・・
X染色体
ヘルマン・ヘンキングによって1891年に発見された
ヘンキングは、この染色体の特殊性について充分には気づかず「X染色体」と名付けて発表した。その後、1900年代に染色体研究が進展し、X染色体が性決定に関与する染色体であることが判明した。
X染色体という名称はヘンキングの命名によるものであり「正体不明」の意味と伝えられる。X染色体・Y染色体がそれぞれアルファベットのX・Yのような形をしているからそう呼ばれるようになったというのは俗説である。… Wikipedia
細胞核 Wikipediaより
…核内には、糸状に連なったDNA分子が結合蛋白質と複合体を構成しながら散らばっており、クロマチン(chromatin)あるいは染色質と呼ばれる…
Wikipediaより 馬回虫 Parascaris equorum
(Goeze, 1782) Yorke & Maplestone, 1926
…ウマ、ロバ、ラバ、シマウマ、ウシの小腸、時に盲腸、結腸に寄生する回虫の1種
体長は♂15-28cm、♀18-50cm。感染様式は経口感染…
染色体は2本と非常に少なく、ドイツの動物学者テオドール・ボヴェリにより、1887年に初めての染色体削減(染色質削減)という現象が報告された動物でもある。…
染色体説 Wikipedia
…染色体説提唱の背景には、全ての細胞は細胞から生じるとする細胞説と、当時再発見されたばかりのメンデルの法則がある。20世紀初頭、黎明期の遺伝学と、先行して発展していた細胞学の融合から、遺伝の染色体説が誕生した。
メンデルの法則は1865年に報告されたが、長い間歴史に埋もれ、「再発見」されたのは35年後の1900年である(詳しくはメンデルの項目を参照)。遺伝の連続性が保証される背景には細胞説があり、これに基づく古典的な細胞学は、染色・観察技術の発達とともに19世紀末までには発展を遂げていた。またアウグスト・ヴァイスマン(August Weismann)は遺伝因子は生殖細胞にあるとする生殖質説を提唱しており、移植実験などからは細胞核に遺伝物質があることが予測されていた。1842年に発見された染色体に関しても、続く研究でさまざまな生物種における種類や数、細胞分裂において母細胞から二つの娘細胞へと受け継がれる様子などの知見が蓄積しつつあった(ヴァルター・フレミング (Walther Flemming)の項参照)。
このように19世紀末までには染色体説の下地ができていたが、遺伝の染色体説を主張するためには、配偶子形成における染色体の挙動を示す必要があった。なぜなら、遺伝の一過程である受精では、卵子と精子の融合によって染色体数が倍加するため、あらかじめ染色体数を半減することが必要である。しかし、この過程に関する知見がまだ得られていなかった。
減数分裂における染色体の挙動と染色体説の提唱
サットンの貢献
体細胞分裂と減数分裂における染色体の分配: 簡単のため一組の相同染色体のみ示した。通常の細胞では父系と母系由来の染色体を一組ずつ持つ(左上)。分裂に先立って染色体の倍加が起こる(左中)。体細胞分裂では2倍になった染色体がそれぞれ娘細胞に受け継がれる(右上)。減数分裂では相同染色体が対になる(左下)。第1分裂で倍加したまま分配され(下中央)、続く第2分裂でさらに分離する(右下)。最終的に形成される配偶子では染色体数が半減する。
遺伝の染色体説を明確に提唱したのはウォルター・サットン(Walter Sutton)の1902年の論文が最初である。彼はバッタの一種 Brachystola magna を用いて減数分裂の細胞学的な研究を行い、配偶子形成における染色体の挙動がメンデルの法則に従うことを見いだした。メンデルの法則が再発見されて間もない頃である。
サットンはこの昆虫では染色体が大きくはっきりと観察できる利点を利用し、配偶子形成における染色体の観察を行った。1902年の論文『 Brachystola magna における染色体群の形態について』において、配偶子形成時の細胞分裂では相同な染色体(相同染色体)どうしが対を作っており、これらが配偶子に一つずつ分配され、染色体数の半減、すなわち減数分裂が起こることを示した(右図、および減数分裂の項目参照)(Sutton, 1902) 。配偶子形成における染色体の減数と分配が明らかになったことで、それまで推測の域を出なかった染色体説に対して最初の明示的な証拠が提出された。この論文の最後の段落でサットンは「この現象がメンデルの法則に従っており、これが遺伝の物理的基盤である可能性を示唆し、この主題について場を改めてすぐに紹介したい」と述べている。そして翌年の論文『遺伝における染色体』では、この仮説をより発展させ、それぞれの染色分体がランダムに分配されることから、メンデルの法則を説明した (Sutton, 1903) 。
配偶子がもつ染色体の組み合わせは、体細胞の相同染色体対の累乗であり、次世代における染色体の組み合わせはさらに累乗する。つまり2組の相同染色体をもつ場合、配偶子は 22=4、次世代は 42=16 通り生じる。これはメンデルが交配実験で得た結果と合致する(具体例はメンデルの法則を参照)。さらに、この論文では一つの染色体には多数の遺伝形質が存在することを予言し、またそれらは不分離だろうと述べている(実際には組換えが起こる)。
このようにして、25歳の大学院生だったサットンによって細胞学から遺伝現象へと手が差し伸べられたのである。後に遺伝学的手法により染色体説を実証したモーガンやアルフレッド・スターティヴァント(Alfred Sturtevant)は「サットンの仮説で染色体説は既に完成していた」と著書や講演の中で述べている。…
…
ヴァルター・フレミング
(Walther Flemming, 1843年4月21日 - 1905年8月4日)ドイツの細胞学者
来歴
ドイツのザクセンベルク(Sachsenberg)生まれ。父親カール・フリードリッヒ・フレミング(Carl Friedrich Flemming)は著名な精神科医。ロストック大学で医学を学び、従軍医として働いた後、プラハ大学に職を得る。1876年より、キール大学の解剖学教授。フリーメイソンの内組織「シュライン(英語版)」に所属していた。
業績
フレミングが描いた染色体の動き Zellsubstanz, Kern und Zelltheilung, 1882
細胞の固定法および染色法の開発と改良に貢献。細胞核内にアニリンで強く染まる構造を見いだし、これをクロマチン(chromatin:染色質)と名付ける。さらに細胞分裂時には、クロマチンが糸状の構造体に変換すること、さらにそれが縦裂することを発見。すなわち、現在の言葉に置き換えれば、染色体凝縮と姉妹染色分体分離の過程を初めて正確に記載したことになる。これらの結果は、1882年、「細胞質、核、細胞分裂 (Zell-substanz, Kern und Zelltheilung)」にまとめられ、その後の有糸分裂研究の基礎となる。有糸分裂 (mitosis) も彼の命名による。mitosisとは、ギリシャ語で糸 (thread) の意。ちなみに染色体(chromosome)という語は、1888年ヴァルデヤー(Heinrich Wilhelm Waldeyer)によって初めて用いられた。
フレミングは、メンデル(1822-1884)の業績を知らなかったといわれ、自らの観察と遺伝の関係について明確に言及することはなかった。しかし、1900年メンデルの法則が“再発見”されるに伴い、フレミングの観察の本質が再評価されることになった。 …Wikipedia
木綿 Wikipedia
・・・・・・・・・・
画面デザイン:「世界情勢」→「オレンジストライプ」 (18-1-18)
→ちょうどいいのが無くて「水」に(18-1-21)
2018年1月14日 16時19分
〜5
生物は概日時計により環境変化をさきどりすることで
環境適応を実現しようとしてきた
環境変化に対応する機構を反応的ホメオスタシス
概日時計を利用した機構を予測的ホメオスタシス
とよぶこともある
多くの遺伝子発現はその二つの「制御を受けることが一般的」
前者は不可欠な制御 後者はそうではない
自然環境下では 後者の制御は長い時間ののちには 少なからぬ影響をもつものとされている
この概日時計の効果の自然条件下での定量的解析は一般に困難だが,シアノバクテリア(藍色細菌,ラン藻)の二つの周期変異体を使った生育競争実験により,概日時計の環境適応的機能が示されている.この方法では,同一試験管内で二つの系統が世代を繰り返すので外部環境は厳密に同じであり,個別の生育測定では得られない精度を持っている.さらに,光や栄養塩類を競合することによりわずかな生育の差が増幅される. 3
“シアノバクテリアの系統発生”
太陽の光エネルギーを利用 水を分解 還元力
光合成の開発 (大発生) 酸素に富む環境
原核生物 あらゆる水圏に生息
「生命進化の道」を開いたといわれ
シアノバクテリアは細胞内に植物の葉緑体とよく似たチラコイドをもち 葉緑体の祖先だと考えられている
“概日リズムの発見”
最初にシアノバクテリアで見いだされた概日リズムは 窒素固定
窒素固定では大気中の窒素分子を一連の反応でアンモニアに還元するが,この反応を触媒する窒素固定酵素は酸素により不可逆的に破壊されてしまうので,シアノバクテリアは光合成により不可避的に生じる酸素から窒素固定を守る必要がある.このため,糸状性シアノバクテリアはヘテロシストとよばれる光合成機能をもたない窒素固定細胞を分化させ,光合成と窒素固定を空間的に分離している.しかし,単細胞のシアノバクテリアではこの戦略は不可能であり,窒素固定を夜間にのみ行うことで時間的に光合成と窒素固定を分離する方法をとっている.従来,この制御はもっぱら光による直接の制御と考えられていたが,1986年になって,二つのグループが単細胞性シアノバクテリアにおいて窒素固定活性リズムが連続明条件下でも持続することを見いだし,この時間的分業が概日時計によっても制御される反応であることを示した.
Golden SS,Ishiura M,Johnson CH,Kondo T(1997)Cyanobacterial circadian rhythms.Annu.Rev.Plant Physiol.48:327-354
“細胞分裂と概日時計”
概日リズムが細胞分裂中も持続するかどうか
いくつかの真核生物では細胞周期が概日周期より短くなると明確な概日リズムが消失し 細胞分裂は概日時計を中断させてしまうと考えられていたが
シアノバクテリアでは 10時間で分裂する細胞も分裂をほとんど停止した細胞とまったく同じ概日リズムを示す
それは 原核生物では概日時計が細胞周期からまったく独立し てり 娘細胞にも位相(時間)が伝達されることを示す
Kondo T,Strayer CA,Kulkarni RD,Taylor W,Ishiura M,Golden SS(1997)Circadian rhythms in rapidly dividing cyanobacteria.Science 275:224-227
“ルシフェラーゼによる概日時計のモニター”
概日時計の分子機構解明のモデル系としての シアノバクテリア
いくつかの系統は遺伝子組換えがきわめて容易で全ゲノムサイズも大腸菌より小さい
こうした系統のひとつ,Synechococcus elongatus PCC7942(以下では,単にシアノバクテリアとよぶ)で,概日時計に制御されているプロモーターにルシフェラーゼ遺伝子を接続しこれを「人工の時計の針」として機能させることで,ほかのモデル生物では得られない高精度で能率のよい解析が可能となった.発光リズムは2週間以上持続し,暗パルスによる位相変位や,25〜36℃の条件下での周期の温度補償性も備えている. 4
Kondo T,Strayer CA,Kulkarni RD,Taylor W,Ishiura M,Golden SS,Johnson CH(1993)Circadian rhythms in prokaryotes:luciferase as a report of circadian gene expression in cyanobacteria.Proc.Natl Acad.Sci.USA 90:5672-5676
“kai遺伝子群のクローニング”
「発光」シアノバクテリアでは寒天培地上の1万個以上のコロニーの概日時計の同時測定が可能
これを利用し,変異源エチルメタンスルホン酸で処理したシアノバクテリアから,14時間から60時間におよぶさまざまな周期変異型,無周期型,低振幅型など,あらゆるタイプの時計異常を含んだ100種以上の変異体が分離された.
Kondo T,Tsinoremas NF,Golden SS,Johnson CH,Kutsuna S,Ishiura M(1994)Circadian clock mutants of cyanobacteria.Science 266:1233-1236
次に,野生型ゲノムライブラリーによる遺伝的相補を利用してこれらの変異の原因遺伝子がクローニングされ,三つの連続した遺伝子,kaiA,kaiB,および kaiC が同定された.kai遺伝子群のコードするアミノ酸配列には既知のタンパク質と相同性は見いだされなかったが,顕著なリズム異常を示す50個以上の変異が kai遺伝子群内に確認された.
また,kai遺伝子群全体,あるいは,いずれの遺伝子を破壊してもリズムは完全に消失し,遺伝子破壊体に kai遺伝子群を再導入すれば完全なリズムが回復することも確認されたので,kai遺伝子群のコードするタンパク質がシアノバクテリアの概日時計機構における中心的な分子であることは明らかである. 5
※7 Ishiura M,Kutsuna S,Aoki S,Iwasaki H,Andersson CR,Tanabe A,Golden SS,Johnson CH,Kondo T(1998)Expression of a gene cluster kaiABC as a circadian feedback process in cyanobacteria.Science 281:1519-1523
“kai遺伝子群の発現制御に基づく振動発生”
kaiA遺伝子,kaiB遺伝子,kaiC遺伝子のそれぞれを大腸菌の誘導性プロモーターを使い過剰発現させると いずれもリズムは消失するため それらの遺伝子の発現抑制が振動発生に重要であることが示唆された
ルシフェラーゼ遺伝子を利用した実験から,kai遺伝子群はkaiA遺伝子とkaiBC遺伝子の二つに分かれて転写されており,二つのプロモーター活性,PkaiAとPkaiBCは,周期や位相は同じだが波形の異なった概日リズムを示すことが明らかになった.さらに,PkaiBCの活性はkaiC遺伝子の過剰発現で完全に抑制され,kaiC遺伝子の発現がその産物 KaiC により強い負のフィードバックを受けており、この制御がシアノバクテリアの概日振動を発生させていると考えられた.逆に,kai遺伝子の過剰発現はPkaiBCの活性を増加させ,kaiA遺伝子の不活性化はPkaiBCの活性を低下させてしまう.すなわち,KaiA はPkaiBCの促進因子である.kaiA遺伝子の発現はゼロになることはないので,kaiBC遺伝子の転写はつねに活性化され KaiC レベルが上昇する.この KaiC はなんらかの操作によりkaiBC遺伝子の転写を抑制し,kaiBC遺伝子の転写が低下すれば KaiC のレベルも低下する.すると,転写抑制が弱まり,kaiBC遺伝子の転写は KaiA によって再び上昇に転ずるだろう.このモデルに従えば, KaiC 量もしくはkaiBC遺伝子転写活性が振動の進行を直接に規定しており,もしこれらを外部から一時的に撹乱すれば,処理を行った時間により異なった位相変位が予測される.
事実 kaiC遺伝子の発現を一時的に上昇させると処理位相に応じた位相変位が誘導され そのことは モデルを支持している 5、6
※7
…シアノバクテリアの概日時計は kai遺伝子群発現の自己制御が基本…
真核生物においても原核生物においても,「時計」という生命には奇異にみえた現象が生命活動の基本原理,すなわち,遺伝子の発現制御で実現されており,さらに,時間を刻む遺伝子が生物群ごとに進化の過程で選ばれていることは興味深いことである.
自己制御ループの理解のためにはさらに未知の分子の同定が不可欠
振動発生機構の構成要素を同定しただけでは不十分だろう
もうひとつの大きな課題は,振動の周期が焼く24時間と長く,しかも温度補償され,さまざまな代謝条件の変動を受けにくい,といった概日振動の特質(概日特性)がどのようなしくみで可能なのかを分子レベルで説明することである.幸い,シアノバクテリアでは「 KaiC の単一アミノ酸変位が大幅に周期の変化をもたらす事実は, KaiC の生化学的機能が周期決定の重要な要因であることを示唆している. 6
“Kai タンパク質群の細胞内動態”
遺伝子発現から予測されるように KaiA KaiB KaiC のタンパク質量は いずれも mRNA のリズムに比べ8時間ほど遅れた位相で振動する
その Kai は出芽酵母内や試験管内でさまざまな組み合わせで相互作用することが確認された
Iwasaki H,Taniguchi Y,Ishiura M, Kondo T(1999)Physical interactions among circadian clock proteins.KaiA,KaiB,KaiC,in cyanobacteria.EMBO J.18:1137-1145
さらに,細胞抽出液で抗KaiC抗体による免疫沈降反応を行うと,KaiA,KaiB,SasA(後述)ともに,KaiC と夜間に強く相互作用していることが明らかになった.また,ゲルろ過法により,Kaiタンパク質群とSasAは夜間に分子量400,000〜600,000の大きな高次複合体を形成し,昼間に分離することが示された.さらに,遺伝子欠失変異体の解析から,KaiCがこの複合体の中心的な分子になっていることや,KaiA と KaiB が共役して KaiC を含む複合体と相互作用することなど,この複合体の動態が明らかになった. 6
Kageyama H,Kondo T,Iwasaki H(2003)Circadian formation of clock protein complexes by KaiA,KaiB,KaiC,and SasA in cyanobacteria.J.Biol.Chem.278:2388-2395
“KaiA による KaiC のリン酸化”
ウェスタンブロット解析では KaiCは二つのバンドになるがホスファターゼ処理により高分子量のバンドが消失するため
KaiC は細胞内でリン酸化されていることがわかる
このリン酸化レベルは概日振動を示し,いくつかのリズム変異体ではこのリン酸化が異常となるので,概日振動の過程に KaiC のリン酸化が重要なステップであることが示唆された.
一方,KaiC 上に KaiA と結合する二つの領域が特定されたが,この領域には多くの時計変異がマップされ,結合の強さが変異により変化する.また,kaiA遺伝子のリズム変異の抑制変異が kaiC遺伝子のこの領域に見いだされている.これらのデータは,KaiA と KaiC のあいだの相互作用が概日振動の性質に大きな影響をもつことを示している.さらに,KaiA によるkai遺伝子群の発現促進に KaiC が必要であることも示され,この二つのタンパク質が協同してKaiBC遺伝子の発現を促進しており,振動持続のための正のフィードバックをも担っていることが示された.最近,細胞内においても試験管内でも,KaiC のリン酸化が KaiA により大きく促進されることが示され, KaiA と KaiC の協同作用が KaiC のリン酸化により制御されると考えられている. 7
Iwasaki H,Nishiwaki T,Kitayama Y,Nakajima M,Kondo T(2002)KaiA-stimulated KaiC phosphorylation in circadian timing loops in cyanobacteria.Proc.Natl.Acad.Sci.USA 99:15788-15793
“KaiB の機能”
KaiA は KaiC のリン酸化を促進するが KaiB は逆に抑制する
また KaiB の細胞内分布を解析すると 主観的昼には膜画分に多く 主観的夜の後半に KaiA KaiC に遅れて細胞質画分蓄積する
これらの結果から,シアノバクテリアでは Kaiタンパク質群の局在が KaiC のリン酸化を調節することでその活性を制御し,概日振動が生まれるというシナリオが考えられる.すなわち,朝の早い時間には KaiC のレベルは低いが,昼になるにつれて KaiC が細胞質に蓄積してくる.この KaiC の蓄積とともに KaiC のリン酸化レベルも上昇する.主観的夜になると安定した KaiA-KaiC複合体が形成され,KaiC のリン酸化は KaiA によってさらに増加し,夜の半ば(CT16)に最大となる(CT:概日時刻,恒常条件において,主観的昼の始まりをCT0およびCT24とする時刻主観的1日を24で割って表しているので,CT1単位は60分とはならない).KaiB は夜の遅い時間(CT20)になると細胞膜から細胞質へ移動し,KaiC と複合体を形成できるようになる.KaiB は KaiA-KaiC 複合体に結合して KaiC のリン酸化と Kaiタンパク質複合体の形成がKaiBC遺伝子の発現を制御し,概日振動を発生させていると考えられる. 8
Kitayama Y,Iwasaki H,Nisiwaki T,Kondo T(2003)KaiB functions as an attenuator of KaiC phosphorylation in the cyanobacterial circadian clock system.EMBO J.9:2127-2134
“Kai タンパク質群の生化学的機能”
KaiCの配列は重複構造をとっていて おのおのの対応する位置にATP/GTP 結合モチーフ(Walker's P-loop)が見いだされており
そのモチーフによってATPと結合することも確認されている
また ATP/GTP 結合モチーフへ変異を導入するとATP結合能も概日リズムも消失する
さらに 試験管内で KaiC がそのセリン/スレオニン残基を自己リン酸化することも見いだされている
Nishiwaki T,Iwasaki H, Ishiura M,Kondo T(2000)Nucleotide binding and autophosphorylation of the clock protein KaiC as a circadian timing process of cyanobacteria.Proc.Natl.Acad.Sci.USA 97:495-499
しかし その活性が細胞内での KaiC およびその複合体の活性としてどのような意味をもつかについて リン酸化部位の決定とその制御機構についてさらに解析が必要
一方 Kai タンパク質群の構造についての解析も進み
示唆に富む情報も得られている
まず,既知のタンパク質との配列比較から KaiC の構造が RecA やヘリカーゼと類似していることが報告されている
Leipe DD,Aravind L,Grishin NV,Koonin EV(2000)The bacterial replicative helicase DnaB evolved from a RecA duplication.Genome Res.10:5-16
その類似性は KaiC と DNA の相関を期待させる
Kaiタンパク質群の立体構造についても研究が進展している
Mori T,Saveliev SV,Xu Y,Stafford WF,Cox MM,Inman RB,Johnson CH (2002)Circadian clock protein KaiC forms ATP-dependent hexameric rings and binds DNA.Proc.Natl Acad.Sci.USA 99:17203-17208
Ditty JL,Williams SB,Golden SS(2003)A cyanobacterial circadian timing mechanism. Annu.Rev.Genet.37:513-543
KaiA については NMR およびX線回折により「構造が決定され,KaiC については電子顕微鏡による観察により ATP存在下で六つの単量体が環状に配列した六量体を形成することが明らかとなっている.
それらの時計タンパク質は多様な複合体として機能していると予測され 構造解析からその機能の説明に至るためには
個々のタンパク質の構造情報のみでなく 時間とともに変動するさまざまな複合体の解析が不可欠 8
『時計遺伝子の分子生物学』2004
同書P5の図「kai遺伝子群発現のフィードバック制御により機能する概日時計」と
repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/110062/1/KJ00004706348.pdf
のP169 図1「kai遺伝子の発現制御による概日時計」は(特に図に関しては)ほぼ同じかと思われる(書中からの引用部分 pdf. いずれも 近藤孝男氏によるもの)
10年以上経っていますが そちらから ちょこちょこ足していきます
//////////////////////////////////////////////////////
ルシフェラーゼ (luciferase) Wikipediaに聞いてみる
発光バクテリアやホタルなどの生物発光において、発光物質が光を放つ化学反応を触媒する作用を持つ酵素の総称である。 発光酵素 とも呼ばれる。
ウェスタンブロッティング (Western blotting; WB)
電気泳動によって分離したタンパク質を膜に転写し 任意のタンパク質に対する抗体でそのタンパク質の存在を検出する手法
別名ウェスタンブロット法(Western blot analysis)
サザンブロッティング(南)、ノーザンブロッティング(北)の流れから、半ばジョークで命名されている(ちなみに様々な手法に「イースタン」と名付けられているが、確立したものはない)。前二者は核酸どうしの相補性を利用しているが、本法は抗体の特異性によって目的のタンパク質分子を区別している。よってイムノブロット (immunoblot; IB) とも呼ばれる。生命科学の研究者の間では、単に「ウェスタン」といえばこれを指す。 Wikipedia
ホスファターゼ ? kotobankに聞いてみた (phosphatase)
…有機燐酸エステル・ポリ燐酸を加水分解する酵素の総称。フォスファターゼ。脱リン酸化酵素。…
…酸性に至適pHをもつものとアルカリ性にもつものが区別される場合が多い.リン酸エステル化されたタンパク質の脱リン酸を触媒する酵素はタンパク質ホスファターゼ.… とか とか kotobank
2017年3月4日 11時27分
シーボルトが長崎を去ったとき日本はまだ鎖国中だった
1859年 ペリー来航から6年後の日本に シーボルトはオランダ貿易会社の顧問として来日 68
江戸参府の機会に集めたもの 診療のお礼として受けとったもの…最初の日本滞在中に集めた大量の標本 書物 工芸品
ヨーロッパで それらをもとに日本の自然誌と文化について三部作の文書にまとめた
(一冊に 豊富な図入りの『日本植物誌』)
キュー図書館に所蔵されている『日本植物誌』は、もともとウィリアム・ジャクソン・フッカーが入手したもので、フッカーの死後は彼の書斎にあった残りの書物といっしょに国に買い上げられた。『日本植物誌』にも植物画が豊富に入っていたが、フッカーが集めた本にはエレットやバウアー兄弟その他が描いたすばらしい植物画が添えられていた。そうした書物を中心に、やがて世界最大級の植物画コレクションが築かれる。一方、キューの実用植物学コレクションの中にも興味深い植物画が存在する。とりわけ貴重なのは26点セットの木製図版で、それぞれに彩色した植物のイラストが載っている。これらの図版も『日本植物誌』と同様、シーボルト関連のものだ。
図版の一点一点は 縦1フィート〔23?〕ほど
木の枝を材料にしてつくられた額に収まっていて
額と 描かれている板は どうやら「描かれている植物」が材料になっているようで
その一つに 漢字とカタカナの下に アルファベットで
「Ginkgo biloba,Linn.」と書かれたラベルがついたものがある
この不思議な木製図版がいつどこで制作されたものか、どのようにしてロンドンに来たのか、キューの記録にはない。だが、似たような木製図版コレクションが東京の小石川植物園、ベルリン=ダーレム植物園、ハーヴァード大学植物標本室、イギリスの個人収蔵品の中に存在しており、そこからヒントが得られる。そうした木板図版の多くは裏面に、小石川植物園(現、東京大学付属植物園)に雇われた初の植物画工である加藤竹斎の、同一の朱色の篆刻印が押されている。印には「春の新作」の文字と、明治11年(1878年)の年号が入っている。
キューとベルリンにはイチョウを描いた木製図版がある。ベルリンのものには「通称、祖父と孫の木、もう少し正式には銀杏」という文章が漢字で記されている。葉と若い珠柄がついたイチョウの枝を描いたキューとベルリンの図版の絵柄は互いによく似ており、また加藤竹斎が1881年に小石川植物園のために制作したイチョウの絵にも似ている。これら三点の絵に描かれている小枝の一部と短枝はほぼ同一で、珠柄についた種子の描かれ方はまったく同じだ。キューの絵にはベルリンの絵に欠けている二、三の細かい部分が見られるが、加藤が描いた小石川の絵にはすべてがそろっている。
加藤竹斎が師事していた東京大学付属植物園の開設当時の教授、伊藤圭介は、1826年に若き日のシーボルトと会っている。加藤は、シーボルトが長崎にいたころシーボルトのために挿絵を描いていた絵師の川原慶賀の影響も受けていたようだ。その結果、これら三点のイチョウの絵は日本とヨーロッパの伝統が融合した様式となり、日本が西洋文化を貪欲にとり入れようとしていた時代を映し出すものとなった。枝の描き方はいかにも日本的だが、空いたスペースに植物学的に興味深い部分の図を差しこむという画法は、シーボルトがもちこんだ西洋の伝統的な学術挿画の様式だ。 70
キューとベルリンの木製図版の板に使われたイチョウの木材は、たいていの樹木と同じ基本構造をしている。イチョウの木を切り落とすと、その幹の見た目はふつうの木となんら変わらない。イチョウの木材を、マツやスギの木材と見分けられるのは専門家だけだ。外側を囲んでいるのは樹皮で、そのすぐ内側にもう少し軟らかい組織の層がある。残りの幹は木部である。
木部は、水と栄養が運ばれている外層部分は明るい色をしているが、水の輸送を担っていない幹の中央にある心材は濃い色をしている。心材の細胞はさまざまな長年の堆積物で塞がっていることが多い。それでも心材は、樹木になくてはならない存在だ。密度と強度のある心材が幹の中央を貫いているおかげで、樹木は支えられている。
イチョウの成木を構成している組織のほとんどは、幹も大枝も小枝も同じ方式でできている。樹皮を除くすべての組織は、もとをたどると細胞一個分の厚さしかない生きた細胞の円柱に行きつく。専門用語で形成層と呼ばれるこの円柱は、たいていの樹木で樹皮の内側の軟らかい組織の層と木部のあいだにある。樹木が成長するとき、この形成層にある細長い細胞は、幹の円形断面に接するところで休むことなく分裂する。細胞分裂により、形成層の外側と内側に新しい細胞ができる。
形成層の内側にできる新しい細胞は、完全にできあがった時点で死ぬ。そして木部の一部となって幹の質量を増やすのに貢献する。この死んだ細胞は木部細胞という。木部細胞が死んだあとに残る細胞壁は、根から葉まで水を輸送する管になる。一方、円柱の外側に分裂してできる細長い細胞は生き続け、水を根から各所に届ける働きをするのに対し、師部細胞は葉で生産した糖を茎や根に運ぶ働きをする。
同じく活発に分裂している層からつくられる組織がもう一つある。ただし、幹の垂直方向ではなく水平方向に走っていて、縦に並んだ死細胞のあいだを縫うようにあちこちに散在している。こちらは放射組織と呼ばれている。細胞壁が薄く、細長い形をした細胞でできた組織だ。木の大部分を構成している死細胞とは違って、放射組織の細胞は生きている。樹液を水平方向に運ぶ働きをしており、冬期にでんぷんを貯蔵することもある。
幹の中の形成層の円柱が外側と内側に細胞分裂することで、水輸送細胞は環状に縦に連なる。環状の縦列はそれぞれ、形成層がくり返す細胞分裂の名残だ。しかし、ところどころに一つの縦列が二つに分かれたように見えるところがある。これは、形成層の細胞がときどき放射状に分裂していることを示している。木の幹が太くなるのはこのためだ。形成層の細胞がときどき放射状に分裂するおかげで、形成層の円柱は直径を広げ、その内側にある木部の質量を増大させることができる。形成層の円柱の直径が増えると幹の円周も増大する。それは結果として、樹皮の亀裂となって表れる。
樹皮は、形成層の円柱のうちもう一つの、あまり明確に境界が定まっていないコルク形成層がつくり出す。コルク形成層の細胞が生む樹皮の質と肌理(きめ)は樹木の種類によりまちまちだ。ブナの樹皮のようにつるつるしたものはコルクがほとんど含まれておらず、幹の周囲に均等に育つ。コナラの樹皮のように深い刻み目の入ったごつごつしたものは、コルク形成層があちこちで盛んに細胞分裂した結果だ。イチョウの樹皮は風合いとしてはその仲間にあたるが、近づいてよく見ると、コルク形成層が毎年の成長に合わせて周期的な層をつくっているのがわかる。
イチョウの木部になっている個々の細胞は
直径が数十万分の一インチに満たないのに
長さが半インチ〔1.3?〕になるものもある 76
〔注〕より
・ウィリアム・ジャクソン・フッカーの死後、彼の4000点の書籍コレクションは、1866年にイギリス政府が1000ポンドで買い上げた。さらに1000ポンドで、フッカーの手紙や草稿、肖像写真その他を買い上げた。キューの植物コレクションは20万点を超し、18世紀、19世紀、20世紀、21世紀のすばらしい作品が含まれている。それらの絵の大半はキュー図書館の別館に保存されており、一部は Shirley Sherwood Gallery of Botanical Art および Marianne North Gallery に展示されている。
・ベルリンのコレクションは、1911年にドイツ海軍上級軍医の Paul Kuegler が買い集めたもの。おそらく19世紀末に日本の作品も買い集めたと思われる(Lack,1999).小石川植物園は同じ様式の図版シリーズ25点を保有している。ロンドンにも数点、個人コレクションの中に存在している。小石川植物園は1684年、小石川薬草園として徳川将軍により設立され、明治維新後は日本の近代植物学研究の発祥地となった。そこには精子が発見されたことで世界で最も有名なイチョウの木がある。
・加藤竹斎は、伊藤圭介(1802-1901)と賀来飛霞(1786-1862)の編集による『小石川植物園草本図説』のために、イチョウの図を用意していた。以下参照、Ito and Kaku(1881-1883).賀来の兄はシーボルトの下で学んでいた。伊藤圭介はシーボルトに、イチョウを含む乾燥植物標本のコレクション 14点を与えた。シーボルトはそれらをヨーロッパにもち帰った。
・製材するとき放射組織をどう切断するかにより、高級材の「木目」が決まる。イチョウの場合、くっきりとした木目が出るほど放射組織は厚くない。イチョウ材の放射組織細胞についての詳細は、Barghoorn(1940,321).
・コルクガシの樹皮に含まれるコルク質にはスベリンが含まれており、曲げやすく耐水性にすぐれている。
・通水用の死細胞(仮道管)は、幅が2000分の1インチから3000分の1インチ、長さは幹では10分の1インチから30分の1インチ、根では40分の1インチになる。多くの被子植物の木部にある特別な水輸送細胞(道管の構成要素)の長さはけた違いで、14インチ〔36?〕にまで達することもある(Sperry et al.2006;Wilson and Knoll,2010).イチョウの水輸送細胞についている小さな弁は、水抵抗を最小眼にしながら塞栓形成を防いで、水の輸送効率を高めている。以下参照、Hacke et al.(2004)and Pittermann et al.(2005).
『イチョウ 奇跡の2億年史』2014
ピーター・クレイン/矢野真千子 訳
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
pdf ニュースレター - 小石川植物園後援会
イチョウ精子発見者平瀬作五郎:その業績と周辺
pdf 2006年11月号 - 東京大学 大学院理学系研究科・理学部
pdf 2011年4月18日(月) - 小石川植物園を守る会
2017年2月5日 18時0分
『イチョウ』より
イチョウの根
・土壌中の水分や養分の吸収
・いくらかの有機栄.養物質の貯蔵
・樹体を支持する作用
さらに 根蘗をよく出して 繁殖と更新の作用も始められる
イチョウ 根系
【垂直分布】
50〜100年生のイチョウ大樹の場合 根系深度は1.5m前後に達するが
根系の多くは20〜70?の土層中に見られ
その層中の根量は総根量の約76.4%を占める
適した土壌条件であれば根系の深度が5m前後にも達することがある
細根は20〜70?の土層に多く 総細根量の約81.8%を占める
【水平分布】
イチョウの水平側根は主根に比べて長く 一般に樹冠幅半径の1.8〜2.5倍
たとえば 50〜100年生のイチョウの場合 樹幹から5〜8mの範囲内の根重は総根重の62.5%を占め 細根は樹幹から4メートル離れると次第に多くなるが 9m離れると減る傾向にあり 5〜8mの範囲内の重量は細根総重量の77.3%を占めると言われる
50年生の実生樹は接ぎ木樹に比べて総根重が37.1% 総根重が36.4%少なかった という調査例がある
イチョウ根系の水平分布は広く 栄養吸収力を高めるほか 特に風などへの抵抗力を増加して樹体の保全に大きい力を発揮する
【年成長の動態】
イチョウの年間の根系成長では 二つの時期で高いカーブがあり
分布地域で異なるが 一般に根系は3月上〜中旬に芽生えが始まり12月上旬には成長が停止…期間は約250日
1回目の高いカーブは5月上旬から7月中旬に現れ 約70日間前後 その時期の根系成長量は比較的大きく 50〜100年生の大樹でその成長量は約80?になる
地上部の成長も同様なカーブを示すが その時期の樹体は養分や水分の要求が最大になる
2回目の高いカーブは10月中旬〜11月下旬に現れ 約40日間前後 根系成長量は小さく 同樹で約18?
その時期は種実が落下し 樹体の成長が緩慢になり 葉の黄変が始まり 葉と樹体の中の養分が還流するため 根系成長に有利となり2回目の高いカーブ期が現れる
イチョウ苗の植栽や接ぎ木用台木としての実生苗の栽培の幼齢木で 主根下部に果肉質根の発生を見ることがある
幹と枝
イチョウは落葉喬木で樹幹がまっすぐ伸び、成長は比較的緩慢で結実開始は遅いが、期間は千年を上回り、寿命の長い果樹である。
幼樹の樹皮は浅く縦に裂けているが、大樹の樹皮は灰褐色で、浅く縦に裂けて粗っぽい。
枝条は長枝と短枝(鱗枝または乳枝とも言う)に分かれる。
長枝の成長は早く、一年で1メートルに達するのもあり、輪生に近く、斜め上へ伸びる。一年目の長枝は浅黄褐色、2年目から灰色に変わり、細い縦裂紋が出てくる。
枝には葉腋ごとに芽があり、節間があり、内にあまり発達しない髄心と皮部を持ち、木質部は硬く横断面の主要部分を占め、樹脂道がすこし見られる。靭皮部は薄く外部は皮膚と表皮の組織から成る。
短枝は乳首状で一般に年成長が0.3センチ程度のごくわずか、頂端に頂芽があってそこから葉が群生する。落葉すると魚鱗状の痕跡が見られる。
髄腔は大きく、中に多くの薄壁細胞の組織があり、外層は薄い木質部と靭皮部から成り、木質部は柔らかい。髄部は空隙が大きく亀裂状で、組織中に紅色の結晶粒がある。短枝中の管細胞は長枝に比べて大きい。
茎幹中には螺状紋管細胞が二次生の木質部の孔紋管細胞で取り囲まれ、この木質部は縁孔を持った円形の管細胞で組成されており、茎の主要部分を占める。
また柾目面では、管細胞壁に散生状で対生か互生する1〜2列の縁孔が見られ、板目面では紋孔が成長期と休眠期に交替して表われる。射線は一個の細胞でほとんど発達しない。年輪は比較的明瞭である。
長・短の枝型を生ずる主な原因は、長枝頂端の分生組織で作られる初生茎組織中の細胞分裂と伸長する持続時間が短いためで、両種の成長方式は可逆的であるとされている。ある実験では、伸長する長枝中に発生する成長素が、腋芽が発育して長枝になるのを抑制し、短枝を形成させると発表している。 59
イチョウが結実年齢になると、その延伸枝と頂側枝の中〜下部の腋芽は二年目に短枝を発生し、5〜10枚の葉を着けるが、冬季落葉後に短枝台に変わり頂部に混合芽を形成し、三年目に頂芽が結実枝を出して、葉腋に開花する。この短枝台は、年々枝を出し、結実した後も続けて形成され、一般に10余年も成長できる。
また、延長枝と頂側枝は頂の数芽が長枝を出すほかに、節ごとの腋芽が短枝を出すことができて、年々結実するが、この腋芽からの短枝は位置的な陽光条件などの違いによって成育に差が見られる。
中国の古樹で、大枝がまれに自然折断し、樹姿が乱れる現象がおこることがあり、外力の作用ではないが、その原因についてはまだ明らかになっていない。
イチョウ大樹の主側枝か大枝の下面に、鍾乳石状の垂下がよく見られ、多くの呼称はあるが、日本では「チチ(垂乳)」と呼び、比較的雄樹に多い。 60
(芽と葉 より)
イチョウの学名 Ginkgo biloba の種名である biloba は、ラテン語の二裂の意であるが、実際には同一樹でも葉の裂け方に差異があり、樹齢や枝の類型などとのかかわりから、異形葉性として葉の系列中における重要な現象と見られている。
葉の上部表皮には気孔がほとんど無く、下側が柵状組織で形成され、細胞内に多くの葉緑粒が含まれ、下部表皮には気孔が多く、海綿状組織の細胞中にも多くの葉緑粒が含まれる。そのため表裏両面とも色合いの深浅の差も少なく、緑色を呈する。ゆえにイチョウ葉には表裏の違いがないという説もある。
葉脈は規則的に、二叉分岐する維管束で、その集合が葉柄となるが、この形態は一つの特徴であり、シダ類植物に多く見られる。 (61)
葉の角質層は病原菌の侵入や物理的損傷を受けると、細胞壁が厚みを増し防止することが知られており、また葉には多種の有機酸などの含有が認められて、それが抑菌・殺虫の作用を起こすと言われ、これがイチョウ長寿の重要な要因になっている。
イチョウ種実が葉上に着生するオハツキイチョウ葉は、正常な葉の三分の二〜五分の三と小さく、奇怪な感を与える。 63
(花と種実 より)
一般に木本植物は種子の発芽から幼年期・成熟期の時間を経て老衰期に入る。当初の発育は栄養成長を主とし、個体形成の時期であるが、生理的条件が整うと生殖成長へ移り、成年期の到来を示す花を着ける。そして開花〜栄養成長〜結実〜芽形成〜休眠の年周期を繰り返すことになる。
花原基の形成は、栄養条件が満たされると、内外の影響要因によって頂端の分生組織が活動して行われ、花になる(花芽分化)。
イチョウは花を備える種子植物
単性花で原則的には雌雄異株(同株も発見されている)
雄花は雄花の短枝の葉腋に新葉とともに群生し
3〜8個の小胞子葉に長さ1.5〜2.0センチの穂状花序の状態で着く
同一の樹・枝でも雄花の成熟に差があり 授粉条件が変わる 63
まれに発現する 雌雄同株
1950年代 中国の李生理が初めてイチョウの雌雄同株を調査観察し 報告 70
それによると、この樹は北京市の寺院遺跡にあり、樹齢500〜600年以上、樹高約18メートルで、主幹下部に雄花が多く、中部以上に雌花を着けて、雌花は種実を結び、よく繁茂しているという。これについてさらに、自然形成か人工接ぎ木によるものか、枝幹の観察では接ぎ木の痕跡は見られなかったと記している。(梁立興『中国当代銀杏大全』1993年)
日本では吉岡金市が1965年に岩手県内で二株の雌雄同株のイチョウ樹を調査し、その結果を詳しく記述している。
それによると、一株は丘陵高地の畑に在って樹齢約1200年、樹高30メートルの古老木で、一本の太枝(直径15センチ、長さ4メートル)の中間部に葡萄様の穂状に雌花が咲いて結実し、他の枝には多くの裂葉と嚢(ふくろ)状の奇形葉が見られたという。別の一株は寺院庭に在り、樹齢約100年、樹高約20メートルの古木で、一本の小枝(直径1センチ、長さ30センチ)にやはり葡萄状に雌花が咲いて結実するという。
もともとこの二株とも雄株であるが、雌枝は枝幹が疎らで陽光が良くあたる樹冠の南・西側に生じ、また比較的湿潤で肥沃な土壌条件にあることから考えると、この二つの状況は植物体の一部分を雌雄性に分ける転化の刺激要因になっているのではないかと、指摘している。(吉岡金市『果樹の接木交雑による新種・新品種育成の理論と実際』第一巻、1967年)
最近の実験によると 植物の性転換は主に鉱物質の栄養・光線・温度・損傷・輻射・化学物質などの刺激が引き起こす とされている 71
雌雄同株の樹で結実するイチョウ種実の種核(ギンナン)は
他に比べ細長く軽く最小で 結実の起源性を示して出土する種核化石に似ている
イチョウ雌雄同株の発現は その種の最も原始的な性状の現れで 異株に分化する以前の過程として今も微かな繰り返しを続けているといえ
その「先祖返り的な遺伝の発現は進化上の原始性を保持し続けている証(あかし」」 72
『イチョウ』2005 今野敏雄
....................
税務署近くの 根が吸盤様のあれは イチョウかどうかはあれですが 「水平」現象関連の何かでしょうか?
イチョウについては ぽつぽつ 向き合いたいかしら
2017年1月24日 21時59分
Symbiotic Planet/1999/Lynn Margulis
共生とは、ドイツの植物学者アントン・ド=バリが1873年に考え出した用語で、異種の生物どうしが一緒に生活することを指す。
ド=バリは「異なる名称をもつ生物が一緒に暮らすこと」と定義 55
共生発生は、ロシアのコンスタンティン・メレシコフスキー(1855〜1921)が提唱した概念だ。
進化を支える基本的な事実である 56
〈取り込みで生じる個体〉 55〜79
共生発生が新核細胞の起源であるという私の説は、四つの過程があることを証明する必要がある。この説は過去に起きたにちがいない段階的な出来事を、とりわけ植物の緑色細胞で的確に描き出す。すべての植物の構造上の単位は細胞である。ゼブリナ、ムラサキツユクサなどの花でとくによく見える細い雄しべも、細胞が並んでできている。細胞壁のある大型の緑色の細胞は植物の登場以前から存在した。植物の祖先である水生の緑藻の段階ですでに完成していたのである。真核生物が合体によって生じたことを理解するには、植物を見るのがよい。植物の細胞は大きくて美しく、構成要素であるオルガネラが完全な状態で観察できるからだ。考え方は簡単で、かつて完全に独立し、離れていた4種類の祖先がきまった順序で合体し、緑藻の細胞になったとみる。四つはすべて細菌であり、それぞれ今日でもそれと推測できるほど違っていた。四種類の細菌の子孫は、合体したタイプとしても自由生活のタイプとしても現存している。四種類はたがいの捕虜となり、植物のなかに植物として閉じ込められているのだと言う人もいる。かつての細菌はそれぞれ、その祖先型についての手がかりを備えている――生命体は化学的にきわめて保守的なので、結合が起こった順序まで推定できる。連続細胞内共生説の「連続」という言葉は、一連の合体に順序があることを指している。
いまでは多くの研究者や学生に、細胞の一部分であるオルガネラが、永続的な共生の結果として生じたという説を受け入れてもらえたと確信している。もちろんこの説の裏づけとなる所見のうち私が出したものはごくわずかで、何百人もの研究者がいまも貢献をつづけている。 56、7
もし共生体が完全に合体すれば すなわち融合して新しい種類の生物ができれば
合体の結果である新しい「個体」は当然 共生発生を通して進化したことになる
共生発生という概念は1世紀も前に提唱されたもの 57
この概念のあらましをできるだけ簡潔に書いてみる。まず、発酵性「古細菌」(サーモアシドフィル)と呼ばれる、硫黄と熱を好むタイプの細菌が、遊走性の細菌と一緒になった。一体化した二つは、動植物や菌類の細胞の祖先細胞の基本となる核を含む細胞質を構成した。この原初の遊走性プロチスト[狭義の原生生物で、多くは単細胞]は嫌気性でありこれと同じ子孫が現存する。この種の生物にとっては酸素が毒物だったので、有機物が豊富な泥や砂のなか、岩の割れ目、水たまりなど、酸素がまったくあるいはほとんどないところに生息していた。動植物や菌類の細胞はいずれも真核細胞であり、水分が豊富で透明なので核が見える(菌類には、キノコ類や酵母が含まれる)。植物や動物、それに一部の菌類やプロトクチスト(原生生物)では、細胞が分裂するたびに、核膜が溶解して核が消え、染色体が見えるようになる。染色体を構成しているのは赤く染まるクロマチン(染色質)で、これがコイルのように巻いて見えやすい構造になる。教科書には、クロマチンが凝縮して目に見えるようになり、各生物種特有の本数の染色体になると説明されている。やがて染色体が見えなくなって、ゆるく巻いたクロマチンとなり、核膜がふたたび出現する。この染色体のダンス(染色体運動)は有糸分裂と呼ばれる独特の細胞分裂を構成する。プロトクチストや菌類の段階でさまざまな分裂を試みた後に真核生物になって確立したのが、有糸分裂だ。まず、有糸分裂をするようになった遊走性のプロチストに別のタイプの自由生活微生物である酸素呼吸細菌が組み込まれた。こうして大きくて複雑な細胞が生まれたのである。この酸素呼吸性の三者(好熱好酸菌、遊走性細菌、酸素呼吸細菌)複合体は、微粒子状の食物をのみこめるようになった。この複雑で驚異的な生物、つまり遊走能と酸素呼吸能をもつ真核細胞が地球上に現れたのは、およそ20億年前のことだった。
この第二の合併体、すなわち酸素呼吸能を獲得した遊走性の嫌気性菌は、三つの構成要素をもち、大気中に蓄積した酸素に対処できる細胞になった。小さな遊走性細菌と耐酸性や耐熱性の嫌気性菌と酸素呼吸細菌の三つからできたこの細胞から、数々の動物が生まれることになる。
複合細胞が生まれた一連の合体の終わりとして、真核細胞のうちのあるものが緑色の光合成細菌をのみこみ、消化しそこなって体内に残した。細胞内での闘いのすえに、消化されなかった緑色細菌は葉緑体になった。日光を好み光合成ができる緑色細菌が第四のパートナーとして完全に一体化したのだ。この最後の合体で生まれた遊走性の緑藻が、今日の植物の祖先である。植物細胞を構成する個々の要素はいまなお独立の細胞としても生きており、遊走、発酵、酸素呼吸をしている。
私の最大の業績は、連続細胞内共生説の細部を練りあげたことであり、その中心となったのは、真核細胞の細胞質にある遺伝子は「裸の遺伝子」ではなく、細菌の遺伝子に由来するという考えである。これらの遺伝子は、激しく争った結果停戦協定を結んだ細胞たちの遺産なのだ。はるか昔に他の生物に食べられ、その体内に閉じこめられて葉緑体になった「シアノバクテリア」の仲間は、光合成をして酸素を生産する細菌としていまも池や小川、泥のなかや砂浜に生息している。
昔の植物遺伝学者は植物細胞の葉緑体に遺伝子を発見して驚いたが、シアノバクテリアの子孫なのだから遺伝子があって当然だ。
シアノバクテリアはいまも広く繁栄している。シャワーカーテンにこびりついたり、プールやトイレや池の水面をおおっており、日光があたって温まった、よどんだ水たまりを数日のうちにあざやかな緑色にする。大半のシアノバクテリアは今日でも自由生活をしているが、緑色植物の葉の空洞や根や幹に共生しているものもいる。
一方 ミトコンドリアは酸素呼吸をする自由生活細菌と近い関係にある 58〜61
動植物のミトコンドリアの直系の祖先が 自由生活細菌だったという主張はこれまで無視され続けてきた
ミトコンドリアは細胞内のエネルギー工場として 化学エネルギーを産み出している
それらの生物の祖先である微生物や プロトクチストの大多数の中でも はたらいている
ミトコンドリアは筋肉の運動 消化 脳での思考の動力源 62
私は、学生や同僚と一緒に、連続細胞内共生説(SET)が主張する四つの闘いのうちの三つを明らかにしたことを自慢にしている。私たちはいまや、細胞を構成する四つのパートナーの三つまでを同定できる。この説に熱中している研究者のあいだでは、細胞の基本となる細胞質は核も含めて嫌気性細菌の子孫だという点で意見が一致している。とくにタンパク質をつくる代謝の大半は、好熱好酸性細菌(サーモプラズマに似ている)に由来する(ステップ1)。真核細胞内で酸素呼吸をするミトコンドリアは、「紅色細菌」あるいは「プロテオバクテリア」と呼ばれている細菌が共生したものだ(ステップ3)。葉緑体その他の色素体は、かつては光合成シアノバクテリアだった(ステップ4)。ここでステップ2が抜けている。
遊泳するための付属物である繊毛はどこからきたのかという大問題が一つ残っており、大半の研究者が私と意見を異にするのはここだ。マックス・テイラーを初め多くの研究者は、私の主張を「極端なSET」と決めつける。ブリティッシュ・コロンビア大学のテイラーと彼の同僚のトム・カヴァリア=スミスは、真核細胞の起源について非共生的な「派生」説をとっており、その仮説がいまも有力だ。しかし、まだ正体は不明だが共生の第2段階に、ある細菌が関わったことを示す知見があると私は思っている。 62、3
(「遊走する微生物が、真核細胞の起源の最初の段階で共生したという私の仮説は、SETのなかでいちばんあいまいな部分だが、20億年ほど前にこれが起きたと思う。SETの鍵となるステップ2をこう考えると、繊毛、精子の尾、感覚突起、そのほか数多くの真核細胞の付属物が、嫌気性菌と遊走性細菌との融合から生じたことになる」 63)
(マックス・テイラーの仮説…直接派生説など 65〜66)
マクマスター大学のラドニー・グプタは、最古の真核細胞が「キメラ的な」性質をもっていたことを示す知見を、数多くの必須タンパク質のアミノ酸配列を分析した結果出している。彼が使っている用語や分類は私たちのものとはちがうが、基本的な考え――古細菌と細菌との融合で膜に囲まれた核をもつ細胞が生まれたという考え――は同じである。 71
つねに乾燥や食物不足や有害物などの潜在的な災難にさらされている外に比べれば、細胞内環境は水分と栄養分に恵まれたところだ。古細菌の細胞膜という障壁を突き破ったスピロヘータ(あるいはそのほかの遊泳性の細菌)は、常にエネルギーと食物を享受できることになった。襲撃したものとされたものの増殖のしかたはしだいに関連してきた。生息の拠点となる元の細胞を制圧してしまったのでは、襲撃者も長くは生き伸びられない。襲撃者は共生体となり、時の経過とともにオルガネラとなったのである。合体のあと新しい生き残りの策略が生まれたのだ。私は、くねくねと動く酸素に弱い細菌が食物を求めて古細菌を襲い、侵入していった場面を心に描く。動く細菌にすみつかれた古細菌は、そのおかげで速く動けるようになった。真核細胞は、「染色体のダンス」と呼ばれる有糸分裂をするが、これこそスピロヘータのたえまない動きに由来するという私の考えは、別の機会に書いた。 72
ミトコンドリアをもつ細胞はかならず、昔のスピロヘータの名残である微小管をもっている。これはスピロヘータと古細菌の共生が最初に確立したという考えと合致する。今日、有糸分裂をする遊泳性細胞のなかには、嫌気性でミトコンドリアをもっていないものもある。そこで私は、真核生物の共通祖先である有糸分裂型の祖先は、大気のすみずみまで酸素が充満する前に進化したと推定している。
現存のスピロヘータは、酸素の豊富な環境にも、乏しい環境にもいる。どきどき近くの生物に付着するが、その巧みさは、生物学者がその付着部を中心小体/キネトソームと、体部を繊毛とまちがえるほどだ。スピロヘータは、木質を食べる昆虫の腸に大量に生息し、人間の腸や精巣にもいる。泥のなかやトリコモナスなどのプロチストの細胞膜上で暮らすものもいる。湿り気と養分の多い暗いところが好きなのだ。スピロヘータの一生は、くねくねと動き、養分をとり、細菌と同じ分裂によって増殖するというものだ。繊毛への道は、初期のスピロヘータたちがねらいやすい近くの細菌に、可能なかぎり侵入し、一部がそのまま外に出なかったのがはじまりだ。たくさんの小さなスピロヘータが共同して運動し、それが統合していき、核をもつ遊泳者、最初のプロチストが生じた。
中心小体とキネトソームは、いわば友好的なジキル博士とハイド氏で、分裂中の細胞内に両方が同時に姿を見せることはない。中心小体は有糸細胞分裂が終わるとすぐにキネトソームに変わり、軸糸をのばす。これは両者が同一のものであることを示している。1898年に、パリの生理学教授L・F・エネギュイとブカレストのミハリー・フォン・レンホセックが、動物細胞の中心小体とキネトソームが同じものであることに気づいた。有糸分裂のあと中心体が極から移動してきてキネトソームになるという彼らの考えは「エネギュイ=レンホセック説」と呼ばれている。この説は彼らの死後に、電子顕微鏡の所見によって証明され、私が中心小体/キネトソームという二重の名称を使うきっかけになった。 73、4『共生生命体の30億年』2000 リン・マーギュリス
中村桂子 訳
訳者あとがき P199 に
…(お断りしておきたいのは、共生とは、この文字から受ける印象とはちがって、それぞれの生物が懸命に生きようとし、時には闘いながら、結局そこに落ち着いた姿であるということだ。共生とは相手を思いやってのことではなく、そうでなければ生きられない生き方と見た方がよい。)… と
「状況証拠を越えるものがほしい」 200
......................................................
ふたをされていたような 「学校」「教科書」その他の機会などで提示されなかったあれこれでしょうか?
興味深く また 現実味の感じられる部分について 相当入り込んだのでは
2017年1月17日 18時42分
非再生系細胞と再生系細胞
再生系の細胞では生命維持のためにアポトーシスがあり、細胞の置き換えが行われているのに対し、非再生系の細胞にはそのような役割はありません。 51
*
血液中の血球細胞(赤血球 リンパ球 血小板)は
骨髄にある造血幹細胞から分化してつくられていく
それぞれ特定の機能を持った血球細胞になる一歩手前の状態で
常に余分に用意されていることがわかっている
たとえば赤血球の場合 造血幹細胞から分化した赤芽球という細胞が待機しているが 多くは赤血球になることなく アポトーシスにより消去されている 40
身体の中の組織や臓器で どれくらいの細胞を維持すべきかは
多くの場合 特定のホルモンの量に依存して決定されていて
赤血球の場合 赤芽球から赤血球に分化する量はエリスロポエチンというホルモンによってコントロールされている
大量に出血したときにエリスロポエチンの量を調べてみると
急激に増えていることがわかる
非常事態に備えて赤芽球を多めに用意しておき
すぐ増産して対処できるようにしているのだ
怪我をした際に 傷口から透明な体液が出てくる
…血を止めるために出てくる血小板
血小板には細胞を増殖させる因子となるホルモンを放出する役割もあり 傷口付近の皮膚細胞は そのホルモンに反応して増殖を始める
細胞は分裂して増殖しますから、新しくできる細胞は必ず2個、4個、8個、16個、32個……と「2のn乗個」になります。ちょうど傷口をぴったり埋める数だけ細胞を増やすというわけにはいきません。
ではどうするのかと言えば、やはりちょっと多めに新しい細胞をつくるのです。傷が直る際に皮膚が盛り上がってふさがるのはこのためで、その後、不要な分がアポトーシスによって消去され、もとの皮膚の形に落ち着いていきます。 42
ホルモンの分泌とアポトーシス
温度変化 食事による血中の糖分(グルコース)の上昇といった変化が起こると その変化に対応して内部環境をもとに戻そうとする
そのように 身体を一定の状態に維持しようとする性質は
「ホメオスタシス(恒常性)」と呼ばれる
ホメオスタシスを保つために中心的な役割を果たしている
「ホルモン」
ホルモンの分泌とアポトーシスによる生体維持の間には深い関わりがある
ホルモンの量によって細胞がその数を増やしたり減らしたりする現象は さまざまなシーンで見られる 42
よく取り上げられるケース…去勢したラットの前立腺萎縮の例
ラットを去勢すると、前立腺細胞は一週間以内におよそ85%が死滅します。これは、前立腺の細胞が男性ホルモンであるアンドロゲンに依存して増殖しているためです。去勢によってアンドロゲン量が減少し、減った分だけ細胞に増殖刺激が伝わらなくなって、アポトーシスが誘発されるのです。
前立腺ガンの治療では、睾丸を摘出する手術を行う場合があります。これは前立腺のガン細胞がアンドロゲンによって増殖するためで、アンドロゲンの供給を絶つことによってアポトーシスを誘導し、ガンを退縮させることを目的としているのです。 43
ぜんそくやアレルギーに対してステロイドホルモンが使われることと アポトーシスとの関わり
ぜんそくやアレルギーは身体に過剰な免疫反応が起こることによる病気ですから、症状を抑えるには免疫反応に関わっているリンパ球の働きを抑制することが必要となります。つまり、リンパ球のアポトーシスを促進し、数を減らせばよいわけです。そこで登場するのが、ステロイドホルモン。
もっともこの治療法には、多くのリンパ球がステロイドホルモンによって死滅してしまうために免疫力が落ち、細菌やウイルスに感染しやすくなるというデメリットがあります。ステロイドホルモンが処方される際、同時に抗生物質が出るのはこのためです。
ホルモンと細胞量の関係で最もわかりやすい例は
人間の体の老化現象に見出すことができる
老化により性ホルモンの分泌は少なくなっていき それに伴い ホルモンの量によって細胞数がコントロールされている臓器は小さくなる
細胞増殖によって補給される細胞よりも アポトーシスによって死んでいく細胞のほうが多くなっていく(身体が徐々に小さくなっていく) 44
アポトーシスによる異常細胞の除去
ウイルス感染により発症する インフルエンザやHIV(ヒト免疫不全ウイルス)
・一度感染すると放置していては治らないAIDS(後天性免疫不全症候群)
・ある期間が経過すると治癒するインフルエンザ
そのような違い
細胞を溶解させる溶解性ウイルスに感染した場合
細胞は機械的に破壊されてネクローシスを起こして死滅
細胞のDNAに組み込まれた後 細胞のアポトーシスを抑制して
そのなかで生きながらえるHIVのようなものもある
インフルエンザウイルスに感染した細胞は
アポトーシスによって体内から消去されていく
細胞には、DNAに異常が発生したときに、それを修復する能力が備わっています。しかし、ウイルスがDNAに入り込んでしまうと、それを取り除いてもとに戻すのは非常に難しいのです。悪質な異常を起こした細胞は、可能な限りまるごと除去してしまうのが生体にとって最も安全な方法と言えます。
また、人間の身体のなかでは、日常的にぽつぽつとガン細胞ができています。しかし、すべてのガン細胞が増殖し、ガンと診断されるまでに至るわけではありません。
では、一度できてしまったガン細胞の多くがどうなるのかというと、やはりアポトーシスによって死んでいくのです。
「異常をきたした細胞をアポトーシスによって死滅させ、新たな細胞に置き換える仕組みは、非常に理にかなった修復機構であると言えます」 46
アポトーシスには「制御」と「防御」の役割がある
アポトーシスとは「不必要な細胞が自ら死ぬことで 固体の生命を維持する」機能として考えることができる
「何のために細胞が死ぬのか」という役割などを個別のケースで見ていくとそれぞれ異なる現象のようにも見えるが 細胞社会の中で役割を果たし終えたり 異常になったりしたときに自らプログラムを発動して死んでいくという共通点がある 47
アポトーシスの役割 大きく分けて二つ
・細胞の増殖や分化と同様 本来的に備わった基本機能として固体の完全性を保つ「生体制御」の役割
・ウイルスやバクテリア ガン細胞といった内外の敵が現れたとき 異常をきたした細胞をアポトーシスの発動によって消去する 生体防御の役割 48
*
…顕微鏡の向こうに見えた「細胞の自殺」…
1972年 スコットランドに留学していた病理学者
J・F・カーは論文を一本発表した
病変を起こした組織の切片を顕微鏡で観察している最中、カーはプレパラートの上に不思議な光景を見たのです。それは、死にゆく細胞の様子でした。
その細胞は、彼が知っている細胞の死に方――膨らみ、破裂して死を迎える細胞の壊死=ネクローシス(necrosis)――とは、まったく異なる姿を示していました。正常な細胞と比べて少し小さく、一部は小片となった、見慣れない像。しかもその像は一つではなく、いくつも見て取ることができる。
カーはその細胞死の観察結果から、細胞が自ら一定のプロセスを経て死んでいく、壊死とは別の「死に方」があるのではないかと考えました。そして、その「死に方」をアポトーシス(apoptosis)と名づけ、論文にまとめたのです。 16
医学的な現象は、ギリシャ語で名前をつけることが慣例となっています。ギリシャ語で“apo”は「離れる」、“ptosis”は「落ちる」という意味。英語で言えば、“falling off”です。カーは、細胞の小片が散る様を、秋に木の葉が落ちる様子になぞらえたのでしう。
ユニークなことに、カーは論文のなかで apoptosisの発音にまで「セカンドpはサイレントで、アクセントはtに」と細かく注文をつけています。普通に読むと「エイ(ア)ポプトーシス」となるところを、「アポトーシス」と呼ぶのはこのためです。
カーが論文を発表するまで、細胞の「死に方」には分類が存在していませんでした。細胞死は壊死という言葉で一括りにされ、誰もそのことに疑問を挟まなかったのです。 16
*
1980年代末 細胞の死に関する文献に当たり始めた
当時はまだC・エレガンスのゲノム解析もおそらく終わっていなかったわけですが、ともあれ、私はカーの論文にたどり着き、“apoptosis”という言葉と出合ったのです。
まず唸ったのは、「木の葉が落ちる」というウイットに富んだネーミング。こと科学の分野でも、長く残り親しまれるネーミングは示唆に富んでいるものなのです。細胞の終焉を落ち葉になぞらえつつ、「マイトーシス(細胞分裂)」「ネクローシス(壊死)」といった古くからある言葉と語尾をそろえてあり、うまく考えたと感心したものです。
何より、細胞死といえばすべて「壊死」で片づけられていたなか、遺伝子に死がプログラムされているのではないかという考え方は、非常に新鮮に映りました。
私がそこから得たのは、細胞が死にゆくプロセスがあらかじめプログラムされたものならば、それがどう制御されているかを解明することが重要なのではないかという着想でした。 64
その頃は“apoptosis”という言葉がまだ知られておらず
日本でどう表記するかも決まっていなかった
「壊死」と訳すことにならい 「自滅死」「自爆死」「自死」などと日本語をあてる案もあったが 原著論文の「セカンドpをサイレントに アクセントはtに」という指定に従って「アポトーシス」と発音・表記しようということになったという経緯がある 65
「災害に備えて」さまざまな缶詰を備蓄
消費期限を迎え 廃棄 入れ換え…
その「古いものを消去する」仕組みを担保しているのが
アポトーシス 68
免疫細胞は遺伝子の組み換えによってランダムにつくられるため なかには有用な抗体をつくり出せないものや 自己(自分の生体成分)に対する抗体をつくってしまうものもある
自分自身に対する抗体をつくってしまう免疫細胞は人体にとって危険ですから、血液中に出てくる前に完全に除去しなくてはなりません。これを可能にしているのも、アポトーシスなのです。 69
免疫細胞は骨髄でその前身となる細胞が生まれると、血液に乗って胸腺に運ばれ、そこで成熟するという過程を経ています。このとき、胸腺のなかではストローマ細胞という“教官”が「あなたは死になさい」「あなたは大丈夫ですよ」というように“教育(エデュケーション)”を行います。
この“教育”により、非自己を認識できないものや自己抗体をつくるようなものに死のシグナルを送り、アポトーシスを起こさせることで免疫システムは維持されているのです。“教育”の過程で、およそ95%もの免疫細胞が死滅すると言われていることからも、免疫システムにおいてアポトーシスがいかに重要な役割を果たしているかを感じ取ることができるでしょう。
免疫細胞への“教育”がうまくいかず、自己抗体をつくるものが血液中に流れてしまうと 重病になる
顔に蝶形の赤斑が出る全身性エリテマトーデスや 関節リウマチなどは「膠原病」と総称される自己免疫疾患の一つ 70
『ヒトはどうして死ぬのか』死の遺伝子の謎 2010
田沼靖一
1952年山梨県生まれ/東京大学大学院薬学系研究科博士課程修了
米国国立衛生研究所(NIH)研究員等を経て東京理科大学薬学部教授/専門は生化学・分子生物学/同大ゲノム創薬研究センター長
高校生になる頃には野球選手になる夢はついえ
バレーボール部 生物部とかけもちする生活
いまでも覚えているのは、大学の先生が寄稿した科学雑誌を見て、文化祭のテーマとしてメダカの性転換に挑戦したことです。
その記事には容器のなかに「 性」ホルモン「 」を入れ
「 化」する手順が書かれていた
薬局に行って…店主から
「君が打つんじゃないよね?」と尋ねられた 4『ヒトはどうして死ぬのか』
「 系の 」では「 」のために 「 」があり・・
という 響き があるようす
10.3 自己貪食胞
lysosome:一群の加水分解酵素を含み消化分解作用をもつ小器官
じしょく‐さよう【自食作用】⇒ オートファジー
* * *
Wikipediaは?
・間質細胞 Stromal cell
・骨髄間質細胞 Marrow stromal cell
2016年9月21日 6時54分
『身体をめぐるリンパの不思議』2015 中西貴之
リンパ系は体内に蓄積する不要物を余剰な水分と共に回収し 細胞をフレッシュな状態に保ち さらに侵入した病原菌や毒素などの外来異物を処分する重要な役割を担う組織
その外来異物の処分の役割を特に「免疫」と呼ぶ
大量の細菌やウイルスなどが満ちあふれている環境で 免疫機能が失われると それらに感染し 全身はエサや住みかとして利用され 生きることができない(免疫機能を失ったマウスの実験で確認された)
一方 リンパから発症する病気もあり 起床時に顔がパンパンになったり 猫にひっかかれて腕や足が腫れ上がったり がん細胞にリンパを悪用されて全身に腫瘍が転移 してしまうなどの事実から 体を保つにあたり リンパが重要なポジションにあることがわかる
リンパ節は、ファンタジーに例えるなら、勇者や武器職人であるリンパ球がたくさん待機している街のようなもので、ひとたび敵が侵入してくると、そこは戦場にもなります。
このリンパ節には、何本ものリンパ管がつながっていて、その管を通して、周辺からその破片の毒素が紛れ込んでいることがあります。それらがリンパ節に入ってくると、待ち受けていたリンパ球が免疫反応、つまり身体の健康状態を維持するための活動を行い、その結果として炎症が起き、リンパ節が腫れ上がることがあります。
そのような仕掛けが 全身のあらゆる場所に仕込まれているため 雑菌あふれる環境で生きられる
つまり 一般に理解されている「リンパ」とは 全身に広がる「リンパシステム」の広大な世界の中のごくごく一部分でしかない
リンパシステムは全身に分散しているリンパ器官をリンパ管がつなぎ その管の中をリンパ液に運ばれるリンパ球が移動しているものだと表現でき
リンパシステムは 脳を除いて頭の先から足の先まで 皮膚近くから内蔵の奥深くまであらゆる場所にリンパ管を張り巡らせ リンパネットワークを形成している
リンパシステム(リンパ系):リンパ管 リンパ液 リンパ球 リンパ器官から成る
リンパ管…血管系における血管に相当する体内の水路で リンパ組織とそれ以外の組織 静脈の相互を接続し その中をリンパ液やリンパ球が移動
リンパ器官は 細胞が集まって形成された臓器のような構造体で 胸腺 脾臓 リンパ節 骨髄などがある
リンパ球には着色した細胞が無いため リンパ液は淡い黄色に見えたり また 食べた食品が脂肪分を多く含む場合は白色に見えたり と 目立たない色がリンパシステムの存在感を薄くしている理由でもある
リンパシステムの働き
・病原菌などの侵入に対抗するための防御機能
・身体の水分量の調節
人間の体はほとんど水でできていて 体内の水は純粋な水ではなく タンパク質や微量成分などが溶けこみ 生命化学反応が起きる場として重要な役目を持つ
その水は およそ3分の2(66%)は 細胞の内部にあり 細胞は細胞膜-油成分でできた袋のようなもので囲まれ 内部の水は外へ流れ出すことなく化学反応が行われている
3分の1の水「体液」は細胞の外に存在し 比較的自由に体内を移動…体液には血液 リンパ液の他に 細胞と細胞の隙間を潤している間質液(組織液)や 脳を包み込んで衝撃から守ったり栄養供給の媒介をする脳脊髄液 眼球の中の眼房水などが含まれ (尿も膀胱にある間は体液)
「体液」の中で リンパシステムに関係が深いのは 「血漿」と「リンパ液」 〜16
●リンパ管はどうやって形成されたか 109〜118
リンパ系は、血管系と一部の機能を重複させながら、いくつかの特定のリンパ臓器と密接に関係して、複雑、かつ高度な機能を担っています。このことから、生物の進化におけるリンパ系の獲得は、非常に興味深い点です。
ある動物がこれまで進化してきた過程を繰り返しているように見えます。このことを、生物進化を研究する領域では「個体発生は系統発生を繰り返す」と説明しています。この説を「ヘッケルの反復説」といいます。
その説の例として出されるのが ほ乳類
ほ乳類の受精卵が生き物らしい形を形成する初期段階で、エラの様な構造が現れますが、それはすぐに消えてしまいます。これをもって、ほ乳類が魚類を経て進化した証拠だと考え、魚類だったころのほ乳類の姿を繰り返している、というのです。
この説に関しては、エラのある一時期の胎児は魚なのか、というあまりに極端な議論を呼び起こしたため、進化の過程を繰り返すという、胎児と太古の生物を同一視する点においては大きな違和感があり、完全に受け入れられているわけではありません。しかし、進化的に、ほ乳類よりも古い生物の特徴が現れることは否定できない、と多くの科学者は考えています。
とすると ほ乳類の誕生の過程でリンパ管はどのように挙動しているのか?
そこに、わたしたちが進化の過程でどのようにしてリンパ管系を獲得したのか、のヒントが隠されているかもしれません。
卵子は 受精をすると細胞分裂を開始し 数回の細胞分裂を繰り返すと 将来胎児になる細胞に性質が二分され 中が空洞のボールのような状態に成長した胚盤胞になる
その時のボールの中にあるひとかたまりの内部細胞塊と呼ばれる細胞が さらに細胞分裂を繰り返して胎児の体を形作る
(内部細胞塊:再生医療に使用することが可能だと期待されて研究が進められていたES細胞は その内部細胞塊を取り出して培養したもの)
内部細胞塊は、胎児になる前準備として、さらに三種類の異なる性質を持つ細胞の集団に分かれます。それらは内胚葉、外胚葉、中胚葉と呼ばれます。
血管系は、中胚葉の細胞がさらに枝分かれして血管芽細胞となり、この細胞が管状に細胞分裂して作り出されます。
受精卵から胎児になる過程で、リンパ管系がどの段階でどの種類の細胞から作り出されるのかは、実はよくわかっていませんが、2通りの予想が有力視されています。
・静脈の管壁を構成する内皮細胞からリンパ管が形成され全身に広がる
・組織内で何らかの種類の細胞がリンパ管壁となる内皮細胞に変化し 形成されたリンパ管が次第にネットワークを形成する
人間はもちろんのこと ほ乳類が誕生する過程で リンパ管系がどのように形成されるのかを観察することは非常に困難
小さな魚「ゼブラフィッシュ」を使って観察実験が行われた
ゼブラフィッシュの場合 リンパ管系細胞の由来は 特定の場所から伸びていく管と全身のあちこちで湧き出るように誕生する管の二つがある…人間同様に静脈角と呼ばれるリンパ管と静脈が合流する位置の静脈からリンパ管が枝分かれするように成長を始め 同時に全身では組織の内部で発生したリンパ管の断片のような構造が互いに接続して リンパ管のネットワークを形成している
見分けの付かない一つのリンパ管ネットワークが、異なる由来の細胞同士によって形成され、やがてそれらが一体になって機能するというのが本当のリンパ管の由来であれば、その調節メカニズムについては非常に興味が持たれる部分です。しかしその点については未だ解明されていません。
魚類では 血管系が種類によって明確な血管系のない開放形だったり 心臓が4つの部屋から成っていなかったりなど 構造は異なり
魚類とほ乳類のリンパシステムの最大の違い…
・ほ乳類ではリンパ管の途中にリンパ節があるのが一般的
・魚類ではリンパ節とリンパ管は一体になっていない
(メダカのようにリンパ節がないと報告されている魚類もあるが メダカのリンパ節はあっても相当小さいことが想像される)
一方 トラフグの研究では エラに大量のリンパ球が集まった塊が点在していることが発見され エラはリンパ組織の一つである可能性が示唆される観察結果もあり 外部から侵入してくる雑菌などに抵抗するために 粘膜層にリンパ節が集中していることを考えると エラがリンパ器官というのはさほど奇想天外な話ではないが まだ結論は出ていない
リンパシステムには血管から栄養などと共に間質液として放出された余分な水分を回収して全身の水分バランスを保つという役目があるため 閉鎖した血管を持つ生物には必ずリンパシステムが存在すると多くのリンパ学者は考えている
《歴史》
〈動物のリンパ管研究〉
紀元前5世紀の医師ヒポクラテスがリンパ管についての最初の記述をしたとされ
紀元前4世紀にアリストテレスが無色の液体が流れる管としてリンパ管を記載
紀元前3世紀 アレクサンドリアの医師ヘロフィロスとエラシストラトスが 解剖の結果として乳び管と呼ばれる小腸周辺のリンパ管と思われるものを記載
16世紀になるとイタリアの解剖学者エウスタキオは馬の胸部リンパ管を発見し それを静脈として記述
イタリアの外科医師アセリが イヌを解剖しているときに 乳び管を発見したと記述…空腹の動物を解剖しても乳び管は見つけられないが エサを食べた後は見た目が大きく変化…アセリは偶然十分にエサを摂取していたイヌで実験したため 容易に発見できたものと思われる
実験動物では 実験上の都合で乳び管が最も目立つ存在だったため 初期には乳び管の研究が熱心に行われた
〈人間のリンパ管研究〉
人間の体内で最大のリンパ管は「胸管」…下半身全体のリンパを静脈に輸送するリンパ管
(海外では古くから解剖学が進展していたが)リンパ管系については 特に人間の死体ではリンパ液があっという間に静脈に抜け出てしまい非常に観察しにくいという問題があり また 当時は死体を美しく保存するのは不可能だった
(現在は遺体の血管に樹脂を入れ型どりする技術 プラスティネーションなどの手法がある)
17世紀のヨーロッパで 樹脂によるコピーの元祖「ムラージュ」という手法が発見されていた
ミニチュア模型の精密パーツを自分で複製する手法に似て 解剖した死体を石膏などで型取り ロウを入れ複製を作り色を塗る…その手法の開発により 臓器の立体模型が普及し 研究や医学に活用され 毛細血管の詳細までわかるようなムラージュに至っては 現在美術品としても扱われることもある
現在の研究においても トレーサーと呼ばれる放射性物質や色素を注入して その挙動を追跡…その技術もその原形は17世紀のヨーロッパで開発されたもので 当時の科学者は リンパ液の流れの全体像に興味を持ち 工夫 たとえば 空気や牛乳などを注入 追跡
17世紀も終わりに近づくと 水銀をトレーサーとして使用する技術が開発され アントニオ・ヌックは 水銀でリンパ管系の詳細を描き出し出版…水銀注入法には水銀毒性の問題があるが 多くのリンパ管に関する書籍が発行された
19世紀末に油性色素をトレーサーとして使用する手法が ルーマニアのゲロータにより開発された…組織間隙に色素を注入し リンパ管がそれを吸収して着色することを利用したもの
〈日本でのリンパ研究〉
西洋医学の導入…18世紀の蘭学による医学知識伝来と「解体新書」の翻訳…蘭学者杉田玄白 前野良沢 中川淳庵
ドイツ語の医学書「解体学表」-ドイツ人ヨハン・アダム・クルムス…そのオランダ語訳「ターヘル・アナトミア」
(日本の医学でリンパが登場したのは「解体新書」1774 が最初だろうと考えられている)
「解体学表」が書かれた頃には 人間のリンパ管系についてもすでに色々わかっていたため 「解体新書」では 腸間膜から始まって 左静脈角に至る主要部分の全体像が描かれている
1812年に波多野貫道が著した「解観大意」が 日本人が初めて自らリンパ管系を観察して図解した医学書だとされている
20世紀の日本では 京都大学を中心に血管系やリンパ管系がどこにどのように広がっていて どのような役目を果たしているのかに関する研究が盛んに行われた
リンパ管や関連する組織の構造は 管の数や形 つながり方に至るまで 大きな個人差があり 日本人のリンパ管に関する総説がまとめられたのは1960年代になってのことで 当初は体内での張り巡らされ方についての記述に集中 20世紀になり分析装置の発展に伴い リンパ液そのものの化学的組成に関するアプローチも行われ始めた
(画像化…リンパ管造影)
『身体をめぐるリンパの不思議』
同書 “飼い主”に感染 (はてな 7.26分)
〈リンパ系フィラリア症〉
フィラリア糸状虫と総称される線虫の中には、リンパシステムに成虫が寄生する種がいます。ヒトのリンパシステムに寄生する糸状虫は、バンクロフト糸状虫、マレー糸状虫、チモール糸状虫の3種類ですが、リンパ系疾患の原因のほとんどはバンクロフト糸状虫だとされています。
成虫は雄は4センチ程度 雌は10センチに達し 5年体内で生き続ける
感染源は蚊で 媒介して人から人へと感染
成虫が人の体内で子供を産んで その子供で体長0.3ミリ弱のミクロフィラリアが血液中に移動
患者を刺した蚊が糸状虫を取り込み中間宿主となって 別の人を刺した時に感染する
急性期にはリンパ管炎を発症して発熱し、リンパが貯蔵することによってリンパ液の送液が正常に行えなくなり、リンパ液の循環が徐々に損なわれリンパ管が破れることもあります。悪化すると手足の浮腫や象皮病へと進んでいきます。ミクロフィラリアは、それ自身が花粉同様にアレルギー源となり、ぜんそくのような症状も起こします。血液中にミクロフィラリアを検出することで診断し、駆虫薬で治療します。
原因となる糸状虫は、熱帯〜亜熱帯地方を中心に広い範囲に生息しています。日本においても、沖縄県と鹿児島県にかつて生息していましたが、1970年代に根絶されました。しかし、世界中ではいまだ1億人もの糸状虫感染者がいると言われており、WHOは2020年を目標に根絶に取り組んでいます。
なお、糸状虫の感染で見られるリンパ管の拡張と同様の症状は、ケガややけどが原因で起きることもあります。 147、8
〈猫ひっかき病〉
別名 非細菌性局所性リンパ節炎 という立派なリンパ関連疾患
猫キックをされた際などに爪でひっかかれ 1週間程度経過した後に 傷の部分やリンパ節が腫れ上がる病気
容易に感染症とわかる病気だが 詳細が明らかになったのは1990年代に入ってからのこと
ひっかかれた傷口から 猫が持つ病原菌:バルトネラ・ヘンセラ菌が体内に侵入することで発疹が起きる
その菌は非常に強力なため リンパ球やマクロファージとの激しい戦いが繰り広げられ リンパ管を通じてリンパ節にまで入り込んだ菌との攻防戦によってリンパ節が腫れ上がる
保菌者は 間違いなく猫で 猫同士はノミが媒介して感染が広がると考えられていて 猫に対しては何も病原性を持たない
自然に治癒することも多いが 激しい症状が長く続くこともある(通院して感染症治療を行う) 148
〈リンパ球性脈絡髄膜炎〉
ペットが原因となると思われるリンパ系の病気で ハムスターやハツカネズミが持つアレナウイルス(LCMV)と呼ばれるウイルスの人間への感染が原因
(猫ひっかき病は日本中で発生している)
ハムスター・ハツカネズミ由来リンパ球性髄膜炎は 日本では明確にその患者だと確認された例がない
というのも猫ひっかき病が かわいらしい名前の割りに症状が激しく ひっかき傷とセットになった炎症が非常に目立ち診断しやすいのに対し
リンパ球性脈絡髄膜炎は そのおどろおどろしい名前とは対照的に症状はたいしたことはなく 一般的なウイルス感染による髄膜炎と区別がつきにくく 適切な治療を行えば 大きな問題には進展しない炎症性疾患
(とみられている が)
その病原ウイルス LCMV を実験動物の脳内に注入すると リンパ球の一種である細胞障害性T細胞がウイルスを除去しようとして脳の中で異常な活動を示し その動物は死んでしまうことから そのウイルス自体の有害性は 低いものではないようだ
猫ひっかき病にしても ハムスター・ハツカネズミ由来リンパ球性髄膜炎にしても その病原体を持っている張本人のペットたちは 基本的にはそのような症状を見せない
飼い主に感染して初めて大変なことになる
そのため ペットが健康だから 自分の病気の原因となるはずはないと考えるのは早計で 感染症疾患の場合 ペットに関する情報も適切な診断とそれに基づく適切な治療に有用な情報だと思われる 149『身体をめぐる リンパの不思議』2015 中西貴之
2016年7月31日 7時47分
『リンパの科学 第二の体液循環系のふしぎ』2013 加藤征治
「がんはリンパがお好き?」より
がんがリンパ節に転移する場合にも、血管と同様、がん自身が組織周辺にリンパ管の新生を促進させて、好んでリンパ管に入っていくのでしょうか?
もしそうだととすれば がん細胞とリンパ管内皮細胞との間で
特異的な相互作用が行われている可能性がある
がんがリンパを好むのであれば、がん細胞のほうからリンパ管に対して、何らかの働きかけをしているのでしょうか?たとえば、がん細胞自身かあるいは他の細胞からリンパ管内皮細胞の増殖を誘引するリンパ管内皮細胞の増殖因子を誘引する「リンパ管増殖因子」(VEGF-C、VEGF-D)を産生させて、リンパ管に作用するのでしょうか?
P213
リンパ節転移を起こしやすい乳がんや前立腺がんでは がん細胞がVEGF-CやVEGF-Dを産生することが臨床的に知られていて
転移性の高い悪性黒色腫(メラノーマ)-皮膚などの色素細胞(メラノサイト)に由来-では 転移性の低いものに比べ腫瘍周囲にリンパ管が多く分布していることも知られている
P214『リンパの科学 第二の体液循環系のふしぎ』
・・・・・・・・・・・・・・・
「リンパ管増殖因子」と入れますと 出てまいりますのは…
血管内皮細胞増殖因子 けっかんないひさいぼうぞうしょくいんし-Wikipedia
「脈管形成(胚形成期に、血管がないところに新たに血管がつくられること)および血管新生(既存の血管から分枝伸長して血管を形成すること)に関与する一群の糖タンパク」だそうで
英語の vascular endothelial growth factor から VEGF(ブイイージーエフ)と呼ばれることが多い。
血管内皮細胞成長因子、血管内皮増殖因子、血管内皮成長因子などと呼ばれることもある。
VEGFは主に血管内皮細胞表面にある血管内皮細胞増殖因子受容体 (VEGFR) にリガンドとして結合し、細胞分裂や遊走、分化を刺激したり、微小血管の血管透過性を亢進させたりする働きをもつが、その他単球・マクロファージの活性化にも関与する。
正常な体の血管新生に関わる他、腫瘍の血管形成や転移など、悪性化の過程にも関与している。
1983年マウス腹水から血管透過性を亢進させる物質として発見され、1989年ウシ濾胞星状細胞の培養液から45 kDa(キロダルトン)の糖タンパクとしてVEGF-Aが単離、クローニングされた。
-Wikipedia
・・・・・・・・・・・・・・・
『リンパの科学 第二の体液循環系のふしぎ』
「がんはリンパ節にどう転移するのか?」より
がん細胞がリンパ節に転移するには、まず組織にあるがん細胞のが周囲のリンパ管に侵入することがキーステップとなります。そのしくみはまだ十分に解明されていませんが、がん細胞が偶発的に既存のリンパ管に侵入するというよりは、リンパ管を好んで、能動的に移動して侵入するのではないかと考えられています。
ある特性をもつがん細胞と、そのがん細胞の転移を受けるべく特異な微小環境を保持した臓器・組織の両者の協調作用によって、がんの転移が成立するという考え方があります。19世紀のイギリスの外科医パゲット博士が乳がんが骨に転移しやすいことを報告し、「播種理論」を提唱しました。播種とは、転移によるがん細胞の分散を種播にたとえたものです。
転移先の組織とがん細胞とを取もつのがリンパ管であり その結果転移が起こるのであれば リンパ管を増殖させるような化学物質の放出などの可能性が考えられ
あるいは 増殖因子となる化学物質の放出はなくても がん組織がリンパ管増殖に適した環境を提供する可能性もある
P215
近年、リンパ管内皮細胞の分化・新生と関連して、細胞内カルシウムイオン(Ca2+)濃度の変化など、生理的機能を知るための研究方法としてリンパ管内皮細胞培養法が開発され、リンパ管内皮細胞が低酸素濃度の培養条件で増殖・新生することが明らかになりました。
がんの組織環境も血管に乏しく、低酸素状態にありますので、リンパ管増殖には好都合といえます。
P215、6
マウスのがん転移の実験モデルやヒト乳がんの症例などの最近の研究では…がんのリンパ節転移の過程で がん組織の周辺の組織内(リンパ節外)でリンパ管の新生が促進されること以外に…
リンパ節内のリンパ管の新生が誘導されることが観察されていて
がん細胞のリンパ節内における捕捉を低下させ
リンパ流に乗ってがん細胞が容易にリンパ節を通過し
輸出リンパ管から他の組織へ輸送されることが示唆される
P216
「リンパはがんがお好き?」より P217〜
リンパ節転移を示すヒト悪性黒色腫では、リンパ管内皮細胞が産生するサイトカイン(細胞産生因子)の一種であるケモカイン(化学物質因子)CCR21に対する受容体であるCCR7が発現します。その結果、がん細胞は内皮細胞上のCCR21に対して遊走して集まっていくことが報告されています。このような現象を「ケモタキシス」とよびます。食道がんや頭頸部腫瘍のリンパ節転移も、同様のメカニズムと考えられています。
また、リンパ管からのがん細胞に対する積極的な働きかけはないにしても、リンパ管系そのものが、がん細胞にとって都合のいいようにできている可能性も考えられます。リンパ管系はもともと、体内の余分な水分や老廃物、侵入してきた異物の回収によって生態の恒常性維持・防御を目的として発達したものですので、異物としてのがん細胞を受け入れやすい状況にあることが推測されるからです。P217
「腹腔や胸腔におけるがん転移」より
腹腔内に特有ながんの転移形式が「播種」
がんの原発巣から腹腔内に遊離したがん細胞が腹腔面に着床した後 増殖してリンパ管に入り 転移
腹腔にある腸間膜で構成されている大網に
「乳斑」とよばれるリンパ組織があり
大網乳斑にはリンパ管が分布し
腹腔内の異物や出血による赤血球などが吸収される
腹膜は発生上、中胚葉由来の中皮細胞層に覆われていますが、乳斑部は中皮細胞が完全には覆っていないため、抵抗性が弱いところでは腹腔内の物質や細胞が通過しやすくなっています。
そのような箇所では、腹水中で塊をなしているがん細胞なども浸潤しやすいのです。
さらに 腹腔のがん細胞が他の場所に転移する経路として
横隔膜の中皮直下にあるリンパ管が考えられる
また、腹膜からがん細胞がまるで種を播くようによく飛散(播種性転移)する部位の一つとして、女性の直腸と子宮のくぼみ(直腸子宮窩、別名ダグラス窩)にある腹膜が重要な領域として挙げられます。直腸子宮窩は、仰向けに横たわった状態では腹腔のいちばん低い位置にあるため、重力と関連して腹水が溜まりやすく、がん細胞の播種が生じやすいのです。
肺の表面と胸膜の内面は 呼吸のために膨らんだり収縮したりする肺を包みこんでいるため 薄い漿膜(胸膜)で覆われている
胸膜は直接肺の表面を覆う肺胸膜と
胸壁内面を覆う壁側胸膜の二重の膜で構成されている
壁側胸膜にはよく発達したリンパ管網が分布しており
肺における組織液の調整に働いている
リンパ管網の発達は同時に
肺がんの進展過程における胸膜播種や
胸水の貯留とも深く関連している
〜P219
「転移するがんの“見張り役”」より
がんがリンパに乗って広がることは 18世紀から認識されていた
19世紀後半になって、ウィルヒョウによって臓器のリンパ流域に属するいわゆる所属リンパ節の、免疫防御器官としての重要性が提唱されました。20世紀に入り、微小ながんの塊がリンパ流に乗って転移する際、最初に転移するリンパ節、あるいはもっとも転移しやすいリンパ節が存在することが指摘されました。
そのようなリンパ節を「センチネルリンパ節」(SN)とよび
がんの局所転移として注目されてきている
センチネルには「歩哨」「見張る」という意味がある
(がんの最初の微小転移を見張っている)
がんのリンパ行性転移は、がん組織周辺におけるリンパ管網の構築とリンパの流れに関係するもので、たとえば胃がんでは、肺や肝臓、脳などに転移したものを遠隔転移といい、これによってがんの進行度を判定しています。
P219〜221
『リンパの科学 第二の体液循環系のふしぎ』
※太字は記入者によるもの
・・・・・・・・・・・・・・・
太字のあたりの
一つには 「重力」云々 ということがありますか
そして 個人的な… 今朝方の あるいは 長期的な
「痛」に繋がるキイワードでもある
「直腸子宮窩 別名ダグラス窩」
個人的には 数字では表されませんでしたが
其処での癒着による 激痛の長年の持続 と説明されました
そのあたりを Wikipediaより
「腹膜や卵巣の病巣の深度や大きさ、癒着の程度、ダグラス窩の閉鎖をスコア化し、合計点数によってStage I〜IVの4段階に分類する」
子宮内膜症 Endometriosis
子宮内膜やそれに類似した組織が
子宮内腔や子宮体部以外の骨盤内で増殖する疾患
「転移や浸潤するなど悪性腫瘍のような性質も併せ持っている」
2015年12月27日 14時46分
Self-organization の 12.2分
「さいこうせい」に引かせていただいたのは…
(血液から漏れ出した)組織液を吸収・排出
不要な老廃物を交換し 生態環境を維持するとともに
リンパ球やリンパ組織 リンパ器官を含む
生態の免疫機能に深く関与 P4
心臓というポンプをもたない…
輸送は からだの位置や姿勢により リンパ管周囲の筋肉などの
組織が動くことに伴って受動的な管壁の収縮が生じ…
くねるような蠕動運動 弁の開閉による振り子運動などにより
運ばれ 血流よりはきわめてゆっくりと でも 確実に P6
血管系では血液循環というが リンパ管系ではリンパ輸送といい
リンパ管は体の抹消部分の組織内に端を発して
一方向のみに流れる P25
『解体新書』では「Lympha」を無視して 「Water」水という訳
(原本の『ターヘル・アナトミア』では「Lympha,Water」)
のちに リンパ管に「水道」 中身に「水液」の訳をあてた P20
リンパ研究は 日本では江戸末期から長い空白があり
20世紀に入り 足立文太郎(京都大学解剖学初代教授)により
動静脈やリンパ管研究が精力的になされるようになった P73
『リンパの科学 第二の体液循環系のふしぎ』
というあたり
*
末梢血 まっしょうけつ Peripheral blood とは
血管の中を流れている通常の血液のことである。
血液検査や献血の為には通常は腕の血管から採取する。
骨髄や脾臓・肝臓にプールされている血液やリンパ、組織液、臍帯血などと区別するために末梢血という。
-Wikipedia
『リンパの科学 第二の体液循環系のふしぎ』2013 加藤征治
「細胞の終末の姿」と誤解されたリンパ球 P182〜
各細胞における核に対して細胞質の占める割合は
若い細胞ほど大きく
成熟するにしたがって小さくなる傾向があり
(抹梢血やリンパ組織での免疫系)リンパ球の大部分は
核に対して細胞質の占める割合がきわめて小さい
「免疫現象」(細胞性免疫能)が研究される以前の1950年代頃には リンパ球は「すでに分化し終えた終末の細胞」と見なされ
機能不明の “謎の白血球”だった
1960年代に入り
感染症などに対する複雑な免疫反応のメカニズムが調べられ
リンパ球が
生体の免疫反応に直接関与していることが明らかになる
「いまや、免疫を担当する“ミクロの戦士”」
リンパ球には、免疫系の中心機関である胸腺(Thymus)で成熟する「Tリンパ球」(胸腺由来T細胞)と、骨髄で成熟する「Bリンパ球」(骨髄由来B細胞)の2種類があり、免疫担当細胞として脚光を浴びてきました。TとBの二つの細胞群は、免疫機能細胞論的には、T細胞が移植免疫や遅延型アレルギー反応など「細胞性免疫」を、B細胞が抗体をつくって抗原を攻撃する「体液性免疫」をつかさどると区分されています。
遅延型アレルギー反応とは、T細胞のグループで特殊な機能を持つキラーT細胞と、活性化されたマクロファージの過剰反応による組織障害を指します。薬品や金属、うるしなどによる、いわゆる「かぶれ」としての接触性皮膚炎や、結核菌に対する防衛反応の程度を見る検査としてよく知られているツベルクリン反応などがこれにあたります。
20世紀後半に入り
ヒトの血液中のリンパ球を細胞分裂促進剤とともに培養する実験が行われ
リンパ球は非特異的に反応して しだいに肥大化し
2〜3日後には 細胞質の広い大型のリンパ芽球(芽球化リンパ球)へと変化し 分裂することが明らかになった
それ以前は、リンパ球は最終的に分化・成熟した血球であり、それ以上は分裂・増殖しないものと考えられていたため、驚くべき発見でした。“血球の先祖返り”ともいうべきこの現象は、リンパ球の幼若化・芽球化とよばれ、当時たいへんな注目を集めました。
35年以上も前の古い話ですが、筆者は当時、博士論文のテーマとして“培養系でのリンパ球反応の研究”を行っていました。採血した自身の末梢血を遠心分離機にかけて効率よくリンパ球を他の血球から分離し、分裂促進剤を加えた培養液中で37℃に保ち、3日間培養して観察しました。この培養系では、健常人の末梢血中では見られない大型のリンパ芽球が出現しますが、このようなリンパ球の芽球化反応は、生体の局所において、抗原刺激に対する特異的免疫反応として起こる現象でもあります。
〜P185
////////////////////////////////////////////////////////
ここのカテゴリ設定では
数字を定めることにより
表示順を変更できますが
かねてより浮かんでいた
逆に表されるような位置
…そのような機能は無い
急激に増えることも無い
一つずつ数字を入れ込む
という作業を増加ごとに
行おうと思っております
2015.12.25
2015年12月24日 11時22分
(コピペです−こぴぺ者)
60秒でわかるプレスリリース
ES細胞から神経細胞へ分化開始させるスイッチ因子を解明
−高選択性で神経細胞を産生させる基盤を確立、脳疾患の応用などに期待−
Zfp521遺伝子の機能を阻害したES細胞は、神経細胞への分化だけが選択的に阻害
私たちの体を構成するさまざまな細胞に分化する能力を持つES細胞やiPS細胞は、多能性幹細胞として再生医療などを実現すると世界中で注目されています。しかし、血液や増殖因子などを含む通常の培養液で培養すると多種類の細胞が混在して分化してしまうため、医療などに必要な一種類の細胞を限定して分化させる培養法などを特別に工夫することが必要となっています。発生・再生科学総合研究センター器官発生研究グループらは、細胞に刺激を与える物質を除いて培養すると、ES細胞・ iPS細胞が自発的に神経前駆細胞や神経細胞に効率よく神経分化することを明らかにしてきましたが、そのメカニズムは不明のままでした。
研究グループは、網羅的なゲノム・スクリーニングを行い、この培養液を用いたときにだけES細胞内で強く働くZfp521という核内タンパク質を同定し、このタンパク質の働きで、ES細胞が神経前駆細胞へ分化することを初めて明らかにしました。さらに、血液や増殖因子などが、Zfp521タンパク質の発現を抑えて神経分化を低下させることや、たとえ血液や増殖因子などが存在してもZfp521タンパク質さえを発現させれば神経分化が効率良く進むことを発見しました。また、Zfp521遺伝子の機能を阻害したES細胞の場合、試験管内でも、マウスの胎児の中でも脳の神経細胞を産生できないことを証明しました。同時に、 Zfp521タンパク質が脳・神経細胞への分化スイッチを特異的にオンにする役割を果たしていることが判明しました。
この結果、謎であったES細胞・ iPS細胞からの神経分化の開始機序が分かり、脳疾患の再生医療への応用に必至な神経細胞の選択的産生技術やそれに伴う安全性の向上に貢献すると期待されます。
理化学研究所
発生・再生科学総合研究センター 器官発生研究グループ
グループディレクター 笹井 芳樹(ささい よしき)
2011年2月17日 独立行政法人 理化学研究所
/////////////////////////////////////////////
報道発表資料
ES細胞から神経細胞へ分化開始させるスイッチ因子を解明
−高選択性で神経細胞を産生させる基盤を確立、脳疾患の応用などに期待−
ポイント
•神経細胞への分化開始スイッチは、ES細胞で発現する核内タンパク質Zfp521
•Zfp521遺伝子の阻害は、ES細胞の神経細胞への分化だけを止める
•Zfp521タンパク質は複数の神経特異的遺伝子をオンにし、選択的に神経分化を誘導
要旨
独立行政法人理化学研究所(野依良治理事長)は、ES細胞やiPS細胞などの多能性幹細胞※1が神経細胞※2へと分化※3を開始するときに働くスイッチの制御機構を明らかにしました。理研発生・再生科学総合研究センター(竹市雅俊センター長)器官発生研究グループの笹井芳樹グループディレクターと上谷大介研究員らを中心とした研究グループの成果です。
ヒトや動物のES細胞・iPS細胞は、分化を起こしやすい条件で培養すると、神経細胞をはじめ、心筋細胞、血液細胞、網膜細胞などさまざまな種類の細胞に試験管内で分化していくことが知られ、再生医療などへの利用が期待されています。しかし、血清や増殖因子※4を含む培養液を用いた通常の培養方法では、こうした多種類の細胞が混在して産生されてしまいます。このため、疾患に関係した特定の種類の細胞を産生する培養条件を特別に工夫する必要があります。研究グループはこれまでの研究で、血清や増殖因子など、細胞へ刺激を与える物質を除いた培養液で培養すると、ES細胞・iPS細胞は自発的に神経前駆細胞※2や神経細胞へ効率よく分化(神経分化)することを明らかにしてきましたが、そのメカニズムは不明でした。
今回、網羅的なゲノム・スクリーニングを行い、血清や増殖因子などを除いた培養液を用いた場合にだけES細胞の中で強く働くZfp521という核内タンパク質を同定し、これが働くことで、ES細胞が神経前駆細胞へ分化を開始することを明らかにしました。また、血清や増殖因子などは、Zfp521タンパク質の発現を抑えて神経分化を低下させること、血清や増殖因子の存在下でもZfp521タンパク質さえ発現させれば、神経分化は効率良く進むことも発見しました。
さらに研究グループは、Zfp521遺伝子の機能を阻害したES細胞の場合、試験管内でもマウス胎児の中でも、脳の神経細胞を産生できないことを証明しました。一方、Zfp521遺伝子が働かなくても、脳以外の組織への分化は正常に起こったことから、Zfp521タンパク質が脳・神経細胞への分化スイッチを特異的にオンにする役割を果たしていることが判明しました。また、Zfp521タンパク質は、核の中でDNAに結合して、神経細胞への分化に必要な複数の遺伝子の発現を直接オンにする転写促進因子※5であることも明らかにすることができました。
今回の研究成果は、これまで謎であったES細胞・iPS細胞からの神経分化の開始機序を明らかにし、脳疾患の再生医療への応用に必須である神経細胞の選択的産生技術やそれに伴う安全性の向上に大きく貢献します。
本研究成果は、文部科学省の「再生医療の実現化プロジェクト」の一環として行い、英国の科学誌「Nature」2月24月号に掲載されるに先立ち、オンライン版(2月16日付:日本時間2月17日)に掲載されます。
背景
ES細胞やiPS細胞などの多能性幹細胞は、すべての種類の体細胞に分化する能力(多能性)を有しており、試験管内で医学的に有用な細胞を産生する提供源として注目を集めています。ある細胞種が生体内で変性するために起こる病気に対して、ヒトES細胞・iPS細胞から分化させたその細胞を自分自身に移植して治療しようとする再生医療は、難病克服の切り札として期待が寄せられています。例えば、研究グループはこれまでに、マウスやヒトのES細胞・iPS細胞から、中脳ドーパミン神経細胞、大脳神経細胞、網膜細胞、小脳細胞、視床下部内分泌細胞などに試験管内で分化誘導することに成功しており、パーキンソン病や網膜難病の治療を目指した前臨床研究を進めています。また、ES細胞などから神経細胞やその前駆細胞を効率よく分化させる方法として、無血清凝集浮遊培養法(SFEBq法)※6という簡便な方法を開発しています。この手法は、ES細胞やiPS細胞を分化誘導する際に、通常の細胞培養で添加する牛血清や増殖因子を除いた培養液で培養する方法です。ES細胞やiPS細胞は、中胚葉※7や内胚葉※7への分化には牛血清や増殖因子が必要であるのに対し、神経前駆細胞への分化には牛血清や増殖因子は不要で、むしろこれらの添加が抑制的に働くという特徴を持つことが分かったため、その現象を利用しています。
実は、この現象がES細胞・iPS細胞にとどまらず、広く脊椎動物の初期胚の未分化な細胞に共通したものであることが、過去十数年の発生学の研究から明らかとなっています。つまり、初期胚の未分化な多能性細胞は、分化する際に、外部から増殖因子シグナルなどの特別な刺激を受けずにいると、基底状態(デフォルト)として神経前駆細胞になる性質を持っています。これは、ES細胞やiPS細胞から脳などの組織を産生する際に非常に好都合で、SFEBq法の誘導効率が約9割と高いのもこの現象によるものです。
一方、なぜES細胞やiPS細胞などの多能性幹細胞の分化の基底状態は、多々ある細胞分化方向の中で、特に神経分化方向へセットされてしまうのかという疑問は、発生学や幹細胞生物学での大きな謎の1つでした。今回、研究グループは、システム生物学的手法を駆使して、この謎に挑みました。
研究手法と成果
(1)ES細胞の神経分化の開始時点で働く遺伝子のスクリーニング
マウスES細胞を用いて、ES細胞が神経前駆細胞へと分化する非常に初期の段階で活性化される(発現を始める)遺伝子を探索しました。具体的には、SFEBq法で3日間培養し、神経前駆細胞になったばかりの細胞と、未分化なままとどまっている細胞に対して、DNAチップ法による網羅的遺伝子発現解析※8を行い、神経前駆細胞へ分化した場合にだけ発現する遺伝子をスクリーニングしました。その結果、104個の遺伝子が神経分化に伴って発現量が増えていることが判明しました。それらの遺伝子のうち、神経以外の組織にはほとんど発現していなかった29個が、神経分化を制御している可能性が高いと研究グループは考えました。
(2)核内タンパク質Zfp521はES細胞の神経分化を強く促進する
これら29個の遺伝子を単離し、遺伝子操作でES細胞の中にそれぞれ1個ずつ強制的に強く発現させる実験を行いました。その結果、ES細胞の神経分化を亢進させる遺伝子が1個見つかり、それが核内に存在するZnフィンガータンパク質※9をコードするZfp521遺伝子であることを明らかにすることができました。
Zfp521遺伝子を強く発現させたES細胞は、高い神経分化の能力を発揮しました。例えば、通常のES細胞では神経分化を起こさないBMP4という神経分化阻害因子を含んだ培養液でも、Zfp521遺伝子を強制的に発現させたES細胞は、効率よく神経細胞へと分化することが分かりました。
(3)Zfp521タンパク質は動物やヒトのES細胞の神経分化開始に必須の制御因子
RNAi法※10を用いて、Zfp521タンパク質が細胞内で発現できないように遺伝子操作したマウスES細胞を作製しました。このZfp521遺伝子の機能を阻害したマウスES細胞は、通常は神経分化を誘導するSFEBq法でも、神経分化が誘導しませんでした。同様にヒトES細胞でも、Zfp521遺伝子は神経分化の初期過程で強く発現していましたが、RNAi法でZfp521遺伝子の機能を阻害すると、神経分化の効率が大きく低下しました。これらの結果から、Zfp521タンパク質は、動物およびヒト多能性幹細胞(ES細胞)の神経分化を開始するために不可欠な神経分化促進因子であることが判明しました。
一方で、Zfp521遺伝子の機能を阻害したマウスES細胞を、牛血清などを用いて中胚葉や内胚葉、あるいは表皮細胞などへ分化誘導させたところ、通常のES細胞と同様に効率よく分化が起こることが分かりました。従って、Zfp521タンパク質は、未分化細胞から神経前駆細胞を産生する分化だけに特異的に必要とされる因子で、他の分化の方向には関わらないことが明らかとなりました。
(4)Zfp521タンパク質は初期胚の発生においても脳の神経細胞の発生に不可欠である
Zfp521遺伝子の機能を阻害したマウスES細胞を、マウスの着床前胚である胚盤胞に注入してキメラ胚を作製※11しました。通常のES細胞を胚盤胞に注入して、その胚を着床させ発生させると、注入したES細胞はマウス胎児のすべての組織にほぼ均一に取り込まれて、それぞれの組織の細胞に分化しました。一方、Zfp521遺伝子の機能を阻害したマウスES細胞を注入したキメラ胚では、ES細胞は脳の組織には取り込まれず、脳の神経細胞への分化は認められませんでした。このキメラ胚のその他の組織は、Zfp521遺伝子の機能を阻害したES細胞から分化した細胞を含んでおり、ES細胞から脳への発生だけが起こらなかったことが判明しました。
これらの結果は、Zfp521遺伝子が、ES細胞が試験管内で神経分化を開始するために必要なだけではなく、胚の環境において、未分化細胞から脳組織が発生する初期段階でも必須の役割を果たすことを示しています。
(5)Zfp521タンパク質はDNAに結合し、神経特異的な遺伝子の発現をオンにする転写促進因子として働く
Zfp521タンパク質がどのように神経分化を促進するのかを明らかにするため、細胞核でのDNAとの相互作用を分子生物学的手法で解析しました。その結果、Zfp521タンパク質は、神経前駆細胞の分化開始後に強く発現する複数の遺伝子(Sox3、Pax6遺伝子など)のDNAに強く結合していることが分かりました。Zfp521タンパク質は、これらの遺伝子の位置に転写を活性化するp300というタンパク質を引き込んでくる働きをし、その結果、神経細胞に特有の遺伝子だけを活性化する(発現をオンにする)転写促進因子として機能することが判明しました。
今後の期待
本研究は、哺乳類の脳の発生を開始させる制御機構を初めて分子レベルで解明し、そのスイッチ因子がZfp521タンパク質であることを明らかにしました。哺乳類の初期発生を再現するES細胞やiPS細胞の分化においても、Zfp521タンパク質が働くことで神経分化を開始するスイッチが入ることが分かりました。「なぜ、胚の未分化細胞やES細胞などは、特定の増殖因子などの刺激を受けないと、基底状態(デフォルト)として、神経前駆細胞に分化するのか?」という長年の謎に対して、分化の過程でZfp521タンパク質が細胞内で自然に蓄積されるためであるという答えを明らかにすることができました。逆に、BMP4などの増殖因子シグナルが細胞に入ると、それらのシグナルがZfp521タンパク質の発現を阻害してしまい、神経分化の効率が低下することも分かりました。現在、研究グループでは、次の大きな謎「Zfp521タンパク質がなぜ自然に分化過程のES細胞の中で発現しだすのか?」を解くために、さらに分化のメカニズムを明らかにし、ES細胞やiPS細胞からさまざまな細胞が産生される制御機構を体系的に理解しようと解析を進めています。
研究グループがこれまでに開発してきたSFEBq法では、ヒトES細胞やiPS細胞から、約9割の細胞を神経前駆細胞に分化させることに成功しています。しかし逆を言えば、1割弱の細胞は、神経系細胞以外のものであり、こうした不純物の混入は、再生医療における細胞移植において、がん化や副作用などのリスクを増大させる可能性があります。今回の研究で、ES細胞・iPS細胞が神経系の細胞になるか、他の種類の細胞になるかをZfp521タンパク質の存在が決定することが分かり、今後、細胞中でZfp521タンパク質の発現を増やす培養条件を検討することで、さらに高度に選択的な神経細胞の産生を可能にし、再生医療の安全性の向上に貢献することができると考えています。
発表者
理化学研究所
発生・再生科学総合研究センター 器官発生研究グループ
グループディレクター 笹井 芳樹(ささい よしき)
2011年2月17日 独立行政法人 理化学研究所
※
1.多能性幹細胞脊椎動物の初期胚が持つ、全ての種類の体細胞へ分化する能力を多能性という。多能性を有し、試験管内で培養して未分化なまま無限に増やすことができる細胞を多能性幹細胞という。哺乳類の着床前胚(胚盤胞)に存在する多能性細胞(内部細胞塊)から作製した胚性幹細胞(ES細胞)は、最も典型的な多能性幹細胞である。マウス、サル、ヒトなどで樹立しており、マウスのES細胞を初めて樹立したマーチン・エバンス卿(英国)は2007年のノーベル賞医学・生理学賞を受賞した。そのほか、皮膚細胞などの体細胞にOct3、Sox2、Klf4遺伝子などを導入して初期化し、多能性を持たせたiPS細胞も人工的な多能性幹細胞である。これらの細胞は多能性を有しているため、体のさまざまな細胞に分化する能力があり、再生医療の材料としての利用が期待されている。
2.神経細胞、神経前駆細胞神経細胞は、一旦分化すると原則として分裂せず、形態的にも特長のある樹状突起や軸索などを持つ細胞である。神経細胞に最終分化する前の未熟な細胞で、細胞分裂をする能力を持つ細胞を神経前駆細胞と呼ぶ。
3.分化胚の細胞や幹細胞などの未熟な性格を持った細胞(未分化細胞)が、より特定の機能的な性格を持った細胞に変化すること。例えば、ES細胞が神経細胞に分化した、という表現がされる。
4.増殖因子細胞培養や生体内において、細胞の増殖を刺激するような活性を有する物質。多くの種類があるが、タンパク質であるものが多い。典型的な増殖因子は、BMP4、Wnt、Fgf、Activinなどである。増殖因子は、増殖刺激以外にも多様な生理活性を有しているものが多く、ES細胞などの幹細胞の分化の制御などでも多彩な機能を発揮することが知られている。
5.転写促進因子哺乳類のゲノムDNAの上には、3万個程度の遺伝子が存在し、細胞の種類ごとに決まった遺伝子が活性化されている。こうした遺伝子に直接働きかけ、活性化する働きを持つタンパク性因子を転写促進因子という。転写促進因子が結合した遺伝子のDNAからは、RNAが転写され、転写されたRNAからはその遺伝子産物であるタンパク質が合成される。
6.無血清凝集浮遊培養法(SFEBq法)Serum-free Floating culture of Embryoid Body-like aggregates with quick reaggregationの略。ES細胞などを酵素によりバラバラに分散させ、それを3,000個程度の細胞の塊に再凝集させたものを分化培養の材料に用いる。この細胞凝集塊を、血清や転写因子などの神経分化阻害効果のある成分を一切含まない特殊な培養液に浮遊させて数日培養することで、9割以上の細胞を中枢神経系の細胞に分化させることが可能である。
7.中胚葉、内胚葉胚の初期発生で多能性細胞が分化を始めると、最初に外胚葉、中胚葉、内胚葉の3つの胚葉組織が形成される。外胚葉は神経細胞や表皮細胞を生み出す能力を持ち、内胚葉からは消化管上皮、肝臓、膵臓、気道上皮などが発生する。中胚葉からは、血管、血液、筋肉、心筋、腎臓などが生じる。試験管内でのES細胞やiPS細胞の分化培養でも、基本的にこの分化経路は再現され、例えば神経細胞は外胚葉組織を経由して分化することが知られている。
8.DNAチップ法による網羅的遺伝子発現解析哺乳類のゲノムDNAの上にある3万程度の遺伝子の断片の1種類ずつを、小さな点として集積したガラスをDNAチップという。これを用いると、細胞の中でどの遺伝子がどの程度活性化しているかを一度に網羅的に調べることが可能である。この方法を用いて、今回は神経前駆細胞になった細胞ではオンであり、ES細胞などではオフである遺伝子を探索して、Zfp521遺伝子を同定した。
9.Znフィンガータンパク質Znフィンガーと呼ばれる亜鉛(Zn)に結合する、20個のアミノ酸配列からなるタンパク質。多くはZfp521タンパク質のように核内に存在し、転写などを調整する。Zfp521タンパク質はZnフィンガー配列の30回繰り返し構造を含んでいる。
10.RNAi法特定の遺伝子の機能だけを阻害する方法。特定の遺伝子のRNAに相補的な配列を持った短いRNA(short-hairpin RNA)を遺伝子操作により細胞内で合成させ、そのRNAからのタンパク質への翻訳を選択的に抑制することで遺伝子機能を阻害する。
11.胚盤胞への細胞注入によるキメラ胚作製ES細胞は、着床寸前の胚である胚盤胞に由来する幹細胞であり、逆にマウスの胚盤胞に注入すると、胚のいろいろな細胞に分化して多様な胚組織に組み込まれる。これは、元々の胚の細胞と、注入したES細胞の混ざり物となるため、「キメラ」胚と呼ばれる。この方法を用いると、ES細胞が胚発生の生体内環境でどんな細胞に分化することができるかを検討することが可能である。通常のマウスES細胞では、すべての体細胞および生殖細胞に分化できることが分っている。
©sasai(RIKEN, Japan.)
/////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////
(医療系単行本 タイトル覚書)
【再生医療を実現化する幹細胞のメディカルサイエンス stemnessと分化の制御、新規因子の発見から三次元組織形成など臨床につながる最新成果まで】
(第1章)幹細胞のサイエンス 分化と多能性のメカニズム Zfp521による多能性幹細胞の神経分化の開始機序(解説/特集)
Author:上谷 大介(名古屋大学 大学院理学研究科生命理学専攻細胞制御学グループ), 笹井 芳樹
Source: 実験医学 (0288-5514)30巻10号 Page1567-1573(2012.06)
Abstract:ヒトや動物のES細胞・iPS細胞は、分化を起こしやすい各種条件で培養すると、神経細胞をはじめ、心筋細胞、血液細胞などさまざまな種類の細胞に試験管内で分化していくことが知られ、再生医療などへの利用が期待されている。われわれはこれまでの研究で、血清や増殖因子などを除いた培養液で培養すると、自発的に神経前駆細胞へ効率良く分化することを明らかにしてきたが、そのメカニズムについては不明であった。今回、われわれは網羅的なゲノム・スクリーニングによって、血清や増殖因子などを除いた培養液を用いた場合にだけES細胞の中で強く発現するZfp521という核内タンパク質を同定し、これが転写活性化因子として働くことで、ES細胞が神経前駆細胞へ分化を開始することを明らかにした。(著者抄録)
MedicalOnlineより
2015年11月23日 10時57分
画:髄鞘をもつ末梢ニューロンの模式図(不正あり)
軸索にシュワン細胞が幾重にも巻き付くことによって髄鞘が形成されている。 シュワン細胞のすき間にはランヴィエの絞輪がある。
muon 2015-03-18/エンシ(``)ョウかもね より
。
『細胞「私」をつくる60兆個の力(NHKサイエンスZERO)』2011
-「NHKサイエンスZERO」取材班+近藤滋・笹井芳樹 編著
(「免疫は他者=細菌が鍛える」 P81〜)
「免疫寛容」 P84〜
(T細胞は他の免疫細胞が取り込んだ細菌の情報を得ようと 接触を試みるが Treg細胞は細菌を取り込んだ免疫細胞に素早く取りついて T細胞の邪魔をし 情報が得られないT細胞は その免疫能力を抑えられてしまう
他者を攻撃するはずの免疫細胞に 実はその反応を抑えるブレーキ役が存在する)
1995年 坂口志文博士-京都大学再生医科学研究所所長(現・大阪大学免疫学フロンティア研究センター)が
(概念だけでない)「免疫寛容」の存在を突き止めた
Treg細胞も腸内細菌-クロストリジウム菌 によって変化する
(本田博士が)無菌マウスにクロストリジウムを投与したとき
9%だったTreg細胞が3週間で36%と飛躍的に増加
「クロストリジウムは、非常にたくさんの代謝産物を産み出すことが知られています。食べ物を分解して代謝産物を生み出し、その代謝産物がTreg細胞の誘導に効果を発揮している可能性が高いと考えています」
クロストリジウムは人間が消化できない食べ物を沢山分解している腸内細菌
食べ物を分解したときに出る 代謝産物
それが腸を刺激して T細胞をTreg細胞に変化させるのではないかというのが本田博士の想像している流れ
体内に入ってきた他者を「徹底的に排除すればいい」という単純な関係でないことは明らか
(杓子定規に排除するわけにはいかない)
免疫システムがつくる自己と他者の境界も柔軟に 動的に対処する必要がある
(柔軟にして強靭な見張り役に育てるには実践的な訓練を経てつくりあげるのが有効)
(Th-17細胞やTreg細胞が誘導されるなど、免疫システムが腸内細菌との相互作用によって高度化されるのは、その象徴といえるでしょう)
その相互作用のおかげで、細胞の世界の境界は実用的な柔軟さを保ち、臨機応変に変わるものになっています。そして、境界が動くたびに、細菌(単細胞生物)は自己になったり、他者になったり、クルクルと立場を変えるのです。
ちなみに、Treg細胞を誘導したクロストリジウムは、あの伊藤博士が30年の奮闘を繰り広げた腸内細菌です。じつは本田博士の研究は、伊藤博士から愛蔵のクロストリジウムをもらって進めたものでした。
「46株のクロストリジウム菌を伊藤先生からいただいて、無菌マウスに飲ませると、ものすごく強力にTreg細胞が誘導されたので、非常にびっくりしました。伊藤先生のそういう基礎研究がなければ、私たちの研究も、5年、10年は遅れていたと思います」(本田博士)
「長年やってきたことが、新たな結果を得ることができたということで、うれしく思っています。我々の取り組んできた対象にどういう意味があるのかをさらに明らかにしてくれたわけで、非常に感謝しております」(伊藤博士)
アクセル役とブレーキ役が揃った免疫システム
他者である腸内細菌の助けなくしてはありえない
(その事実を日本人研究者たちのコラボレーションが明らかにした)
「細胞からみた脳の世界」 P87〜
(免疫システムが他者を自己として扱う例の逆)
免疫システムが自己を他者として扱う例
すぐに思い浮かぶのは「自己免疫疾患」
(免疫システムが自己である自分自身の正常な細胞や組織に対して 攻撃を加えてしまう疾患)
(関節リウマチや膠原病)
「自己を他者と勘違いしてしまう」
免疫システムの「誤作動」のほかに
「自らの細胞や組織を攻撃する」ことがある
いま注目を集めているのは 脳のなかの免疫システムの働き
細胞のもつ自立性や相互作用の力が脳の世界独自の形で発揮されている
脳にある細胞 神経細胞はいったんできあがると 分裂をしない長寿命の細胞(体細胞としては例外的な存在)
多細胞の場合、体をつくる細胞(これが体細胞です)は代謝によって置き換わっていきます。
(古くなったり、傷ついた細胞はアポトーシス(細胞死)を起こして、その変わりに細胞分裂によって新しい細胞が補われます。体の部位によって置き換わる平均的な日数は長短ありますが、皮膚細胞は28日のサイクルで、古い皮膚細胞は垢となって剥がれ落ちていきます)
神経細胞と心筋細胞は 例外で…
ほとんど新たな補充はなく、一度生まれた細胞がずっと生きつづけます。人間の場合は、100年を超える寿命をもっているということになります。
皮膚細胞の1か月足らずという短命に比べると 雲泥の差
その一方
神経細胞でできた脳を使って 学習・記憶などする
「神経細胞は一部が変化することで 脳全体の柔軟性を生んでいる」河西春郎博士/東京大学大学院医学系研究科教授
脳内部に張りめぐらされたネットワークをつくる神経細胞は ひとつひとつがさまざまな方向に樹状突起を出している
わずか1ミクロンのトゲ
-スパインがたくさん並んでついている
スパインは ほかの神経細胞とつながる接合部
シナプスを形成している
スパインに起きる変化に注目した河西博士
「じつは、このスパインは記憶を保存していると考えられます。スパインは大脳の神経のネットワークの要なんです」
この小さなスパインが、記憶とどう関わっているのか、そのメカニズムの解明に活躍したのは最新の2光子顕微鏡です。マウスの脳の神経細胞に、あらかじめ蛍光色素を仕込んでおき、ある波長の赤外光を当てると、蛍光色素が発光します。その光を2光子顕微鏡で捉えることで、生きたマウスの脳の神経細胞を、直接リアルタイムで観察できるようになりました。さらに2つの光子を同時に蛍光物質に当てる特別な光学技術を用いて、これまで以上に、組織の表面だけではなくその内部深くまでみることができます。生きたマウスの神経細胞の観察では、直径約10ミクロンの樹状突起が根のように深い部分までつながっている姿まで確認できます。
体積の増加は一時的な記憶であると河西博士
「スパインというのは、その記憶にとって1ピクセルにあたる記憶素子だと考えられます。あることを経験すると、その情報は信号になってネットワークに伝わります。その刺激でスパインはすばやく変化し、記憶を一時的に蓄積していると考えられるのです」
脳は さまざまな刺激をスパインにメモリさせることにより 記憶を蓄積している
(マウスの脳組織を取り出し 一週間生かし スパイン観察-河西博士)
スパインの変化はきわめて活発
(2〜3日のあいだに 無かったスパインが生まれたり
反対に しっかりあったスパインが消えたり)
新しい記憶をどんどん蓄積する一方
不要となれば消される運命
その柔軟な仕組みが脳の機能を支えている
「私たちが観察していたのは、1個の神経細胞のスパインなんですけれども、実際には、まわりじゅうたくさんの神経細胞のたくさんのスパインに囲まれています。だから新しい記憶をつくるために、新しいスパインをつくるには、無駄なスパインを取り除く必要があります。この積極的な切り捨てが、よりよい脳のネットワークを生むのです」河西博士
一度生まれたら死ぬまで細胞分裂しない神経細胞は、スパインをつくったり、消したりすることによって、脳に記憶を蓄積するという高度なシステムをつくりあげたのです。
このシステムのなかで、私たちは改めて細胞の自主性をみることができます。後天的な経験をDNAに反映することは基本的にできません。その対応は、神経細胞という現場で自主的に行われているのです。
P93〜
「免疫が担う自己の形成 …脳のなかの免疫細胞」
(学び 記憶するという機能の根底に 神経細胞という現場で起きるスパインの消滅がある)
長い時間の変化での 神経細胞の対応
脳の免疫システムが重要な役割をはたしている
マウスを使って 脳が成長に伴ってどのように変化していくのかを研究している 鍋倉淳一博士(愛知県岡崎市 生理学研究所/生体恒常機能発達機構研究部門教授)
脳の免疫細胞として知られ 「脳のなかのお医者さん」と呼ばれる 「ミクログリア細胞」
2009年に鍋倉博士たちのグループは その「お医者さんぶり」を示す映像を発表し 世界の注目を集めた
ミクログリア細胞は脳卒中や脳血管障害で傷ついたとき働くとされ、特に不要となったものを取り除く役割をはたしていると考えられていました。
(実態はわからないままだった)
鍋倉博士たちは 独自に改良した2光子顕微鏡を用いて「ライブ映像」の撮影に世界で初めて成功した
その様子はまさに、お医者さんの行う触診のようでした。ミクログリア細胞は神経細胞のつなぎめであるシナプスに近づいては、触手のセンサーを伸ばし、その健康状態をチェックしていたのです。その頻度は通常、1時間に1回、正確に5分間でした。その過程を博士たちは
「まるでシナプスに聴診器をあてるように先端をふくらませて異常がないか“触って検査”」していたと報告しています。
このミクログリア細胞による検診は、脳梗塞などのために障害を受けると、より慎重なものに変わります。じつに1時間以上、シナプスの健康状態をチェックすることになります。
その触診は「精密検診」だ と 鍋倉博士たちは表現した
その後の進み具合をみると 「最後通牒」のようでもあり
「しばしばミクログリア細胞による“精密検診”のあと、あたかも修復が困難であると判断したかのようにシナプスが消えてなくなる」というのです。免疫細胞としてミクログリア細胞が貪食した可能性が指摘されています。
(そのときの発表は 脳神経が障害を受けたケースを中心にしたもの)
(脳の発達段階でも同じようにミクログリア細胞が働いている可能性が指摘された)
「発達段階のケースは 大人用のネットワークに切り替えていくための回路の「つなぎ換え」である」と鍋倉博士
(「つなぎ換えというのは、一生分裂しない神経細胞にとって脳機能を維持する、または脳の機能を変えていくための重要な過程と考えています(略)」鍋倉博士)
鍋倉博士たちの研究で非常に興味深い点は
「自己」の形成が脳の免疫システムを担う細胞に大きく依っているということ
ミクログリア細胞による 健康か否かという判断基準での選別
(回復できないとなれば そのシナプスは他者の地位へと転落し 免疫によって攻撃される対象となる)
成長していくにつれ 未来は少しずつ限定されていき
選択した生き方において特に必要なものも はっきりしていく
もはや無限の可能性を優先する段階ではない
この段階においておそらく、ミクログリア細胞の選択基準として、「健康か否か」に加えて、「必要か否か」が重要になっていくと考えられます。
必要性が確かなシナプスは保護される一方、不要と判断されたシナプスは、脳の免疫細胞であるミクログリアの攻撃対象になるのです。細胞の免疫システムがあたかも他者と判断したかのようです。
それまでは間違いなく自己であったものが一転して
他者になる…
…細胞世界の境界がもつ動的な一面の如実な表れ
排除されたシナプスは、まったく違う人生の選択をしたとき、大切にされていたのかもしれません。違う人生を歩むなかでは、排除されたほうこそ、自己であったのかもしれません。
それは偶然のようにもみえます。少なくともはっきりといえるのは、私たちの個のありようは、すべてが決定論的に決まっていたわけではないということです。決定論的な要素はあっても、その場その場の自主的な選択が新たな流れをつくっていくということができるでしょう。
選択次第で自分自身が変わる、本当の自分も変わる …そんな人生の機微を、自己と他者が能動的に移り変わる細胞の世界は教えてくれているのです。
。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。
マウスの脳での実験 …結果
「私たち」というのは?
現場でも 入り込み方などが半端ではなくて
自(ヒト)他(マウス)の境界が 動的なのかもしれない
と この(薄い)書を開いていて よく浮かぶ
マウスの記憶の更新・蓄積は どのような感じなのだろう
誰かデータを持っていたりするのだろうか
。
「週はじめ」の求人に
「T大 技術補佐員」 というパート募集が載っていて
「資格」は「自宅等で動物の飼育を行なっていない方」 とのこと
弥生1の1の1 か
研究動物(マウス等)の管理・ゲージ等の清掃…
個人的には関わりがない カカワルコトハナイ
この「段階」は……
もはや… 「必要か否か」の世界だろうか
離れられない 両者 なのだろうか
2015年7月27日 16時49分
『細胞の運命を決める機械的な力』
-Stefano Piccolo
遺伝子だけでなく,物理的な力が細胞の運命を左右し
その細胞が骨になるか筋肉になるかを決めている
場合によっては致命的な腫瘍になることもある
〜組織が適切に再生するにはYAP/TAZが“適量”になっていなければならない
少なすぎると傷を治せず
多すぎるとがん化のリスクを生じる〜
(幹細胞や再生医療の研究者は
傷ついた組織を再生する方法を模索している
一方でがん研究者は
細胞増殖を抑えるという正反対の課題に取り組んでいる
ここでも細胞にかかる物理的な力が重要になるだろう)
*臓器を形作る力*
生物医学の分野で幹細胞が注目されてきたのは,様々な細胞に分化できる能力があるからにほかならない。幹細胞をうまく誘導すれば,傷ついた組織を修復・補填したり,交換用の臓器を作り出すこともできると期待されている。しかし幹細胞を活用するには,それらが物理的な力にどう反応するかを理解しておく必要がある。
例えば筋肉に分化する幹細胞を利用すれば,筋ジストロフィー患者の弱った筋肉を強化できる可能性がある。だが治療に使うには大量の幹細胞を体外で培養する必要がある。スタンフォード大学のブラウ(Helen Blau)は,幹細胞を普通の筋肉と同じ硬さに合わせた材質の上で育てた場合に初めて,そうした大量培養が可能になることを示した。
体外で新たに臓器を作るというSFじみた話が現実味を帯びつつあるが,この現実も物理的な力が細胞の挙動を変える仕組みを理解することにかかっている。SF映画『ブレードランナー』では眼が容器の中で作られた。これまでに,理化学研究所の笹井芳樹らは,最初は同一な幹細胞を軟らかな細胞外マトリックスに浮かべて培養し,立体的な網膜組織を作り出せることを示した。球状の細胞塊がある程度の大きさになると細胞層が自動的に折りたたまれて凹み,生きた折り紙のごとく機械的に自己組織化して眼のような構造になる。
この現象は、シャーレの平らな壁から細胞を離して力学的な制約を受けないようにした場合にのみ起こる。こうすると細胞に内在するプログラムが作動し,折りたたみや伸展,ここは硬くあそこは軟らかくといった調整など,一連の機械的工程が進むのだ。
イングバーらが最近発表したいわゆる「臓器チップ」も,こうした物理的な刺激に反応する。細胞をシャーレで培養するのではなく,流体によって微小な圧力をかけられるごく小さな容器を用いる。圧力を高精度で調節できるようになっていて,実際の組織で生じているのと同様の特有の負荷を細胞に与えられる。
イングバーらは肺細胞に呼吸の際に生じるような加圧と減圧を繰り返し加えたり,消化管の蠕(ぜん)運動をまねて腸細胞を伸縮させたりした。こうして体内の自然なリズムと圧力を再現すると,それまで眠っていた未分化の細胞塊が予想外の挙動を示した。一部の細胞が臓器に似た構造に自発的に変わったのだ。
組織が幹細胞の数を調整するのにYAP/TAZの機械的調節を使っているなら,このスイッチで幹細胞を必要なだけ増やせるかもしれない。幹細胞は組織のすみにあり,へりや出っ張り,中空チューブの底など,ほかとは力学的に異なる特別な場所にだけ存在する。これら限られた特殊な場所が,細胞に「幹細胞性」(自分自身を増やしつつ様々な種類の子孫細胞を生む能力)を付与しているのかもしれない。これらの場所のいくつかでは幹細胞の核内YAP/TAZの量が多く増殖能が高くなっており,場所がYAP/TAZの量に影響を与えていると考えられる。
体内のこうした場所に似せた環境を人工的に作ることで,希少な幹細胞集団を実験室で増やせるようになるだろう。近い将来,YAP/TAZの活性を高める薬剤を使って生体組織中の幹細胞を操作できるようになるかもしれない。あるいは活性を下げる薬剤で細胞増殖を止め,特定の組織に必要な細胞に分化させられるかもしれない。
だが,幹細胞を使った治療法には負の側面もある。幹細胞が望みの組織に分化せずに増殖を続けたら,効果がないどころか危険だろう。がん細胞の中でもとりわけ厄介な「がん幹細胞」はそんな挙動を示す。こうした懸念もあって,私たちメカノバイオロジー研究者の多くは,治療として患者に幹細胞を注入する今後の試みでは,その幹細胞が必ず適切な物理的環境に行き着くように保証する必要があると考えている。環境から間違った力を受けると注入された幹細胞が誤った道を進み,望まない細胞に分化したり,がんのように増殖する恐れがある。
***** ***** ***** ***** *****
【細胞の特性が変わる仕組み】
細胞ではYAP/TAZというタンパク質のペアが細胞増殖を制御している。YAP/TAZの動きは細胞にかかわる圧力や張力の影響を受ける。この力の変化は,コラーゲンなどの繊維でできた細胞外マトリックスの張り具合を通じてYAP/TAZに伝わる。これらの繊維は細胞膜を貫通するインテグリンというタンパク質を介して,アクチンなどの繊維で構成される細胞骨格とつながっている。著者らの研究によると,アクチンは阻害分子(金色の三日月)を擁しており,アクチンがたるむとこれが解き放たれて,YAP/TAZの活性を抑える。
*つぶれた細胞*
細胞が密集していると,周辺の細胞外マトリックスや内部の細胞骨格の繊維がたるむ。これによって阻害分子が解き放たれてYAP/TAZに結合するようだ。阻害分子が結合するとYAP/TAZは核に移行できず,細胞の挙動を制御する遺伝子を活性化できない。
*伸びた細胞*
細胞が広がる余地があるとき,阻害分子はピンと張った細胞骨格のアクチン繊維に拘束されている。このためYAP/TAZは自由になって核に入り,他の分子とともに細胞分裂や組織の再生にかかわる遺伝子を活性化する。
***** ***** ***** ***** *****
(古代ギリシャの哲学者アリストテレスは,形をあらゆる生ける実体の魂であると考えた。細胞生物学者は形の奥深い役割を現代的な観点から理解し始めている。形は細胞が臓器を形成・修復する一方で,健康を脅かすこともあるのだ。)
形の力について理解を深めていけば,それをコントロールして役立てることができるだろう。
(編集部 訳)
『細胞の運命を決める機械的な力』
-日経サイエンス*2015.7
S.ピッコロ Stefano Piccolo
伊パドバ大学教授 分子生物学
細胞生物学 原題“Twists of Fate”
(SCIENTIFIC AMERICAN October 2014)
*
「望みの組織」
そこで「操作」する(される)ことで達成可能なのか
「治療」(行為)することなのか されたいのか
同様な物事を(体)内で行うのか
…というあたりでも ややこしさが続くのか
あるいはシンプルさに向かうのか
「鏡」を眺めて逆の世界を続けるのか ということも
好みの問題なのだろう
2015年7月3日 16時36分
遺伝子だけでなく,物理的な力が細胞の運命を左右し
その細胞が骨になるか筋肉になるかを決めている
場合によっては致命的な腫瘍になることもある
-S.ピッコロ
(「細胞骨格とマトリックスは常に綱引き」
例えば周辺のマトリックスが歪むと
細胞外側の接続部位が引っ張られ
逆らわなければ細胞は伸びてしまうだろうが
細胞は張力に対して同等の力で内側に収縮し 細胞骨格を再構築する
その調整作用が細胞の形を安定化しているが
それは「明らかに動的な過程」
加わる力のパターンが変化すると細胞はすぐにリセットされ ついには細胞全体の形が変わってしまうだろう)
(1970年代後半から)
細胞の構造に影響を与えている力の信号が
細胞分裂(増殖)の制御に不可欠であることが認識され始めた
イングバー Donald Ingber
-ハーバード大学ヴィース生体模倣工学研究所 と
ワット Fiona Watt-ロンドン大学キングスカレッジ は
スライドグラスに細胞外マトリックスの粘着性タンパク質を点状にプリントし
そこに細胞を貼り付けることで細胞の形を変える方法を開発した。
まったく同じ細胞を狭いところに置いた場合には丸くなって分裂をやめ,遺伝プログラムが切り替わって,特殊化した細胞に分化したり死んだりした。
それらの発見は大きな注目を集めたが 欠けている部分があった
物理的な力が細胞の増殖や分化を制御するには,まず細胞核にあるゲノムに作用して増殖や細胞死をつかさどっている遺伝子を活性化しなければならない。
物理的信号を生体反応につないでいるものは何だろう?
細胞に加わった力がどのようにして,完璧に調和のとれた遺伝子活性の変化に翻訳されるのか?
(5年前,私たちの研究室のデュポン(Sirio Dupont)は,正統的な手法でその手がかりを探し始めた)
遺伝子データベースを検索し 機械的力を受けて活性化する遺伝子(細胞が引っ張られたときに活動を始める遺伝子)を探し
それらの遺伝子の制御に関与しているタンパク質を探した
それが「YAPとTAZ」
(YAPとTAZが実際にスイッチとなって物理的な力を細胞の反応に変えていることを実験で確認)
細胞内で作られるYAPとTAZの量を実験的に増減したところ
細胞がどんな形を取っているかによらず
その挙動をコントロールできた
*スイッチの働き*
YAPとTAZは通常,細胞質に存在しているが,細胞骨格が引き延ばされると核に移動し,DNAの決まった場所に結合して,細胞増殖を促す特定の遺伝子を活性化する。
YAPとTAZの量が増えると,核に移動して活動するものが増える。
逆に窮屈な場所に閉じ込められた丸い細胞では,YAPとTAZは細胞質にとどまったまま劣化していき,核には移動しない。
YAPとTAZは名前こそ違うが同種のタンパク質だ。分子構造がよく似ていて機能も重複している。そのため通常,ひとくくりにしてYAP/TAZと呼ばれている。
*臓器の形が維持されるわけ*
組織や臓器におけるYAP/TAZの働きを調べた研究から,このスイッチが身体機能の維持に重要な役割を果たしていることが明らかになってきた。
例えば切傷などにより細胞が失われると
残った細胞にかかる圧力が下がり 空きスペースがあることが伝わり
細胞が広がって大きくなっていき
細胞骨格が伸びた状態になり
それによってYAP/TAZが活性化し 細胞分裂が進むようだ
損傷部位が新しい細胞で埋まり,増殖を抑える窮屈な環境が整うと,このプロセスは止まる。
(その一連の過程が実際の組織でどのように機能しているかを示した実験)
大腸炎で傷んだ腸の内側の細胞層の再生にYAPが役立っていることをマウスの実験で実証した
-パン(Doujia Pan)ジョン・ホプキンズ大学
心筋梗塞の後にYAP/TAZが一部の心筋の再生を促すことを示した
-オルソン(Eric Olson)テキサス大学南西医療センター
遺伝子操作で皮膚細胞のYAPを過剰にしたマウスでは 皮膚の表層が分厚く 層が異常になることを示した
-フックス(Elaine Fuchs)ロックフェラー大学/カマルゴ(Fernando Camargo)ボストン小児病院
組織が適切に再生するにはYAP/TAZが“適量”になっている必要があると考えられ
少なすぎると治癒できず 多すぎると異常な組織が集積してがん化のリスクを生むだろう
(略)
臓器はぎゅうぎゅう詰めの集合住宅のようなもので,様々なタイプの細胞群が見事な立体構造の中に収まっている。
(略)
臓器の造りは複雑
それを形作るくぼみやへり 凸や凹の面 平らな層 と
様々な構造は いずれも 細胞外マトリックスの足場のどこに細胞が配置されるかで決まる
(足場はそこに乗っかっている細胞よりも実際に長生きで
新たに補充されてくる細胞のための空間的位置を記憶したメモリーとなり
それが「どの細胞をどこに」という問いに対する答えとなる)
(足場がそれを どうやってこれを実行しているか)
ネルソン(Celeste Nelson/プリンストン大学)とチェン(Christopher Chen)は
(S.ピッコロ研究室の)アラゴーナ(Mariaceleste Aragona)とともに 足場の多様な形に答えがあることを示した
足場の形の違いによって異なる力が発生し
それが細胞の挙動に影響する
例えば私たちが自作装置で細胞層を特定箇所で曲げて凸凹にしたところ(道路の減速バンプの出っ張りのようなイメージ),凸部で広げられた細胞だけでYAP/TAZが活性化し,増殖した。
その発見から 組織のその場その場の構造がYAP/TAZの活性に影響を与えることで細胞の挙動を制御していると考えられた
活性化して核に移行するYAP/TAZの量は,組織が湾曲・伸展した領域で最も多く,平らで細胞が密に詰まった層では少ない。
そのようにして組織の造りが鋳型となり
そこで細胞が入れ替わることで 臓器の形がずっと維持される
細胞自身が臓器の形を覚えているのではなく鋳型が記憶しているのだ
細胞の周辺環境に対するYAP/TAZの反応から
別の問題の答えも見えてきた
臓器が成長を停止するタイミングをどのようにして知るのかという謎
(私たちがYAP/TAZに物理的な力を核に伝える働きがあることを発見したとき,これらはすでに大きな注目を集めていた
これらの活性が通常よりも高い動物では臓器が巨大になることが観察されていたからだ)
組織の造りがYAP/TAZの活性に影響すること,そして臓器が成長するにつれて物理的な力が変わることから,私たちは臓器が適切な大きさに達すると力のバランスがとれてYAP/TAZの活性が下がり,成長が止まるのではないかと考えた。
物理的な力に影響して細胞の運命を左右するのは臓器の造りだけではなく
細胞が接する“地盤”の違いも影響する
実際 細胞を固定している細胞外マトリックスは一様ではなく 質感が異なる
例えば骨などの組織のマトリックスは岩のように硬くて密なのに対し
脳組織や脂肪組織ではずっと軟らかい
つまり 臓器ごとにマトリックスの性質は特有なものになっている
これらの特徴が,臓器の発達と再生において決定的な役割を果たしているとみられる。
特に,臓器のこうした機械的特性の違いは「間葉系幹細胞」という非常に重要な細胞の分化を制御している。
この幹細胞は成体の多くの臓器にあって損傷組織の修復に寄与しており,骨や脂肪,神経,筋肉など実に様々な細胞に分化できる。
(研究者は長年,間葉系幹細胞がどの細胞に分化するかを決めているのは修復場所で接する種々の化学物質だと考えていた)
(だが2006年)
ともにペンシルベニア大学にいたエングラー(Adam Engler)とディッシャー(Dennis Discher)はCell誌に発表した論文でこの考えを打ち砕いた。
彼らはいくつかの組織に合わせた特有の硬さの人工マトリックスを作った
間葉系幹細胞はこれらの異なるマトリックスの中でカメレオンのような変化を見せ
脳の硬さに合わせたマトリックスの中では神経に
筋肉の硬さのマトリックスの中では筋肉に変わった
(間葉系幹細胞のYAP/TAZは活性がマトリックスの硬さによって変化することを発見-デュポンがパドバ大学で再現実験)
マトリックスが非常に硬いとYAP/TAZは活性が高まり
間葉系幹細胞を骨になるよう導く
軟らかな環境では全体量と活性が下がり
間葉系幹細胞を脂肪細胞に変える
(実験的にYAP/TAZの量と活性を操作して,間葉系幹細胞を“だます”こともできた。軟らかなマトリックス中の間葉系幹細胞(そのままだと脂肪細胞になる)に改変したYAP/TAZを導入すると,硬いマトリックス中にあるかのように振る舞い,脂肪ではなく骨になったのだ。)
『細胞の運命を決める機械的な力』
-日経サイエンス*2015.7
細胞生物学 原題“Twists of Fate”
(SCIENTIFIC AMERICAN October 2014)
-S.ピッコロ Stefano Piccolo
伊パドバ大学教授 分子生物学
***
イガタねえ…
「組織の造りが鋳型となり」
「臓器の形」を記憶しているのは「鋳型」
このページなどで 度々…
人名を刻むときに
「質感」(シッカン?)「足場」「地盤」「鋳型」(組織イメージ)が浮かんでいたような……
「活性化して核に移行する」バランス
…「適量」
これは あまりにも…(「地盤」「足場」(「質感」)「硬・軟」…など)
…多様なのでは と感じ
「多」「少」の
「多」は さほど… 殆ど
=「密」という点くらい
「少」の「平ら」で「密」(気味)は
別面… 別層…
なんだろう……
(言葉は出なくとも……常に湧いているようなカンジ)
* * * * *
「鋳型(ねえ)」と 仰るか? それとも… ?
笹井 芳樹(1962年(昭和37年)3月5日 - 2014年(平成26年)8月5日)は、日本の発生学者、医学者。-Wikipedia
「理研はクビにもしてくれない」母親に愚痴ってた笹井芳樹氏…野依理事長ら幹部の退任ないのか!(2014/8/14 16:43)(より 一部)
四面楚歌に陥った笹井氏を最後に追い詰めたのは、7月27日に放送されたNHKスペシャル「調査報告 STAP細胞 不正の深層」だったという指摘があると週刊朝日も書いている。
理研関係者が、笹井氏は放送後かなり滅入っていて、あれが引き金だったんじゃないかと語っている。理研改革委員長の岸輝雄・東大名誉教授はこう指弾する。
<「こうした事態を招いた理研の責任は重い。一連の提言は野依良治理事長が決断すればすぐに実行できたはずなのですが、あまりにも対応が遅かった。組織を守る気持ちはわかりますが、ある種の怠慢であり、謙虚さに欠けていたと感じざるをえません。もはや理事長も含めた幹部の退任まで考えないと、世間は納得しないのではないでしょうか」>
…などなど 1日に軽い検索を経て 近隣の収蔵物を予約
上記の誌は あと1ページくらいか…というときに
氏の名が登場し そちらが個人的には本筋かもしれず
中断してムカウことに → 「細胞社会」のもつ「自主性」「根源的な力」 ?
2015年7月2日 17時19分
『細胞の世界』2O05
ベッカー / クレインスミス / バーディン 著
村松正實 / 木南凌 監訳
「細胞外マトリックスと細胞壁は細胞にとっては外界である」
細胞膜を通じて細胞が外に出した物質によって形成される細胞外構造の影響によっても ほとんどの細胞はその特徴が変わってくる
動物細胞にとって そのような構造は 細胞外マトリックス-extracelluar matrix(ECM)とよばれ
主にコラーゲン線維とプロテオグリカンからなる
植物細胞にとっては細胞外構造というのは硬い細胞壁-cell wallであり
これは主にセルロースミクロフィブリル-cellulose microfibril が他の多糖類と少量のタンパク質を含む基質に埋め込まれた構造をしている
動物細胞と植物細胞のその違いは 真核細胞の大きな2つの範疇の生活様式の違いに対応している
植物は基本的には運動しない
これは細胞壁が生物にあたえた硬直性と矛盾しない生活様式である
動物はふつう 運動能力がある
食物を探すのに必要であるのみならず 他の生物の食物になることから逃れるためにも必須の形質であるから
細胞は硬い細胞壁に包み込まれないで 弾力性のあるコラーゲン線維の網状構造に囲まれている
動物細胞の細胞外マトリックスの構造は細胞の種類によって種々様々
ECMの第1の機能は支持機能だが 種々の細胞外物質のうちのどれが どのように蓄積しているかによって
細胞の運動性と移動 細胞分裂 細胞の認識と接着 胚発生のときの分化などの多様なプロセスが調節されている可能性もある
動物の細胞外構造の主な成分はコラーゲン線維とそれを取り巻くプロテオグリカンの網状構造であり
コラーゲンは一般に不溶性の糖タンパク質の集まりで 大量のグリシンと 水酸化型のリシン およびプロリンを含む
脊椎動物ではコラーゲンは腱 軟骨 骨に非常に豊富に存在するので動物体内で一番多いタンパク質である
(植物細胞の細胞壁の2つのタイプ)
細胞分裂のとき壊される細胞壁は一次細胞壁 primary cell wall とよばれ,主にゲル様の多糖類の基質の中に埋め込まれたセルロースフィブリルからなる。一次細胞壁は柔軟性も伸展性もあるので,細胞が大きくなったり,伸びたりするのに応じて幾分かは伸展できる。細胞が最終的な大きさと形になると,一次細胞壁の内面に細胞壁をつくる物質がさらに蓄積して,一次よりもはるかに厚く,もっと硬い二次細胞壁 secondary cell wall の形成が可能となる。二次細胞壁は通常一次よりも多くのセルロースを含み,木材の主な成分であるリグニン lignin を高濃度に含むことがある。二次細胞壁が沈着すると細胞はほとんど伸展性がなくなるので,細胞の大きさと形が最終的にきまることになる。
隣同士の植物細胞は細胞壁で隔てられているが,実際は多くの原形質連絡 plasmodesma(複数形は plasmodesmata)とよばれる細胞壁を貫通する細胞質間の橋によって結ばれている。細胞間を結ぶチャンネルの内面は細胞膜で裏打ちされているので,隣接する細胞同士の細胞膜は連続しているといえる。典型的な原形質連絡の直径は水や低分子の溶質を細胞の内外に自由に通すのに十分な大きさがある。植物細胞のほとんどはこのように相互に結ばれている。
動物細胞もまた相互に通信することができる。しかし動物細胞にあるのは,原形質連絡ではなく,隣接細胞の細胞質の間で物質の輸送を専門とするギャップ結合 gap junction とよばれる細胞間結合である。他に2種類の細胞間結合があるが,これらも動物細胞に特有である。密着結合 tight junction は隣接する細胞をがっちり保持するので,細胞と細胞の間隙を通っての物質の移動は事実上阻止される。固定結合 adhesive junction も隣接する細胞を結びつけるが,その目的は結合によって頑丈かつ柔軟性のある細胞のシートをつくることにある。
ほとんどの原核生物も細胞壁とよばれる細胞外構造に取り囲まれている。しかし,細菌の細胞壁はセルロースではなく主にペプチドグリカン peptidoglycan からなる。ペプチドグリカンは,アミノ糖であるN-アセチルグルコサミン N-acetylglucosamine(GlcNAc)と N-アセチルムラミン酸 N-acetylmuramic acid(MurNAc)を含む繰り返し単位からなる。さらに,細菌の細胞壁はほかにも多様な成分を含むが,そのなかには細菌を構造によって分類したとき,それぞれの種類に特有なものがある。そのような特徴の有無はGram染色 Gram stain に対する反応によって明らかとなる。Gram染色は,これを考案したデンマーク人の細菌学者 Hans Christian Gram にちなんで名づけられた。細菌の菌体をクリスタルバイオレットとヨウ素の溶液で染色した後,アルコールまたはアセトンで脱色すると,Gram陽性の細菌は脱色されないで,濃青色のままであるが,Gram陰性の細菌は迅速に脱色される。
Gram陰性の細菌の細胞壁に特有の成分としてはリポ多糖類 lipopolysaccharide やリポタンパク質 lipoproteinなどがある。Gram陽性細菌のみにみられる化合物にはテイコ酸 teichoic acid がある。これは炭素数が3つもしくは5つのアルコール(それぞれグリセロールとリビトール)がリン酸基によって結合したポリマーが骨格となる構造をしている。
2015年6月7日 20時19分
『ミトコンドリアが進化を決めた』2007 ニック・レーン
体のなかの対立 (277)
一個の細胞が体の集中管理から抜け出し
細菌のように増殖する
必ずとは限らないが たいていガンは遺伝子の変異により発生する
変異がひとつだけでは めったにガンにはならない
細胞は通常、かなり特殊な遺伝子に8個から10個の変異が蓄積して初めて悪性細胞になり、そのとたん、身体の利益よりみずからの利益を優先させるようになる。
ガンを引き起こすには特定の組み合わせが必要で
主にガン遺伝子とガン抑制遺伝子という2種類の遺伝子に変異が起きなければならない
(どちらも正常な「細胞周期」-体内で出されるシグナルに反応して細胞が増殖したり死んだりする過程-を制御するタンパク質のコードを指定している)
ガン遺伝子の産物は ふだんなら特定の刺激に反応して(感染死した細胞の代わりを用意するためなどに)細胞分裂を命じるシグナルを送るが
ガンではそのシグナルのスイッチが「オン」になりっぱなしになる
反対に ガン抑制遺伝子の産物は通常
細胞分裂の暴走にブレーキをかける役目を果たす
増殖を命じるシグナルを取り消して
細胞を活動停止にするか 自殺に追い込む
ガンの場合 ガン抑制遺伝子のシグナルのスイッチは
えてして「オフ」のままになる
(ガン化した細胞は もはや体の命令に対して正常に反応せず 増殖して腫瘍を形成)
それでも良性腫瘍と悪性腫瘍のあいだにはまだ大きな開きがあり
ガンが広がるには ほかにも多くの変化が起きなければならない
まず 腫瘍が直径数ミリメートル以上に成長するには栄養が要る
腫瘍の表面からゆっくり栄養を吸収するのではもう足りない-内部への血液供給が欠かせない
そこで血液供給を得るべく、しかるべき化学的なメッセンジャー(成長因子)を適切な量だけ作り出して、腫瘍内部への血管形成を確保しないといけない。さらなる成長を遂げるには、周囲の組織を消化し、腫瘍が侵入するスペースを確保しないといけない。
そのため腫瘍の細胞は、組織の構造を破壊する強力な酵素をまき散らすことになる。ガンで最も恐れられている段階は、体のどこかに離れた場所に飛び移ること―「転移」―ではなかろうか。それに求められるのは、互いに相反した特異な性質だ。
転移する細胞は、腫瘍の魔の手から逃げ出せるぐらいツルツルしていなければならないと同時に、体内のどこかで血管壁に貼り付けるぐらいべたべたしていなければならないのである。
それらはしばしば、ツルツルしているのにくっつきあう細胞塊に「かくまわれて」、血管系やリンパ系を流れていく。その間、免疫系に見つからないようにすることが不可欠だ。
目的地に到着したら、その細胞は血管に穴を空けて、背後の組織の安全地帯にもぐり込む―だがあとはそこにとどまる―必要がある。
さらに 別の臓器という新大陸に腫瘍の足がかりを築くために
増殖する能力を保っていないといけない
(転移ガンを生じさせるのに必要な相反した性質を兼ね備えるようになる細胞は ごくわずかしかない)
細胞はガン化に必要なすべての性質をどうやって獲得するのか?
答えは ―ガン細胞は自然選択によって「進化を遂げる」のだ
われわれが一生を過ごすあいだに、細胞には数々の変異が生じる。その一部がたまたま、細胞周期を調節するガン遺伝子やガン抑制遺伝子に影響を及ぼすことがある。1個の細胞が、いつもなら増殖を阻んでいる束縛から解き放たれると、当然増殖する。
ほどなく、それは1個の細胞ではなく細胞のコロニーとなり、そのすべてがまた新たな変異をせっせとためていく。
こうした変異の多くは中立的なものだが、ほかは細胞にとって有害で、そのうちに1個の細胞に悪性化の道を進ませる変異もわずかながら生じる。
その道を一歩進むたびに、細胞の子孫は増殖し、もとは一個だった変異体が膨大な集団となるが、それもまた、次の一歩に適応した別の細胞に取って代わられる。
ガンが体じゅうにはびこる
ガン細胞には未来はない
「変異と選択の容赦なき盲目的な論理が決定する行程」
彼らはただなすべきこと すなわち増殖と変化を続けていく
(279)
細胞死には主としてふたつのタイプがある。ひとつは突然あっさりと非業の死を遂げるもので、ネクローシス(壊死)という。これは派手な死に方で、いわば絨毯に血痕や血糊が残っている。
もうひとつはアポトーシスで、覚悟を決めて青酸カリを飲むような静かな死に方であり、自然の形跡は残らない。これはスパイの最期であり、スターリン主義の体制を敷いている身体にふさわしいように思える。
それにひきかえ、ネクローシスによる死はひどい炎症反応を引き起こす。まるで警察が爆弾テロの現場を捜査するようなもので、そのあいだに死体が多く見つかり、騒ぎが収まるまでに時間がかかる。(282)
アポトーシスは なぜ どうやって単細胞生物で進化を遂げたのか?
なぜ 独立のできる細胞が自殺を「承服」したのか? (281)
アポトーシスにかんする知見の多くは
ガンにおける役割の研究から得られている
アポトーシスについての理解が進むほど
ミトコンドリアがそこで主役を演じていることがわかってきている
進化の歴史をさかのぼると、コロニーが無法地帯だった時代、つまり最初のころの真核生物において、ミトコンドリアと宿主細胞が主導権を競い合ったことからアポトーシスが進化したという構図が浮かび上がってくる。
(281)
アポトーシスという名前は
1972年 当時アバディーン大学にいたジョン・カー アンドルー・ワイリー アラステア・カリーが
同じ大学のギリシャ語の教授だったジェームズ・コーマックの提案に従って生み出された
この言葉は「剥がれ落ちる」ことを意味し、『英国ガン雑誌(British Journal of Cancer)』に掲載された彼らの論文のタイトルで、次のように初めて使われた―「アポトーシス 組織の動態において幅広い意味をもつ基本的な生体現象」。
アポトーシスは本来ギリシャ語なので、二番目の「p」は無声となって「アポトーシス」と発音される。
この言葉の使用は 古代ギリシャの医師ヒポクラテスまでさかのぼる
そのときは「骨が剥がれ落ちる」という意味で使われ
壊疽で巻いた包帯のなかで 骨が砕けて崩れ落ちることを指すあいまいな表現だった
(のちにガレノスは その意味を「かさぶたが剥がれ落ちる」ことにまで押し広げている)
現代になって、ジョン・カーはラットにおいて、肝臓のサイズが一定ではなく血流の変動にともなって絶えず変化することに気づいた。
肝臓のどれかの葉(よう)で血流が低下すると、それに合わせて、その葉は数週間かけて徐々に小さくなった。細胞がアポトーシスによって失われたためである。
反対に、血流が回復すると、その葉はまた数週間かけて重さを増した。血流の回復に応じて細胞が増殖したからだ。
このように均衡を保つ働きは いろいろな場合に広く当てはまる
(例えば)ヒトの体は数十兆個の細胞からなると言われているが 毎日 約1兆個もの細胞が死に 新しい細胞に入れ替わっている
それらの細胞は いきなり非業の死を迎えるのではなく
アポトーシスによって知らぬ間に粛々と取り除かれ
死んだ細胞の形跡はすべて近隣の細胞に食べられる
これはつまり、アポトーシスが体内で細胞分裂を調整していることを意味している。要するに、正常な整理機能において、アポトーシスは細胞分裂と同じぐらい重要な役目を果たしているのだ。
(カーとワイリーとカリーは 1972年の論文で 多重多様な状況 ―正常な胎児の発育や奇形の発生-胎児の先天性異常 健常な成体の組織やガン化や腫瘍の退縮 あるいは 使われなくなったり老化したりした組織の萎縮― において細胞死の形態が基本的に似ていることを証拠立てている)
アポトーシスは 免疫機能にとっても重要
体組織に反応する免疫細胞は 個体発生の過程でアポトーシスを引き起こし
それで免疫系は「自己」と「非自己」を見分けられるようになっている
免疫細胞はその後 ダメージを受けたり感染したりした細胞に
みずからアポトーシスを起こすように仕向けることによって その影響力の多くを行使する
このような選別を免疫細胞がおこなうため ガン細胞は増殖のきっかけをつかむ前の初期段階で その芽を積み取られる
アポトーシスの一連の筋書きは 細かく定められている
・細胞が縮小し 表面に泡のような突起ができてくる
・核にあるDNAとタンパク質の複合体(クロマチン)が核膜のそばで凝縮する
・最後に細胞はアポトーシス小体という 膜に包まれた小さな構造体に断片化し
免疫細胞に取り込まれる
結局 細胞はわが身を一口大のかたまりに分けて梱包し
ひっそりと別の細胞に食べられてしまうのだ
筋書きどおりに事を運ぶため
アポトーシスはATPという形のエネルギー源を必要とする
(ATPがないと細胞はアポトーシスを引き起こせない)
したがって、このプロセスは、細胞が膨れて破裂するネクローシス ―いきなり訪れる非業の死― の場合と大きく異なっている。おまけにネクローシスと違い、アポトーシスには後遺症、わけても炎症がない。細胞が死んだ形跡は、ただなくなったこと以外に何もなくなるのである。
それは予告された死だが、記憶されないのだ。
(285)
『ミトコンドリアが進化を決めた』
2015年5月30日 11時21分
あの「型」… (永いこと)固まったままでは……
オサマラナイ
列島(後方糸引き(各人)) 相応
どのような照応を 有効な様に施しての顕現でしょう?
島のカタチが似ているというほうのソウジでしょうか
それとも仕込み系の何かでしょうか
横に 何々(サイキン)ヘイキと並べて検索しますと
「豚連鎖球菌」と一緒だよ と 出
(例:四川ブタ連鎖球菌伝染病 四川省 2005.8.8)
真実なのか 怖がらせるため等々の捏造系流布なのか
どちらもなのか あるいは… 何であれ
浮き上がってくるものがあるかもしれませんが
それに沿って清算などがなされる というだけのことで
そのようなときにこそ 活きてくる「カルマ」という「法則」
(態々作られたのでしょうから)
他に回し続けると ぐちゃぐちゃが益々積まれて 更に大変に
錯乱繰り返しは認められない → どうなる?
「収穫」「獲得」 逃げられない彼是
「法則」関係なし
(2〜3日前に流れていたものをメモしました)
米国の医師(西アフリカでもみられるようす)に
「高眼圧症」「瞳の色の変色」などというアラワレ
また 酷い疲労感 聴力の低下
関節の衰弱や筋肉痛
エボラ出血熱の生存者のおよそ40%に
眼球の炎症や痛み
視界がぼやける
視野の一部が見えない
などの アラワレが
(獲得したものを)手入れしなければならないのか
それとも カエすべきなのか
獲得方法などのバランスがどうだったのか
あるいは それらが 彼らのものでないのなら
該当者 当事者の方々が負うべき「視界」その他
・
『細胞の老化』2006 井出利憲
【G1期チェックポイント機構】
細胞周期の回転には 様々なステップにチェックポイントと呼ばれる機構があり
次の段階に進んで良いか否かをチェックしていて OKが出なければ次へ進めない
S期に入る前には G1期チェックポイント機構があり、細胞のサイズを含めた細胞内の準備ができているかどうかと、細胞障害がないかをチェックする。
G1期チェックポイントの機能は Rポイントの機能と一部重なっている
細胞障害のひとつは DNAの損傷
DNAの損傷は日常的に起きていることで
損傷があるままでS期へ進行してDNA合成が進むと
DNA損傷が塩基の修飾であった場合には 様々な種類の突然変異が生じて細胞が癌化したり 異常機能の細胞になったりする
DNA損傷が一本鎖や二本鎖の切断であったときには
複製進行と共に二本鎖切断になって 細胞死につながる
これを防ぐために DNA損傷の有無をチェックし
損傷がなくなったことを確認してからS期への進入を許す機構が
G1期チェックポイント機構
ただ、G1期チェックポイント機構はDNA損傷だけを見ているわけではなく、その他様々な不都合をチェックしていることは確かであるが、詳細についてはよく分かっていない。
中心的な役割を果たすのは
p53という遺伝子から作られるp53タンパク質で
様々な遺伝子の働きを活性化したり抑制したりする転写因子である
p53タンパク質は普段でも合成されているが
MDM2というタンパク質と会合して分解が進むため 細胞内にはごくわずかしか存在していない
DNA損傷を含めてS期進入にとって不適切な細胞内からのシグナルがあると
p53タンパク質が修飾されて量が蓄積すると共に活性化し
様々な遺伝子の働きを変更させて改善を図る
例えばDNA損傷を発見すると ATMや類似したATRなどのタンパク質リン酸化酵素をリン酸化され
さらにChk1やChk2などのタンパク質リン酸化酵素をリン酸化することで活性化する
それらによりp53がリン酸化されると MDM2からはずれて分解されなくなるために蓄積し
さらにアセチル化を受けて活性になり 様々な遺伝子を活性させる
活性化される遺伝子のひとつがp21で p21タンパク質が蓄積することでS期への進入を停止させる
他方 DNA損傷を修復する修復酵素の遺伝子を活性化させ
修復酵素をたくさん作り出してDNA損傷を修復し 不適切な状況を改善する
損傷が修復されればp53の活性状態は元に戻り
p21の急速な分解が起きて S期への進行が可能になる
修復不能な場合には p53の別のセリンにもリン酸化が起きるなどして
p53が転写因子として活性化する遺伝子群が変更される
その結果 細胞を自滅(アポトーシス)させるのに必要な酵素の遺伝子群を活性化し
アポトーシスを誘発して 周囲への影響を最小限にとどめる
細胞老化との関係では、細胞が老化してくるとp53の活性化が起きてp21がたくさん作られて増殖が停止する、というのはもっとも簡単な説明である。
【癌抑制遺伝子と癌遺伝子】
いままで登場したいくつかの遺伝子は 細胞の増殖に関わるものだが
癌抑制遺伝子 あるいは 癌遺伝子としても知られているもので
増殖に関わる遺伝子の機能の異常を起こすことにより
癌細胞の異常増殖 自律的増殖という性質の獲得につながる
「自律的増殖というのは、周囲の状況を無視して、勝手に増殖することである」
・癌抑制遺伝子
p53とRBは 代表的な癌抑制遺伝子として知られている
ヒトの癌の60%以上でp53に関わる変異が知られていて
多くの場合 p53が突然変異しないと癌になれないということができる
(前記のように)p53の性質から p53遺伝子が変異を起こしてp53タンパク質が働きを失うと
正常なG1チェックポイント機構が失われて DNA損傷があっても修復せずにS期へ進行するため
変異をもった細胞を次々生み出して やがて癌細胞を誕生させ さらに高頻度に変異を生じつつ悪性化することの原因となる
癌細胞に正常なp53遺伝子を導入すると 癌細胞の性質が(全部ではないにせよ)正常細胞の性質に戻る
(癌の遺伝子治療として臨床的にも検討されている)
Rbというのは ヒトの網膜芽細胞種(retinoblastoma)という癌の原因遺伝子で
この癌はRbが変異あるいは欠失することが原因で生ずる
Rbが働きをなくしていれば E2Fがいつも活性化して S期への進行を抑えるものがなくなるわけで
これも癌の自立的増殖の原因になっている
つまり、正常な状況では、調節された増殖を保証することに働いる遺伝子、それが働きを失うことで、癌の自立的増殖の原因になる。
それが、癌抑制遺伝子と呼ばれる理由である。
p53の場合も RBの場合も S期への進行に関して細胞内の準備ができているか否かに関わらずS期への進行がゴーになることで細胞に混乱が生じる。
・癌遺伝子
(前出 増殖のシグナル伝達のところでの) ras raf jun fos myc などの遺伝子から作られるタンパク質は
増殖因子が来てシグナル伝達が働くときに初めて活性化される
増殖因子が来なければ 細胞内にあるこれらの遺伝子に変異が起きて
変異遺伝子から作られるタンパク質が 増殖因子の有無に関わらず活性状態であるようなタンパク質になってしまったら 細胞はどうなるか
増殖因子が来なくても 増殖のシグナル伝達系が働きだし 細胞は自立的増殖を始める原因になる
「そのように変異した遺伝子を癌遺伝子と呼んでいる」
「正常な細胞で増殖誘導に関わる遺伝子が 変異を起こして癌遺伝子になる」のだ
ヒトの多くの癌では、癌遺伝子と癌抑制遺伝子の両方が変異していることが知られており、正常細胞が癌細胞になるためには、複数の癌抑制遺伝子と複数の癌遺伝子が必要であると考えられている。
【複製開始のライセンス】
DNA合成の材料やDNA合成酵素が用意されさえすれば 自動的にDNA合成が開始するわけではない
DNA合成が開始するためには (言い換えれば)複製開始点が働くためには
ライセンスファクターと呼ばれるタンパク質複合体が複製開始点に結合することが必要であることがわかっている
このファクターは複製開始点が一度働くと活性を失い
次のM期に核膜が消失することで 新たに細胞質から供給される
つまり、M期が終了(G1期が開始)することによって、複製開始の新たなライセンスが得られる。
真核生物の細胞では、一度使われた複製開始点は、全部のDNA複製が完了して、さらにG2期、M期を経ない限り、もう一度働くことがなく、同一のS期内には二度と複製開始点が働かないという endoreduplicationの禁止を支える機構でもある。
【複製開始の調節】
複製開始のライセンスが与えられ チェックポイントのチェックが済んで
S期進行に必要なDNA合成の材料やDNA合成酵素が用意されたとしても
「それだけで なし崩し的にS期が開始するわけではないらしい」
ただ、具体的にS期開始(DNA合成開始)のゴーサインを与える機構は実はよく分かっていない。
(細かいことを知ってもらうつもりはなく、ましてや覚えてもらうつもりは毛頭ないのだけれども、細胞というものがいかに複雑で、用意周到で、注意深い仕組みを備えたものであるかを、感覚的にでも察してもらうためには、この程度まで話をする必要があったのである。)
(章の締めくくりの項)
【細胞老化による増殖停止】
細胞がS期への進行を調節する仕組みがあり 細胞分裂寿命の限界に近づくにつれ
G1期チェックポイント機構が働いて p53が活性化され p21がたくさん合成され蓄積することによって
RBのリン酸化反応以降が阻止され その結果 S期への進行が阻止されている
-『細胞の老化』
(分裂寿命を延長させることができる)
(p53が活性化され p21の発現が高まる)
(言い換えれば p53を活性化させるシグナル伝達系の上流には何があるか)
(テロメアの短縮という現像が最初のシグナルを発信する)
-『細胞の老化』
と流れは続くようですが
ここで この書は節目 一休み 保留 か 何か
・
15 の 朝 移動しながら打ち込みをしておりまして
雑司が谷墓地内でも少々彷徨き… あるベンチで落ち着いて
どっしり作業していると
暫くして目の前に車が停まり 石の-形などを変えるような-
生業の方が
丁寧な声かけをしてくださる
「彫刻をしますので煩くなります」
「ありがとうございます …移動するなりいたします」
(通りかかられた方との目の前での会話が耳に…「木下さん」「ホウジョウ寺?」キョウチョウ単語)
8:08に すぐ後ろで作業が開始され
8:30に其処では終了
内部での移動の前に「終わりましたので…」と
これまたテイネイなご挨拶をいただき
「お疲れさまでした」と
日常のリフジン系があるためなのか?
支障なく打ち込み続けた
(複製開始点 あたりを中心とした前後)
2015年5月15日 9時11分
列島 雛型説
島々のカタチを利用された方々は
どんな呪い 術 で
ライン・カタチ 相互間バランスなどを保ってこられたのでしょう
何とかパワーが世界中に駆け巡っちゃって
後始末が大変だ
・
ああ「逃げ場」?… 信濃・皆神山
出雲と吉備を結ぶ葦嶽山ピラミッド
飛騨高山の日輪神社を中心とする16方位のネットワーク
富山の尖山 津軽の岩木山を頂点するピラミッド
等々の それぞれが 「群(システム)として独自に作動」する 一方「全体においても相互に連携する関係」に あるらしい
「御皇城(おんみじん)山と立山 位山が太古日本のピラミッド・センターの位置を占めていたというのは事実だったのではないか」
「何度か 地球の大異変によって神都を移転せざるを得ない状況があったにも関わらず 一貫して「すべての人類の元宮」としての地位を保っている」
(御皇城山 立山 位山のピラミッド・ゾーンと富士を結ぶラインは)
「太平洋側から押し寄せるマントル対流の圧力を最も強く受けるところであり」
いわば 列島の「重心に相当する地点」
「その圧力を防御の盾としながら 御皇城山 立山 位山のピラミッド総山が背後から支えている関係が見て取れる」
「確実に大地のツボを押さえ」
「最も緊張度の高いところを選んでピラミッドが建設されたことによって」
「異変と破滅の危機から救われている」
そして「大地から受けるエネルギーのコントロール」などにより
「大地のバランスを保ってきた」
「ばらばらに千切れてしまいそうな」列島を
「要所要所で固定し」
「その安定化を図っているように見え」
(…むしろ そんな風に蓄積することが何かに繋がるような気もしますが)
「ほとんど唯一」「世界に類がない」ほど「見事に組織されたピラミッド・ネットワーク」
それらが凄く効いたままで「安定化」も そのままならば
「見事」なほどに目覚めなくても 不思議はないでしょう
歪みなどは相当溜め込んだままで
「ほとんど唯一」変化しないことを「固定」し続ける「島」
「ネットワーク」外の動きなどもありましょうから
そのままかどうか?
・
『細胞の老化』2006 井出利憲
【Rポイント】
Rポイント - レストリクションポイント
細胞周期の中で 周期の回転を調節するポイントがある ことは「古くから知られていた」
適切な増殖因子を与えれば細胞は増殖する
(増殖抑制のシグナルがはずれている必要はある)
が 増殖因子を抜けば増殖を停止してG0期にとどまる
細胞周期全体の中で 増殖因子が必要なところを解析したところ
G1期の終わり S期の直前までの段階であることが分かった
増殖因子存在下で細胞周期を回っている細胞でも
増殖因子を与えてG0期から細胞周期を向かって走っている細胞でも
増殖因子が必要なのはG1期の終わり(Rポイント)までであって
その後は増殖因子を抜いてしまっても
細胞はS期 G2期 M期を順調に終了して次のG1期まで進行する
Rポイントまでの間の途中で増殖因子を除去すると
細胞はその先の細胞周期進行ができず G0期に戻ってしまう
「増殖因子によって刺激され続ける必要があるのが Rポイントまでの時期」
つまり G1期の終わり近くには 細胞がDNAを合成し
さらに細胞分裂をするための準備が終了する重要なポイントがあると考えられ
これをRポイントと呼んだ
ひとたびRポイントを越えてしまえば
増殖因子なしで次のG1期まで順調に進行できる
細胞周期をさらに詳しく見ると、増殖因子に感受性の高い時期であることが分かった。タンパク質合成を完全に停止させれば細胞周期のどの時期の進行も妨げられるが、この期間だけは、タンパク質合成をわずか20〜30%阻止するだけでもRポイントに到達できなくなる。
この期間は、細胞が増殖因子によって刺激され続け、その刺激によって構成されるタンパク質合成が非常に重要な役割を持っている、もう少し具体的にいえば、分解を上回る合成があって、タンパク質が蓄積する必要がある何事かが起きているものと推定される。
老化細胞に増殖因子を与えたとき 細胞内で何も反応が起きないのではなく
むしろ Rポイント近くまでは進行できるけれども
そこを越えることができないように見える
(老化細胞がなぜ増殖できないのか)
Rポイントに至る細胞内で 何が起きているのか
【Rポイントで起きること】
G1期の細胞内では RBというタンパク質が
E2Fというタンパク質と結合した状態にある
E2Fタンパク質は S期に必要なタンパク質や酵素の遺伝子を活性化する 転写調節因子の複合体である
E2Fが活性になると DNAの材料であるデオキシリボヌクレオチドを提供するヌクレオチド還元酵素や
高分子DNAを構成するDNA合成酵素など DNA合成に必要な酵素の遺伝子を活性化する
遺伝子が活性化されることで それらの酵素がたくさん作られるようになって
S期への進入の最終的な準備に入れる
G1期には E2FがRBと結合しているために
E2Fは活性がない
つまり S期に必要な遺伝子を活性化できない状態にある
「G1期の終わりの時期に S期へ進行する全ての準備が整った」
その先は増殖因子がなくても先に進んでよろしい という判断がなされ
実際に『S期へ進め』という信号が発せられると考えられる
「実はその信号が何であるのか、具体的にはよく分かっていない」
「一番肝腎なところが分かっていない、というのは良くある話」
細胞の準備がそろうと 信号が発せられ
それまでに蓄積していたサイクリン・CDK複合体が活性化され タンパク質をリン酸化できるようになる
リン酸化されるタンパク質として重要なもののひとつがRBで
RBがリン酸化されるとE2Fが活性状態になり S期に必要な遺伝子が活性化される
「これが 具体的にRポイントを超える、ということなのだろうと考えられる」
【DNA合成に至るG1期のブレーキ】
(もうひとつの)サイクリン・CDK複合体の活性を調節する重要なタンパク質
CKI (cyclin-dependent kinase inhibiter)というタンパク質のファミリー
たくさんの種類のタンパク質を含んでいる
名の通り サイクリン・CDK複合体の活性を阻害する
増殖を抑制する環境にさらされると
それらのいずれかが作られて
サイクリン・CDK複合体の活性を抑制する
老化細胞でたくさん合成され 蓄積していたp21というタンパク質は
CKIファミリーのひとつ
つまり 老化細胞では p21が蓄積していて 増殖因子によってサイクリン・CDKが合成・蓄積しても活性が抑制されていて
そのため RBのリン酸化が起きず
E2Fが活性化されず S期を開始することができない
増殖を停止している若い細胞では同様にp21が蓄積していて、増殖因子を与えた後にはむしろ合成と蓄積が高まり、どんどん蓄積するサイクリン・CDK複合体に結合して、S期へ進んでもよろしいという細胞内の準備がそろうまで、複合体を不活性状態に保っている。だから、若い細胞でも、増殖停止期にはDNA合成開始を阻止する物質を含んでいた。
細胞内の準備がそろって、もう先へ進んでよろしいとなると、p21タンパク質が急速に分解し、同時にサイクリン・CDKタンパク質の特定のアミノ酸にリン酸化と脱リン酸化が起きて、リン酸化酵素活性が現れる。
(Rポイントの実態に含まれる反応のひとつ)
【CKIはファミリーである】
CKIタンパク質は p21以外にも p15 p16 p19 p27 p57 など 多くの種類のタンパク質から成るファミリー
それらのCKIタンパク質は細胞接着や 増殖因子の低下 その他細胞が増殖に不都合な状態にあるとたくさん作られて
サイクリン・CDK複合体のタンパク質リン酸化活性を抑制する
いずれも G1期で細胞周期をS期へ進めないように抑制しているブレーキの役割をしているタンパク質のファミリーなのである
どのような条件下でどのCKIが作られて働くかについては
細胞の種類や増殖停止の条件に応じて 役割分担があるらしい
-『細胞の老化』
2015年5月14日 15時55分
「ドラマ」の絡みなどは何ともいえませんが
「獲得形質」というのは もしや潰されている面があるのでは
けっこう多いのでは?
(「種」(間)のそれらも) こねくりまわして? ナンカシタ?
そんなことが 巡りにメグル ぐるぐると・・ ^^
◆
『植物という不思議な生き方』2005 蓮実香佑
(「鏡の国のアリス」「エンドファイト」につながる部分)
(植物体内に同居する共生菌)
「巨悪な組織が開発した新型の菌」
(この菌に感染した人々は脳をあやつられ… ピンチ)
(ヒーローものドラマ 略)
(菌にあやつられていたんだ…)
「自然界に目を向けて見ると あながちこどもだましのお話では片付けられないようだ」
「菌の支配」
レウコクロリディウムという寄生虫に寄生された
ある種のカタツムリは実に奇妙な行動をとる
カタツムリは湿った日陰で暮らしているが
寄生されると日当たりの良い葉の上に移動する
(催眠術などであやつられていると 目が正気でないとわかることがある)
寄生されたカタツムリも目を見れば
操られていることは「一目瞭然」
突き出た目は先端が異常に膨れ上がり
奇妙な縞模様が動いている
(気味の悪い目)
目の中で動きまわっている縞模様の物体が
カタツムリをあやつる寄生虫で
縞模様を目立たせ 鳥を呼びよせる
「寄生虫が鳥を呼びよせるわけ」
レウコクロディウムはもともと鳥の寄生虫
鳥の体内で寄生虫の産んだ卵は鳥の糞といっしょに対外に出される
そして カタツムリが餌を食べるときに
一緒にカタツムリの口に入り 体内に侵入する
(人間なら「だから食べる前に手を洗いなさいって言ったでしょ」と怒るところ)
(残念ながらカタツムリに手はない)
カタツムリの体内に侵入した寄生虫の難問
「カタツムリの体内から鳥の体内への移動」
葉の上に移動したカタツムリの異常な行動は
寄生虫が鳥の体内に移動するために だった
「カタツムリと一緒に食べられて寄生虫は無事 鳥の体内に戻ることができる」
カタツムリの命と引き換えに
「悪魔の麦」
体内に住む寄生者が影響を与える 植物での例
新約聖書「マタイ伝」に
ドクムギ という植物の話が登場する
「ドクムギは麦畑の深刻な雑草」
有毒なので 家畜や人間が誤って食べると中毒を起こす
マタイ伝によれば
「人々の眠っている間に悪魔が畑にドクムギの種をまいてしまう」のだとか
…よくよく調べてみると 本来は有毒ではないらしい
「なぜ 中毒を起こすと古くから言われているのだろうか」
植物の体内にエンドファイトと呼ばれる菌が潜んでいて
せっせと毒素を作り出しているのだという
「こうしてドクムギはエンドファイトによって恐ろしい植物に仕立てられてしまった」
ずいぶん昔から体内に住みついていて 種子にも感染するため
一度感染すると子々孫々に至るまで
エンドファイトの感染を受け続けることになる
エンドファイトとドクムギの共生の歴史は古く
古代エジプトのファラオの墓から発見された
ドクムギの種子はすでにエンドファイトが感染していた らしい
「ドクムギはけっして特殊な事例ではない」
牧草にも感染して植物体内で毒素を作り出すので
家畜の中毒の原因となることもあるのだ
ところが ゴルフ場などで使われているシバのほとんどには
わざわざエンドファイトを感染させてあるという
「エンドファイトを感染させて大丈夫なのだろうか」
エンドファイトにもさまざまな種類があり
なかには 毒性ではなく有用な機能を付与するエンドファイトも少なくない
「エンドファイトの感染によって植物が病害虫に対する抵抗性を持つことがある」
「あるいは乾燥に対して強くなることもある」
(さまざまな「サクセスストーリー」 略)
エンドファイトのファイトは「植物」という意味
エンドは「内部」という意味なので
「植物体内の」という造語
体内に住みついたエンドファイトがさまざまな能力を授けるのは
(植物の夢をかなえるためではなく)
「生活の場にしている」植物が
病気になったり 食べられたり 枯れてしまったりしては
自身の生存も危ぶまれるから
感染した植物を強くするように働いているのだ
「植物体内に住むエンドファイトは 他の菌にはない大きな特徴がある」
菌類の生活史は「不完全世代と完全世代」という二つの世代に大別される
「不完全世代」は「菌糸」などを使って増える方法
「完全世代」は 雄と雌によって子孫を残すように
受精により「有性胞子」を作る世代
エンドファイトの中には「完全世代」を持たないものがいる らしい
「「雄」と「雌」の世代がない」
細胞分裂をして増える「無性生殖」は 自分と同じ形質を持つクローンができる
雄と雌が交わり遺伝子を交換する「有性生殖」では
親の形質を受け継ぎながらも親とは違うバラエティにとんだ子孫が生まれる
「多様性の創出が有性生殖の利点」
さまざまな形質の子孫を残すことによって
さまざまな環境に適応することができる
(しかし)雄と雌が共に子孫を作る有性生殖は効率の悪い繁殖方法
「例えば雄と雌が受精して繁殖する生物が雌だけで繁殖できるとしたら、世の中すべてが雌になるからそれだけで繁殖の効率は二倍にあがる。
さらに雄と雌が出会うこともけっして簡単ではない。
植物は花粉を雌しべに送り届けるために相当の苦労をしているし、動物は雌を奪い合って戦ったりして無駄なエネルギーを使っている。それだけの困難を乗り越えも首尾よく子孫を残せる保障はまるでない」
(この謎を解く「脚光を浴びている」学説-「赤の女王仮説」の紹介に入ってゆく)
宿主と病原菌との長い争い
「進化し続けなければ 生き残れない」
「常に防御方法を新しくしていかなければ」…
有性生殖であれば 「必ず親とは違う子孫が作られ」
「変化し続けることができる」
→ 病原菌も常に変化を続け
「進化のスピードをさらに早めなければならない」
そのための手段は「有性生殖」
「病原菌と宿主となる生物が変わり続けるために生物は有性生殖を行い、そのために男と女の存在意義があるというのが「赤の女王仮説」である」
(この仮説が正しいかどうかは今後のさらなる研究を待たなければならない)
しかし「病原菌と宿主となる生物が、もう長い間ひたすら走り続けてきたことは間違いない事実である」
◆
「多くの植物が鳥や動物に食べられて種子を運ぶという作戦を選んでいる」
(スイカの種子はできるだけゆっくり時間をかけて胃腸を通り 体内にとどまるようにしている)
(そうすることで 少しでも遠くまで運ばれようとしている)
(胃の中で芽を出したり 盲腸に引っかかるようなヘマをするはずはない)
地球を支配しているかのように振る舞う…
(人類のどれくらいか?は)
「ゆったり」と「全力疾走」で
(スイカの)(「種」を食べずに 「器用に吐き出し」)
永い間「獲得」し続けてきた何か
「獲得」(しようと)しなかった 何か
(何かを食し続けていることに気づきにくいのかもしれない)
同居 同化
馴染んでしまえば ゆったりとした「疾走」は違和感などもなくなり…
何気ない日常と化す
2015年5月2日 7時27分
序文より P5
がん細胞内では、多くの遺伝子が正常なメチル基を失っている。すなわち、「脱メチル化」しているのだ。脱メチル化は、さまざまな遺伝子活動の異常を引き起こす。細胞増殖を抑制できなくなるのも、その一つである。実を言えば、あらゆるがんに共通する顕著な特徴は、何か特定の変化ではなく、遺伝子の脱メチル化なのだ。これはむしろ喜ばしいニュースである。なぜなら、突然変異と違って、エピジェネティックな変化は元に戻せるからだ。
◆タスマニアデビルの生涯 P164
◆地獄からやって来たがん細胞 P166〜8 より
がんはウィルスではないため がんの伝染を目にすることはない
ところが
タスマニアデビルのDFTD-タスマニアデビル顔面腫瘍性疾患 は伝染しているらしい
ウィルスやその他の運び屋-ベクター によって伝染しているわけではない
死骸をめぐる闘争や 求愛行動の際に 個体から個体へと伝染するのである
感染した個体が別の個体を咬むときに 数個のがん細胞が咬まれた側に転移する
DFTDは寄生性のがんなのだ
ある意味では すべてのがんは寄生性だと言える
わたしたちの免疫システムは がん細胞を外界からの侵入者とみなす
発生したがん性あるいは前がん性の細胞は
大半は免疫システムによって異物と見なされ 排除される
免疫システムの攻撃を巧みに逃れたか その力を抑え込んだわずかながん細胞だけが 腫瘍を形成するのである
免疫反応を回避したがん細胞は 寄生生物のように 体の資源を周囲の正常な細胞と奪い合う
体の外から侵入してくるがんのほうが 免疫システムにとっては発見しやすく
破壊しやすいが デビルの免疫システムは この侵入者に対して
これと言って防御策を備えていないように見受けられる
免疫反応全体が壊れているということではない
たいていの攻撃に対してはきちんと反応している
そもそも その食性やひんぱんに傷を負う暮らしぶりからすると
免疫システムがしっかりしていないと 生きていかれないはずなのだ
問題は 認識の段階にあるように思える -がん細胞を異物として認識できない
(タスマニアデビルの抱える免疫反応の問題は 認識の段階だけではない)
自己と異物の区別は 免疫反応の根底をなすものであり だからこそ
われわれの体は移植された臓器を 近親者のものであっても拒むのである
免疫システムの認識過程が狂うと 健康な自分の細胞が攻撃されることがある
過剰な警戒は 関節リウマチや狼瘡(全身エリテマトーデス)などの自己免疫疾患を生じさせる
タスマニアデビルの免疫システムはそれとは逆に
寛容すぎて異物を自己として認めてしまうのである
このような免疫反応の盲点は、最後の氷河期以降に ―もしかすると20世紀になってから― 起きた、遺伝的ボトルネックの結果だと考えられる。遺伝的ボトルネックとは、何らかの圧力を受けて生物集団の個体数が激減し、遺伝的多様性が失われることで、タスマニアデビルの個体数はある時点でわずか数頭まで落ち込んだ可能性があるのだ。その結果、近親交配が進み、すでに貧弱なものとなっていたその遺伝的多様性が、ほとんど失われてしまったのだろう。同様の現象はチーターでも起きている。チーターもやはり遺伝的多様性に乏しく、他の個体から皮膚移植することができる。おそらくDFTDのような接触性がんにも冒されやすいはずだ。
◆細胞ががんになるまで P168〜170
DFTDは異様で気味が悪いが、その細胞はごく普通の典型的ながん細胞である。まず、それは低分化がん(正常な細胞との類似が少ない悪性のがん)で、分化が進んでいないところが体性幹細胞によく似ている。その一方で、これはがん細胞全般に共通する特徴でもあるのだが、DFTDの細胞は、本来なるはずだった細胞の特性をいくつか備えている。同様に典型的なのが、染色体の構成が大幅に変更されていることで、少なくとも一対の染色体が欠損している。染色体の欠損や過剰は、原因が何であれ、がん細胞ではよく見られることだ。
細胞が変質してがん細胞になる過程については 主に二つの見方がある
従来の見方では、がん細胞はニューロンや皮膚細胞などの完全に分化した細胞から生じるとされる。そのような細胞が脱分化して、幹細胞のような増殖能力を取り戻したのががん細胞だ、というのである。この「脱分化=がん化」の立場をとれば、がん細胞が元の細胞の特徴をいくつか保持している理由も説明できる。タスマニアデビルのがん細胞は、その化学的特長から、内分泌系(ホルモン系)をコントロールする神経組織から生じたと考えられている。※
ところが、最近脱分化説に代わる説が発表された。それは、がん細胞は劣化した体性幹細胞から生じるというものである。この「幹細胞説」では、がん細胞が幹細胞に似ているのは、幹細胞からできたからだとされる。正常な体性幹細胞だったものが、道を間違えてがん細胞に変化した、というのである。しかし、この幹細胞は、細胞分裂を経ても、一向に数が増えない。それは次のような理由からだ。
普通の幹細胞と同じく、がん幹細胞の分裂は非対称で、がん幹細胞一個とがん細胞一個に分かれる。ゆえに、幹細胞の数は増えないが、新たに生まれたがん細胞は、普通の細胞のように対称分裂をするので、分裂のたびにその数は倍増していく。このような細胞分裂が繰り返され、最終的に生じる腫瘍は、少数のがん幹細胞と、おびただしい数の(程度はさまざまだが)分化の進んだがん細胞によって構成される。したがって「幹細胞説」では、がん治療の目標は、そのわずかながん幹細胞を消滅させることに置かれる。
つまり、「脱分化説」では、がん細胞は正常な細胞が幹細胞に逆行したものと見なされ、「幹細胞説」では、幹細胞からスタートしたものと見なされているのである。もっとも、この二つの理論は、どちらかが正しく、どちらかが間違っているということでもなさそうだ。多くの前立腺がんにはさまざまな脱分化の兆候が見られるが、白血病などの血液のがんは、幹細胞説のほうがうまく説明できるのだ。
※Loh, Hayes, et al.(2006). しかし murchison,tovar,et,al.(2010)によると、DFTD細胞は、抹消神経系の軸索に栄養補給するグリア細胞の一種、シュワン細胞に由来すると見られる。
(本文や他の注釈は 可能なときがあれば入れます)
◆がんになるのは遺伝子か染色体か P170
あとがき で述べられている 重要テーマ5つ より 5番目:メタ・テーマ P186、7
タンパク質合成 細胞分裂 がんといった生物学的プロセスにおける
遺伝子の役割についての 基本的直感に関わるもの
これまで遺伝子は、そのようなプロセスをスタートさせ、指揮していくエグゼクティブと見られ、遺伝子以外の細胞の要素は、言うなればブルーカラーの労働者として遺伝子の命令どおりに動くものとされてきた。演劇用語で言うなら次のように説明できる。「遺伝子が監督で、タンパク質は役者で、ほかの生化学活動はすべて裏方である」と。
しかし、ここで掲げたもう一つの見方では、この演劇はもっと即興的なものとなり、遺伝子はむしろアンサンブル・キャスト(その他大勢)で、同じくアンサンブルであるタンパク質や生化学的な因子と同格の扱いになる。
そして遺伝子の活動は、タンパク質合成においても、通常のあるいは病理的な細胞の分化においても、原因であると同時にその結果でもある。
このもう一つの見方によると、遺伝子はローマ神話に登場する、門や入り口の守り神、ヤーヌスのように、二つの顔を持つことになる。それは入り口と同時に出口であり、始まりであると同時に終わりでもある。これまで知られていたのは外向きの顔、つまり原因としての面だけである。
そのせいで、遺伝子とその活動のイメージは、単純すぎる、歪んだものになっていた。遺伝子にはもう一つ、内側へ向けた顔がある。それは周囲に反応する側面であり、エピジェネティックの研究ではこの「ヤーヌス」遺伝子の反応する顔のほうに光を当てている。
『エピジェネティクス 操られる遺伝子』2011 リチャード・フランシス
2015年3月12日 15時28分
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright (c) 2006 KURUTEN All right reserved |