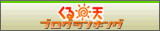| 2024年12月15日 10時23分 |
| シリア独裁の終焉 |
| 親子半世紀にわたるアサド独裁政権が反政府勢力ジャウラ二指導者によって打倒された。あっという間のあっけない幕切れであった。ウクライナ戦争にかかりっきりのロシアの後ろ盾もなく戦闘員としてのヒズボラもイスラエルとの戦闘による消耗が激しくシリア軍自態も弱体化していたという。 国内内戦で640万人にも及ぶ難民(棄民)が発生し、これだけで統治能力、国家としての体裁も威信もないに等しかった。他国の支援に頼り維持した政権も遂に力尽きた。もともとサダトの基盤は大土地所有地主だったといわれる。いわゆる少数支配である。 ジャウラ二指導者はシリアのためにISともアルカイダとも組んだ。その過程は彼に学ぶ機会を与えアサド政権下の人員も採用するとされる。シリア人民のため統一の実をあげられることが期待されている。 難民たちの帰るべき国造りそして中東アラブの安定化に寄与されんことが求められているといえよう。 |
| [カテゴリ:政治] [コメント (0)] [トラックバック (0)] |
| 2024年11月2日 9時53分 |
| 過半数割れがもたらしたもの |
| 衆院選は厳しい国民の裏金批判票となって自民公明の合わせても過半数に満たないという戦後自民党政治に転換点となる結果をもたらした。 自民党が選挙に強いなどというも過去統一教会の加勢がなければこうはならないという化けの皮が剝がれてしまった。 金権腐敗政治がもたらしたもの。経済においてもアベノミクスに象徴される円安誘導による為替で儲けようなどと空利益稼ぎが日本経済に与えた怠惰の風潮、現状に胡坐をかこうとする二流三流意識。GDPは次々と他国に追い抜かれる。 コストカットは国民所得賃金の低下を促進し大企業のみに利益が蓄積していった。そして、大企業富裕層からではなく国民から重税として搾り取る。さらに円安物価高は国民の生活を圧迫して余りあるものだ。 過半数割れはもはや大手を振ってこの路は進めないことを示したものだ。他にも不公正で腐敗した政治の風潮は社会の風潮にも良い影響を与えるはずがない。 政権交代・転換に近い状況で先ずは国民生活を立て直していただきたいものだ。いわゆる分配に力を注ぐことによってかなりの国民経済の好転が期待できると確信するものである。少子化GDPもそうである。 そのうえで輸出立国モノづくり日本が再生する道を開いていただきたい雇用の安定は欠かせないのだが。 日の丸半導体、進んだ省エネ技術...などなど自由で公正な競争のもと日本の進む道を旧保守政治の転換点から歩んでほしいと期待して止まない。 |
| [カテゴリ:政治] [コメント (0)] [トラックバック (0)] |
| 2024年10月19日 14時43分 |
| 過半数割れなるか衆院選 |
| 第50回衆院選2024が公示された。裏金解散と称され国民の厳しい自民批判票が予想される。当初予想では自民党単独では過半数割れで公明票入れてやっとという話しである。野党は乱立も立民・国民民主などは増やすといわれる。 接戦となる選挙区も多く厳しい戦いを勝ち抜かれ国民のための政権交代が成し遂げられますよう祈念。 石破政権なるも安倍派政治の残した負の遺産統一教会問題そして金権政治の自民党マイナスベクトルは一朝一夕に解消できるものとてなく戦後保守政治に区切りが生じようとしている。その経済とてGDP転落円安物価高と既に長く放置してきた責任は拭いようがない。政権交代で心機一転を図る機運の方がむしろ強いであろう。 どうか、過半数割れなくんば、保守政治からの転換はありえないのであって、小党分立で弱いとされる野党勢力からも脱却を図るべく野党調整ができないのであれば、主権者たる国民の手によるドラスティックな投票行動が議論の余地なく過半数割れの状況をひらくというのもあり得るであろう。野党一本化が遅れ否それを狙った戦後最短の解散であったにもかかわらずだ。 野党の中核となる政党には奮闘を期待したいものである。そして主権者たる国民の良識に期待。 |
| [カテゴリ:政治] [コメント (0)] [トラックバック (0)] |
| 2024年10月5日 14時58分 |
| 打てば勝てる解散ならば |
| 石破氏による表紙の付け替えは出来た、急いで解散。あまりにも見え見えではないか。左派リベラルと称される石破氏ならではどこへやら、所信表明演説ト−ンダウン著しく、改革はなし、裏金禊よろしく票を下さいとばかり、余りにも虫が良すぎる、否それ程後がないのが今の自民党の姿である(石破氏はかくゆう党内倒閣運動で脅されたやに聞く)。 裏金議員も地元の公認申請、再発防止策提出により公認の予定であるという(直前、いみじくも公認不可数名、比例重複不可とした)。要するに表紙一枚替えただけで、解散に打って出る、票を下さい。あまりに国民を馬鹿にしてるのではを通り越して、危険な賭けに打って出た。こうしないと、非公認するだけで小選挙区でそれだけで過半数割れ、あまり厳しく処分すると党内右派が勢いづくからともいわれる。 裏金議員を当選復活させるほど国民は甘く見られてるのですか?強行突破できると思われている節があるのである。 もはや、退場しかないであろうに。であれば、野党勢力は政権交代に向けて選挙協力が欠かせない事態となっている。ここでこそ、政治的妥協の努力が、重い課題となる。 国民の意思を実現し、日本をダメにしないために、奮闘を期待したいとこである。 |
| [カテゴリ:政治] [コメント (0)] [トラックバック (0)] |
| 2024年9月23日 16時53分 |
| 野田代表による政権交代 |
| 立憲民主党の臨時党大会で野田佳彦代表が選出された。次期総選挙では勢力拡大ではなく政権交代が責務である以上、選挙に勝てる顔が必要である。如何せん自民党選挙戦能力に開きがあるからには小選挙区において選挙民に体制選択してもらわなくてはならない。従って野党選挙協力が欠かすことができないものとなる。 かの元安倍首相死亡による野党側の首相を務めた野田氏による追悼演説。弁が立つとの評判以上にいみじくも追悼しきった弁舌であった。保守層も一目置いたともいわれる。 日本国をダメにする一歩手前で自民党打倒の急先鋒が立ち上がった格好だ。依然として旧統一教会との関係を総括も決別も怪しげなままでは国の行く末は危ぶまれる。反国家集団と深くかかわってきたものがどう禊が可能なのか、ひとまず、退出は止むを得まい。裏金事件はその体質そのもので全国民の顰蹙を買ってしまった。 日本国の未来は見ての通りの国民的政治的ダイナミズムとなって結果となって現出されるに違いない。その顔として党内団結を図り叡智を結集して励まれんことを希望したいものである。 |
| [カテゴリ:政治] [コメント (0)] [トラックバック (0)] |
| 2024年9月22日 15時14分 |
| 知事不信任可決と失職 |
| 地方自治は民主主義の基本である。ともに選ばれた行政執行機関と議会、運営を巡って対立が生じた場合厳格な議決要件で知事の不信任が認められる。 兵庫県知事のパワハラ(違法事件である)が最大の問題。犠牲者が何人も出ている=県政の混乱。もはや、任せられないというのが民意であろう。公益通報者保護法というものがある。通報が権力者にとって一番蓋をしたいものであろう。蓋をすべく行う処分は軽々に行われるべきではないとしたもので百条委員会が調査権を行使し公正な県政に資するものである。 今回は全会一致で不信任可決された斎藤兵庫県知事はパワハラを否定し告発者の処分を正当とする。亡くなられた当事者はお気の毒であるがパワハラは権限の上位者の立場に乗じた苛烈な追求を極めたという。 パワハラ行為は違法であり人権侵害の内容をもち、行為者の自制、それが効かなければ百条委員会の手により自浄機能により、それが効かなければ投票行動。苟も政党政治自民維新の推薦と支援で首長になったのであるから母体による説得牽制だってある。 パワハラという現代的事案に関することである。知事は権限が与えられたに過ぎない立場の者。しかし、本人は自分は偉い人間と常に思い認識し他者は低い者と見下すのが通例である。 パワハラを防止する一般的な罰則付きの法律があるわけでなく、個別対応するしかないのも現実である。 果たして議会解散となるか=支持母体は大変、少なくとも自制が効くか、兵庫県民の意思はどうであろうか。 |
| [カテゴリ:政治] [コメント (0)] [トラックバック (0)] |
| 2024年9月15日 14時27分 |
| 早期解散を目指すわけ |
| 自民党総裁選で九名にもなる候補者乱立的お祭りム−ドよろしく、最有力候補と思しき小泉氏から出た言葉。歴史上自民党を際限なく信用失墜させた裏金事件。それだけの危機である。表紙を付け替えこれでどうだとばかりイメージだけで総選挙に打って出る。かつて、安倍政権が取った手法の内(但し統一教会の支援があった)を想起してしまう。増税は据置するが民意を問いたいというならまだしも、腐敗の禊がしたいというのでは虫が良すぎる。 弱い野党が支えもしたであろう。裏金事件の解明はできているというにはほど遠い。とってつけたような選択的夫婦別姓制度の言及。解雇規制緩和は国民の安心を更に遠ざける恐れすらある。 大企業政治献金には封をしたまま政治資金規正法違反のレベルに済ませるにせよ、金権政治が招いた自民党体質がどう変わるというものかの提示もないであろう。言うは易く行うは難し。 国会の論戦を避けようというのが従来型の与党の危機回避策にせよ、国民がもうごまかせないという賢明な意識を堅持し、代わるべき野党勢力の動向が見逃せない中、戦後民主主義がどこまで国民の主権者としての意識を高めたかである。 所詮選挙に勝っての話である。国民の方向をしっかり見て、ぶれない選挙協力があってこそ国民をよき方向に導くことができるのは間近いのないことではなかろうか。 |
| [カテゴリ:政治] [コメント (0)] [トラックバック (0)] |
| 2024年8月24日 19時35分 |
| 自民総裁選から見えるもの |
| 裏金事件に端を発した政権与党の信用失墜は事実上の岸田総理の辞任そして表紙の付け替えにと総裁選挙に挽回をかけて我も我もと候補者が寄ってくるかの如し。果たして国民の不信が拭えるに足る総裁選出となるかである。 自民党は既成勢力既得権益の代表のようなものである。総理大臣は卑しくも全国民のそして日本国のリ−ダとして我が国をどのような国にするという明確なビジョンを求められる(例えば成長と分配など)、一自民党の総裁にとどまるものではない。どの候補も役不足。円安不況で国民は上がらぬ実質賃金物価高で苦しんでいる。大企業既得権益を守るに過ぎるは偏った低成長経済、世界から取り残され追い抜かれていくという現実を経験している。 長すぎた30年、怠慢は企業経営者のみでない。高度経済成長優秀と言われた官僚にも認識の甘さが問われるという。国のリ−ダにもこれを引っ張っていく資質に欠けてしまった。そんなことから信頼回復支持率の挽回が目標であれば,所詮コップの中の嵐である。 一方、政権交代が叫ばれながら、立民の人気のなさ、一度国民とのマニュフェストを破り国民の不信を買った古い者を担ぎ出すようでは。連合(組合連合と言っても大企業側に立ち個々の労働者の利益を損ねている、意外にも)に乗っかかりまさに圧力団体政治に堕している。これも、既得権益政治と言える。 こうしてみれば、ともに、一部の圧力団体政治、官僚政治に屈しないリ−ダが如何に大事で、未来へ繋ぐそうした人材の登場が切望されるか、自ずと見えてこようものである。 |
| [カテゴリ:政治] [コメント (0)] [トラックバック (0)] |
| 2024年8月16日 14時4分 |
| 中国経済低迷の先にあるもの |
| ここのところ中国経済の減速が取り沙汰され、その行方に関心が高まっている。GDP世界第二位の経済大国は社会主義経済であるにもかかわらずアメリカ経済に迫り追い抜くかのような勢いがかつてあった。 しかし、その夢は破れ、もはや経済低迷を抱えたまま一種迷走ともいえる状況に陥っているかの如くである。 中国経済を支え起動力となった不動産(定期借地権)もバブル(過剰流動性)となり恒大グループの破綻に象徴される巨大債務超過。そもそも資本主義市場経済が機能しているわけでもなく習近平氏による「共同富裕」の考えが資本主義的論理を排除するものだからだ。資本主義は本来は富の偏在と労働力搾取収奪の上に成り立っているのではなかったか。 世界の工場として世界中から資本や技術の提供を受けモノ余りともいえる供給過剰をうみだした。コロナ禍では徹底した封鎖と隔離で多くの経済活動を封殺してきた結果大規模な需要減を招いた。 供給過剰を消費すべき「一帯一路」もうまくいかない。 こうして陥った中国経済のマイナス要因は習近平氏にその現状報告が届いていないといわれ、改善し上向く気配はみられないといわれる。 中国が独自の道を歩むにせよ人口減少、少子化政策による異常な逆ピラミッド、勢いはすでにインドにぬかれているという。 歴代中国を支配してきた歴史上の国々。永続的に続く支配があった試しとてなく、果たして共産党一党独裁が14憶の中国人民の未来をつなぎとめるものなのかその関心は尽きることはないといえよう。 |
| [カテゴリ:政治] [コメント (0)] [トラックバック (0)] |
| 2024年8月14日 10時15分 |
| 極右暴動に見る英国の情勢 |
| 7/29イギリスのサウスポートで起きた三人の少女の刺殺事件。痛ましいが傾向犯罪者を臭わすにもかかわらず極右勢力者がイスラム系移民者によるものとネット(✕)に嘘情報を流した。たちまち広がり各地で暴動となった。 イギリスではこうした騒乱は珍しくはないそうだが、偽情報が原因の犯罪行為であり当局は徹底的に摘発するという。ネット犯罪も厳しく取り締まることが英国の秩序と名誉を維持するに資するであろう。 沈みゆく旧大英帝国、植民地からの収奪が現在の国を支えているなどとは言わないが目ぼしい産業も金融を除いて乏しい。国民はひどい住宅難とインフレ生活費医療サービスなどの政府の失敗が底流にあるという。 反移民は英国のEU離脱の最大の要因と言われるが、離脱後もむしろ難民流入は増えている(ド-バ-海峡を容易にボ−トで渡る)という。この最大の要因はEU離脱後に「ダブリン協定」(最初に到達したEUの国に難民を送還できる)が効かなくなってしまい難民もこれを見逃さないという皮肉な結果となっている。 さらに、与党も野党も反移民をスローガンにかかげ移民に対してスケ-プゴ-トとなる土壌を作り出しているという。苦しい国民の状況と移民が優遇されているとの落差の思いからヘイト意識につながっているともされる。 こういう中で西側の旗手?たるべくウクライナ支援を更に続けるという。アメリカが離れればその負担は増えるという。そういう苦しい状況に置かれるのは英国だけではなかったのではなかったか。 |
| [カテゴリ:政治] [コメント (0)] [トラックバック (0)] |
次の10件